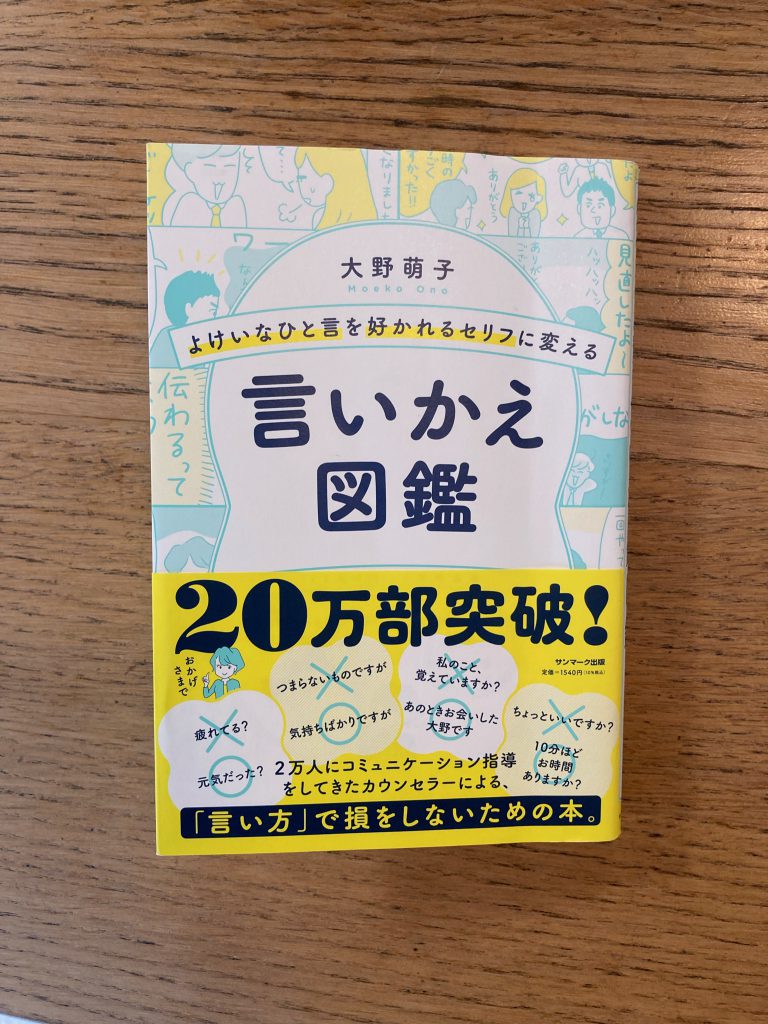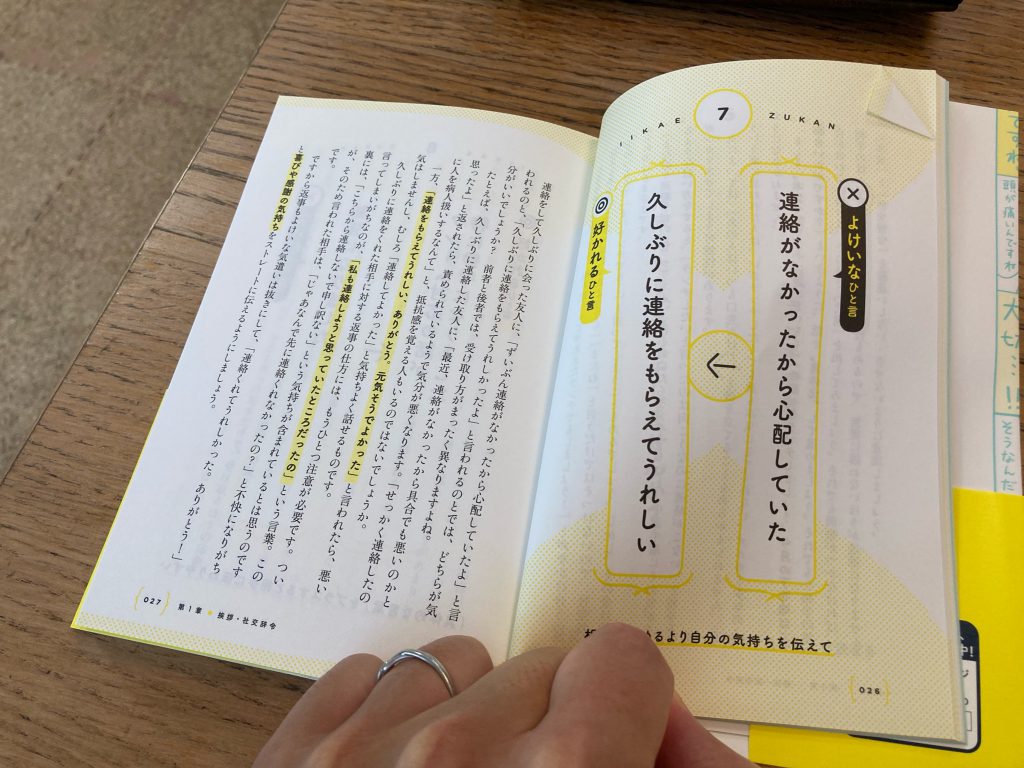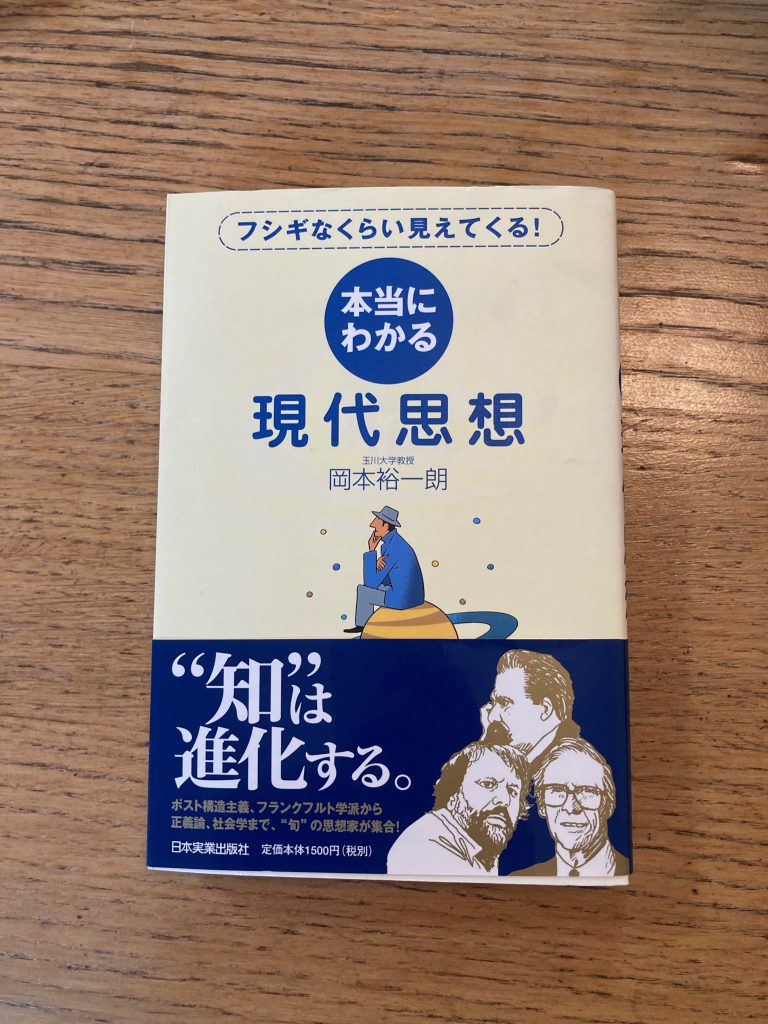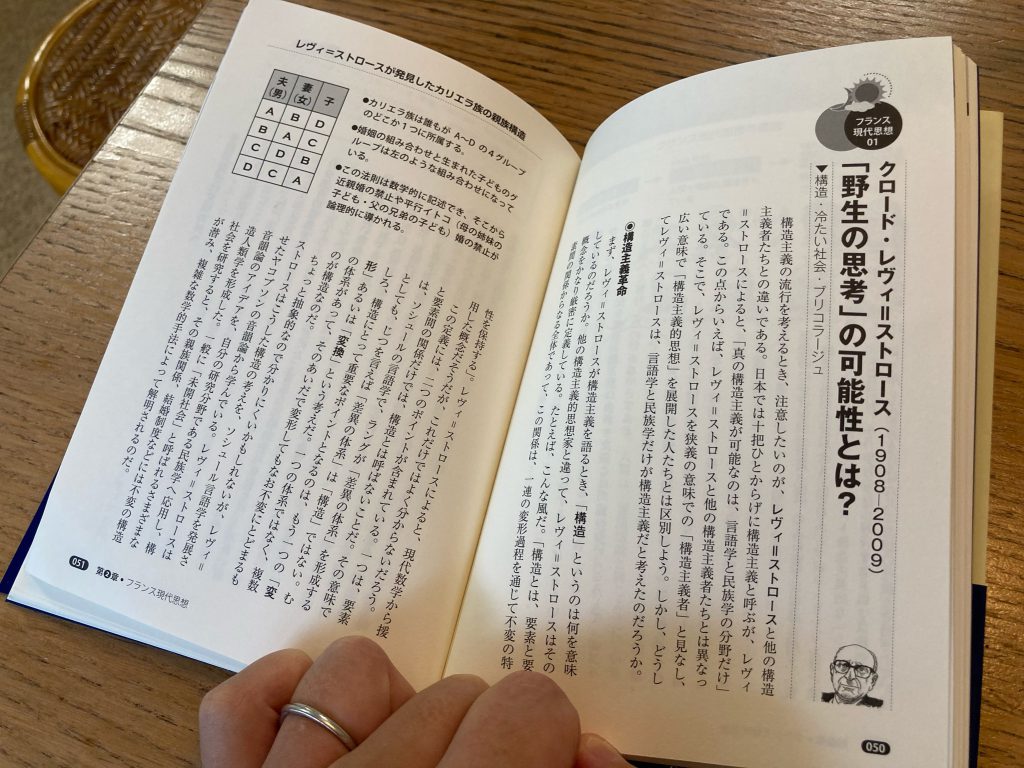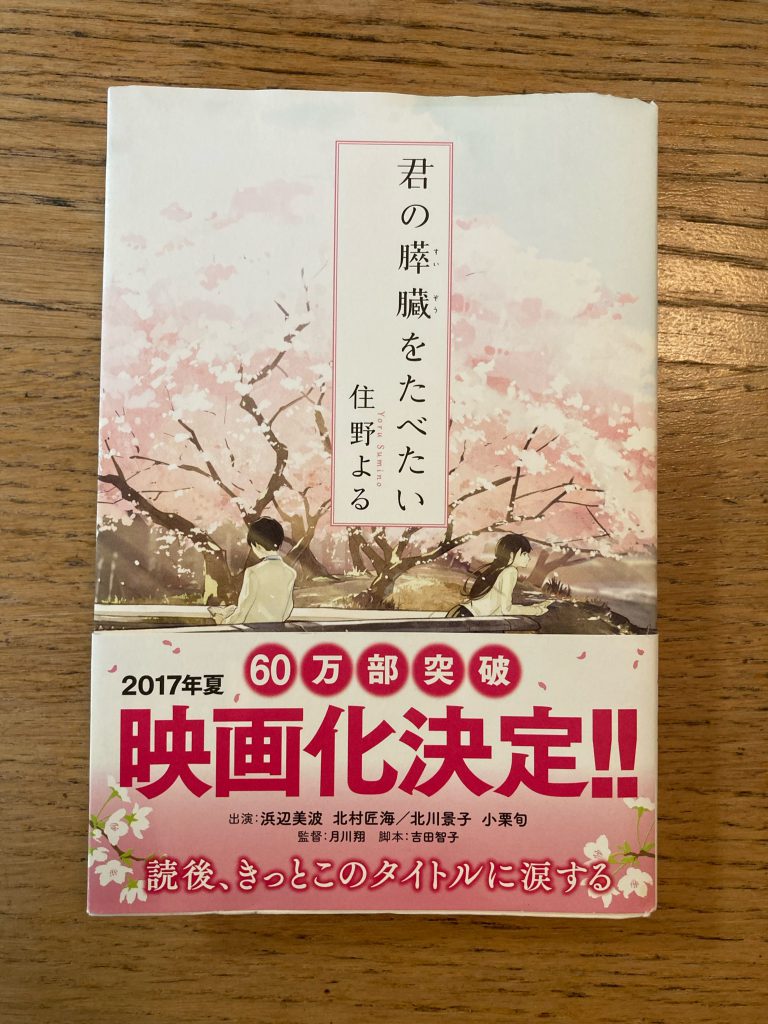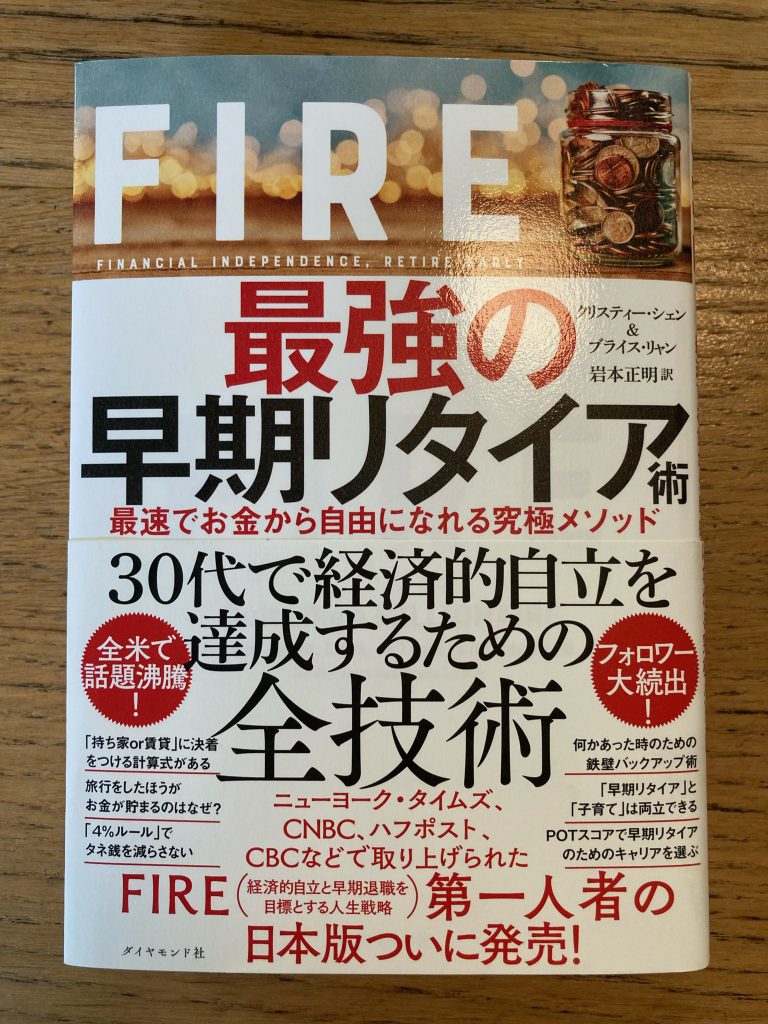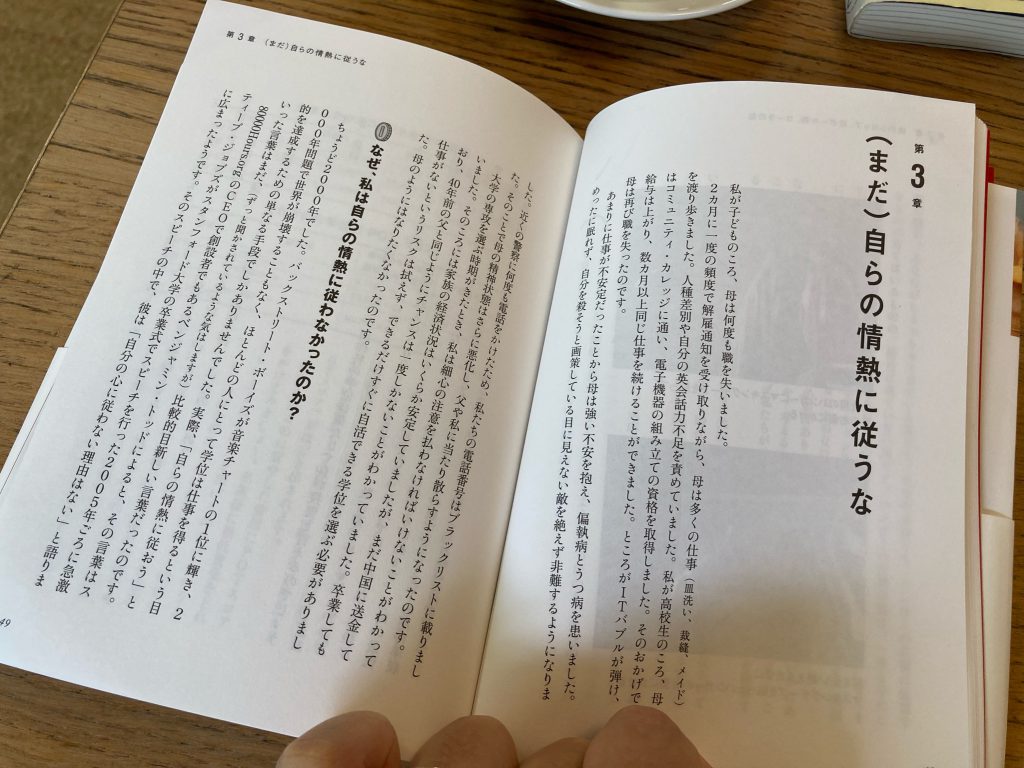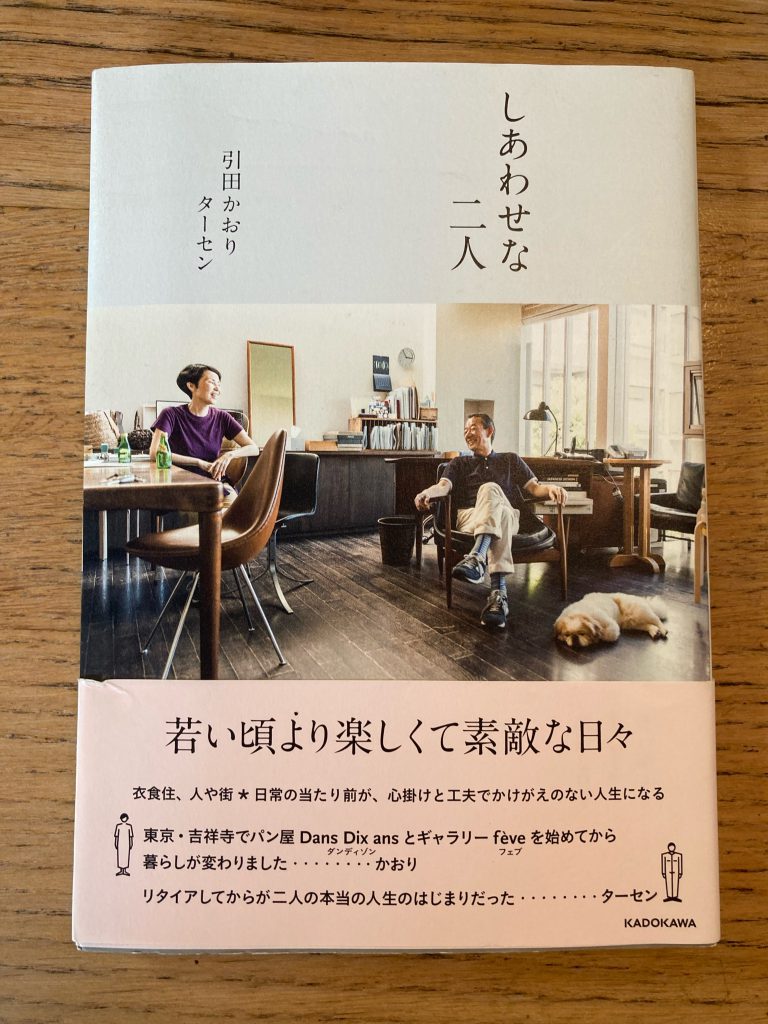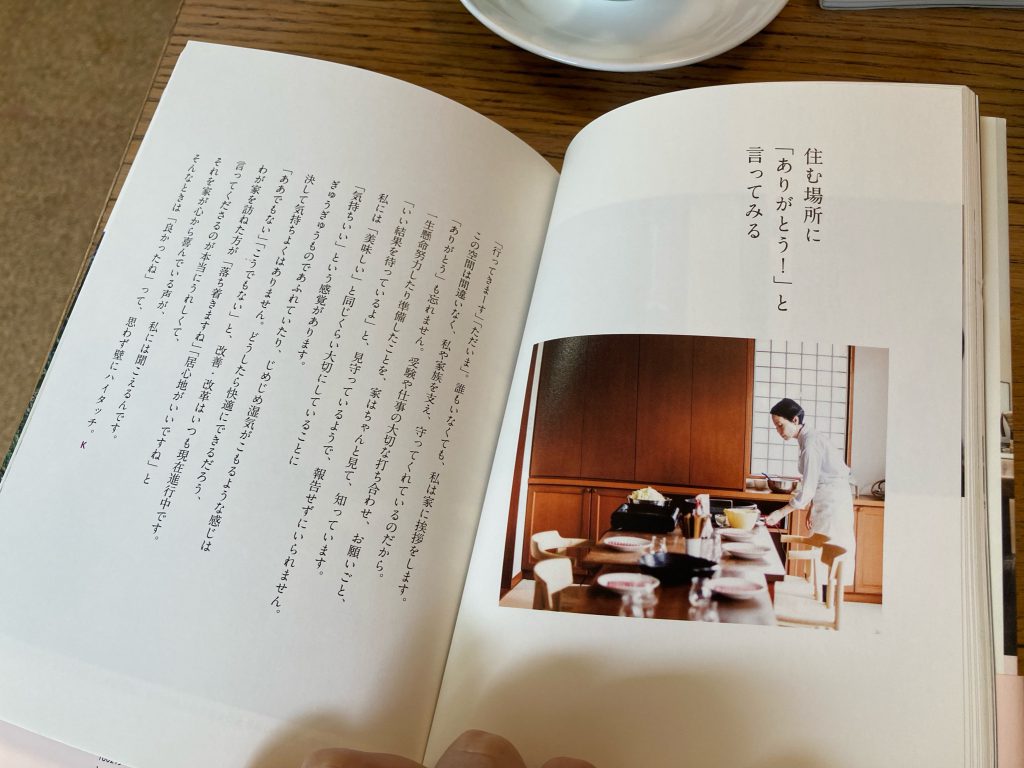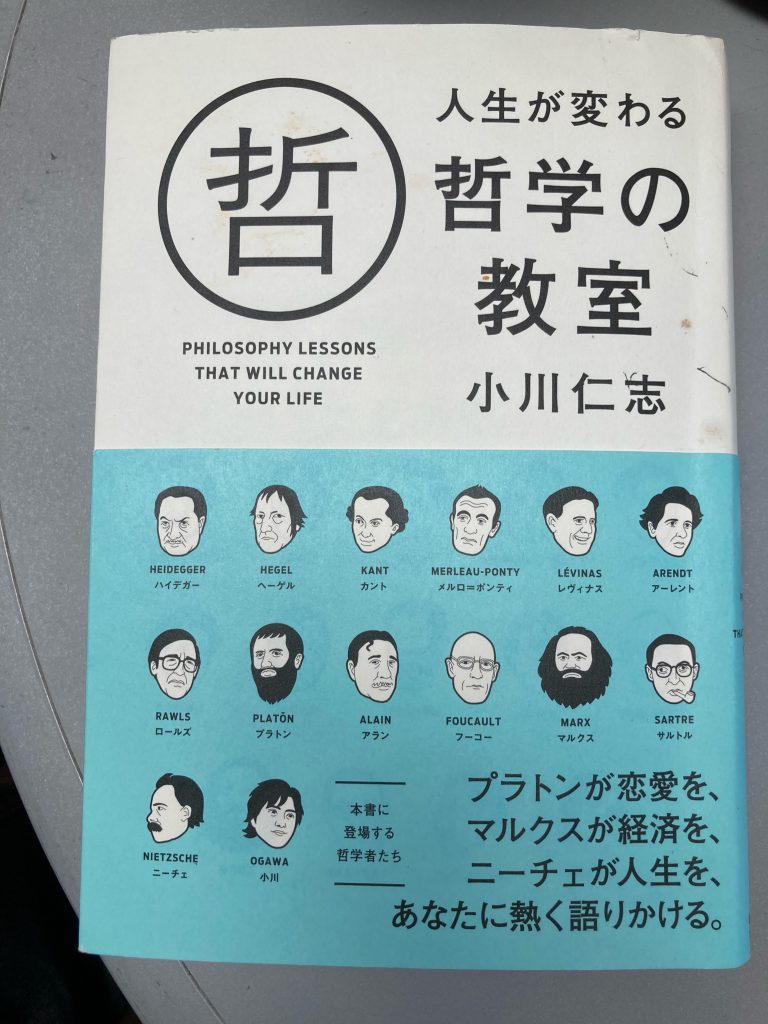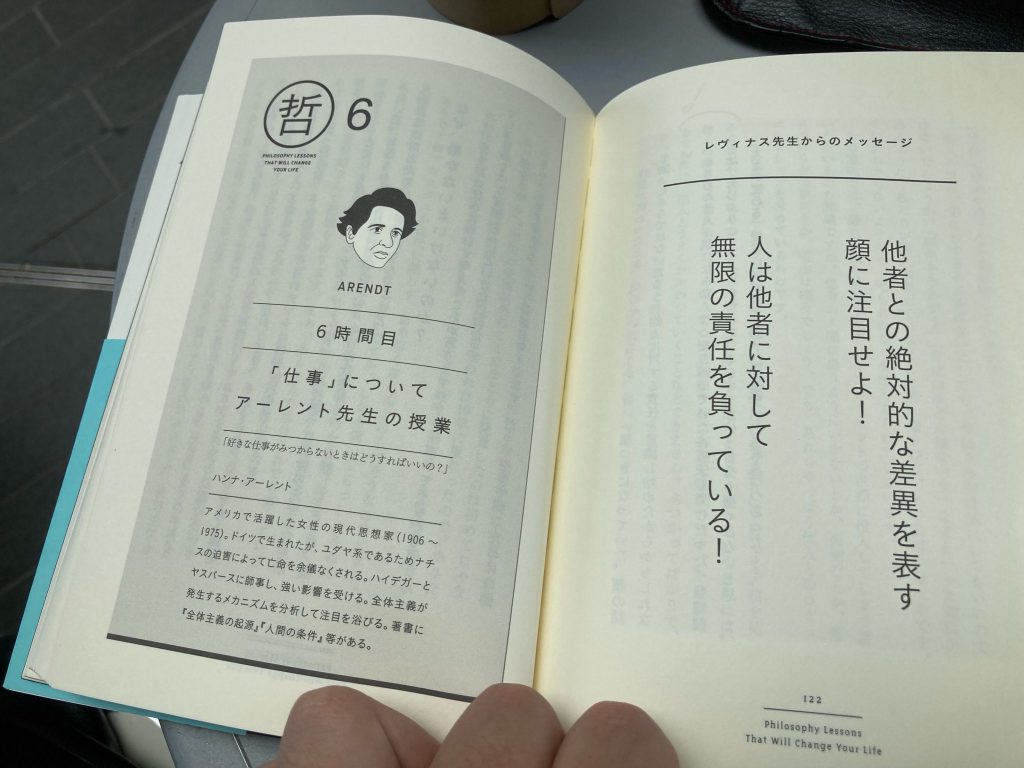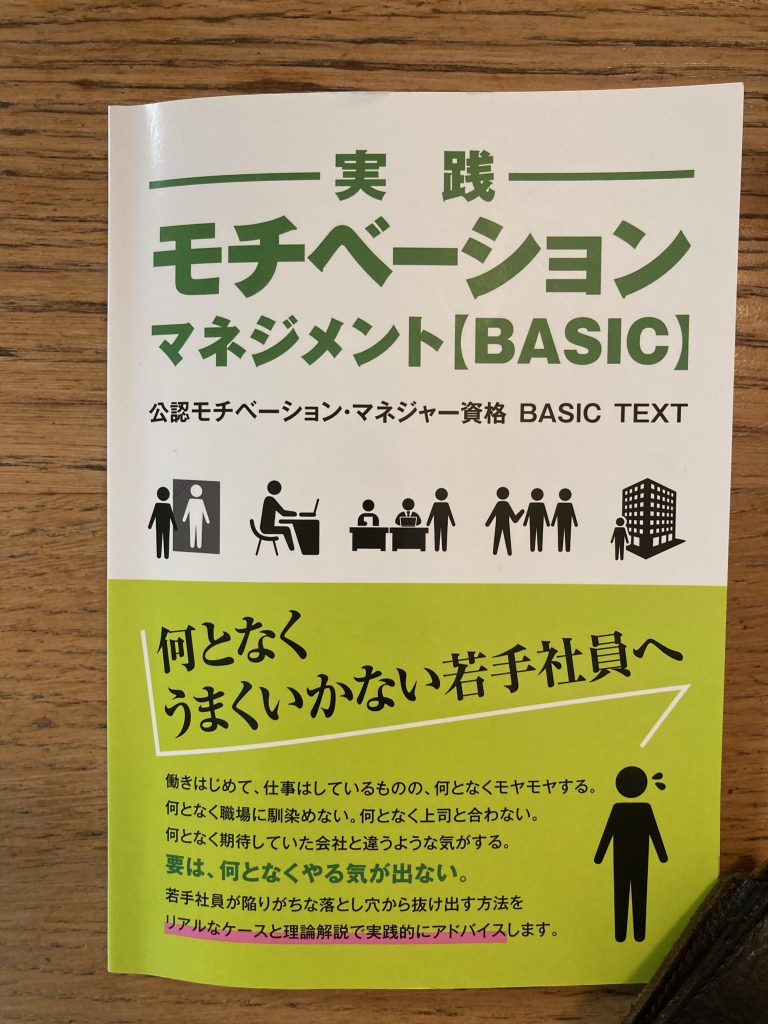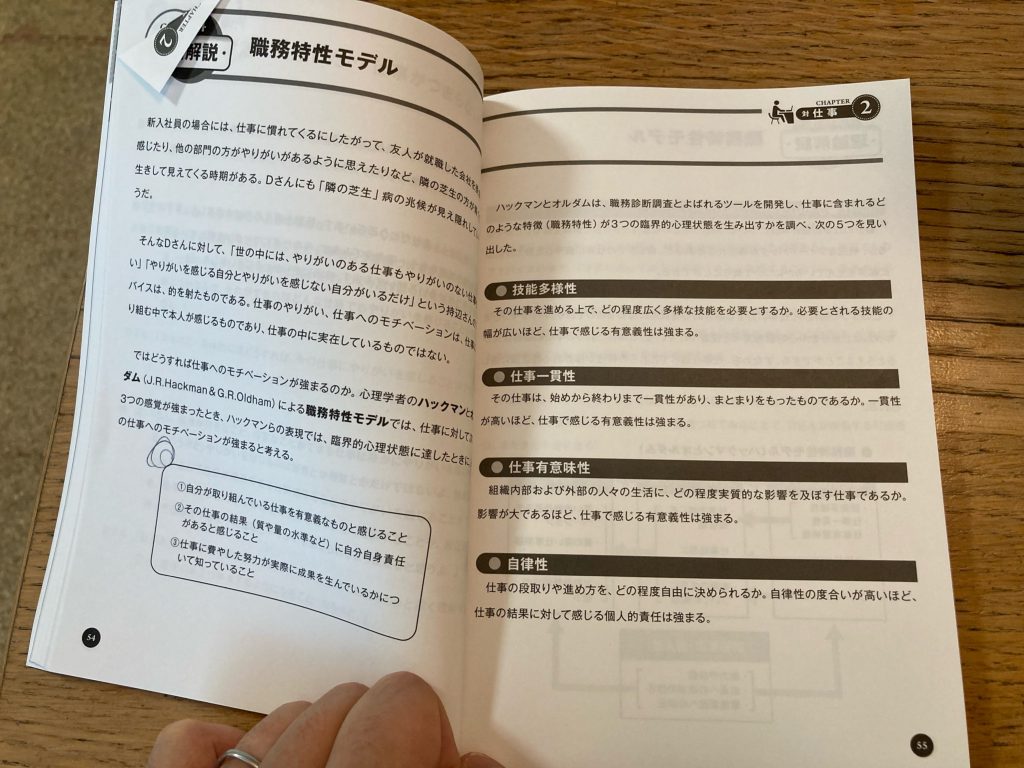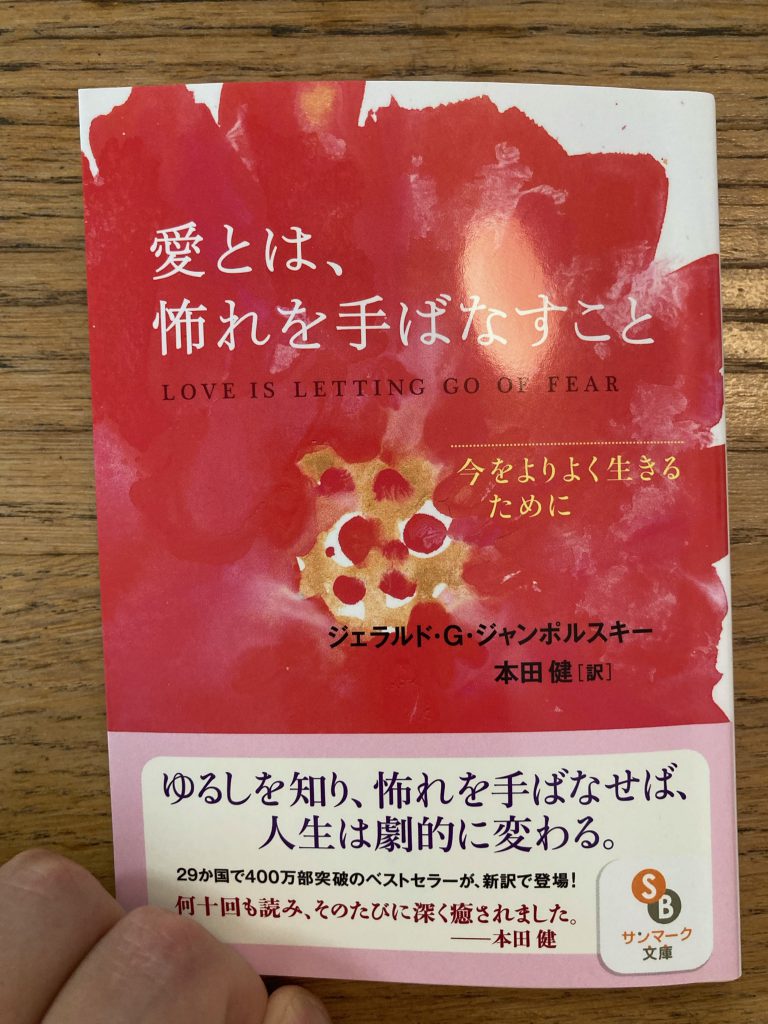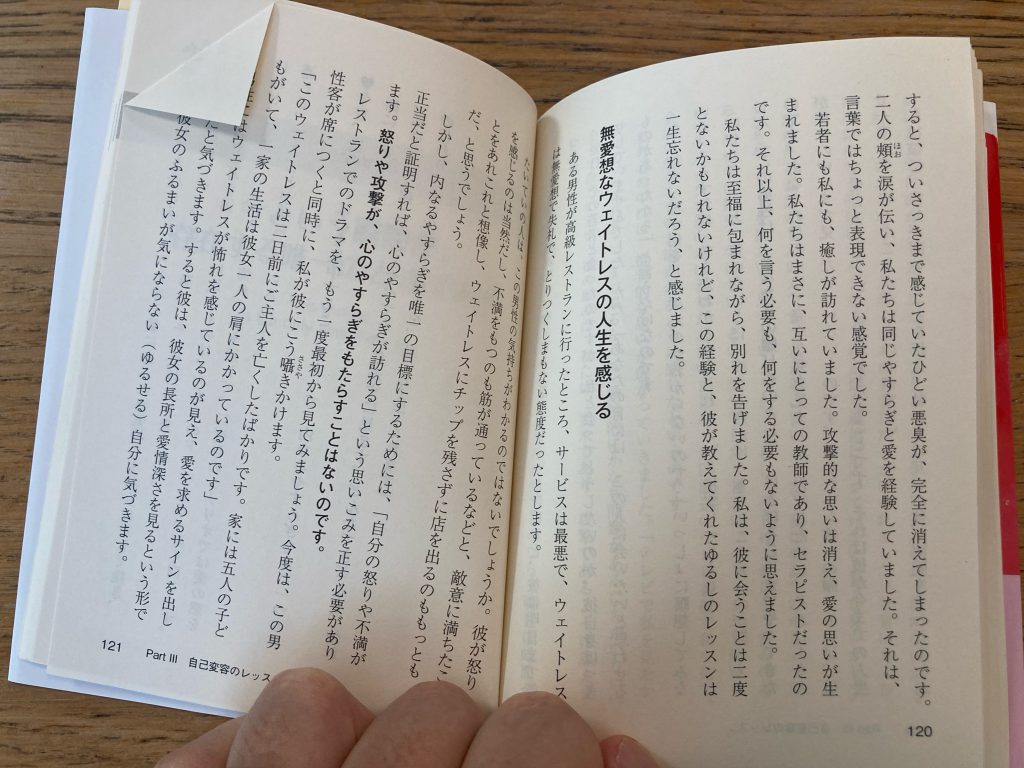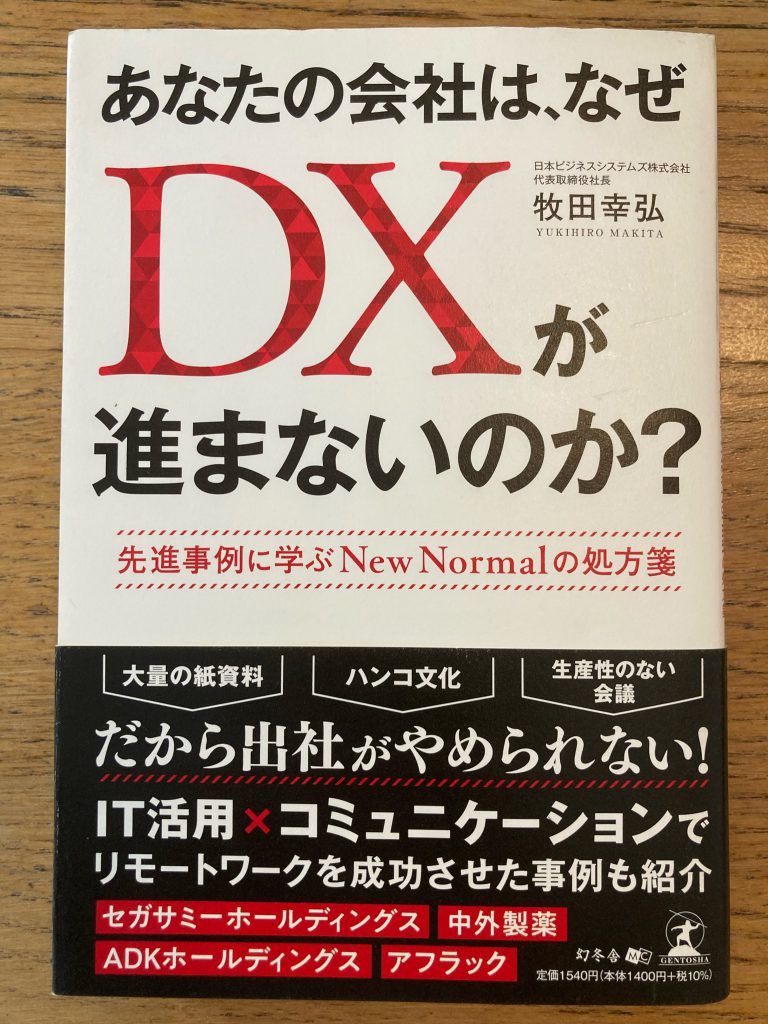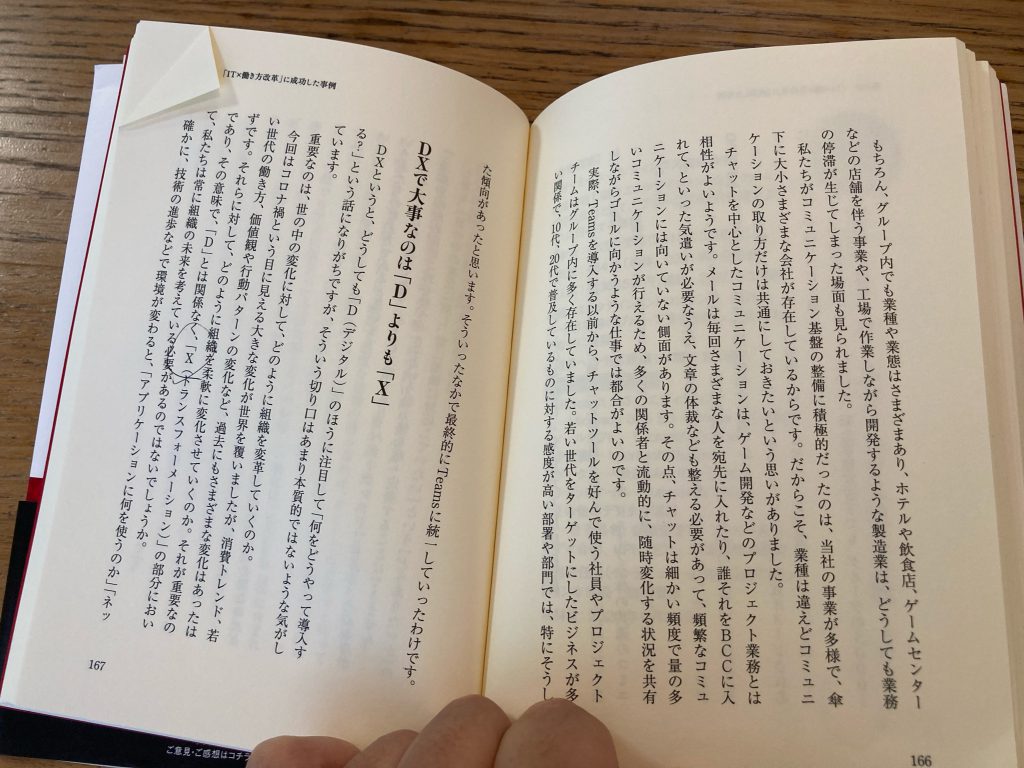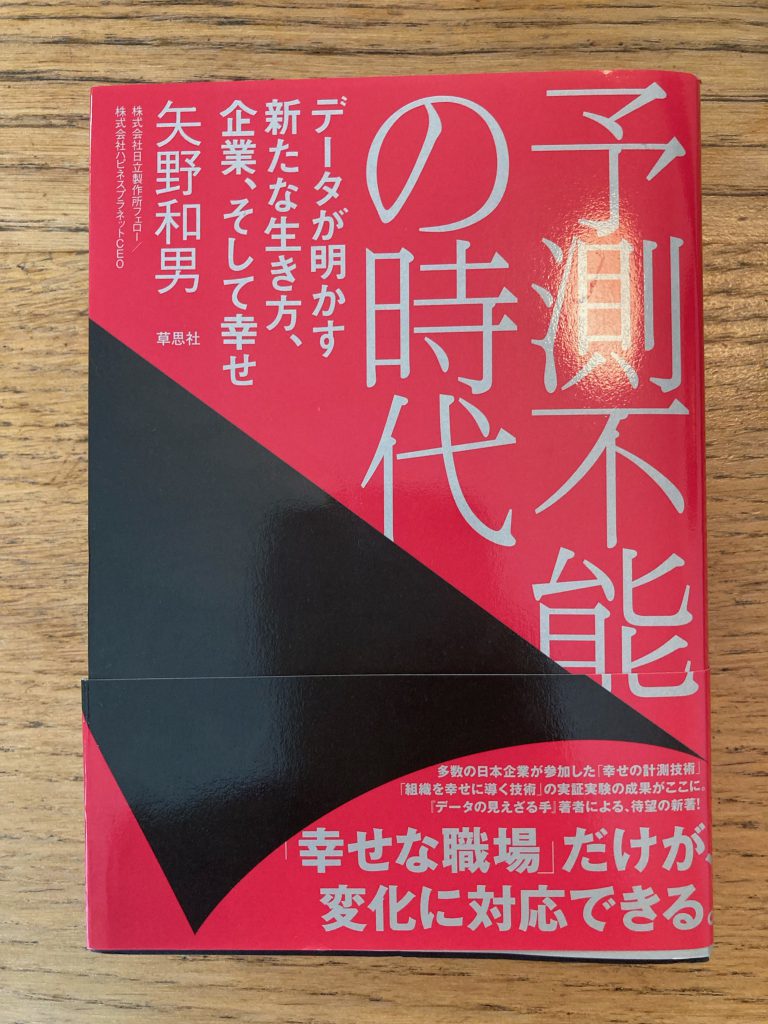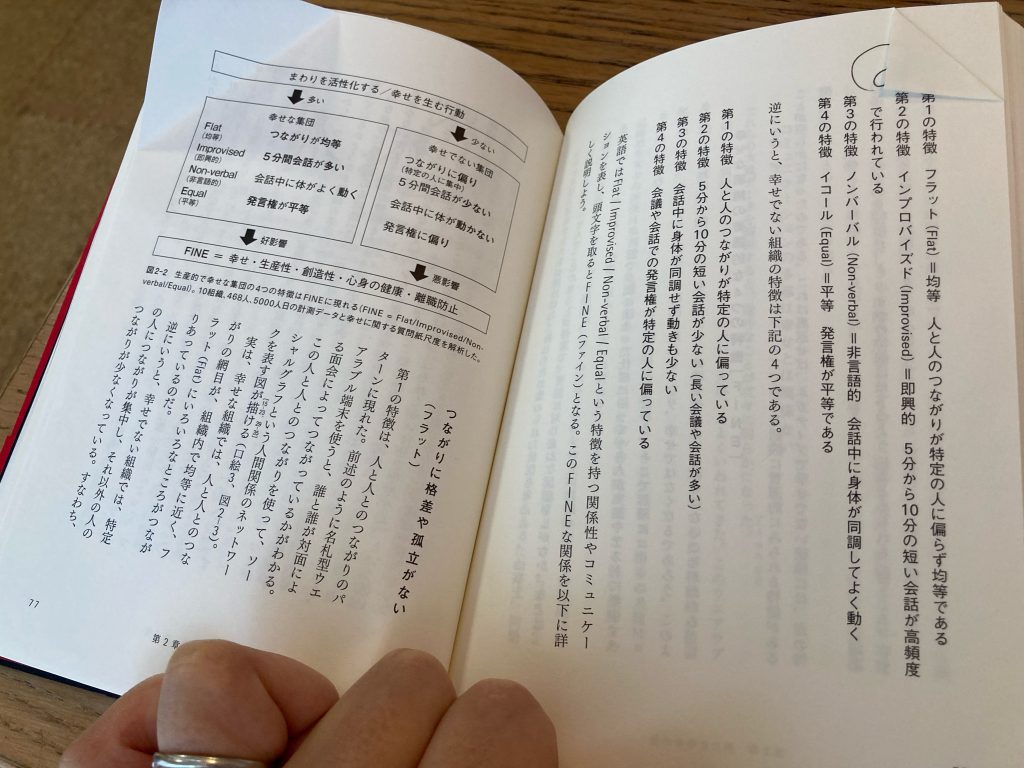第208週
2021/10/8
『言いかえ図鑑』
大野萌子著 サンマーク出版
メール、チャット、会話、全てのコミュニケーション機会で感謝を伝え、肯定表現を使うようにしています。これによって人と「つながる力」が伸び、周囲の方々との関係性が格段に良くなっていったと感じます。今回「つながる力」を更に磨きたいと思い、手に取りました。
本書を読み「好かれるコミュニケーション」について、自分で3つにフレ―ワーク化しました。「常に肯定、常に具体、常に想像」です。
1.常に肯定
「連絡がなかったら心配していた」
→「久しぶりに連絡をもらえてうれしい」
「あ、ドアを閉めないでください」
→「ドアを開けておいていただけますか」
「今月は忙しいから会えない」
→「来月は時間があるから会えるよ」
「会話の基本は肯定系です。」と著者が言っていますが、深く共感します。会話をはじめメールやチャット、全てのコミュニケーションから否定を排除し、肯定でコミュニケーションを行うと人間関係は驚くほどよくなっていきます。
2.常に具体
「ちょっといいですか?」
→「10分ほどお時間ありますか?」
「何でもきいて」
→「〇〇でわからないことがあれば聞いてください」
「さすがだね」
→「〇〇がよかった、さすがだね」
具体的だと相手が分かりやすいです。「ありがとうございました」という御礼の言葉も、具体的に何について感謝しているのか伝えるようにしています。
3.常に想像
「なんとかなるよ。」
→「どうすればよいか一緒に考えよう」
「大変な思いをさせて申し訳ありません」
→「混乱させてしまい、申し訳ございません」
「お詫びの場面など、相手がもっとも訴えたいことをきちんと捉える」と著者が言っていましたが、そのために相手の状況や心情を想像するようにしています。そうすると「分かってくれている」もしくは想像が外れていても「分かろうとしてくれている」ことが伝わり、つながりが強くなる気がします。
「つながる力」に天井はありません。フレームワーク化=教訓化ができたので実践・内省・学びで磨いています。
(819字)