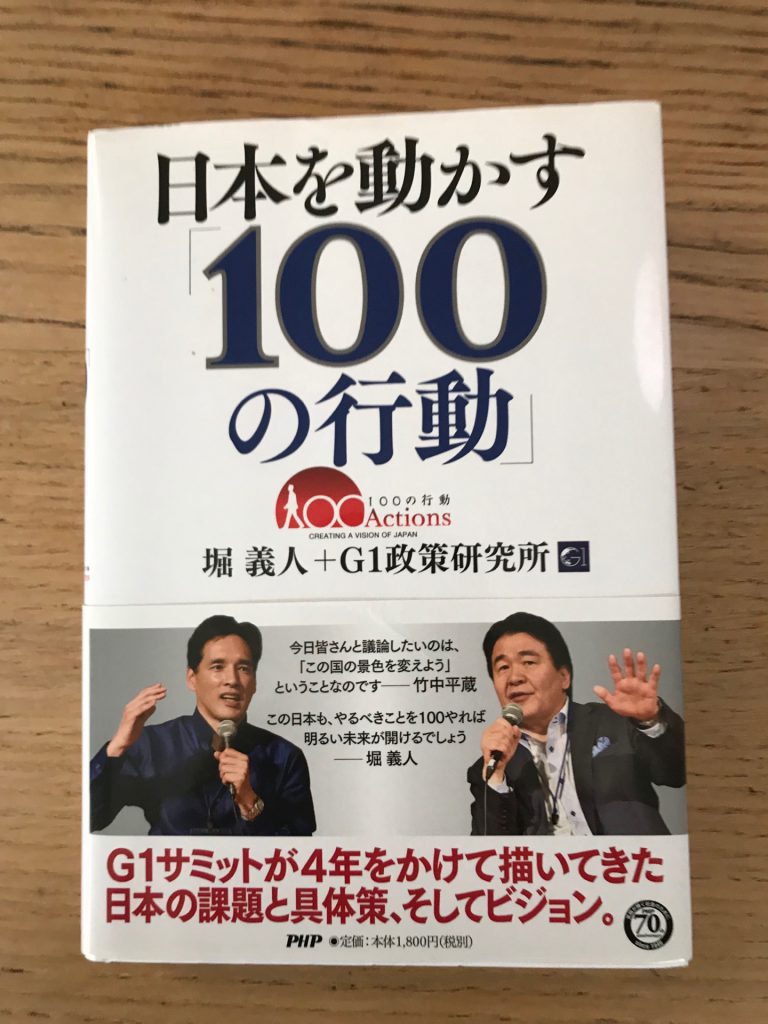第84週
2019/3/10
『日本を動かす「100の行動」』
堀義人+G1政策研究所著 PHP社
成長社会から成熟社会へと進む日本。時代の移り変わりの中で、様々な問題が表出してきています。私の専門領域である教育という枠を超え、日本全体の問題を俯瞰しそれぞれの問題に対して具体的な意見を持つことを目的に本書を手に取りました。今回は「100の行動」のうち、特に印象深かった二つの政策を列記します。
まず、医療費増大に対する政策です。本書に医師数の国際比較表が載っていますが、人口千人当たりの医師数は日本が2.2人で、米国の2.4人、英国の2.7人と比較しても顕著に低いわけではありません。一方、平均在院日数は米国が6.2日、英国が7.7日に対し、日本は32.5日。年間外来受診回数(年間)も、米国3.9回、英国5.0回に対し、日本13.1回と突出した数値となっています。ここから、日本は医師の数が少ないのではなく、患者の数が多いことが分かります。そして患者を減らすために、予防・健康ケア医療への転換が重要になると本書は主張しています。具体的な政策として、健康でいることに対するインセンティブを設け、保険料の差別化等を行うなどは思わず膝を打つような政策であり、発想を換えて臨むことの重要性を感じました。
もう一つは道州制の導入についてです。これはG1目玉の政策であると考えます。都道府県を廃止し、10の「道」と2の特別区を置き、20~40万人からなる300程度の基礎知自治体に再編する「廃県置道」。道州制は中央と地方の役割をはっきりさせ、地方分権を徹底する政策です。少子高齢化により、行政サービスを統廃合して効率化する必要性。そして、地域の多様化の進展により、各地域に見合ったサービスの必要性が背景となります。確かに中央政府が、外交、国防、司法など国家全体に関わる事項に専念できるのは大きなメリットですし、地域主権により政策決定、実施スピードが高まるのも間違いないと思います。ただ、この道州制は、国民がメリット(必然性)を感じにくい政策です。大阪が都になり、そのメリットを府民が享受、実感することが、実現機運が高まる突破口になる気がします。
4年かけて政策としてまとめた著書の熱意と行動に敬服します。正直、日本という大きな枠組みの政策はまだ距離が遠いものが殆どです。ただ、大局観を養うのに役立ちましたし、都度「日本」の大局を考える参考書として活用していきます。
(975字)