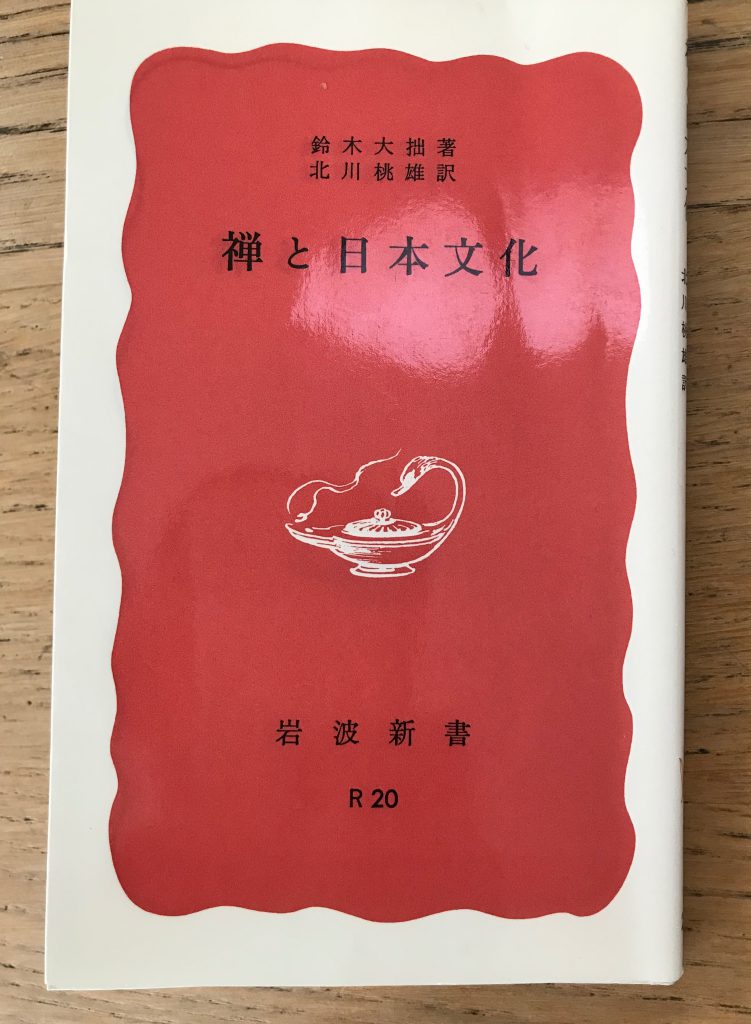第89週
2019/4/13
『禅と日本文化』
鈴木大拙著 岩波新書
今年の大きなテーマは教養を高めること。日本の歴史と文化の見識を深める第二弾として本書を手にしました。
本書は禅が日本人の性格と文化にどのような影響を与えているか、芸術全般と武士、剣道、儒教、茶道、俳句といった日本文化を象徴するものを対象として禅の影響を書いています。
著書鈴木大拙氏は「近代日本最大の仏教学者」ともいわれ、日本の禅文化を英語で著し、広く海外に伝えていった方です。本書の第一刷は1940年発行されています。
やや哲学的で難解であり、全体を網羅しまとめることが難しかったため、今回は中枢と思しき文章を引用し、解釈を加える形にします。
『日本の芸術的才能のいちじるしい特色の一つとして、南宋大画家の一人馬遠に源を発した「一角」様式を挙げることができる。この「一角」様式は、心理的にみれば、日本の画家が『減筆体』といって、絹本や紙本にできるだけ少ない描線や筆触で物の形を表すという伝統と結びつている。』
『非均衡性・非相称性・「一角」性・貧乏性・単純性・さび・わび・孤絶性・その他、日本の美術および文化の最も著しい特性となる同種の観念は、みなすべて「多即一、一即多」という禅の真理を中心から認識するところに発する。』
『茶道については、いつも物事を単純化せんするところに在る。この不必要なものを除け去ることを、全は究極実在の直覚的把握によって成し遂げ、茶は茶室内の喫茶によって典型化させられたものを生活上のものの上にうつすことによって成しとげる。』
究極的には禅とは世界に区切りはなく、自分も世界も全て一緒ということを体感(洞徹)する宗教と私は考えています。世界に区切りを入れ知性論理で真理を探究する西洋哲学と比較し、世界に区切りをつけず感性身体で真理の体感・体得を目指す東洋哲学。その道筋を様式化し、日常に示したのが禅と捉えています。読了し、この禅がもつ華美を避け、無駄を除けるといった清貧的な要素が私の深奥の渇望ではないかと直感的に感じました。例えば、多様性の中に浮き出る超越的な孤絶性が「わび」であり、貧困への信仰と共に禅の思想と結びつているそうです。この日本的感覚を愛で、磨いていきたいと思います。
(900字)