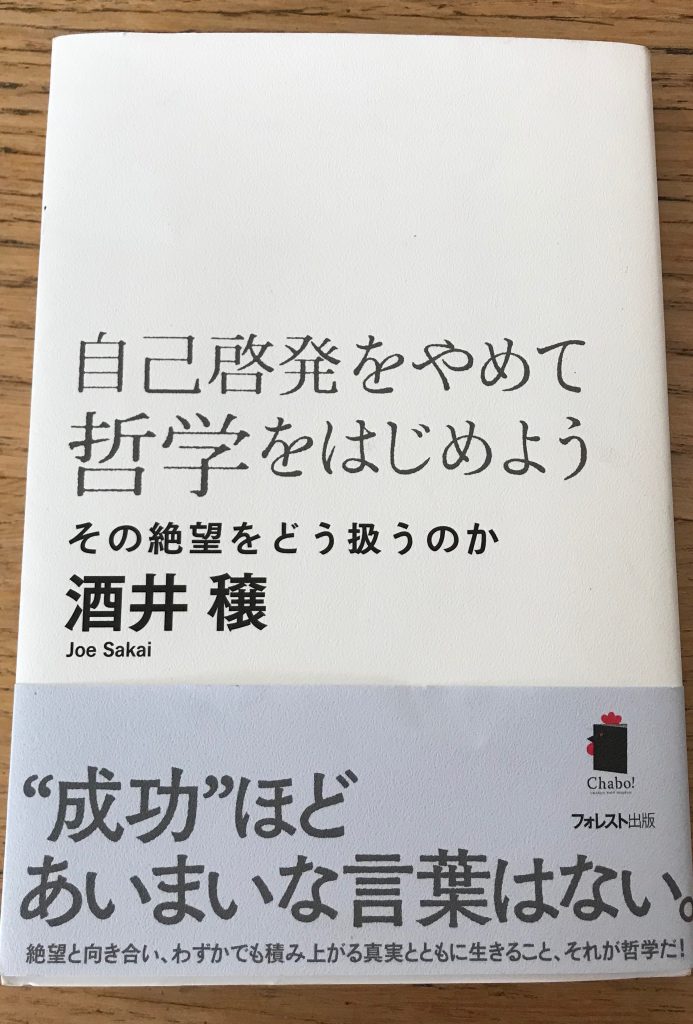第53回
2019/4/20
「成熟と学習 8章人間の発達について考える」
【まとめ】
発達とは、胎児が成熟した個体に成長するまでの、形態や行動が変化していく過程のこと。
身体的な発達は生物学的なものといえる。一方、知的能力や人格の発達を規定する要因には、「成熟」と「学習」の要因があり、発達にはどちらが重要なのであろうか。
ゲゼルとトンプソン(Gesell&Thompson,1929)は、一組の女児一卵性双生児を対象に成熟と学習のどちらが発達に強く影響するのかについて調べた。生後46週目になった時点で、一方の幼児Aだけに階段上りと積み木操作の訓練を始めた。するとAは52週目に援助なしに26秒で上がれるようになった。他方の幼児Bは53週目の訓練開始時に、援助なしに45秒で上がることができ、2週間後にはわずか10秒での上ることができた。積み木の操作についても、53週目ではじめて触れたBは、Aと同様に積み木の操作ができた。この結果からゲゼル達は、発達が成熟の要因に強く規定されるという結論を出した。
しかし、我々は学習が発達を促すという事実を知っている。ただ、その場合にも学習者に「レディネス」(学習のための準備)が備わっている必要がある。最適な時期に学習すると最も効果的に学習内容を習得できる。
現在では発達を規定する要因は学習か成熟かという議論はされなくなった。それはピアジェの理論に代表されるよう、2つの要因が相互作用しながら発達を促すという考えが一般的になったからだ。
(アーノルド・ゲゼル(Arnold Lucius Gesell、1880年6月21日 – 1961年5月19日)は、アメリカ合衆国の心理学者、小児科医。子どもの発達研究の分野のパイオニアとされる。Wikipediaより)
【所感】
他サイトを調べると、ゲゼルの提唱した論は「ゲゼルの成熟優位説」と言われるそうです。成熟前の教育や訓練は効果が上げらないと説き、レディネス(心身の準備)の重要性を提示したこの論は、教育者にとっては留意すべきものと感じます。教育効果=量×質だけでなく、タイミングという因数の存在を示すものであり、教育方法を根本から考える上で、示唆に富む論だからです。
「その子その子に最適なタイミングがある」というのは、学習塾の塾生や我が子に対しても常に感じていることであはります。一方、難しいのは「何を、いつ、どのように行うのがその子にとって最適な教育や訓練なのか」ということです。つまり、対象となる子のレディネスが整うのはいつなのか、ということです。レディネスのタイミングを見極め最適な教育をするには、経験と勘で実行しながら、メソッドとして形式知化し改善をし続けることが道だと思います。
ともあれ、今回「レディネス」という学術用語(概念)を手に入れることができたのは大きく、英克や浩子と塾生に対して、実央とは我が子に対して、レディネスを共通言語にしながら対話をし、共に教育技術を磨いていきます。
(1199字)