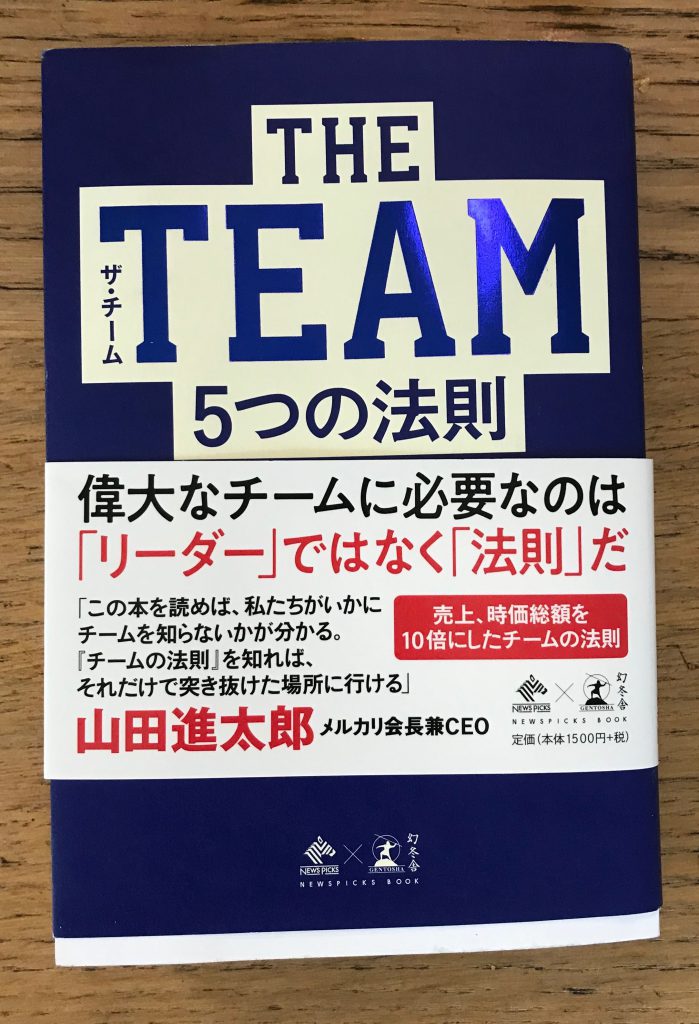第56回
2019/5/25
「臨界期 8章 人間の発達について考える」
【まとめ】
動物行動学者のロレンツ(Lorentz、1952)は、ハイイロガンのヒナが生後十数時間以内に刺激対象が与えられないと追従反応が生じないことを見出した。この時期を「臨界期」と名付けた。ロレンツは、孵化後、自分だけがそこにいるようにした。するとヒナはロレンツを親だと思い追従行動をし続けた。また生涯にわたりそのことを消し去ることができなかった。生後まもなくの限られた時間内に生じ、再学習することが不可能になる学習現象を、ロレンツは刷り込み(インプリンティング)と名付けた。
ヘス(Hess,1958)は、模型の親ガモを回転させ、追従反応が生じるかどうか調べた。孵化後13~16時間で追従反応の生起率は最大になり、29時間~32時間では、ほとんと生じなかった。
では臨界期が人間にもあるのか。人間にも臨界期ほどの強いものではないが、学習に適した敏感期があると言われている。北村(1952)が行った興味深い調査がある。太平洋戦争のために福島県に疎開した子供達が地元のアクセントをどの程度習得したかを年齢ごとでまとめた。6歳以前に疎開した子供達は100%習得できたのに対し、7歳以降は疎開年齢が遅くなるほど習得できなくなっていることが分かった。
【所感】
臨界期の話を聞くと、スキャモン曲線を思い出します。この曲線によると10歳ぐらいまでが神経系が著しく発達する時期とのこと。息子の宗真がアスリートになりたい、という夢があり、幼児運動系の書籍を私が三冊読んだところ、全ての書籍にスキャモン曲線の話がありました。そして三冊とも「競技を決めず、様々な動きをさせることが大事」と主張していました。臨界期というのが運動界において「定説」になっているのだと感じます。
臨界期と聞いてもう一つ思い出すことがあります。トライ時代、慶応中等部出身の社員と大学から慶応に入った社員と、中学受験の算数(図形)の問題を解いてもらったところ、中等部出身の社員は一目で「補助線」を引き、瞬間で答えを導きました。中学受験の算数は、通常の中学、高校だと扱わないため、大学から慶応に入った社員も、中学受験の問題の訓練をすれば、すぐに答えを出せるようになるとは思います。ただ、瞬時に答えを出した所から、この時期だからできる能力の開発があるかもしれないと感じました。
臨界期はよく早期教育の根拠になります。ただ、早期教育に熱を上げるのは、リスクを伴います。先述した「レディネス」の考え方は常に頭に入れておきたいものです。
(1036字)