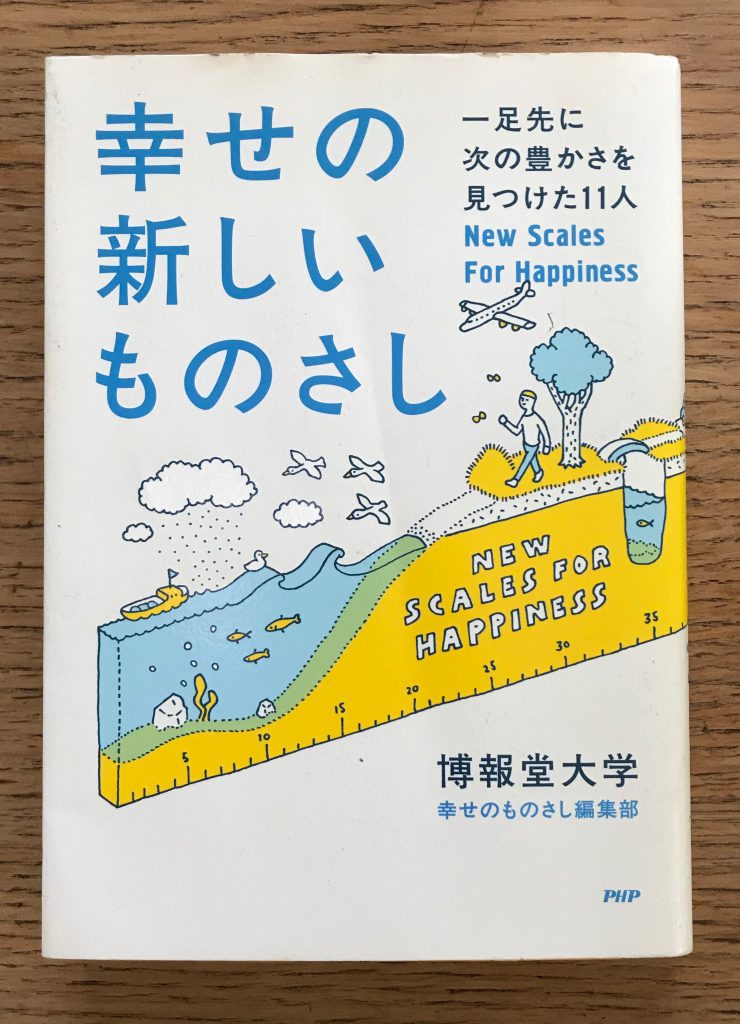第96週
2019/6/2
『幸せの新しいものさし』
博報堂大学 幸せものさし編集部 PHP
吉田の積読シリーズで2010年発行の書籍です。約9年前、自分の「ものさし」を決める必要性を痛感した際に購入した記憶があります。最近自分の「ものさし」の変化を感じ、より多くの様々な「ものさし」に触れたいと思い手に取りました。
序章で、著者は「個人の幸福度は極めて個人的・主観的な尺度のようであって、実は、『世の中かくあるべし』というその社会あるいは時代のコンセンサスに支配されている。」そして「『幸せのものさし』を社会がもはや一本化できなくなったこと自体も生活者の安心をかき乱している。」と言い、その不安を「手詰まり感」という独特のキーワードで表しています。その手詰まり感から抜け出すには、「ものさしが複数あることの良さ」に気づきつつ、「ものさし」を自分で創り、複数の「ものさし」を使い分ける自由度がキーになると主張しています。
新しい「ものさし」を創るのはとても難しいと思います。それは、社会通念が世の人の価値観に強い影響を与えるからです。ものさしの例として、リーマン・ショック前、ものさしの代表例は「お金」でした。多ければ多いほど良い、というのは強いものさしであり、今でも根強く残っていると感じます。本書で出てくる11人のように「ものさし」を創るには、まず今の自分の「ものさし」をはっきりと自覚することが自然で、現実的なステップと考えています。自分は何が好きで、何が大切なのか、自分らしさは何かなど、自己認知していない人は、子供はもとより大人でも案外多いものです。
もう一つ感じたことは、ここに出てくる11人の中で、新しいものさしを広めようとしている方々に共通するのは、体験を大切にしているということでした。無農薬農法を広める大地を守る会は「交流会などで、消費する以外の体験」を。シブヤ大学は「誰もが教えることができ、ここにしかない体験」を。「読書体験」や、ダイアローグインザダークは体験そのものを提供しています。
私達も「ライフスキル」という新しいものさしを創り、広めることが使命です。ブルームウィル企業研修では、外部が行う教育という位置づけでなく、経営者と人事の方にも積極的に関わって頂き、参加者の劇的な成長を実感する体験をしてもらう。咲心舎でも単に塾に任せるではなく、保護者様に子供の成長に関わり、成長していることを「実感」してもらう。様々な方に、共に育成に関わってもらい対象者の成長を実現した喜びを共に実感する体験。本書を通して、この点を更に大切にしていこうと考えました。
(1037字)