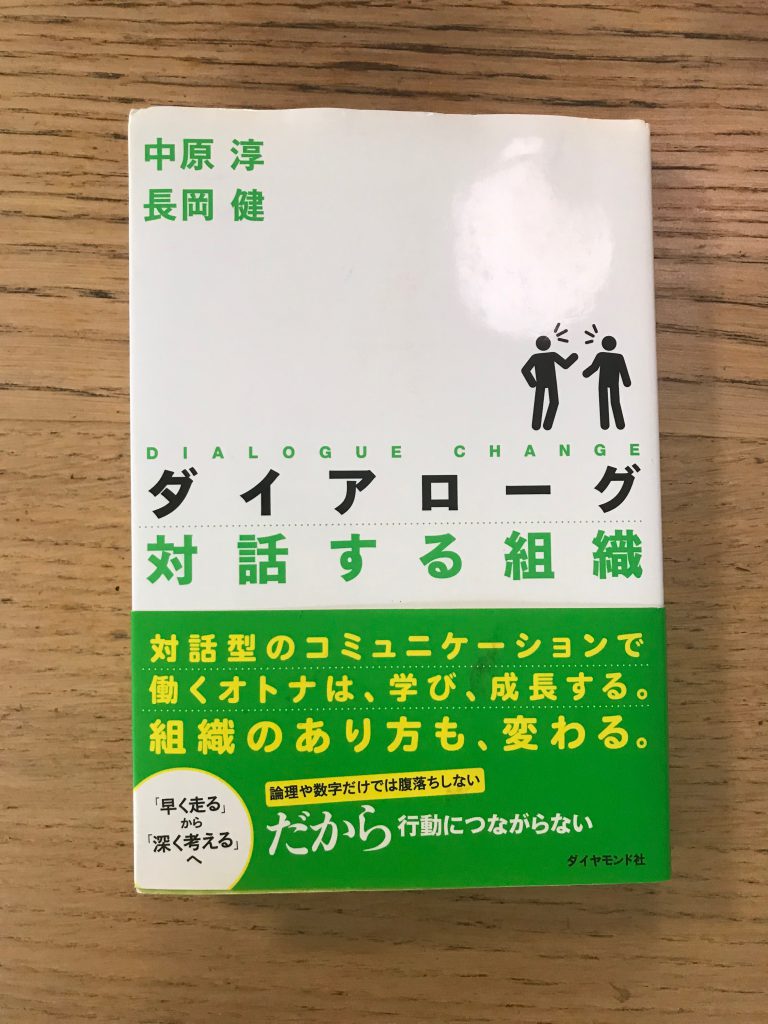第98週
2019/6/15
『ダイアローグ 対話する組織』
中原淳 長岡健著 ダイヤモンド社
私達が提供するプログラムは、ビジョンセッションでも、企業向けリーダーシップ研修でも、ダイアログ(対話)を活用します。今回はダイアログの知見を深め、プログラムを更に発展させたいと考え本書を手に取りました。
「なぜ、ダイアログが自分のビジョンを描くのに有効か」
この問いは、私達がプログラムを提供する際の出発点となる重要な問いです。私達は、ビジョンの描き方として自分を知り、社会を知り、描くとしています。自分の価値観から描く未来像が、情熱が湧きやすく継続しやすいからです。この自分の価値観、つまり「自分」を知るのにダイアログが非常に有効と考えています。
では「なぜダイアログが『自分』を知るのに有効」なのでしょうか。
本書によると、アメリカの心理・哲学者のジョージ・ハーバード・ミードが「自分とは『本質的に社会的構造であり、社会的経験の中から生じる』存在」と提唱しているとのこと。自分というのは他者がいて初めて認識できる。自分らしさは他者との相対の中で認知できるものでということです。確かに「自分らしさ」というものは、確かに無人島で生まれ育った場合、その概念すら出てこないと思います。他者を理解することで、自己理解が深まる。自己を理解することにより他者理解が深まることの相乗効果が発揮できるのがダイアログであり、だからこそ有効と考えられます。
次の問いは、「ダイアログは普通の会話(雑談)と何が違うのか」です。
本書の定義は、ダイアログとは①共有可能なゆるやかなテーマのもとで②聞き手と話し手で担われる③創造的なコミュニケーション行為、としています。この定義が大切というよりも、①~③を行っていくと、物事が意味づけられた背景が共有できるようになります。この物事が意味づけられていくプロセスを共有することがダイアログの本質であることが私の中ではっきりしました。
Aさんが私の懇意にしているBさんに対して、「私はBさんの言う事は信じられない」と言ったとします。その際、不信のきっかけとなった事象だけを聞くのではなく、その意味づけに至った背景を聞き対話をする。そうするとAさんと対立することなく、Bさんことを深く理解することができます。時に不信の根本がその人の幼少期の出来事に結びつくこともあります。人は事象(客観的事実)をどう意味づけするのかで、考えや行動が変わります。本書に「相手の考えている価値前提や行動の背後にある世界観を共有する」と書いてありましたが、これこそがダイアログのもつ力だと思います。
最後に、有効なダイアログ手法の一つとして、ストーリーモードが印象に残りました。単純に言えば、物語を語りあう。コピー機の修理工達が、学ぶのはマニュアルや研修ではなく、経験の語り合いだった。ある会社で理念を共有する際も、ただ言葉の意味を語り合うのではなく、ストーリーを語り合う場を設けて効果が出ていたなど、印象的な例が載っていました。これは自社の企業理念の浸透や、ビジョンセッションのコンテンツ拡充にも活用していきます。
(1248字)