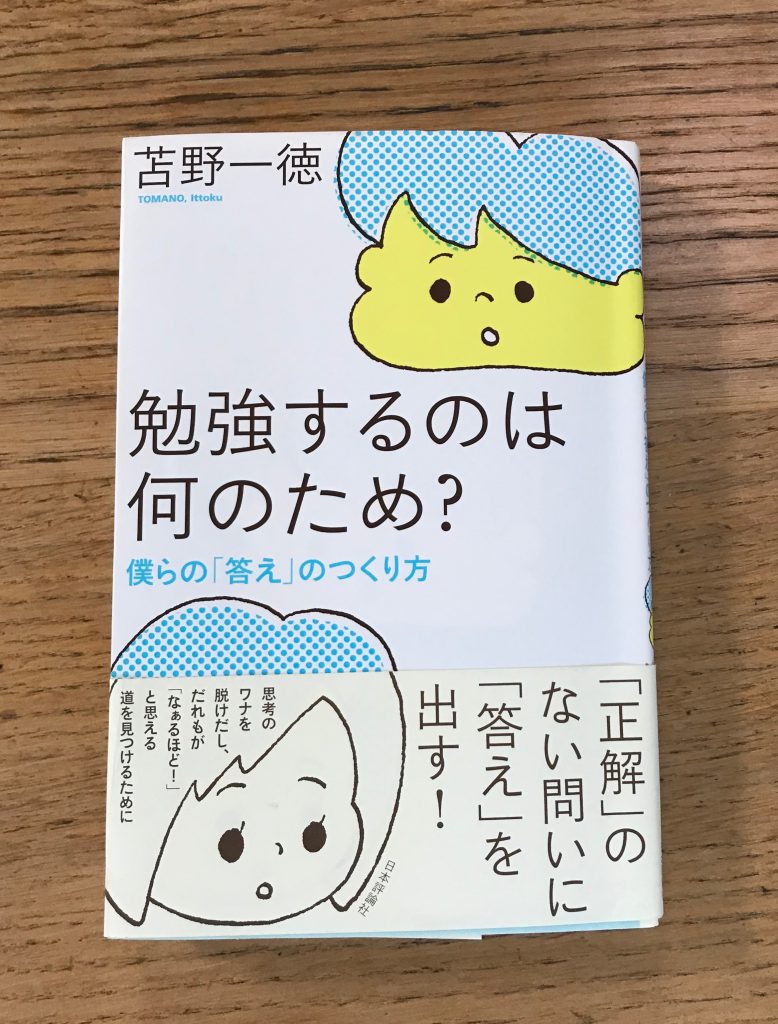今日はプライベートのことです。
先週の火曜日、やむを得ない事情から小2の息子を学校を休ませることにしました。いわゆる謹慎に近いもの。その日は仕事を含め両親が外出しているため、一人でずっと家にいることになりました。
吉田家はテレビはない(正確にいうと見ない)ため、息子は誰とも一言も話さず、本を読むか、一人将棋をするか、一人でレゴするか等していたそうです。
このまま学校に通わせることができないとどうなるか・・・想像をしてみました。
・他者接点が乏しく刺激がない
・音楽&図工をはじめとした実技ができない
・運動会の準備など学校行事に関係する活動がない
勉強は親が教えればよいのですが、それ以外のものは家庭でカバーするのが苦しいです。そもそも刺激がなく、子供から生きる活力を奪っていく感じがし、私自身とても心苦しくなりました(息子は普段活発なのでなおさら)。
当たり前に通わせている学校が、子供にとっても親にとってもこんなにもありがたいものだったのかと、痛感する1日になりました。
翌日から登校許可をし、息子は楽しそうに学校に行きました。
家庭は私自身と一心同体であり、家庭に問題が発生すると、鈍く重い感覚がつきまとい、心身に堪えることもよく分かりました。
(逆に仕事が救いになる的な)
学校というこの社会システムは本当にありがたいです。このありがたく素晴らしい日常が続くよう、パパもしっかりと子供と向き合っていきます。
★お知らせ
9/21(土)PEACE DAY2019開催!@海浜幕張
「Believe in Peace with Love」をコンセプトとして、世代、立場、すべてのジャンルを超えて楽しめる野外フェス「PEACE DAY19」が開催されます。ブルームウィルは特別会員になっており、30枚チケットがあるので、チケットが欲しい方は是非お声がけください(当日券6000円を無料でお渡し致します)。東京在住の方は少し距離がありますが、世界平和に少しでも関心がある方は是非!
URL:https://peaceday.jp/2019/
【一般財団法人PEACE DAYとは(HPより)】
一般財団法人PEACE DAY(以下、PEACE DAY財団)は「争いのない平和な世界を実現する」というビジョンを掲げ、2019年6月に設立されました。野外フェスという場を通して立場の異なる組織や個人が壁を超えて協働し、平和の実現を目指していく仕組みを創ることで、世界平和を実現したいと思っています。
代表理事として株式会社LIFULL代表取締役の井上高志、他にも様々な立場やジャンルの理事たちがそれぞれの想いをもって集まりました。また、野外フェスの企画/運営/制作チームは、野外フェス「旅祭」を主催/運営している株式会社TABIPPOと株式会社A-Worksが担当しています。