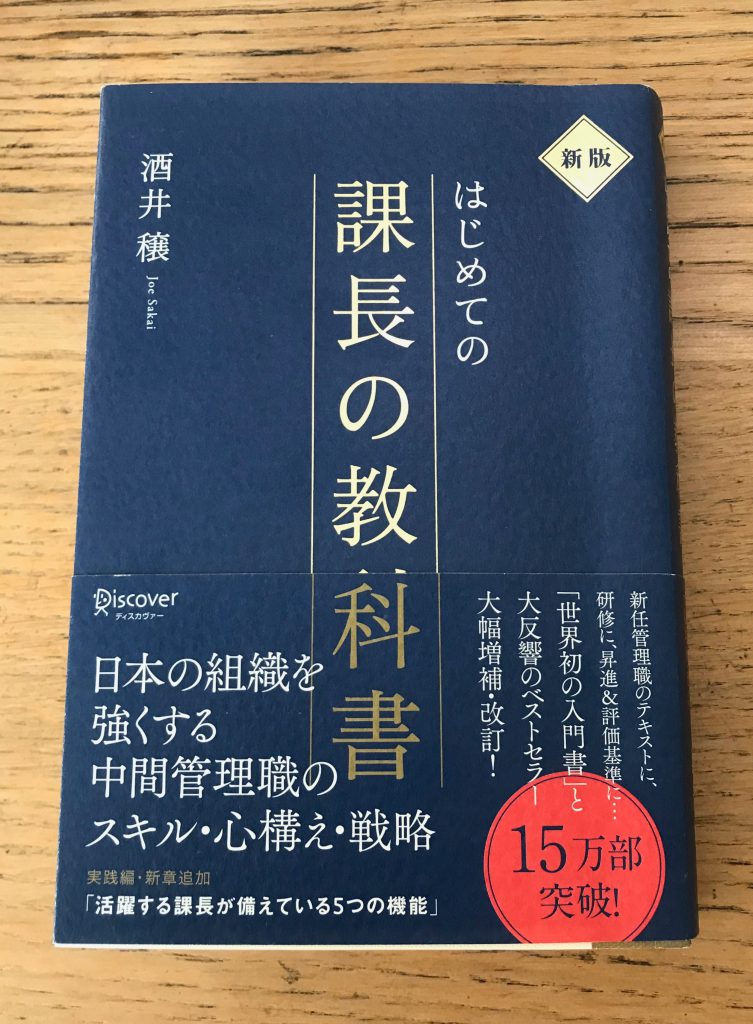先週月曜日は、日本政策学校の同期と久々会食をしました。世田谷区議に当選した方、キャリアカウンセリング協会を立ち上げた方、50歳過ぎて結婚した方など、それぞれがより一層人生を輝かせるため動いていることが確認できました。
さて先週特筆すべきは家族での出来事です。
ここ3年ぐらい会社では議論から対話へと移行をしてきていますが、いよいよ家庭でも対話を中心としたコミュニケーションを多用することにしました。その成果がでたのが木曜日のことです。
木曜日夜に、小2の息子の担任から電話がありました。言った言わない、やったやってないを含めた詳細を省きものすごくシンプルに書くと、
休み時間UNOで遊んで、ズルして上がった相手に、劇怒りをして、泣かせてしまった。
泣かせた子が、先生に通告。
先生が息子を叱り、息子爆発で授業受けられず。
ということでした。
小2の息子は感情のコントロールが課題です。喜怒哀楽の振れ幅が強く、衝突もしばしば。小2で感情のコントロール??と思いましたが、我慢せずにうまく怒りを溶かしていけるよう、親として相方と一緒に試行錯誤をしてきました。
どんな時もまずは必ず言い分は聞くように心がけています。よって今回も言い分を聞いていましたが、元々「感情のコントロール」という根本課題が頭にあるので、これまでであれば言い分を聞いてもそれは「君が悪い」と、最後ぴしゃりと伝えて終わっていたと思います。しかし今回対話を心がけると、息子の爆発ポイントがはっきりとわかりました。
・「俺だけが悪いわけじゃないのに、俺だけ怒られる」という公平性のなさが爆発ポイント。
・「勝負事で相手がズルして上がる」という公正性のなさが爆発ポイント。
・上の二つを大人が「分かってくれない」ことが最大の爆発ポイント。
最後の項目は「僕の気持ちを分かってくれない」と何度も言っていたことから発見できました。
そして対話をする中で、「爆発した上の二つは理解はできるなあ。それ君の怒りポイントだよね。うん、爆発した理由は理解できる。その上で、やはりズルしてあがった相手に劇怒りはやり過ぎだと俺は思うよ。『あ、それズル』だけでいいじゃない。」
と言ったところ、気が済んだのか、すぐに「相手に謝りの電話をする」となりました。
あらためて、対話と承認が物事を上手くいかすためのポイントだなと感じます。麹町中の工藤校長も著書の中で、対話の重要性をしきりに伝えていましたが、対話と承認が手間と時間がかかるようにみえて、実は最短距離で目標に近づけてくれることを私自身大分実感してきています。
我慢することなく、気になったらすぐ対話をしていく。これが家庭の人間関係をうまくいかせるコツなのかもしれません。