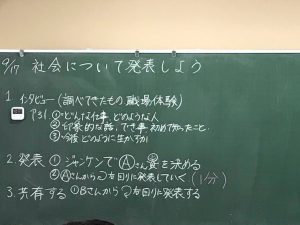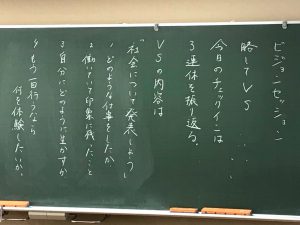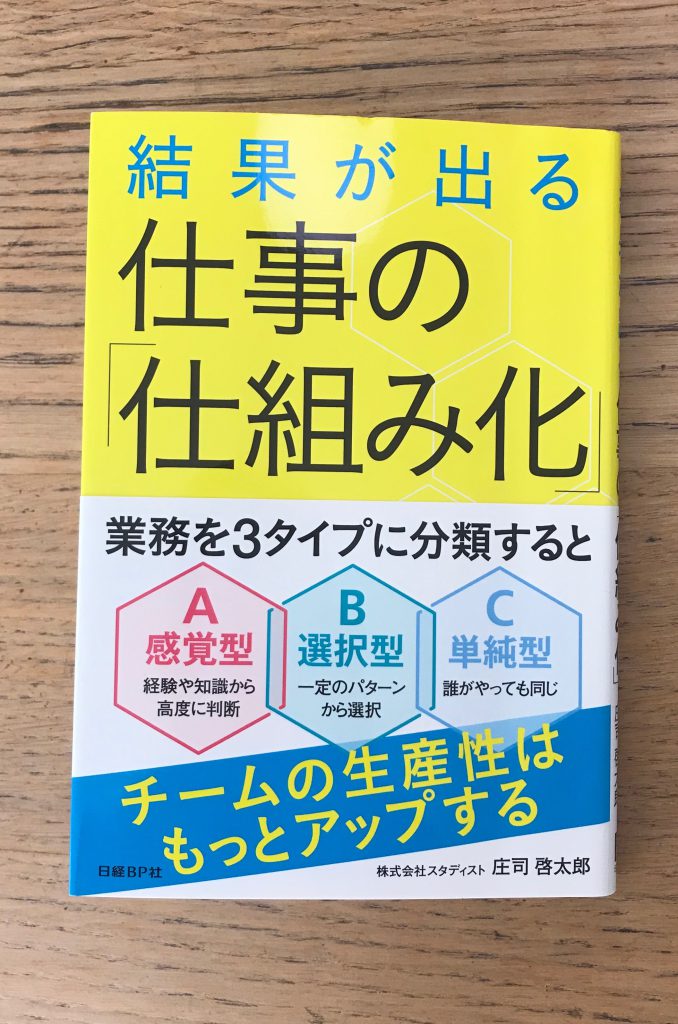第63回
2019/9/22
「母子のきずな 10章 人格発達の基礎」
【まとめ】
幼児期の経験が人格発達に重大な影響をもつことを示すものとして、米ハリー・フレデリック・ハーロウ教授のアカゲザルの赤ちゃんの研究(Harlow, 1971)がある。
アカゲザルの赤ちゃんを母親から分離。
A-1 針金製の母親の模型にしこまれた哺乳瓶からミルクを飲む
A-2 針金製の母親で非授乳
B-1 布製の母親の模型にしこまれた哺乳瓶からミルクを飲む
B-2 布製の母親で非授乳
結果として、B-1、B-2と接触する時間がA-1、A-2より多くなることが分かる。(15時間以上対1時間以内)。ここから、子ザルが母親に愛着を示すのは、母親が空腹を満たしてくれるからではない。母親との暖かい接触を求める欲求がることが分かる。
また、見知らぬ巨大なおもちゃに接触して恐怖を感じるときも子ザルは布製の母親にしがみつく。ここから暖かい接触を与えてくれた「母親」が自分を守ってくれる安全基地となること。安全基地があってはじめて積極的に自分から外に向かっていけるようになることが示唆されている。
更に、ハーロウの研究で生後母親から隔離された子ザルとそうではないサルの成長を比較した。結果、身体的には成熟しているが性行動で差異が出た。隔離されてきたオスはうまくメスを支えられず、受精できない。メスはオスの接触に怯えるとのこと。またメスは自分で生んだ赤ちゃんをすぐに放り出して逃げる行動がみられた。
最後に英ルネ・スピッツ教授(Spitz, 1946)の研究。両親と分かれて施設で育てられる乳幼児について、たとえ施設の衛生面や栄養面で十分な注意が払われていても、通常の子供達と比較して病気への抵抗力や発達の遅れ、無感動・無関心など抑うつ的傾向がみられた。
これは保育者との「母性的な」接触が少ないこと(母性はく奪)によると考えられる。
(ちなみに、スピッツ教授の研究は「愛着理論」の形成に大きな影響を与えた)
母性は必ずしも母親である必要がない。乳幼児期における応答的な「保育者」との暖かい感触が「基本的信頼感」を獲得するなど、人格発達に影響をもつ。
【所感】
非常に示唆に富む章でした。娘と息子が0歳~2歳のときよく「だっこ」と抱っこをせがむんできたことを思い出しました。特に娘はだっこから置くと泣き出す子だったので、だっこちゃん、甘えっこちゃんだなあと思っていました。この章を読むと、それはまだまだ「不安」でいっぱいだったからと推察できます。当時はあまりだっこをし過ぎると、「だっこグセがつく」なんていう話も聞いていたのですが、今しかないからと相方も私も構わずだっこをし続けていました。この章を読んで健全な発達のためには、あらためてそれで良かったのだと思います。
もう一つ「母性」提供する人は、母親や女性である必要がないということは新たな発見でした。母性は父親でも提供できるし、血のつながらない人でもできる。大切なのは「応答的な保育者との暖かい感触」と書いてありました。私の頭ではどこかしら母性は「母親が一番」と思っている節はありました。一番かどうかというより、「応答的・暖かな感触」が重要なのです。母親だから母性を、父親だから父性をというより、父親でも何でも母性提供を大切にしていきたいと感じました。
(1335字)