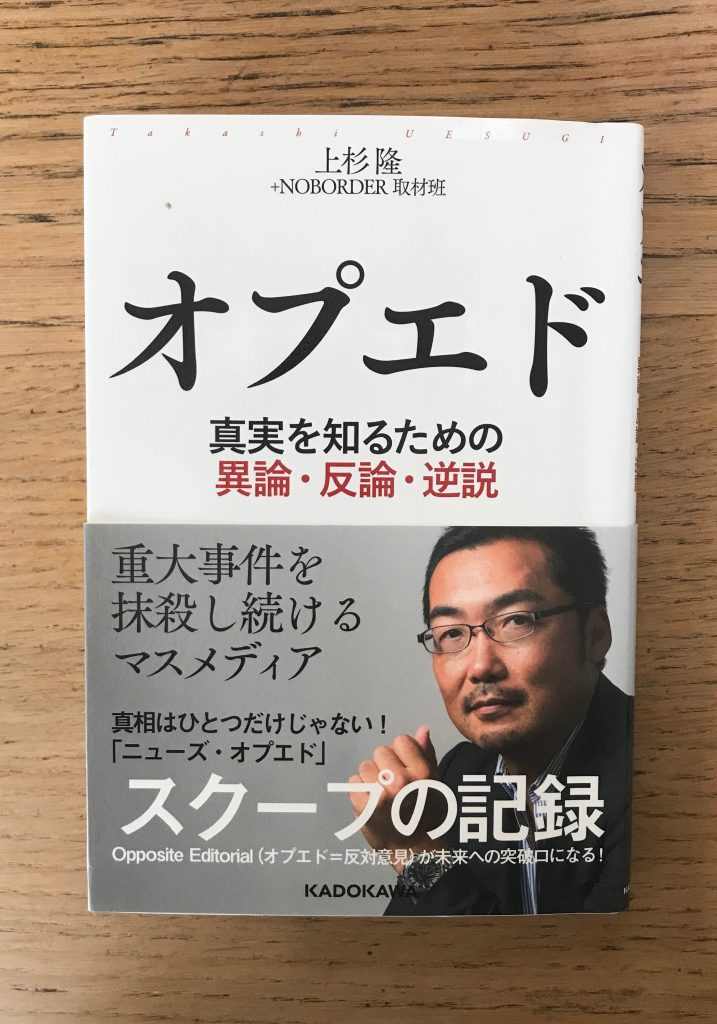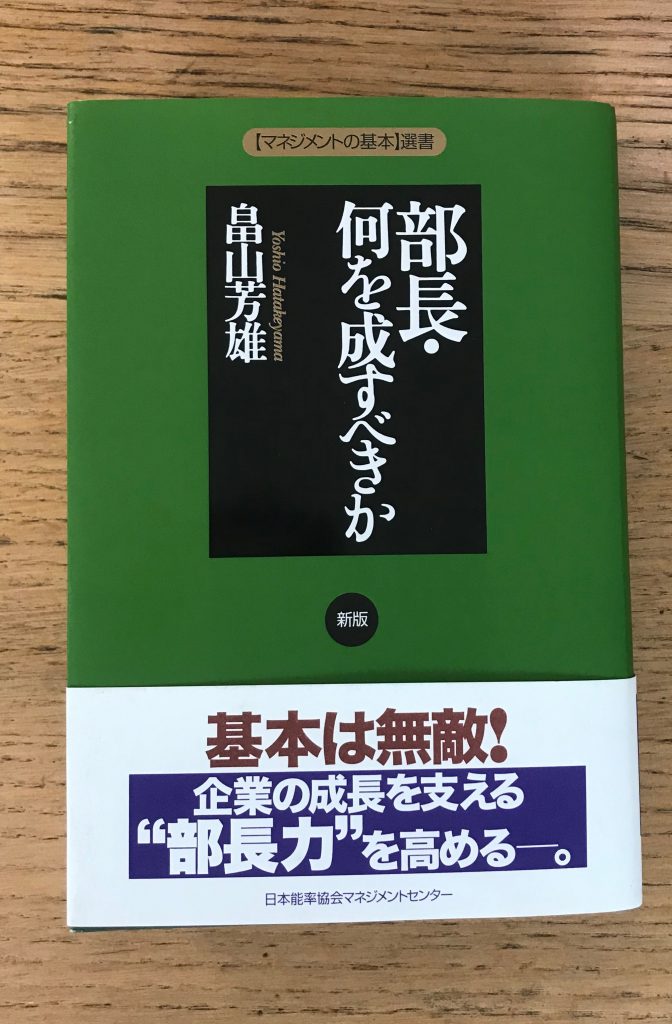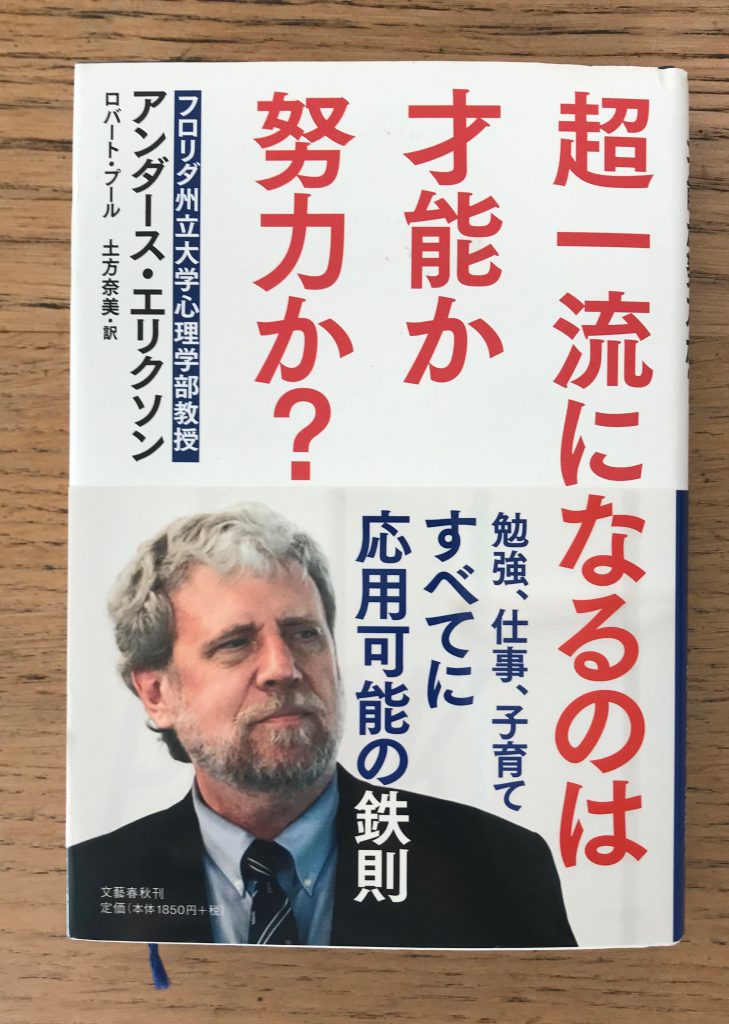先週は研修WEEKで、次世代向けと執行役員向けの2社にリーダーシッププログラム(LSP)を実施しました。
LSPではまず早い時期にサーベイをとり現状把握をします。そして1年後の最終回付近で再度サーベイをとり、変化をみる形にしています。
(サーベイは、上司・メンバー・他部署からの対象者への定量・定性アンケートです)
当初は最終回付近のサーベイのみだったのですが、現在は改変し最初と最後にサーベイをとることをおススメしています。というのも、研修時では言動やアウトプットが秀逸な一方、現場ではメンバーからの信頼を失っている方がいて、早めに参加者も私も「真の姿」を掴むことが成長には必要と痛感したからです。まず早い時期にサーベイをとり、現場での状況を可視化し、参加者と私と課題を共通認識化します。
先週は偶然、2社共に最初のサーベイ結果が出た回となりました。まず次世代の方々のサーベイ内容は皆、素晴らしすぎて感動ものでした。サーベイ結果から上司・メンバー・他部署からの信頼が厚く、今でも間違いなく現場の中核をなし、そしてこれから幹部になっていく方々だなと感じました。このような方々の成長を任せて頂けて本当にありがたい限りです。
一方で、別の会社の執行役員層も1回目のサーベイ結果が出ました。こちらの結果は個性的<笑>。ただまさに会社の中核をなし牽引する方々。新しい会社の形を執行役員の皆さんと共に創るのは大変やりがいがあり、こちらも任せて頂けるのは本当にありがたいです。レベルの高い話し合いなどがとても楽しく、しかも日々多忙を極める中、皆さん自部門の革新に活用頂いているのも感謝です。
先週まで2週間はわりとこもって制作に従事しました。今週は久しぶりに研修がありテンションが上がった週でした。自分にとっては研修で参加者に会えるのがエネルギー源だなとつくづく感じます。