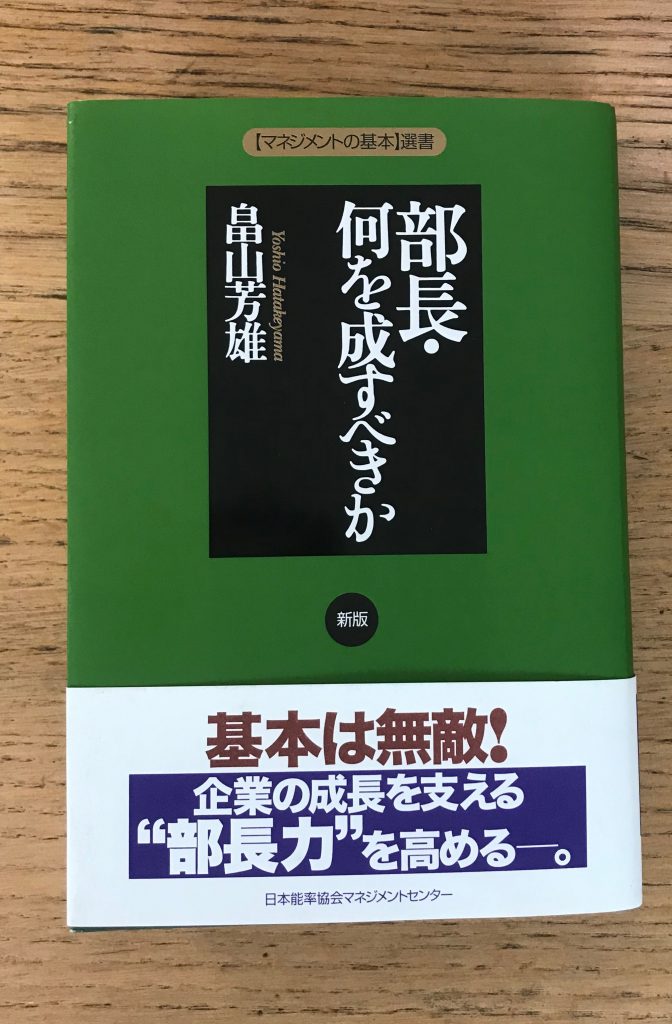第115週
2019/10/20
『部長・何を成すべきか』
畠山芳雄著 日本能率協会マネジメントセンター
私は部長対象の研修も提供していますが、「部長は何をする人なのか」という問いにはっきりと答えられる人は少ないです。それは企業が実用的な形で示せていないことも一因だと思います。人事評価制度の役職定義に書いてあることが、例えば「部長は部門の業績を最大化する」といった抽象的な表現にとどまり、実際に機能や、やり方まで具体的に示されていることは稀ではないでしょうか。研修に参加する部長に、よりはっきりと部長本来の仕事を明示できれば迷いがなくなり成長も促進できると考え、本書を手に取りました。
部長とは一体何か。
著者は「部長は改革者である」と言い切っています。部長の機能は改革機能と維持機能と二つがあります。特に改革機能が重要であり、著者は従来と異なる発想と方法で業務・人間を改革することを部長に求めています。『部長が課長と一緒になって維持業務ばかりに熱中し、実際に新しい販売方式などを生み出したり、部門の風土を改革したりすることができないようでは問題』と著書は言っています。いわば「大課長になるな」ということです。とても共感できる考え方です。
著者が示す部長の三原則(全体最適、長期視点、重点集中)は当たり前に思えることですが、改革を目的としたものであり、特に全体最適については、自社だけでなく、国内外の業界や国内外の社会情勢をも鑑みる重要性を伝えています。これも私達が訴えていることと通じます。
『改革の新発想を経営者に先手で出され、後手に回ってしまう部長がどの会社でも多いが、それは経営者層が部長よりも他業界の経営者や幹部に接し、その情報を得る機会が多いだけにすぎないようにも思われる。』も同感であり、経営層より先に改革のアイデアを出せるよう、「経営層に先を越されるな」という合言葉と共に、アンテナを張り外に出る重要性を研修内で伝えられそうです。
また部長が事業改革者になれない理由も大変参考になりました。それは自縄自縛をするから。ある限界事業化しつつあった事業を任された事業部長に、人件費や販促費をかけてシェアを大きく伸ばすか、同業をみつけてM&Aをするかなどの選択肢を著者から当該事業部長に伝えました。すると『「そうした根本的なことは、トップの考えることで、こちらは示された枠内で、どれだけ生産や販売の効率を上げられるかが問題だと考えていました。」』と返答されたとのこと。この「枠内発想」は感覚値ですが多くの部長が囚われていることであり、この辺りの自縛を私が解き放てれば、部長陣は更に伸びると感じます。
(1046字)