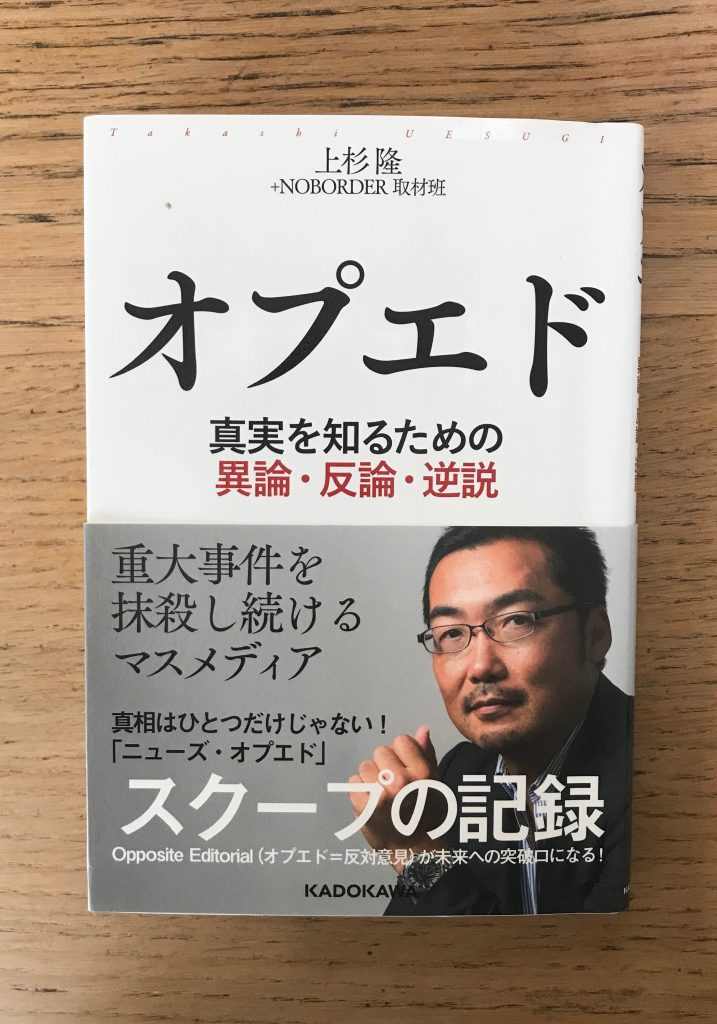第66回
2019/10/27
「クライアント中心療法 10章 カウンセリングとは」
【まとめ】
最終章。カウンセリング、神経症的な問題の治療という側面が強調されるときは心理療法という言葉も使われる。本書では下記の3つを紹介する。
1.クライアント中心療法
2.行動療法
3.認知療法
クライアント中心療法について。アメリカの臨床心理学者カール・ロジャーズ1940年代によって提唱された。
(Carl Ransom Rogers、カウンセリングの研究手法として現在では当然の物となっている面接内容の記録・逐語化や、心理相談の対象者を患者(patient)ではなくクライエント(来談者:client)と称したのも彼が最初である。1982年、アメリカ心理学会によるアンケート調査「もっとも影響力のある10人の心理療法家」では第一位に選ばれた。Wikipediaより)
クライアントは潜在的に自分で問題を解決していく力をもっている。治療者の役割は、一定の制約はあるもののできるだけ許容的な空間をつくり、クライアントが自由に自己を表現し、自分で問題を解決することを手助けすることにあると考えた。横の関係を重視。
ロジャーズは、自己概念と経験2つの輪でカウンセリングの概念を図示している。母親が夫に捨てられた女性。父を憎み、その嫌悪を実際に「経験」したとすると自己概念と経験が一致する(領域I)。しかし、父親のある側面が好きという経験をすると自己概念と一致しないので意識されない(領域III)。それが父と似ている部分が自分にもあり恥ずかしいことだと、自己概念に折り合いがつくよう歪んだ形で意識に現れる(領域II)。
クライアントでは両者のずれが大きく、それが不安や混乱をもたらす。カウンセリングの目標はこの不一致な状態から2つの円がより重なる一致した状態を目指すことともいえる。
ロジャーズは、その為にカウンセラーの理想的態度として、「一致している」、「無条件の肯定的配慮」と「共感的理解」を経験していることを挙げ、それがクライアントに伝われば、クライアントはより自己一致する方向に人格を変化させるとしている。
【所感】
カウンセリングの中枢部分の理解が進む大変貴重な節でした。自己概念と経験の不一致が不安や恐怖などの情緒的な問題を引き起こすと理解ができました。経験の解釈が大切であり、それが自己概念によってかなり左右されるのです。この辺りもう少し掘っていき、自分にとって役立てる、例えば自分自身の不安を解消する材料にするなどしていきたいです。
ロジャーズは人格変化の条件を提示し、カウンセラーの心構え的なものを説いていますが、これはカウンセリングの場だけでなく、日常生活でも起こりえることとしています。家庭や学校、職場など人と触れる所では起こりえることです。私共の研修でも変化する人が多いと言って頂きますが、それは「一致」「肯定的配慮」「共感的理解」がある程度できているからかもしれません。特に肯定的配慮と共感的理解は大切で、実践課題に取りくむマネジメント職に決して無理強いはせず、大変な状況に共感しつつできることを一つだけでもという姿勢を貫いています。すると忙しい中でも実践する方々が多くなります。引き続きこの姿勢を大切にしていきます。
(1309字)