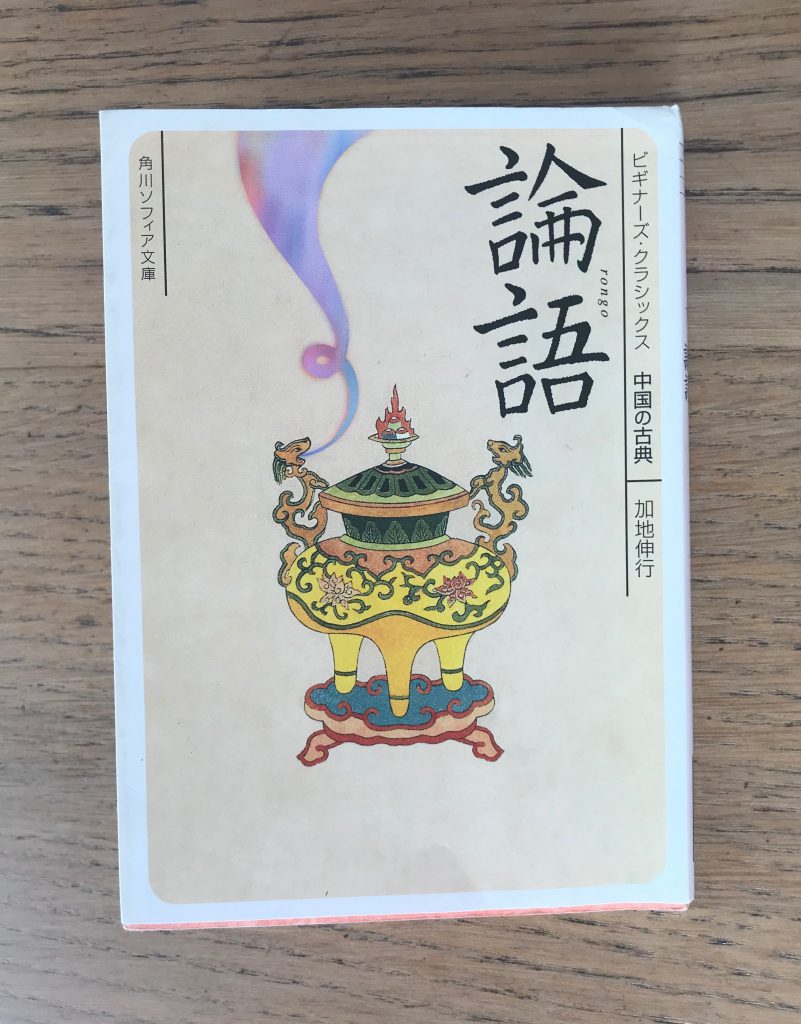第117週
2019/11/4
『論語』
加地伸行著 角川ソフィア文庫
日本人に膾炙(かいしゃ)されている本書。報徳仕法の源流をたどるべく『大学』に続き、手に取りました。今回は「今の私」の琴線に響いた4つの文章を挙げます。
1.『子曰く、吾 十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う(したがう)。七十にして心の欲する所に従いて、矩を踰えず(のりをこえず)。』(為政篇四)
耳順うの訳は『他人のことばを聞くとその細かい気持ちまで分かるようになった』。矩を踰えずの訳は『(自分の心の求めるままに行動しても)規定・規範からはずれるというようなことがなくなった』。
有名な「不惑」や「知命」がある文です。恥ずかしながら六十と、七十があるとは知りませんでした。自身におきかえると、孔子の生き方から大体10年~15年ぐらい遅れているかもしれません。私は二十五辺りから多読を開始し、四十にしてようやく自らの力である程度生活が安定しはじめました。四十にして惑わずの訳は『自信が揺らがず、もう惑うことがなくなった』。私は現在四十一ですが、まだこの境地には到達していません。修練あるのみです。
2.『子曰く、学びて時に之を習う。また悦ばしからずや。』(学而篇一)
訳は『(不遇のときであっても)学ぶことを続け、常に復習する。(それは、いつの日にか世に立つときのためである。)なんと心が浮き立つではないか。』
孔子には不遇の時代があったそうです。そのような時でも希望をもち学び続けるという楽観的で今を楽しむこの感覚に少し癒されます。
3.『子曰く、知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は懼れず』(子罕篇二十九)
訳は『老先生の教え。賢人は迷わない。人格者は心静かである。勇者は恐れない。』
自身におきかえると、未だ迷い、心騒がしく、恐れる、と耳の痛い文になります。しかし、この文は知性のある子貢、心優しい顔淵、勇気ある子路と三人の優秀な弟子の特色を指したものだそうです。全部ではなくても、どれか一つからまずはその境地に到達すればよいと解釈しました。ちなみに、自分としては勇者が一番心惹かれます。
4.『子曰く、君子は矜なるも争わず。群すれど党せず。』(衛霊公篇三)
訳は『老先生の教え。教養人は誇りをもっているが他者と争わない。共同生活はするが徒党は組まない。』
若い頃は自身の意見を通そうと、論破するべくよくいさかいを起こしていました。しかし勝ったとしても遺恨を生み、人間関係に支障を来すこともあります。論語の数ある文章の中で、自戒としての文を一つ選ぶとすると私はこの文になります。染み入ります。(1070字)