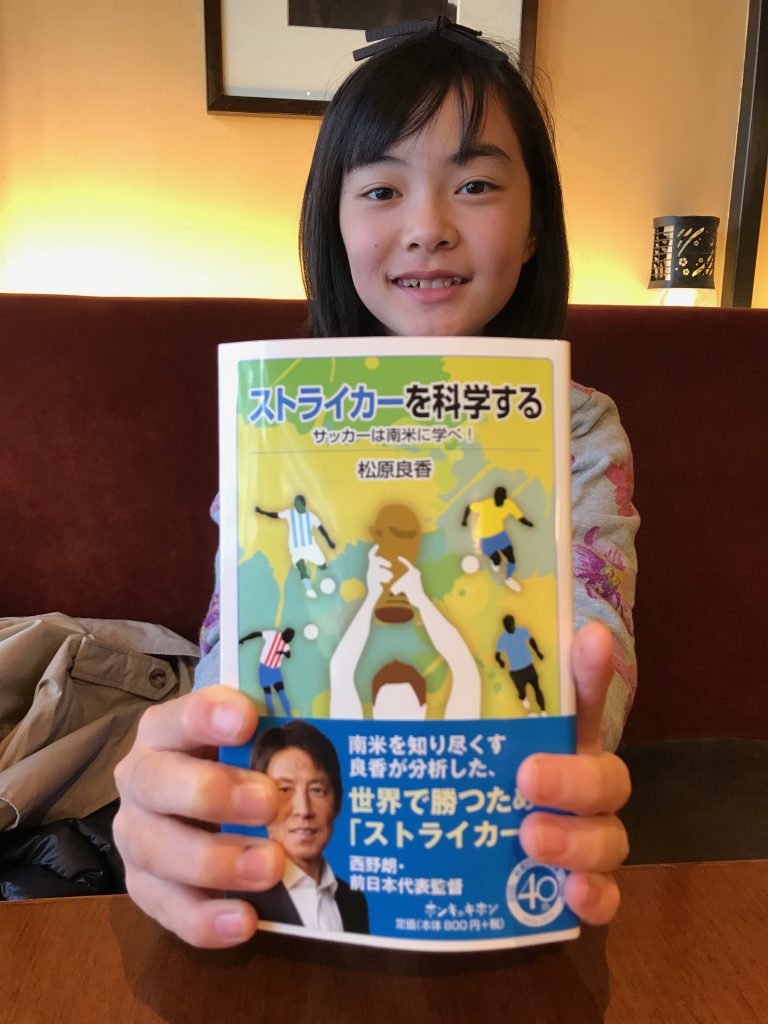第67回
2019/11/10
「行動療法①系統的脱感作法 10章 カウンセリングとは」
【まとめ】
3つの心理療法
1.クライアント中心療法
2.行動療法
3.認知療法
今回は行動療法について。心理学が対象にすべきものは意識ではなく、客観的に観察・測定できる行動を対象にすべきであるという考え方。ジョン・ワトソン(Watson, 1913)が提起。(ワトソンは行動主義心理学の創始者 wikipediaより)
スキナーやパブロフの学修理論はこの考えによるもの。
系統的脱感作法。ジョセフ・ウォルピ(Wolpe, 1958)が提唱。(感作とは繰り返される刺激によって反応が徐々に増大していくプロセス)
脱感作法は不安と相容れない反応を引き起こし、不安反応を全面的ないし部分的に抑制する方法。弛緩(リラクゼーション)、呼吸(深呼吸)、摂食(何かを食べる)。
①患者の不安反応を抑止できるリラクゼーション反応を習得させる
②患者に不安反応を引き起こす刺激場面を挙げさせ、不安階層表を作成する
③不安階層表の各場面の容易なものから順番に患者をイメージさせ、引き起こされた不安をリラクゼーションによって制止。これを繰り返す。
【所感】
感情のコントールは大人でも難しいこと。子供であったら尚更です。息子は2年生からアンガーマネジメントに取り組んでいますが、その手法の一つで妻から提唱されたものに、「爆発しそうな場面でハンカチを吸う」というのがあります。このハンカチは妻の香水がつけてあり、実際に息子に聞いても「いやなことがあって爆発しそうなとき、ハンカチを吸うと落ち着く」のだそうです。これが今回勉強した「行動療法」だったとは露知らず。妻が我流で考案した落ち着き法だと思っていたのですが、勉強して考えた策でした。(先程妻にDBT(弁証法的行動療法)の本を手渡されました<笑>)。
私自身も不安にさいなまれた時、自分に意識をむけ深呼吸するようにしています。完全に不安を払拭することは生きている以上難しいと思います。しかし、少しでも楽に、生き生きと進むには俄かに起こる不安と上手くつきあっていくことが大切ではないでしょうか。自身の心身で行動療法を試していきます。
(866字)