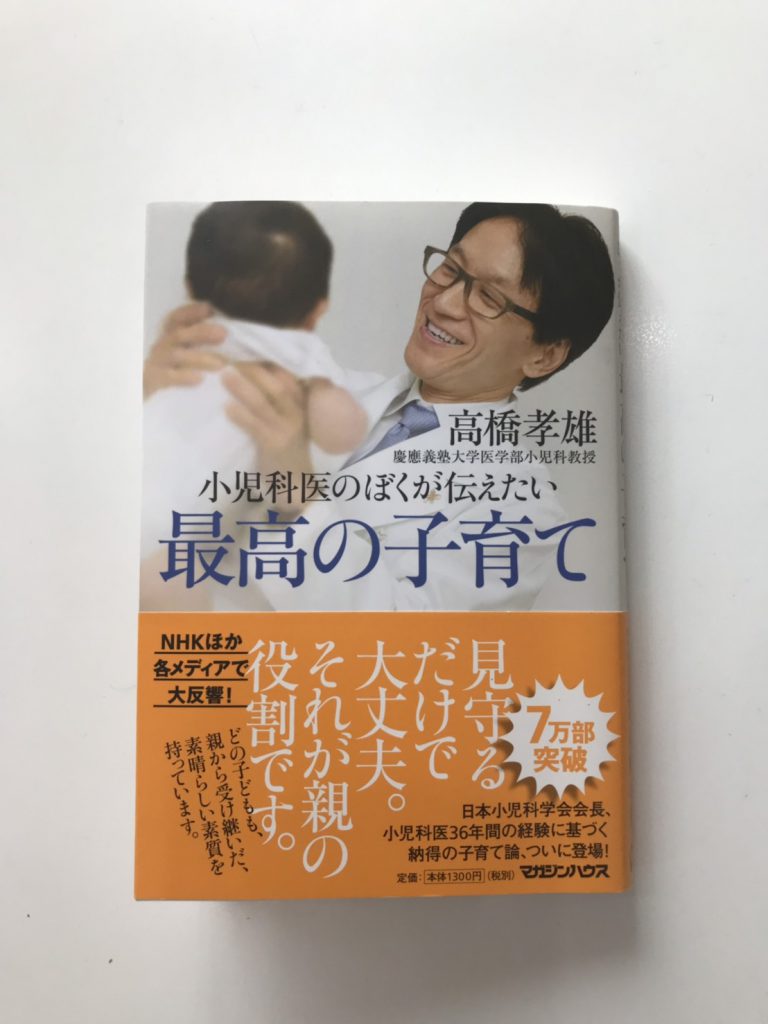今回は学習塾咲心舎の話です。
咲心舎は4月より全学年高橋に任せているため、あまり週の風景にもあがってきませんが、塾生の動向などは高橋の日報で毎日確認しています。先週は2学期の期末試験が近隣の学校全て(千川中、西池袋中、明豊中、板二中)で行われました。それに合わせ高橋も集中指導を行っていましたが、手ごたえ云々というより、高橋から「やはり生活リズムがちゃんとしないとダメですね。なんだかんだ言って、成績が伸びない子は、スマホで夜更かしとかしているんですよ。」という切実な声があがってきました。そして12月から塾生個々が毎月書いている「ビジョン実現シート」に、勉強課題ではなく、生活課題への取り組みを必ず入れてもらうとのことでした。
学校の授業理解がされていない塾生が散見されたため、9月から高橋は学校の授業の聴き方に切り込み、ノートチェック及び、適切な授業の聴き方=先生の話をメモることを指導してきました。そして今度は生活リズムに切り込んでいくことに。携帯使用のガイドラインを設けてはいますが、やはりそれだけでは生活リズムは整いません。塾がどこまで踏み込むかは難しい所ですが、目の前の子供の学力を上げることに一番熱のある人が促進していけばよいのだと思います。塾も研修もまずをもって大切な事は、目の前の参加者の成長にどれだけ情熱を注げるか。実施者の熱の高まりに必ず参加者は呼応します。高橋の更なる熱の高まりを感じた週でした。
今週は、大切な方々との会食が多く入っている週です。体に気をつけて走ります。