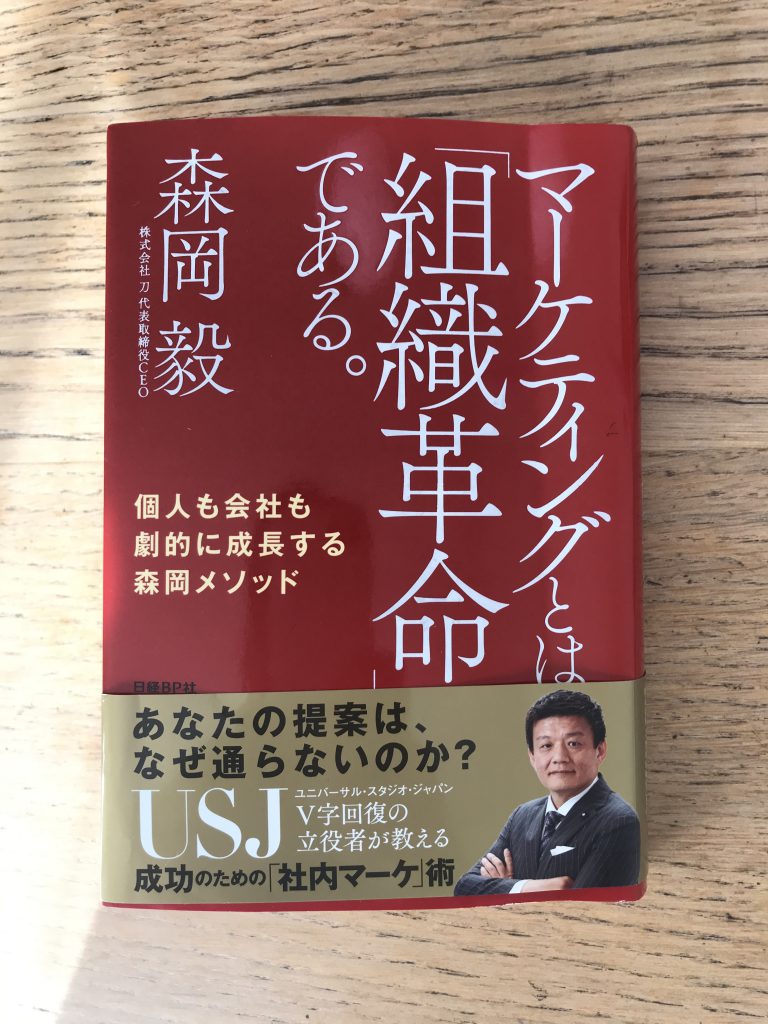仕事納めの先週はプログラム制作WeeKでした。
特に部長向けリーダーシップの新プログラムは相変わらずうんうんとうなりながら、制作していました。参加者の顔や場面を想像しながら決めたものを、一晩寝かして翌日またやっぱりこっちだと変更するなど、納得のいくものに仕上げるべく往来を繰り返しました。例えば社会環境の分析を何年後の社会に設定するのか(社会軸)、会社全体の分析を何年後の会社に設定するのか(会社軸)、そして自部門のビジョン設定を何年後のものにするのか(ビジョン)は、その企業様や同じ企業内で職種によって、いや究極人によって異なります。リアリティをもって燃えられるのは何年後の目標かというのは、個々によって違うものです。パワポ資料に反映されるのはただ年数だけ。よってパワポを打ち込む時間はわずか3分。しかしその3分までに、日をまたいで何年後がよいかなーと考える訳です。
考えてみると、起業して6年半以上、平均毎月10日ぐらいはプログラム制作の時間があったと思います。質を第一に、1社1社、1回1回作りこんでいくためこのように多くの時間をかけることになりましたし、中々生み出せず苦悶する時間も多かったです。ただ、営業側の人間だった自分が、自分の手で創り届けるという「ものづくり」の感覚や喜びを感じることができました。クライアント企業様がいたから体験できたことであり、心から感謝しています。本当にありがとうございます。
今年も色々とありがとうございました。起業してもうすぐ丸7年が経ちます。実は自分としては大きな決断をし、新たな挑戦も開始します。今はその準備なども進めていますが、是非また良いタイミングでお伝えしたいと思います。来年も宜しくお願い致します。