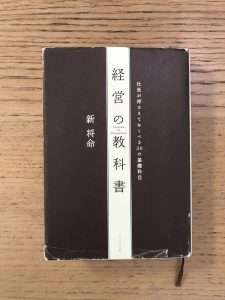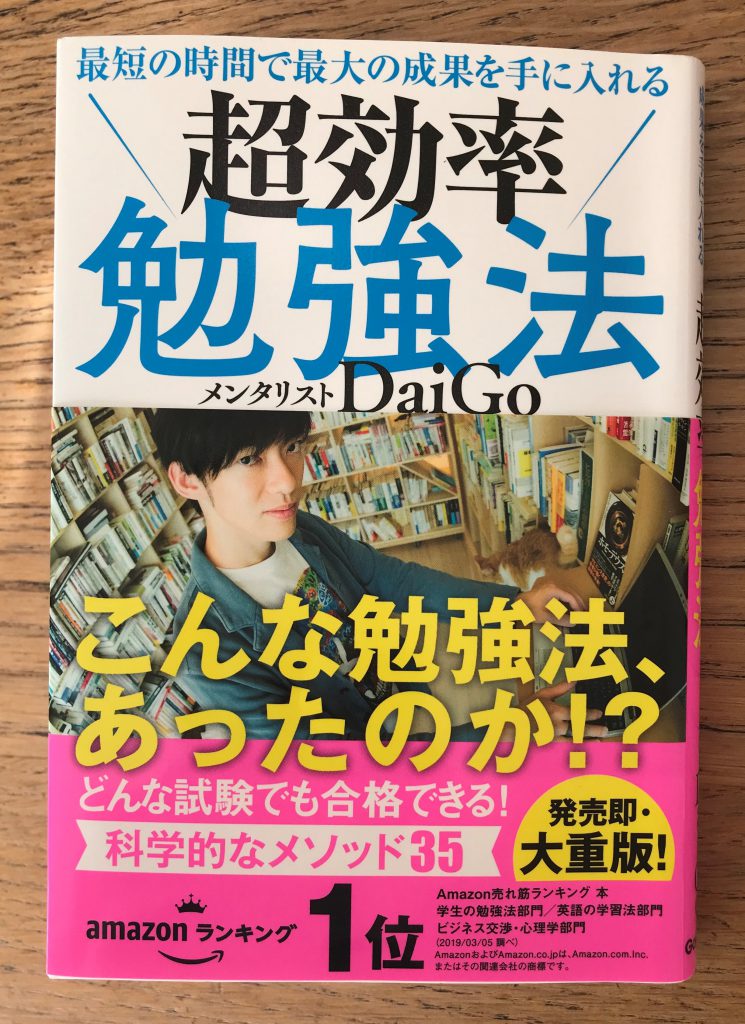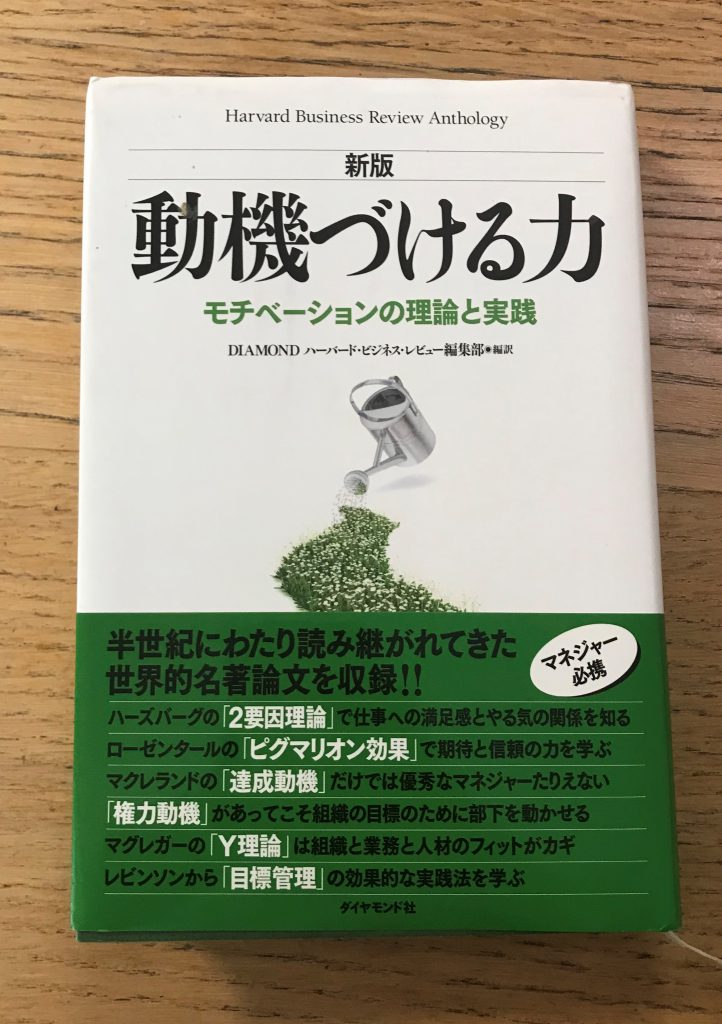引き続き年初から研修などで忙しくしており、ありがたい限りです。正直、研修や会食など書きたい事が沢山あります。その中で一つ書くとすれば先週はやはり創業期からお任せ頂いているモバイル通信会社様のマネージャー・店長研修の最終回のことです。
9月に一旦本編は終了し、自走期間を経てこの1月にサーベイをとり先週の木曜日に研修を実施しました。そしてこの会社様は当日懇親会時に毎期MVPを表彰するのですが、今回は迷いました。というのも今回は全員受講姿勢が抜群で、現場実行度が高く、また成果としても10ヶ月で収益を上げた方が多かったからです。これは人材開発の方々が研修転移策を設計し、実践されたことによります。
※9月に書いたブログです(「過去最高の成果」)。
http://muneoki-yoshida.com/wp/wp-admin/post.php?post=820&action=edit
その中でも抜けた成果を上げた方が4名。更にしぼって突き抜けた成果を出した方は2名。実行(サーベイ結果)、成果、変化の3軸でMVPを決めるのですが、人材開発の皆様とも意見が割れ、嬉しい迷いとなりました。
そして決めたMVPの方、つい半年前はそこまで豪胆なタイプではなかったと思います。それが今は高い目標を掲げ挑戦することにある種の快感や楽しさを覚えたのか、店長会議でエリアの上司や他店長が「大丈夫か?」というぐらいに「高い目標」を掲げ、まず初月達成をしたとのこと。これまでの延長線上の成長ではなく完全に違う路線に入った印象で、これこそが私が追求する劇的成長です。純粋に嬉しいですし、ひたむきな取り組みと成果創出に本当に感謝です。
ふと考えると6年前は、まず実行レベルで大変だった社員の方が、成果で競うようになり、今は非連続の成長が決め手となる。激動の通信業界の中で、会社がどんどん進化されていくのを感じます。私ももっと進化しなくては。
今週は報告、そして制作WEEKです。