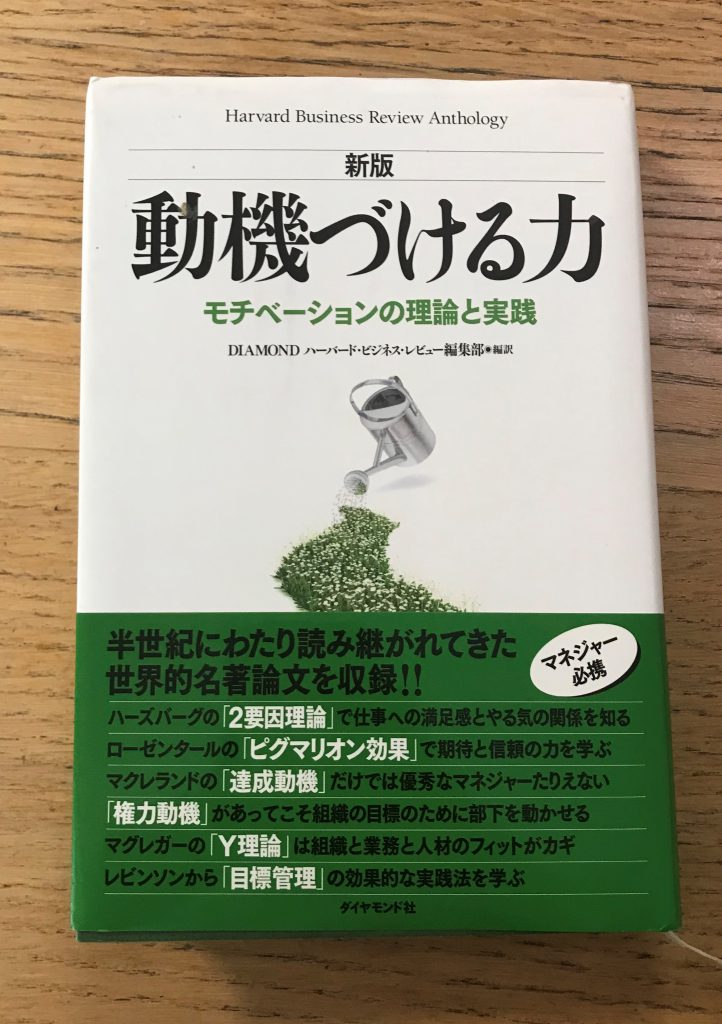第126週
2020/1/12
『動機づける力 モチベーションの理論と実践』
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部 ダイヤモンド社
学術研究により生み出された考察や理論は、数多の情報が氾濫しエビデンス重視の現代においては重要性を増していると感じます。本書は代表的なモチベーションの理論と実践を集めた論文集です。今回私達の研修でも言及しているハーズバーグの2要因理論について新しい気づきを2つ記載します。
一つ目は、『KITA』という言葉。論文の冒頭に出てくる言葉で、「尻を蹴飛ばせ:Kick in the pants」の文字を組み合わせています。そしてKITA的な施策はモチベーションにならないと筆者は言い、効用が乏しいのにも関わらず次々にKITAが生み出されていく流れをシニカルに描写しています。
まずKITAは①労働時間の短縮②賃上げ③フリンジベネフィット(諸手当)からはじまります。しかし、効果が出ず社員の金銭欲も怠け心も飽くことがないことがわかったとき、マネージャーが人間の扱い方を知らないことが原因とされます。そこで④人間関係トレーニングが導入され、その後自分を直視する必要性が生まれ⑤感受性のトレーニングへと移行します。更に、より他者との関係を考える⑥コミュニケーション論が導入されますが、モチベーションは喚起されず、一方的なコミュニケーションが原因とされます。この流れから⑦ツーウェイコミュニケーションの必要性が叫ばれ、モラールサーベイ、提案制度、労使双方のコミュニケーションが開始されます。しかし、これでもモチベーションは改善されず、人間は自己実現を欲するものという心理学に焦点があたり、ネジを締めている行員に「シボレーを作っている」と教えるなど⑧仕事への参画意識をもたせる取り組みがなされます。それでも意欲喚起が難しいため、社員は何か患っているという結論を出し⑨カウンセリングが導入されます。『使い古された積極的KITAが飽きられると、また新種が開発さていくわけである。』とあるように、著書曰くこれらの施策はあくまで全てKITAであると主張しています。
現代で使われている様々な施策が、50年以上前に一巡していることが驚きです。著者は『KITAの効果は短期的である』と言い切っており、アメとムチの効果が一時的であることに強い裏付けとなります。
もう一つは、『仕事の充実化』(Job enrichment)という造語です。これは『仕事の拡大』(Job enlargement)へのアンチテーゼです。著者は、動機づけ要因をうまく操作し、仕事の充実化を図れば社員のモチベーションは持続すると主張しています。仕事の充実化の手法として、より高い目標数字の設定や、同種の仕事の増加という「水平的職務負荷」ではなく、権限と責任を増やし、統制を省くなど「垂直的業務負荷」をかけることを提唱しています。実際の実験でも、「垂直的負荷」を新たに導入したグループの業績格差が半年で10%以上の差となりました。ちなみに、最初の3ヶ月は新たな業務への不安などから、業績が下がっていることも注目です。
まとめると、著者は『苦痛を避けようとする動物的な欲求ではなく、心理的に成長しようとする人間的な欲求』を重視し、人間の心の奥底にある向上心に着目しています。メンバーから給与や休みの不満を言われているマネジメント職に『仕事の充実化』という言葉を含め、新たな手法を伝えていけそうです。
二次情報ではなく、原文、原典という一次情報に触れることは、対象となる項目の根本理解に必須であると再認識しました。論文系は完読するのに物理的な時間を多く要しますが、今年10本程度は挑戦したいと思います。
(1456字)