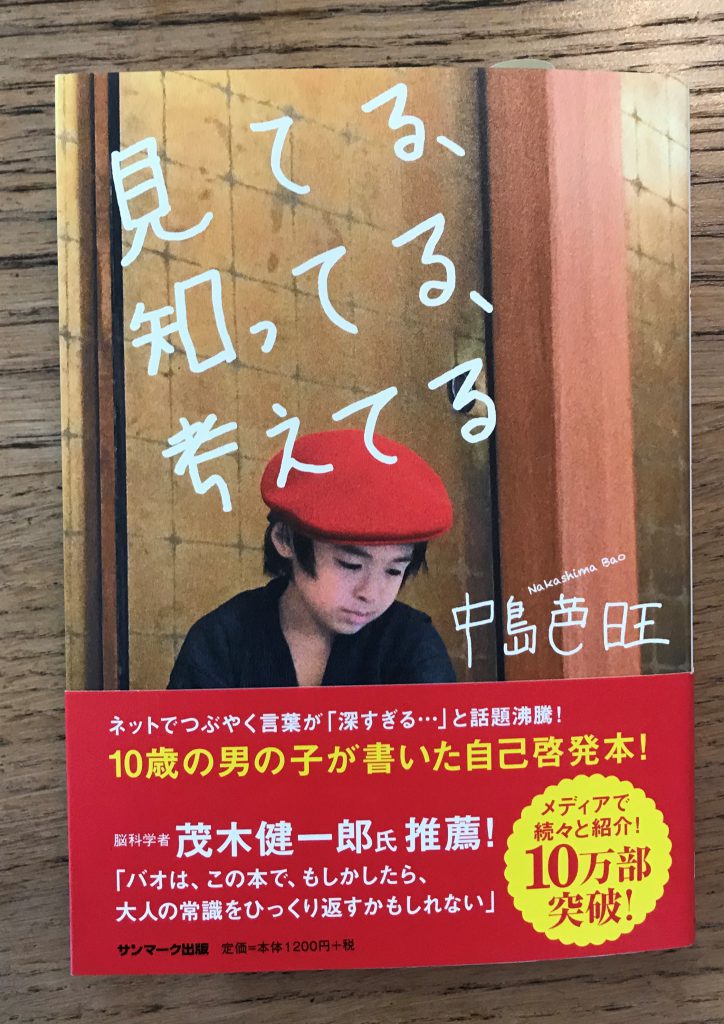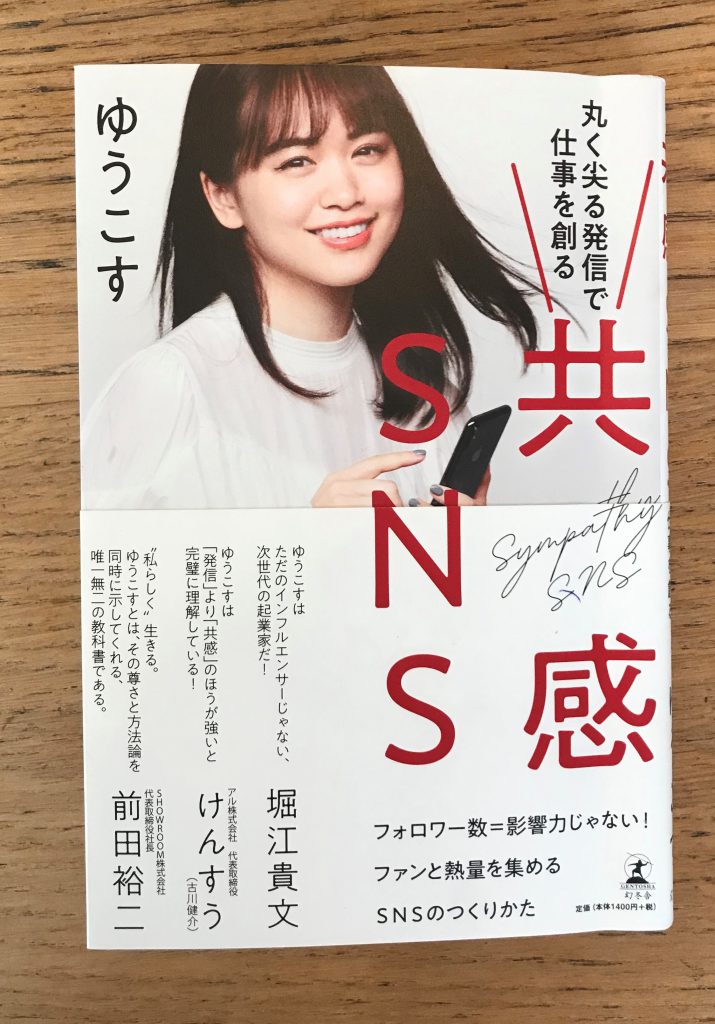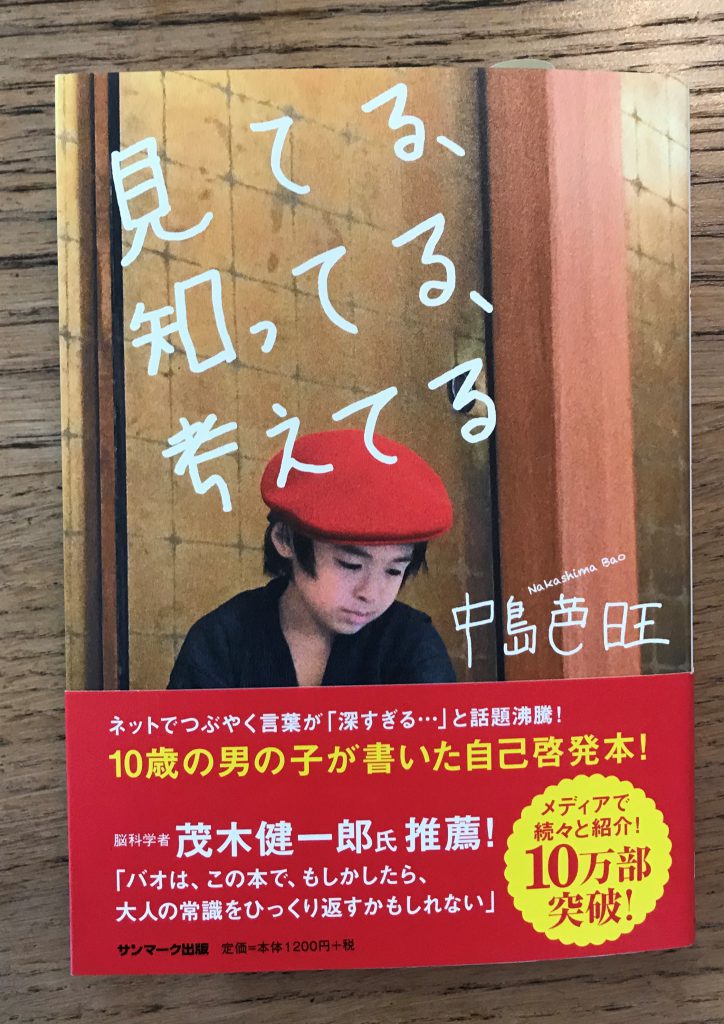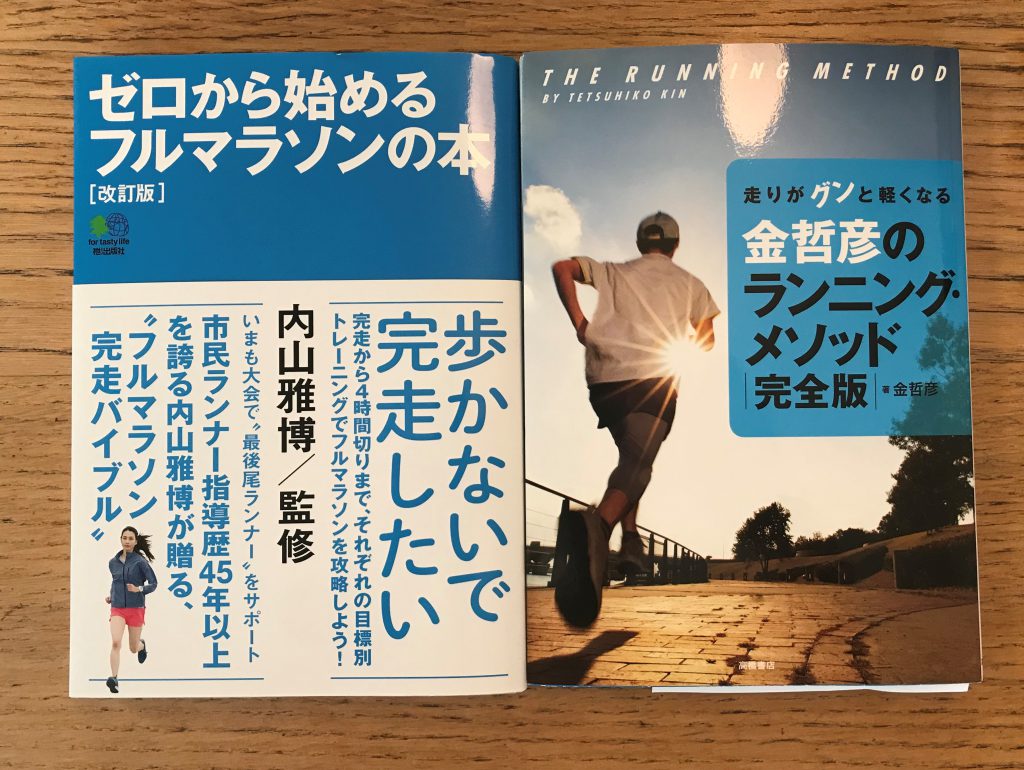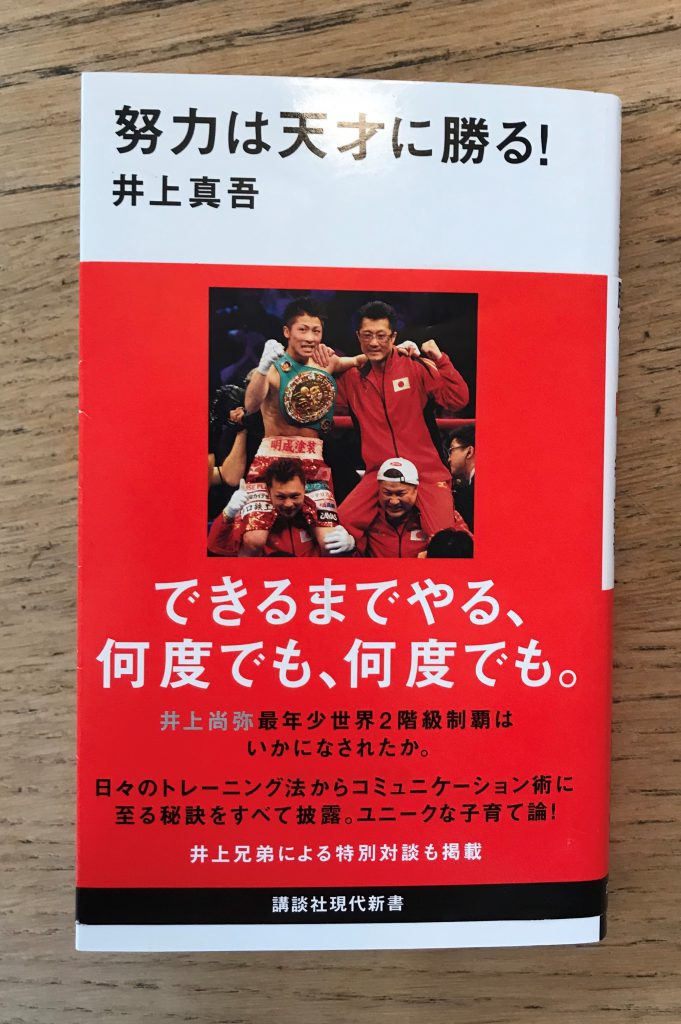第140週
2020/4/20
『見てる、知ってる、考えてる』
中島芭旺著 サンマーク出版
先日、片付けコンサルタントの「こんまりさん」等を世に出した名編集者、高橋朋宏さん(タカトモさん)とお会いする機会がありました。数々のベストセラーを出してきたタカトモさんが手がけた中で、「言葉の力」がよく分かるものとして薦められたのが本書です。
本書は小学校に通学しない10歳の男の子、バオ君の「つぶやき」を書籍化したものです。
1
「僕は泣くなって言われた事がありません。
泣いていい、
悲しい気持ちは涙が流してくれるからって、
いつも言われていました。」
このつぶやきから本書は始まります。いきなり胸に突き刺さります。涙腺が緩く1日1回以上は必ず泣く息子に、小学生になって以降「泣くのはやめなさい」と言ってきたからです。
ここから、沁み込んだ言葉を5つ記します。
6
「自由にやっていいよ!
でも、ゲームはダメだよってどっちだよ!
自分で選んでいいよ!
でも、ゲームはダメだよってなんだよ!
好きにしていいよ!
でも、お母さんの好きなやり方でねーって
もっと子供を信じたら?
自分の子供だよ?」
・・・。これもぐっと言葉が刺さります。そうですね。親は本当はもっと子供を信じたいんですよね。最近小言が多くなっていた気がして、もっと褒めよう、見守ろうと思います。
25
「どうなりたいかという質問に僕は、
『僕は僕でありたい』と答えている。
世界中みんなが自分であるということは
正解がないということ。
正解のない世界でいきていく僕達は、
好きなことをやる勇気が必要だ。
自分の勘を大切に。
自分に正直に。
自分が好きなことをやる勇気。」
いつの時代だろうと、人生には元々「正解がない」ということを10歳で結論づけていることに驚きました。正解がないから「好きなことをやる勇気」が必要、というロジックも素敵です。皆さん、好きなことやってますか?
71
「『こわい』は、やりたいということ。
やりたくなかったら『やりたくない』って思う。
『こわい』ということは、やりたくないわけではない。」
凄い言葉です。勇気をもらえました。こわいはやりたい。研修でも伝えていけます。
80
「今年の僕がもらったクリスマスプレゼントは
ママが生きてて笑っていてくれるってこと。
大切な人は生きていて笑っていてくれれば良い。やっとわかった。」
ママが風邪で寝込んだ場面のことが2ページに渡りつづられ、その後の最後の部分だけ抜き出しました。毎日妻や子供達に「いてくれてありがとう」と伝えようと思います。
83
「自分では気づかないが、
自分の未来は分かっているんだと思う。
だから僕は勘を信じる。」
私達一人一人(の脳)は既に自分の人生を分かっており、人生とはそれを明らかにする過程であるのではないかと最近、私は感じています。僕も自分の勘を信じます。
私は、書籍は出会いだと思っています。固いビジネス本ではなく、こういった柔らかい本を時折読みたくなるのも今自分が必要としているからです。だから沁み込みました。
(1194字)