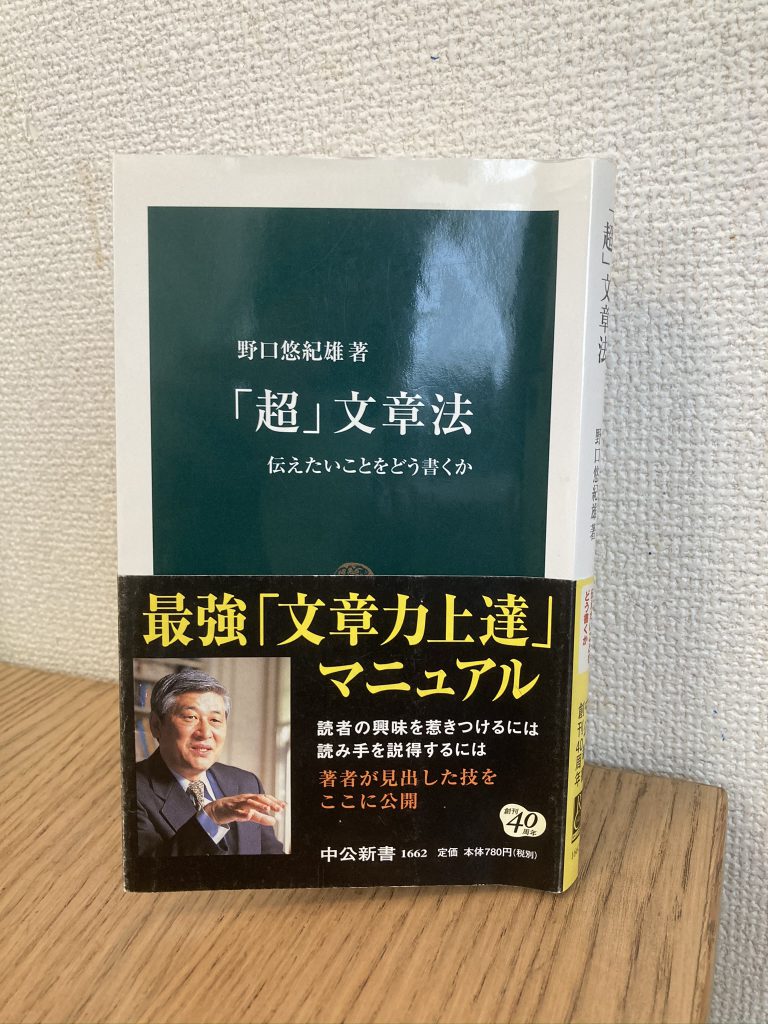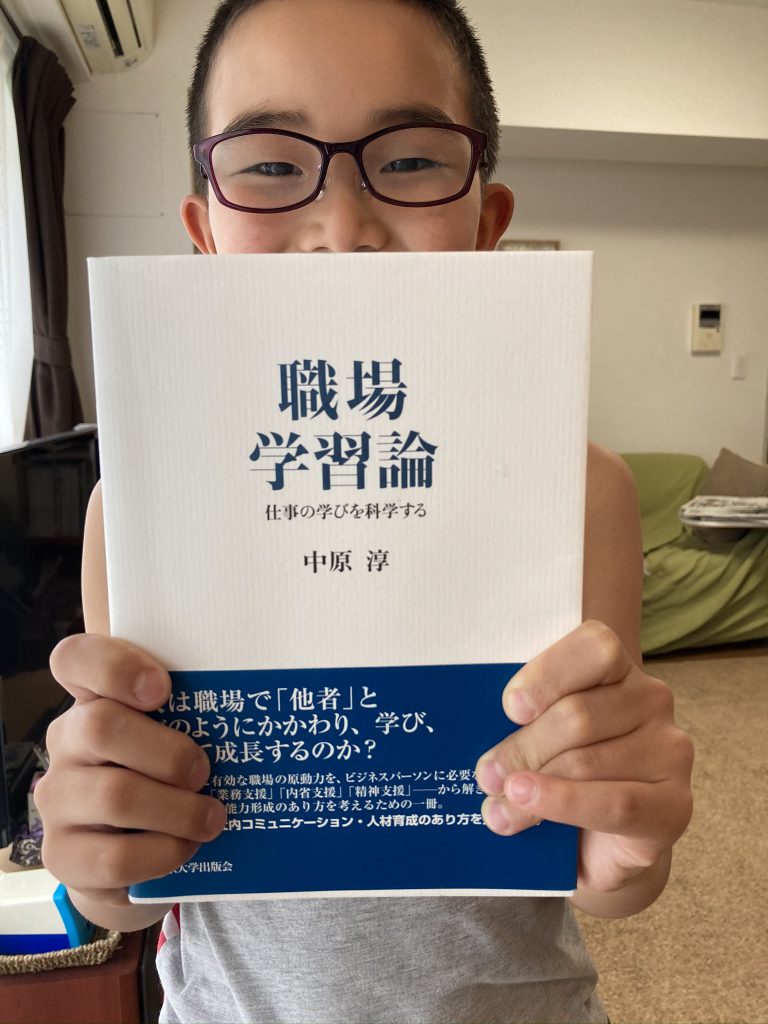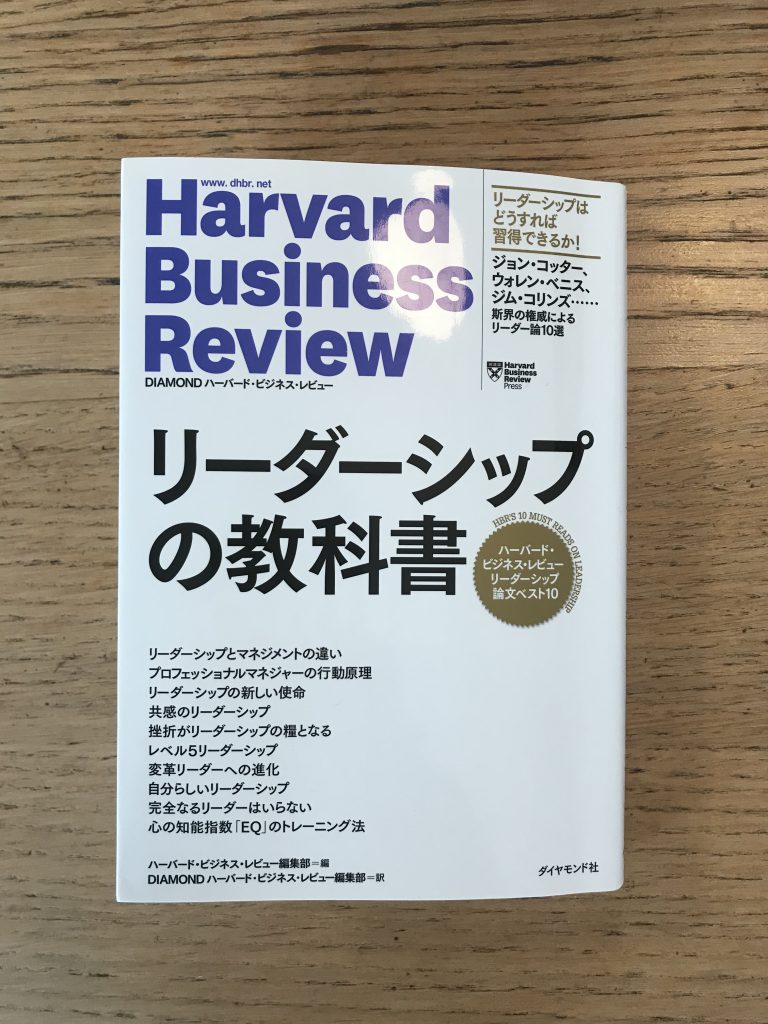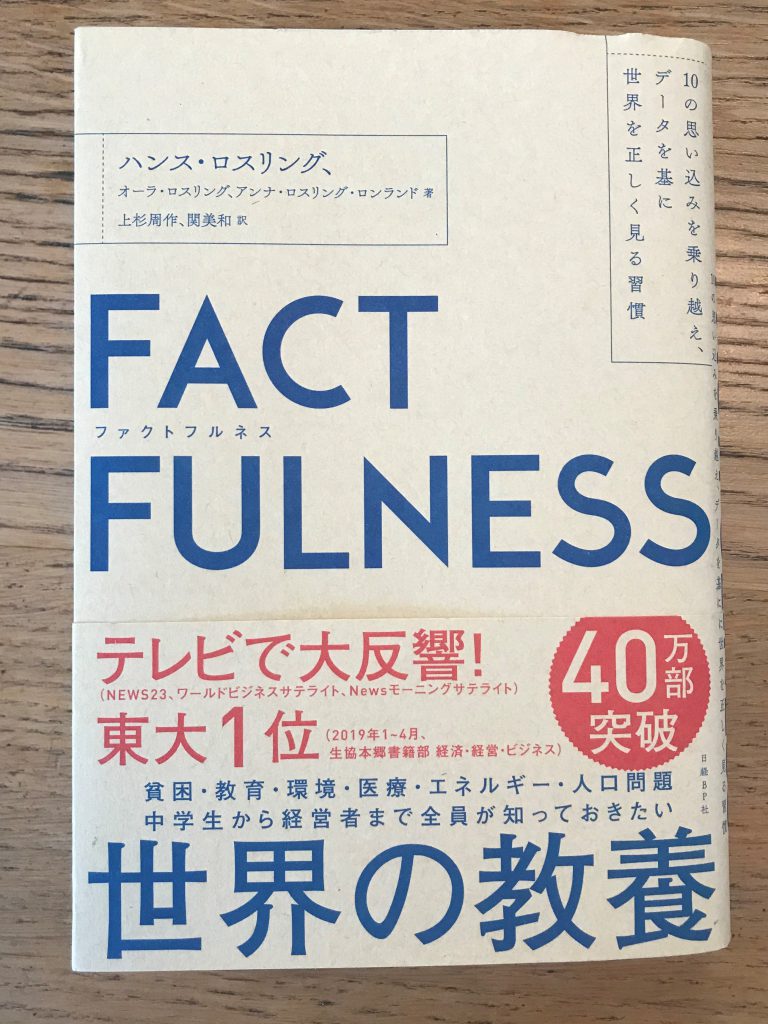第145週
2020/5/31
『「超」文章法』
野口悠紀雄著 中公新書
今年の読書テーマの一つは「筆力強化」。書くという行為は、これから先も増えていくことを見越し、今年のテーマとしました。その第一弾が本書です。
結論として、第1章「メッセージこそ重要だ」がとても響きました。この章だけでも十分財産となりえるものと感じます。
第1章の主張は、「メッセージを明確化せよ」ということです。著書は「メッセージが8割の重要性をもつ」と言っていますが、伝わりやすい文章の核心はここだと感じます。しかも、メッセージは質が問われます。メッセージとなりえるための条件で、メッセージが、ひとことで言えるか、ためになるか、面白いか、の3つが響きました。質の高いメッセージとしてあがっていた例は「猫は笑う」です。おっ?と意外性があり面白く、また雑談のネタの一つとしてためになりそうです。
更に、筆者はメッセージが見つかったときも、読者にとって「ためになるか」「面白いか」と何度も自問自答を繰り返すことを勧めています。要は、「謙虚になれ」ということです。筆者と読者の間には、常に書きたいことと読みたいことの乖離があり、筆力が素人レベルを脱するには、この大河を超えることが必要と感じました。
私の場合、日常で書くのはメールとブログになります。
メールは自分の武器となるので、時間をかけ日頃推敲を重ねた後送るようにしていますが、メッセージを明確にしつつ、宛先の方にこれが伝わるか、ということを謙虚に考えていくこと。この姿勢を続けていきます。
またブログについても、毎回1つメッセージを考え、伝わるかどうか謙虚に考えていきます。
他、表現方法としては、文章は削る、削る、削るで読みやすくなることを取り入れます。つい冗長になりがちですが、思い切って削ることを心がけます。
また、抽象的な概念に名前をつけることもチャレンジしていきたいです。著者はベストセラー『「超」整理法』で、「神様ファイル」「君の名はシンドローム」など抽象概念に名前をつけ、「こみいった概念を上手く伝えるのに役立った」と言っています。まずはユニークに命名されたものにアンテナを張り、収集するところからです。
(876字)