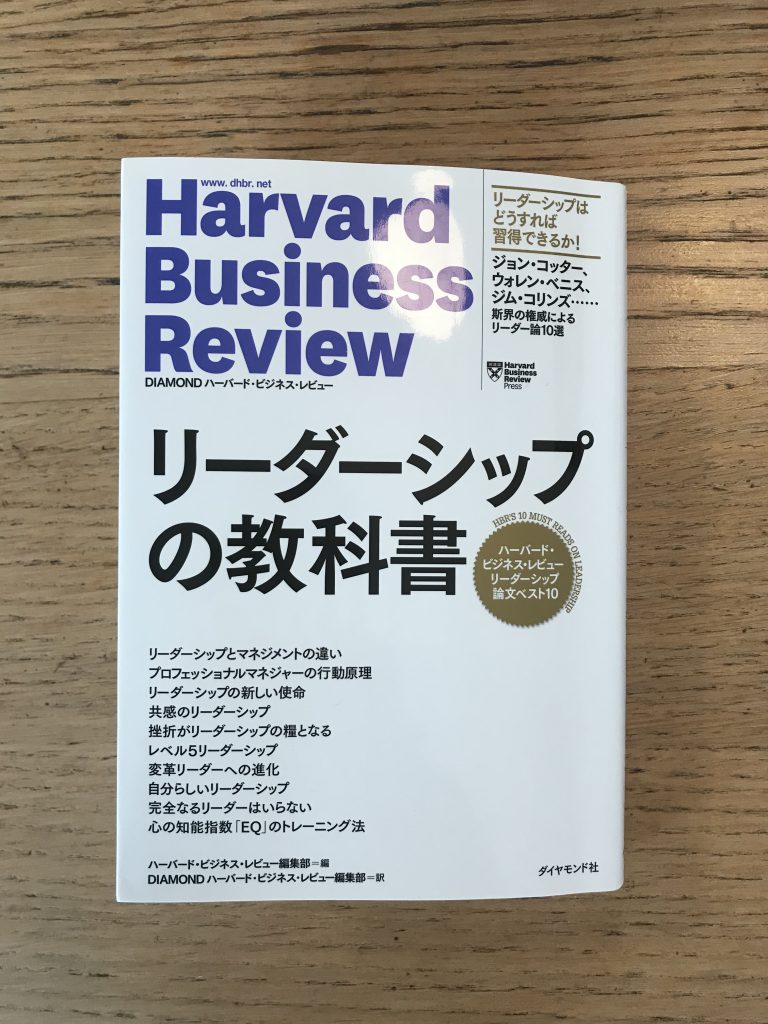第143週
2020/5/10
『リーダーシップの教科書』
ハーバードビジネスレビュー編集部編 ダイヤモンド社
ブルームウィルのリーダーシップ研修を更に進化させるべく手に取った本。リーダーシップ研究が最も進むアメリカにおいて選ばれた10論文が掲載されています。積極的にプログラムに取り入れたい部分を掲載します。
第一章 「リーダーシップとマネジメントの違い」 1990年
ハーバード・ビジネス・スクール 名誉教授 ジョン P. コッター
・「変革を起こすことがリーダーシップの役割である」、
「複雑な状況にうまく対処するのが、マネジメントの役割である」と言い切っている点。リーダーシップ論の大家がリーダーシップ=変革と言い切るのは、私達も勇気をもらえます。
・「ただし、統制のメカニズムのように、正しい方向に無理やり向かわせるのではなく、達成感、帰属意識、正当な評価、自尊心、自分の人生は自分の手に握られているという実感、理想に向かって生きる力など、人間の基本的欲求を満たすことによって、である。このような感情が芽生えることで、人は深く感動したり、力強く行動したりできる。」
この一節はリーダーがビジョンを伝える際、情動に訴える必要性を補強してくれます。キング牧師の演説と共に、「景色」の明確化を促進していきます。
第4章 「共感のリーダーシップ」2000年
ロンドン・ビジネススクール教授 ロバート・ゴーフィー
BBC人事・社内コミュニケーション担当役員 ガレス・ジョーンズ
部下にやる気を出せるリーダーには、共通して4つの資質が備わっています。みずからの弱点を認める、直感を信じる、タフ・エンパシーを実践する、他人との違いを隠さない。
特に、みずからの弱点を認める部分は、メンバーを不安にさせないよう、できる部課長を演じる方が多いと感じるため、エビデンスとして伝えていきたいです。
また、最近の部課長は、メンバーに嫌わられたくない優しい方々が多い印象もあります。「厳しい思いやり」であるタフ・エンパシーもとても響くと考え、伝えていきます。
第6章 「レベル5 リーダーシップ」2001年
コンサルタント ジム・コリンズ
まあまあの企業を偉大な企業へと変革させるためには、「レベル5リーダーシップ」が必要であるという主張です。著者は、対市場平均6.9倍の利回り実績を残した11社に共通している特性として抽出しています。このレベル5リーダーシップは研修というより、私自身が進む道として大変参考になりました。
第8章 「自分らしいリーダーシップ」2007年
ハーバード・ビジネス・スクール教授 ビル・ジョージ
元スタンフォード経営大学院 講師 ピーター・シムズ
元ハーバード・ビジネス・スクール 研究員 アンドリューN.マクリーン
元シティグループ 執行役員 ダイアナ・メイヤー
・「リーダーとして成功する条件は存在しない」と言い切っているのが凄いです。自分らしさを貫くリーダーへの8つの成長ステップのSTEP4外発的動機と内発的動機は何か、の観点は研修の個人軸分析に取り入れてみようと感じました。
・「スタンフォード大学経営大学院の顧問委員化に名を連ねる75人に、『リーダーが伸ばすべき最大の能力は何か』と尋ねたところ、答えはほぼ一致した。『自己認識力』である。」これも個人軸を基軸とする私達の研修の論理補強となります。
現在この自分らしいリーダーシップを更に深堀するべく、別の著書を読んでいます。
ブルームウィルのリーダーシップ論を補強する強い学術的エビデンスとなりそうです。
以上です。学術論文は視野の拡張と、物事の深堀りを促進する素晴らしい材料です。何度も読み返します。
(1457字)