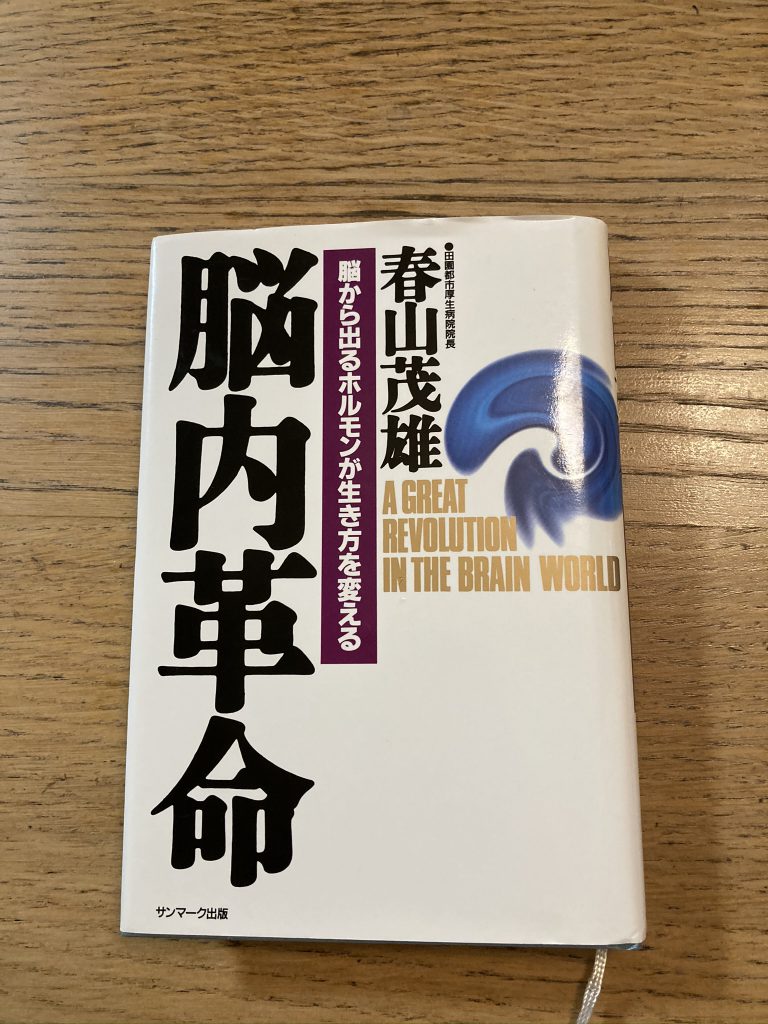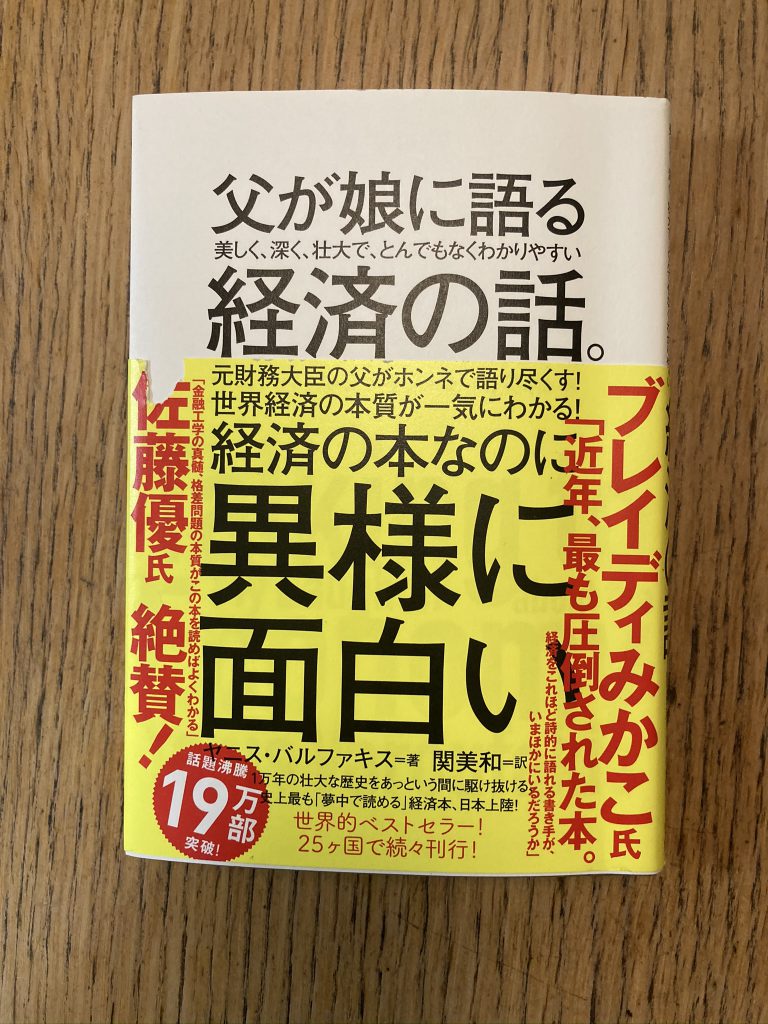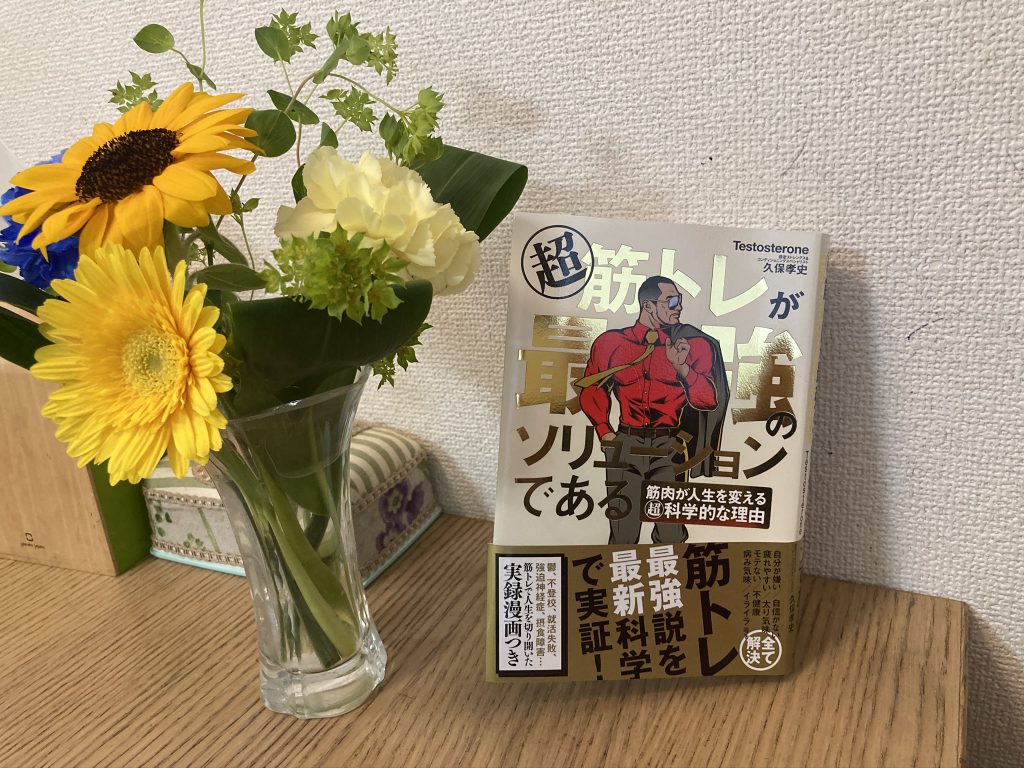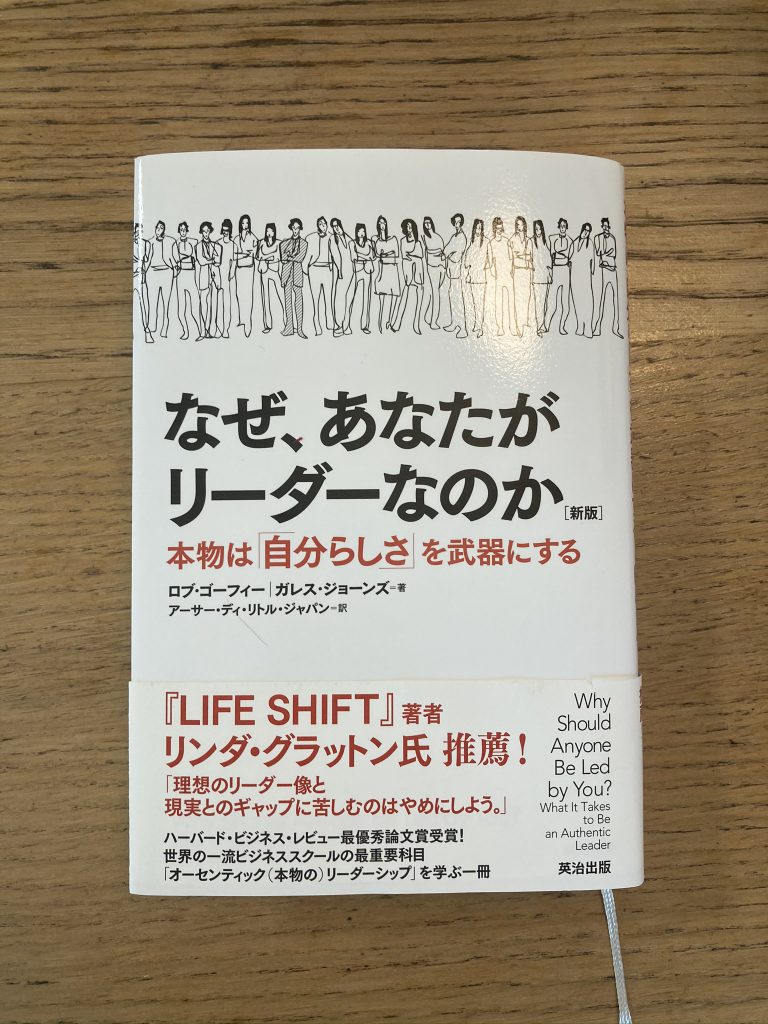第153週
2020/7/27
『脳内革命』
春山茂雄著 サンマーク出版
筆力強化のためのベストセラー研究、第6弾。1995年に出版され、国内累計発行部数の5位410万部をほこるお化け本です。
【読者として】
本書は、病気を治療する西洋医学に対して、病気にさせない東洋医学の効力を科学的に説明したものです。その科学的根拠となるのが「脳内モルヒネ」です。「脳内モルヒネ」は、β―エンドルフィンなどに代表される快楽作用をもたらすホルモンのことであり、「人の気分を良くさせるだけでなく、老化を防止し自然治癒力をたかめる、すぐれた薬理効果がある」と著者は言っています。
今回の私の一番の学びは、瞑想の科学的な効果です。瞑想は、上記の脳内モルヒネを分泌させ、病気の予防に大きな効果を上げるとのこと。実際に著者の病院では、成人病の患者さんに対して食事療法と共に、運動と瞑想を必ずセットで行い、治癒してきたそうです。
例えば、58歳の高脂血症とうつ病の女性。食事療法と運動、瞑想の三点セットの中でも、特によく効いたのは瞑想だったとのことです。この女性は非常に花が好きで、花を見ると顔つきが別人のようになる。それで花がいっぱい映ったイメージビデオをみてもらい、花のイメージトレーニングをしてから瞑想室で瞑想を繰り返してもらいました。すると脳内モルヒネが多量に分泌され(α波で判断)、非常に状態がよくなったそうです。
私自身この半年毎日行ってきた瞑想が、最近忙しくてできていませんでした。本書からの学びが、再開する動機になりそうです。
【書き手として】
■メッセージの秀逸さ×タイミング
『「超」文章法』では、メッセージが8割の重要性をもち、質の高いものはひとことで言えて、面白く、ためになるもの、とありました。本書のメッセージは「病気にならない、させないために」であり、25年前の日本ではまだ病気を治療することが主眼であったため、このメッセージが非常に新しく目から鱗のコンセプトだったのでしょう。書く際にメッセージが最重要であることを再認識させられます。
しかし、これだけでは410万部というお化け本になることはできないと思います。仮説ですが、出版のタイミングが抜群だったのではないでしょうか。多くの人が喉から手が出るほど求めていた時期ではないと、この数字は叩き出せないはずです。
成人病という言葉は、脳卒中、がん、心臓病などの「40歳前後から死亡率が高くなり、40~60歳くらいの働き盛りに多い疾病」として1955年ぐらいから行政的に使用されていたそうです。そして、以前は加齢や遺伝に関係し、病気の発症は仕方のないことであり、早期発見と早期治療に主眼がおかれていましたが、この頃、成人病の発症が生活習慣に関わることが分かってきたようです。本書の影響かどうかは分かりませんが、1997年頃から厚労省が「成人病」を「生活習慣病」という呼称に変更しています。
一年で400万部以上を売り上げるということではなく、何年かに分けてということですから、バブルが終わりモーレツな働き方が見直された、成人病の発症が生活習慣に関わることが分かってきた、このような時代背景により超メガヒットが生み出されたのではないでしょうか。
(1298字)