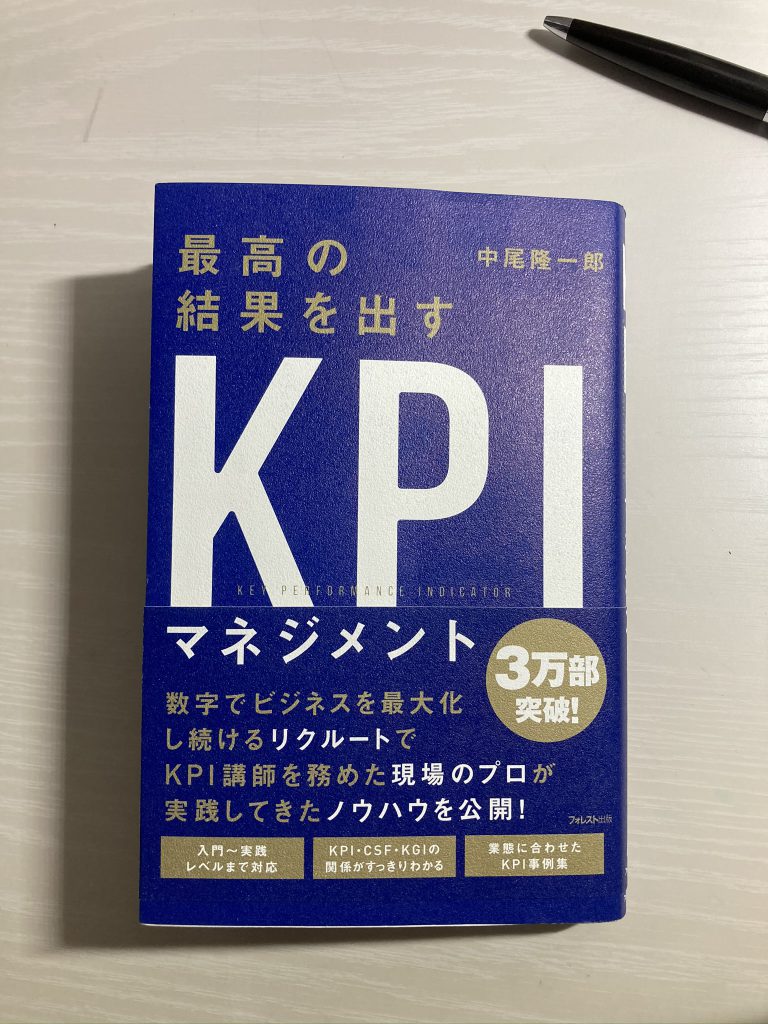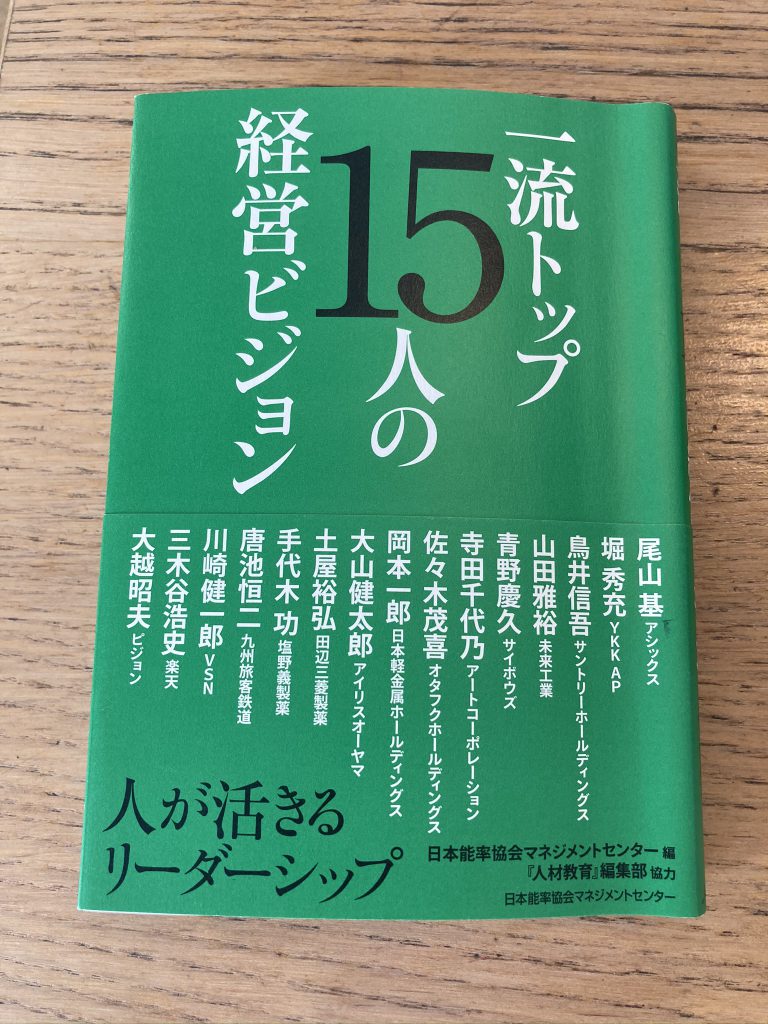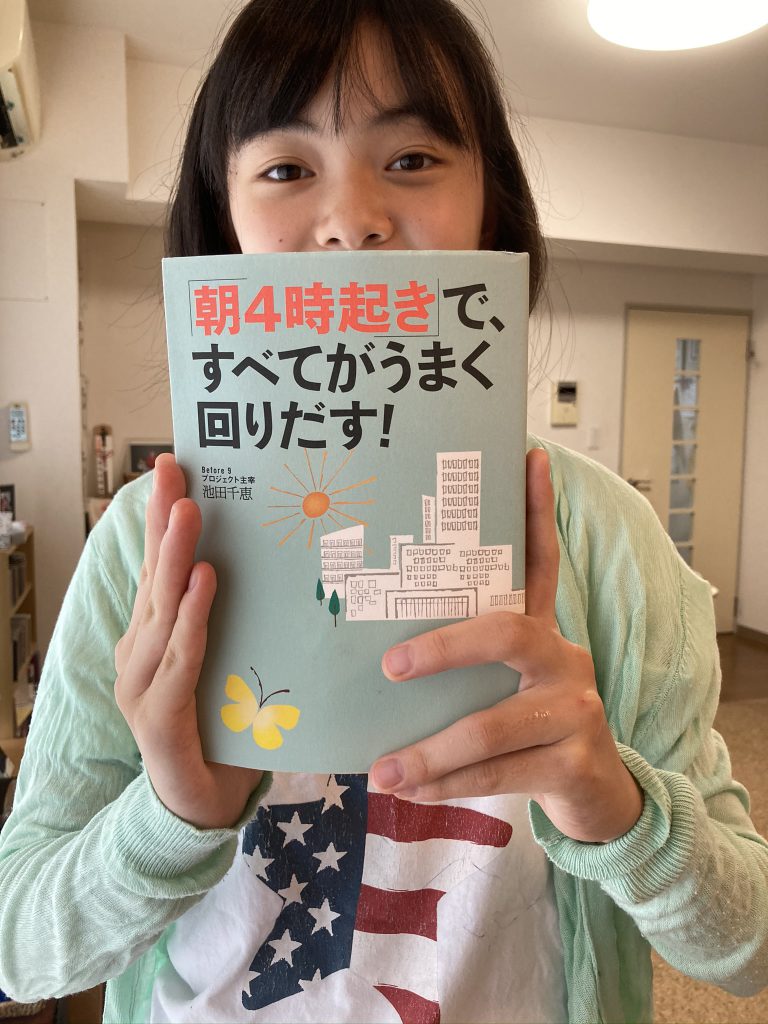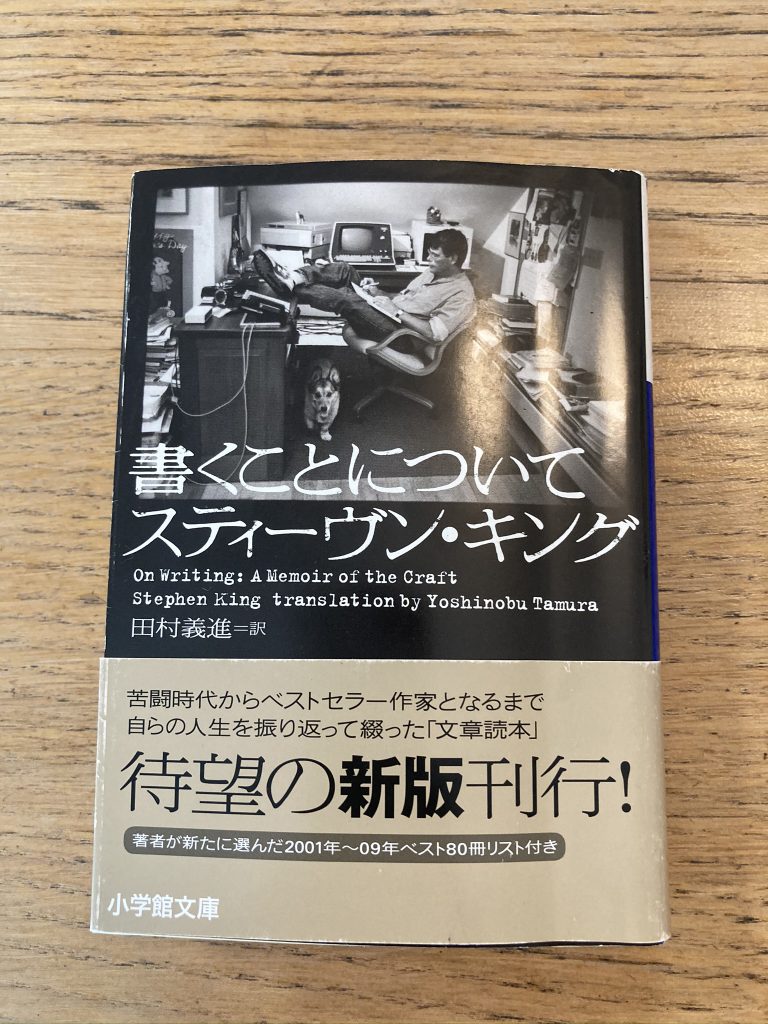第162週
2020/9/26
『最高の結果を出すKPIマネジメント』
フォレスト出版 中尾隆一郎著
LIFULL社の社外取締役である中尾隆一郎さんのノウハウを学ぼうと、手に取った本です。
今回新たに得た言葉としては「CSF」です。これはCritical Success Factorの略で最重要プロセスのことを指し、KPIは「CSFを数値で表したもの」と書いてあります。成果を上げるには、ビジネスプロセスの中で何がCSFかを見抜くことが重要と考えます。
本書より、CSFを見抜くには、二つのアプローチがあると整理ができました。
一つは、KGIを
①因数分解し定数と変数に分け、
②更にその項目をプロセス分解し、
③データ分析で設定する方法。
本書の例だと、下記です。
①売上=利用者数×歩留まり率×平均単価とし、利用者数と歩留まり率を変数とする。
②歩留まり率:認知→利用→企業紹介と分ける。
③データ分析をし、企業紹介において、1社より複数企業を紹介した方が成約になる確率が高いことが分かる。よって複数企業紹介をCSFとし、目標数値を設定する。
もう一つは、
①取引額の高い上位顧客の共通点を探し、
②その条件に沿った効果的な行動をCSFに設定する方法。
本書の例だと、
①規制変化があった業界、一定の規模以上、課題解決の自社ならではの提案ができている、の三条件に加え、ライトパーソン(正しい人)と商談ができている、ことが共通点として分かる。
②規制変化があり、一定の規模以上の新規対象企業をピックアップし、「対象企業ならではの課題解決提案」と「ライトパーソンへのアポ設定」をCSFとして、進捗率をKPIとする。
前々職の組織コンサル時代に、二つ目のアプローチを実施し、受注率を上げた経験があります。取引先企業を調べたところ、98%が自社の研修体験セミナーを受けていることが分かり、体験セミナーの参加者数をプロセス目標と置きました。本書に沿えば、CSFが体験セミナーの呼び込みであり、体験セミナーの参加者数がKPIです。
弊社の新規開拓について、営業はせず「紹介」のみであり、また急拡大も試行していないので、営業におけるKPI設定は今は不要かもしれません。しかし、参加者の成長変化や、顧客の収益拡大率など、プログラム提供におけるCSFやKPIは必要です。本書は難しいと思われがちなKPIを分かりやすく説明してあり、上記設定の際に活用します。
(951字)