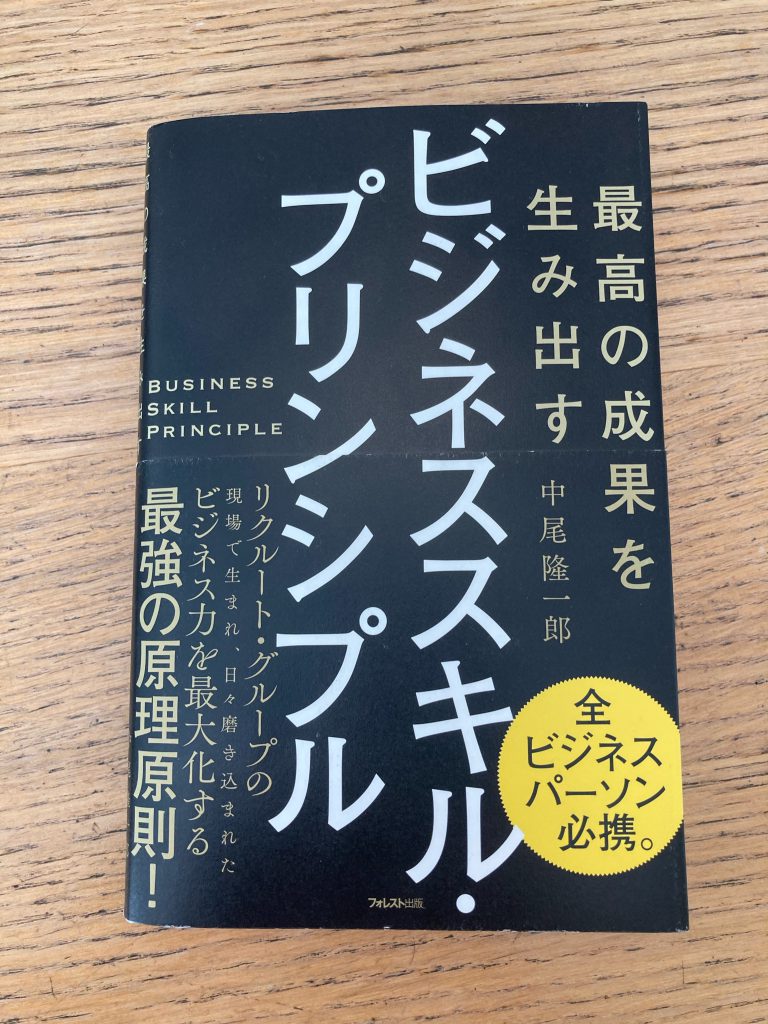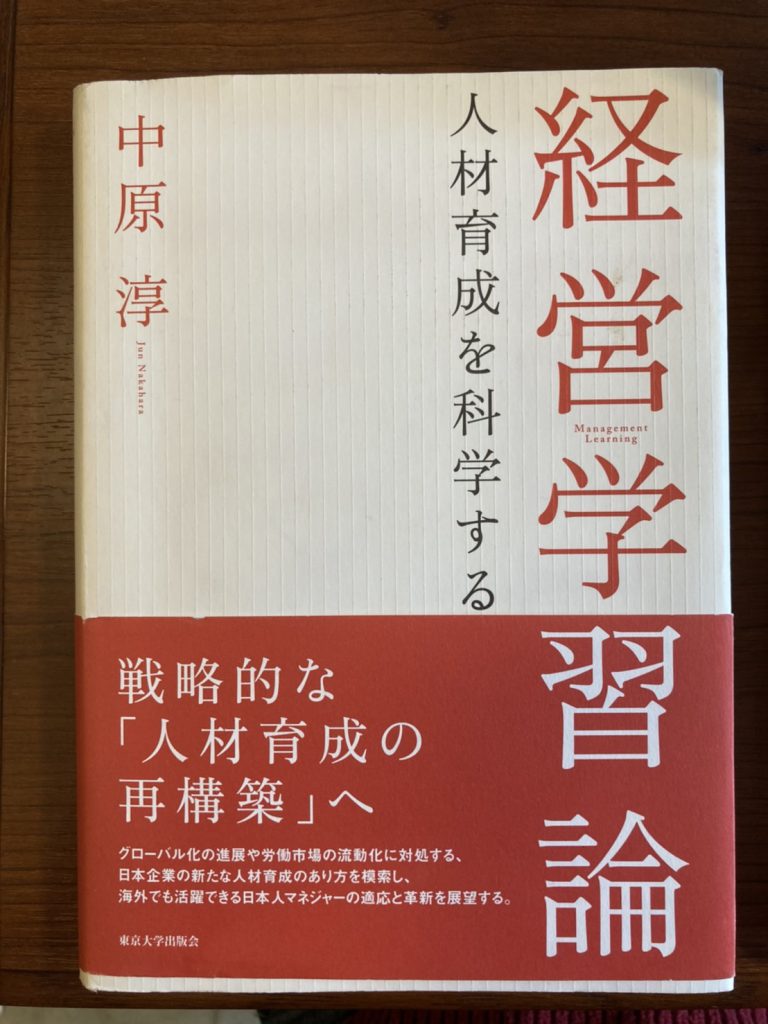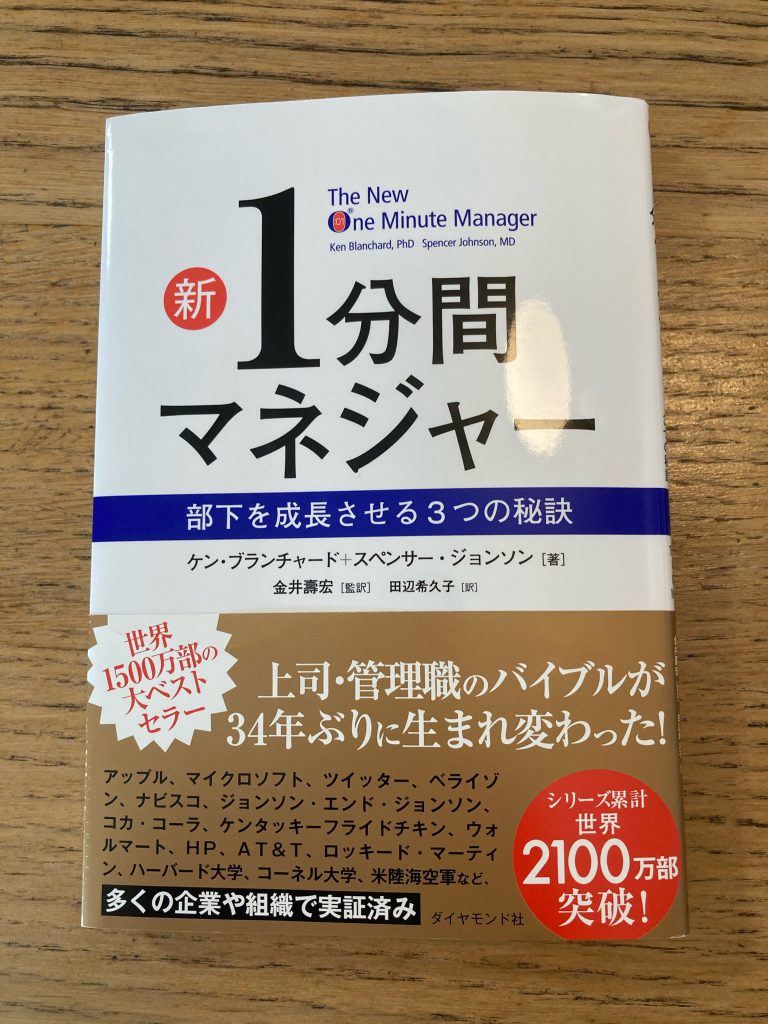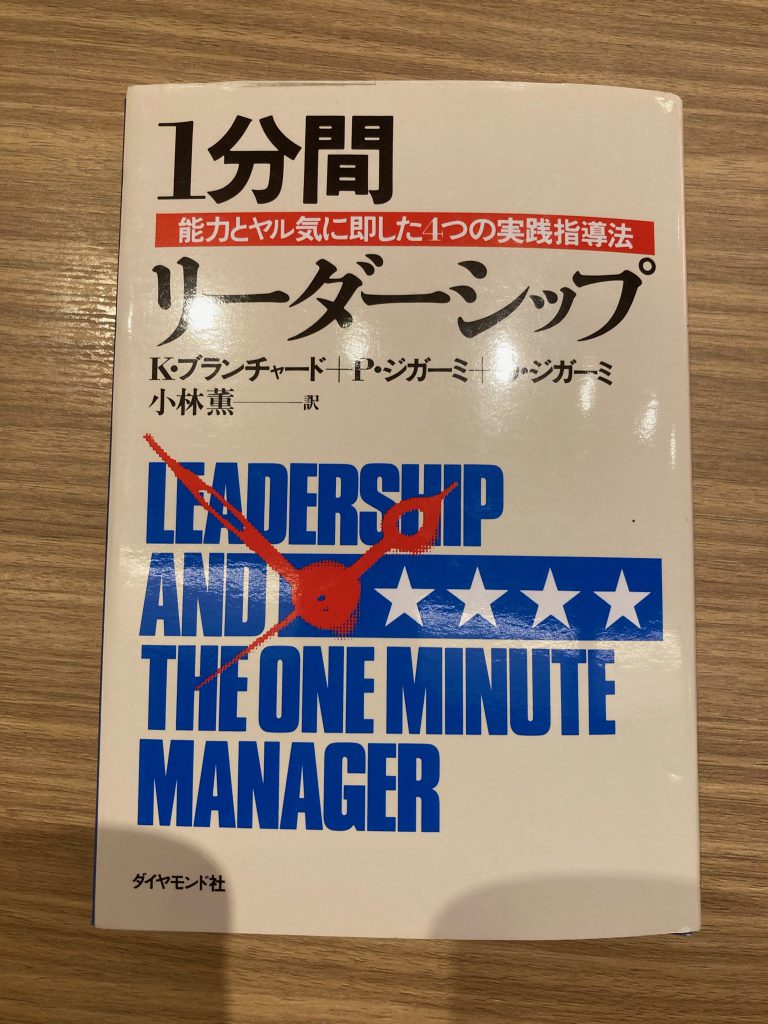第170週
2020/11/23
『最高の成果を生み出す ビジネススキル・プリンシプル』
中尾隆一郎著 フォレスト出版
LIFULL社外取締役の中尾さんの著書2冊目。リクルート時代のエピソードなどをまじえながら、ビジネスで役立つ50のスキルを紹介しています。
この中で二つほど、強く印象に残った章を書きます。
50.「もう一つの仕事」に精を出していませんか?
大阪のマネジャーのエピソードがとても印象的でした。中尾さんが情報誌の企画マネジャーをしていた頃、商品や価格帯、製造工程を標準化する企画を立てました。各エリアの部長は了承をしてくれたのですが、ある大阪のマネジャーが、「納得いかない」と中尾さんの上司に直談判してきました。
上司との面談時には、大阪マーケットの綿密なデータと、施策が難しい理由が理路整然と書かれていました。
理屈には穴も幾つかあり反論する余地もあったそうですが、中尾さんの上司は、
『いやー、あなたは本当に賢いな。その賢さと情熱とエネルギーをこの施策ができないことを説明するために使うのではなく、中尾を助けるために使ってくれないだろうか』
と、ひと言つぶやいたそうです。
すっかり毒気を抜かれた大阪のマネジャーは、「分かりました」と言い、1週間後にどうやったら実現できるか、というレポートを作成し、標準化を積極的にけん引してくれたそうです。
本章は、自分をよく見せる「強がり」に時間を割くのは無駄であるという、考えを載せている章ですが、強がりは無駄ということ以上に、この上司の方の素晴らしさに敬服しました。このような一言が言えるようになりたい、凄いなと、感じました。
44.永続的に伸びる会社を見抜く
①顧客の満足 ②従業員の満足 ③株主の満足 ④社会への貢献
企業が永続的に成長するために、優先順位をつけてください、という問いがあります。
とても難しいです。私は悩みながら、②従業員の満足 ①顧客の満足 ④社会への貢献 ③株主の満足という順番を考えました。
中尾さんが100社の経営者に同じ質問をしたところ、4社だけ「4つとも満足が必要」と回答したそうです。そして、その4社が10年後に成長していました。
そこから、中尾さんは永続的に伸びる企業は、4つを同時に満たしている、と主張されています。
どれかの優先順位下げることなく、1つもないがしろにしないことは、とても難しいことです。嘆息すると共に、合点がいきました。
(938字)