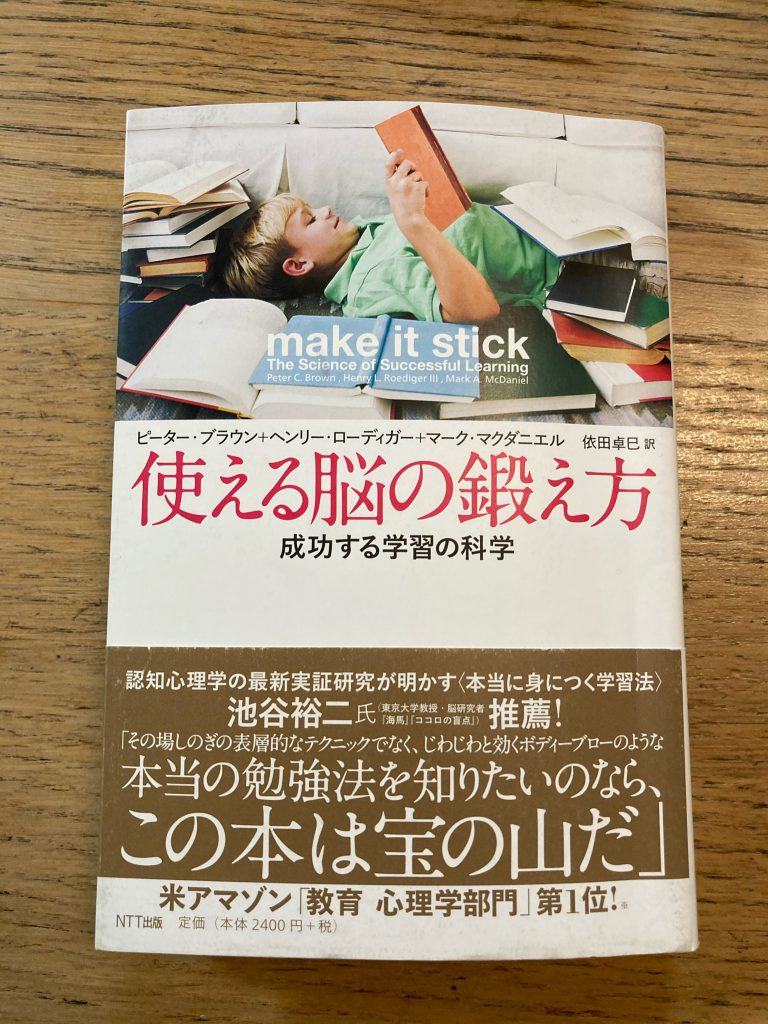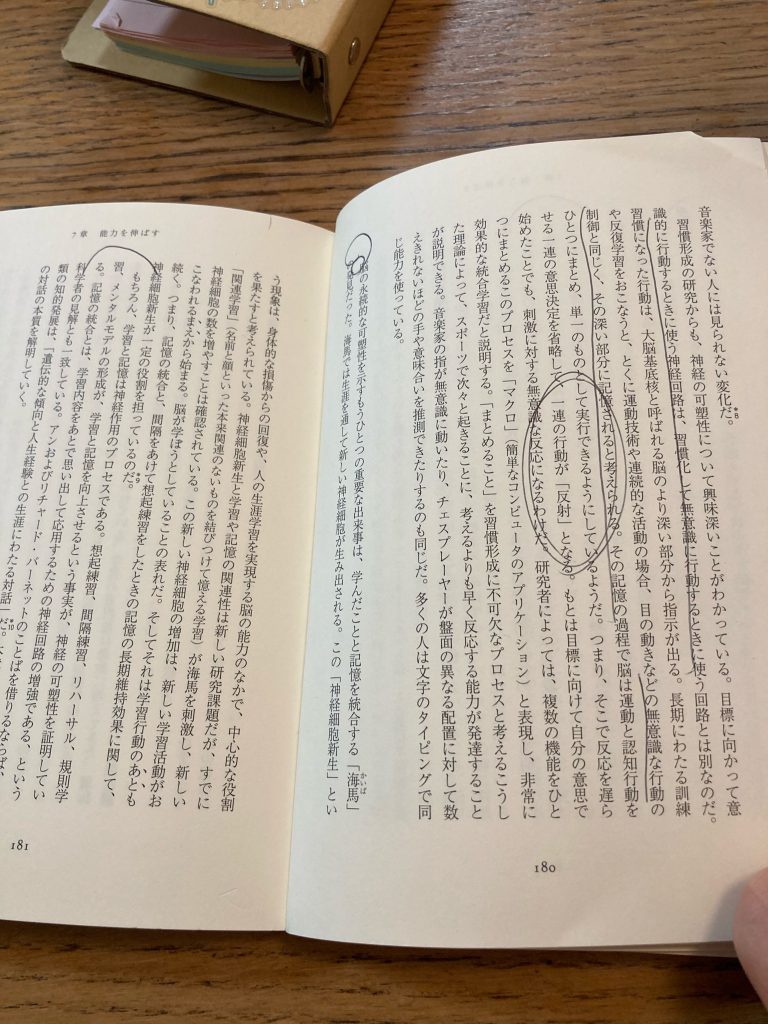第176週
2021/1/10
『使える脳の鍛え方』
ピーター・ブラウン、ヘンリー・ローディガー、マーク・マクダニエル著 依田卓巳訳
知能に重きをおかれているビジネスにおいて、能力を伸ばすことは根源的には脳科学の領域の話だと考えています。今回「どうすれば能力を伸ばせるか」という問いに、脳科学の知見から明確に答えたいと考え手に取りました。
まず、本書には「全ての知識と記憶は、われわれの神経細胞とその回路で起きる生理現象だ。」とあります。ここから能力向上には神経回路の変化が関係していると分かります。そのことを本書では「神経の可塑性(かそせい)」と呼んでいます。可塑性は塑性と同義で「変形しやすい性質。外力を取り去っても歪(ヒズミ)が残り、変形する性質。」(広辞苑)とあります。つまり能力向上の正体は、負荷をかけることで神経を変形させることと言えます。
その変形の仕方は二つです。神経細胞を増やすこと、神経細胞同士のつながりを強くすることです。
一つ目の神経細胞を増やすことについて、「海馬では生涯を通して新しい神経細胞が生み出される。」とあります。海馬は短期記憶や記憶の統合を司る部位です。研究では「関連学習」により海馬の神経細胞自体増え続けることが確認されているとのことです。
二つ目のつながりを強くすることについて、「われわれの知能の処理速度は神経のつながりの強さで決まる。」とあります。
ここは軸索(じくさく)と髄鞘(ずいしょう)がポイントになります。軸索は神経線維と呼ばれており、信号を伝達する導線みたいなものです。髄鞘は軸索を覆うカバーのようなもので、髄鞘の厚みがあるほど、電気信号の強さと速さが増すそうです。
「ピアノの練習量を増やすと、指の動きや作曲の認知プロセスと関連のある神経線維の髄鞘が増えた。」と研究であるように、練習を重ねるほど神経の伝達力とスピードが増し、能力が向上することになります。
今回神経細胞の増加と伝達の強化という、能力向上の根源的なメカニズムの理解が進みました。本書には科学的な分析による効率的な学習手段が書いてあるため、私達なりの学習の体系化にも役立てそうです。
(828字)