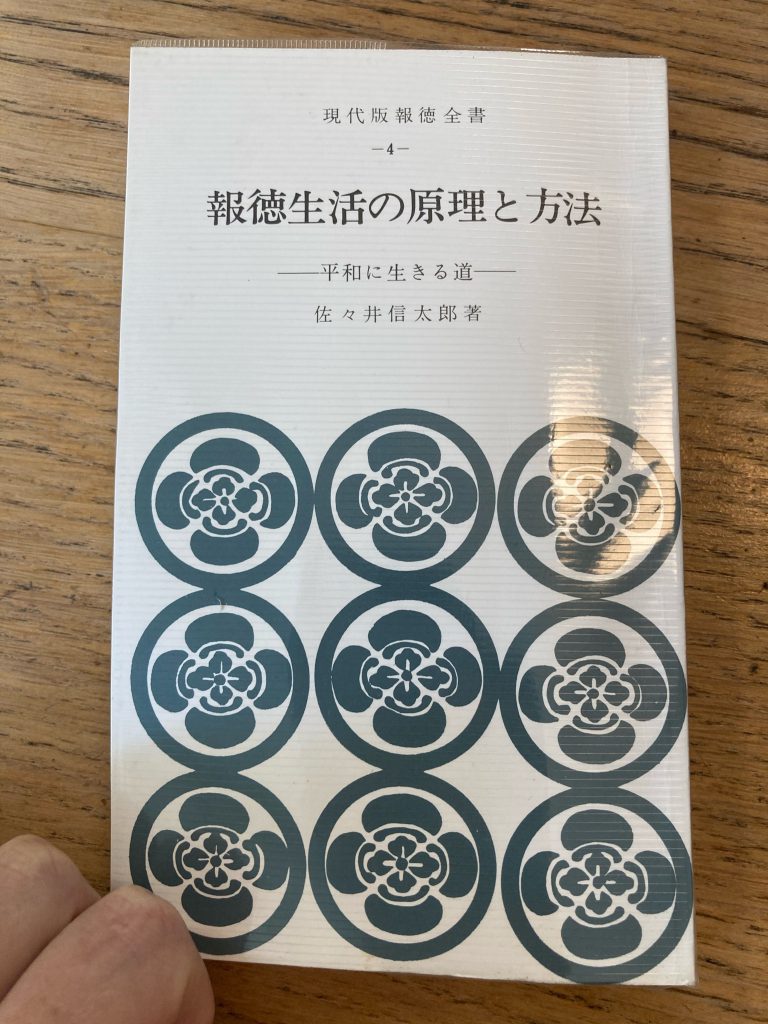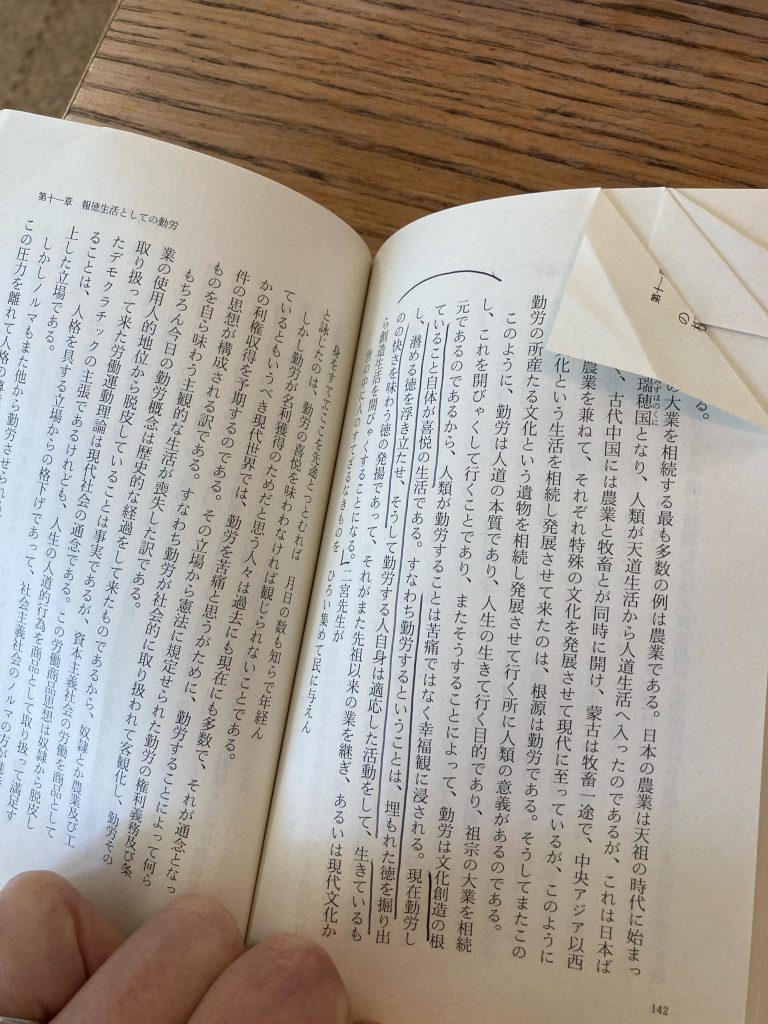第186週
2021/4/18
『報徳生活の原理と方法』
佐々井信太郎著 一円融合会刊
日課の一つに「師」とする方の書籍を読み、心を磨くことをしています。私淑しているのは二宮尊徳翁です。4年前ぐらいから毎日尊徳翁に触れるようにしています。
今回は尊徳翁の研究実践の第一人者である佐々井先生の著書です。報徳仕法をどのように、現在の生活に取り入れていくのか、より探究したく手に取りました。
今日の一文はこれです。
「現在勤労していること自体が嘉悦の生活である。勤労するということは、埋もれた徳を掘り出し、潜める徳を浮き立たせ、そうして勤労する人自身は適応した活動をして、生きているものの快さを味わう徳の発揚であって、それがまた先祖以来の業を受け継ぎ、あるいは現代文化から創造生活を開びゃくすることになる。」
徳に基づいてその特性を表現することは、勤労をすると同義になります。「勤労こそ人生の生きていく目的」と佐々井先生は言い切っています。そこまでの境地には立てていませんが近いものは感じており、仕事が楽しく死ぬときぐらいまでずっとしていたいと思っています。それは社会人になって以来、仕事を通していきがいややりがいが得られ、心から楽しいと感じるからです。
報徳生活をすることは、勤労をすること。難しいことではない。今のままで良いのだとあらためて感じました。
また、一切の衆生に特性があると尊徳翁は仰っています。勤労をすることでその徳に触れた方の徳性が現れ、また別の人に特が伝わり・・・という輪廻をしていく。尊徳翁は仕法の反対者の徳性をどう示現させるかを考え実行した結果、桜町の「全村民はそれぞれの天分の徳に基づいてその特性を表現すると、一家の貧困者なく、明治初年まで四十年間一人の犯罪者も出さなかった。」そうです。「自責」から更に進んだ考え方であり、新たな言葉を考えたいです。
(735字)