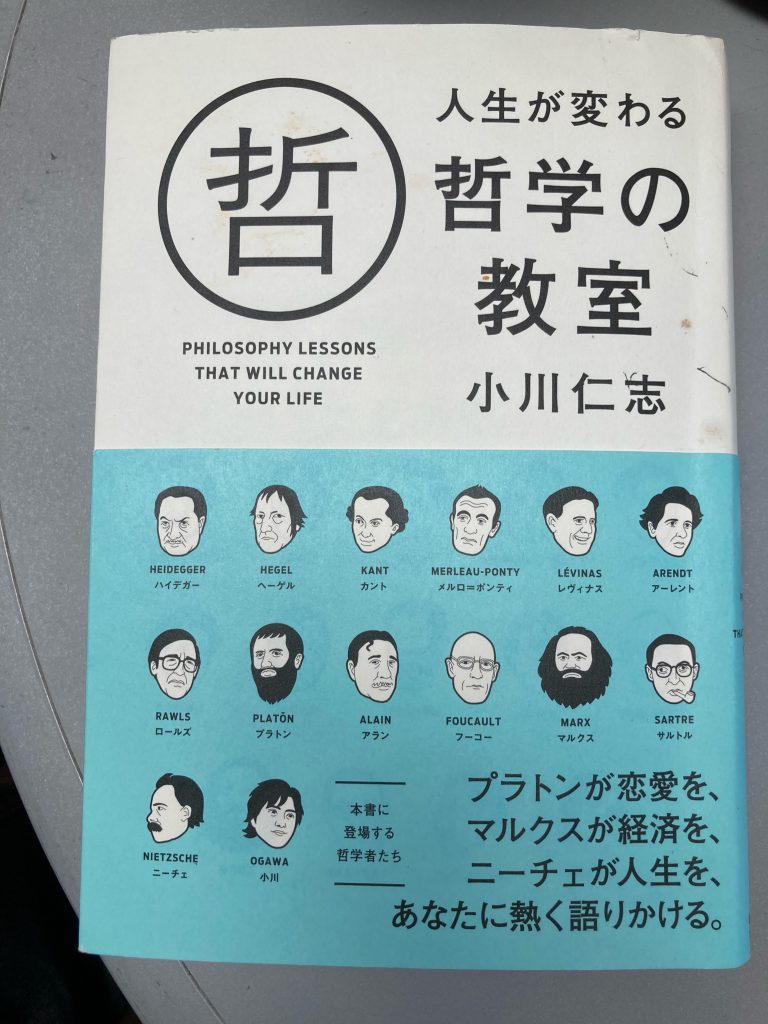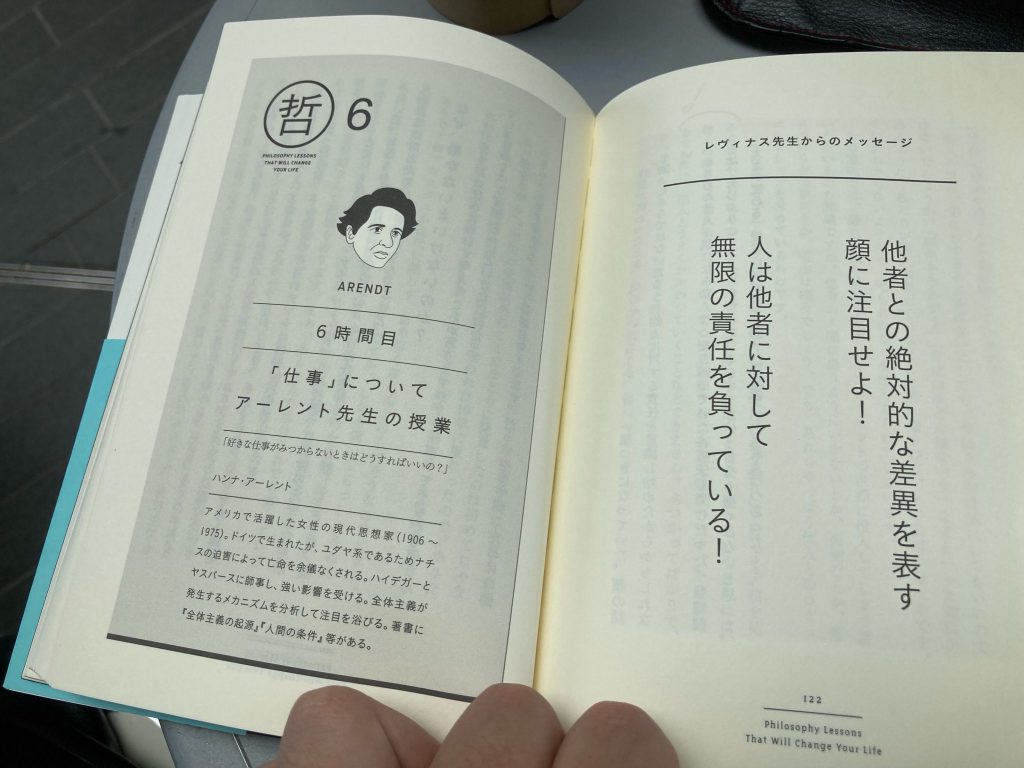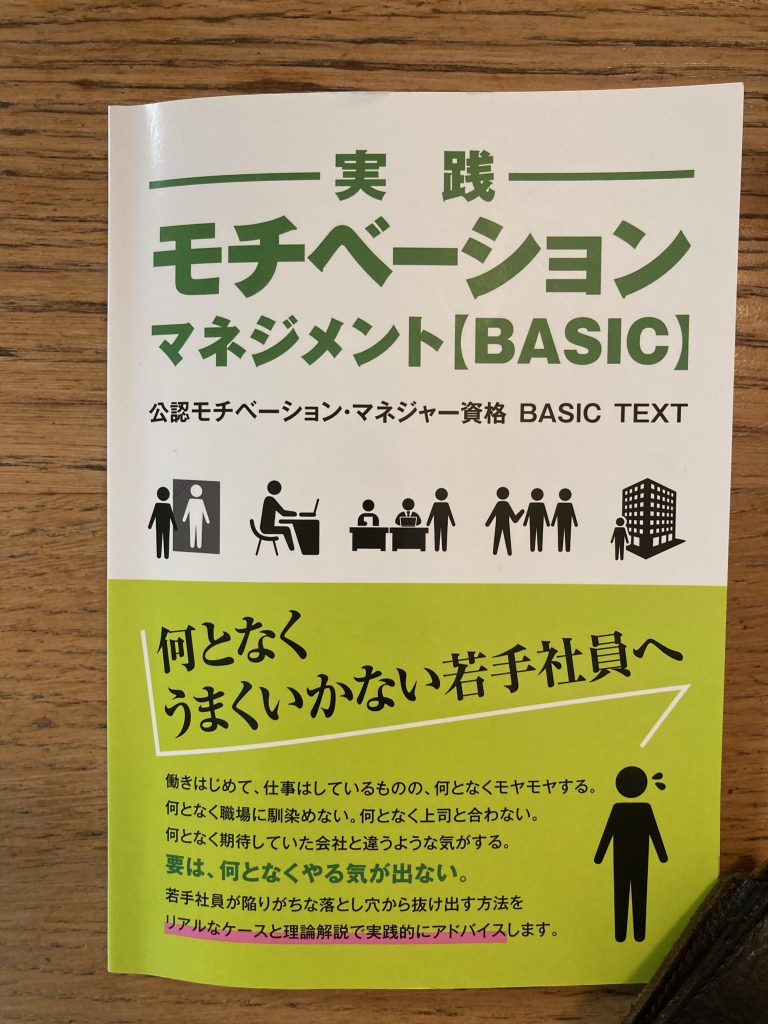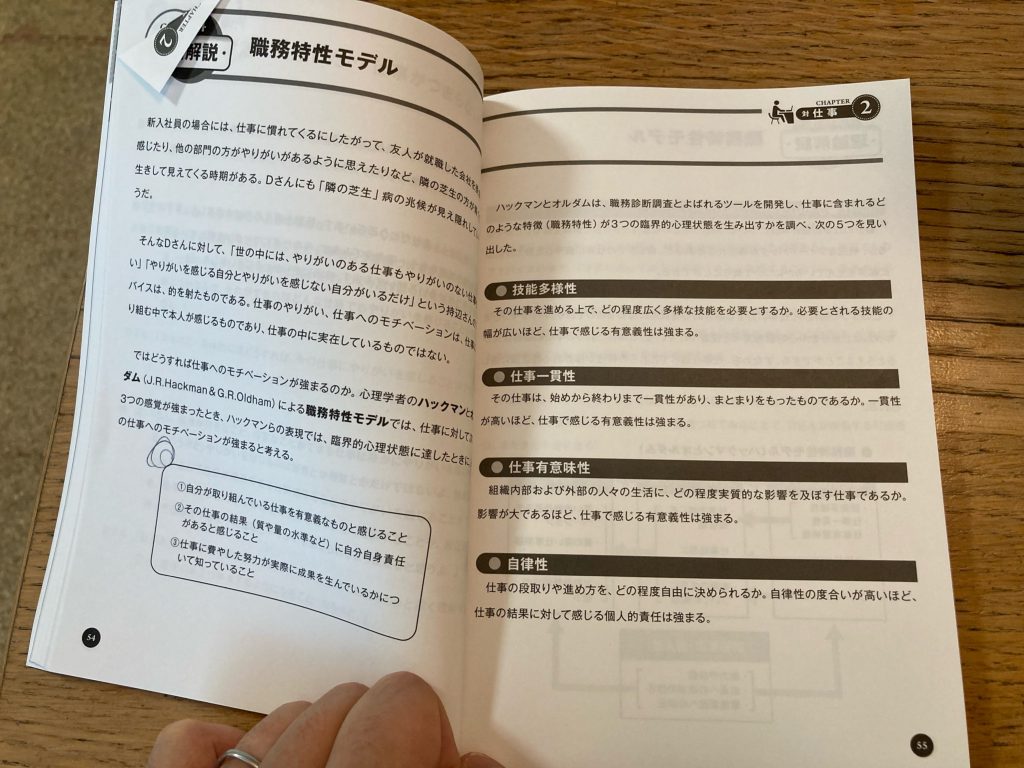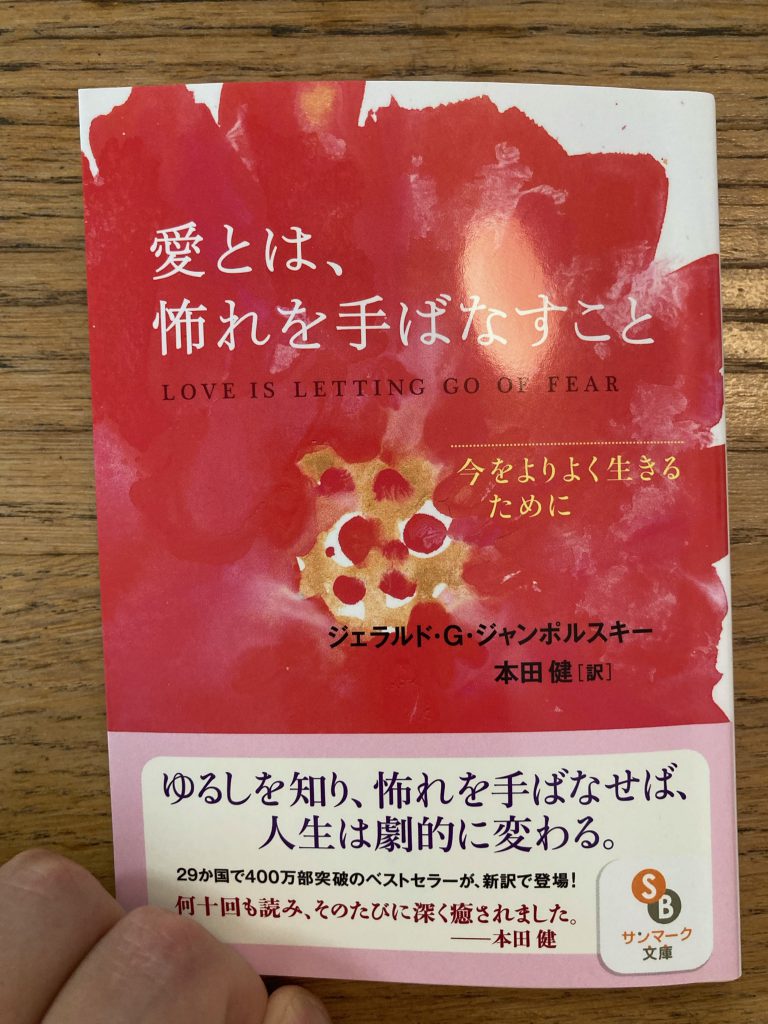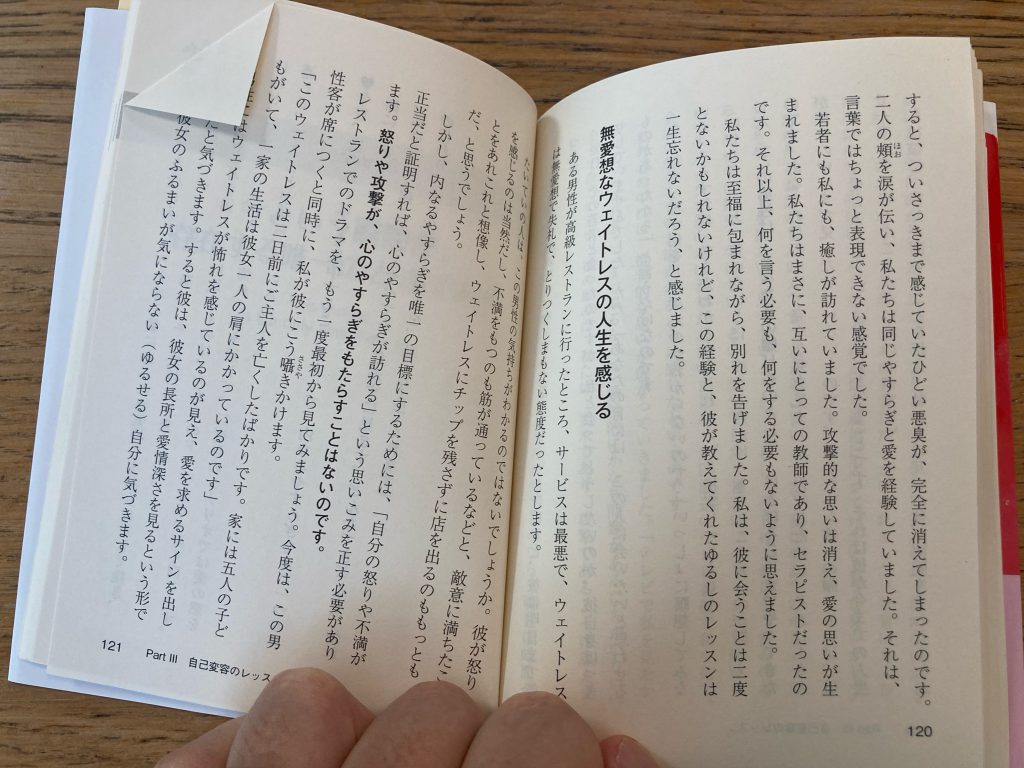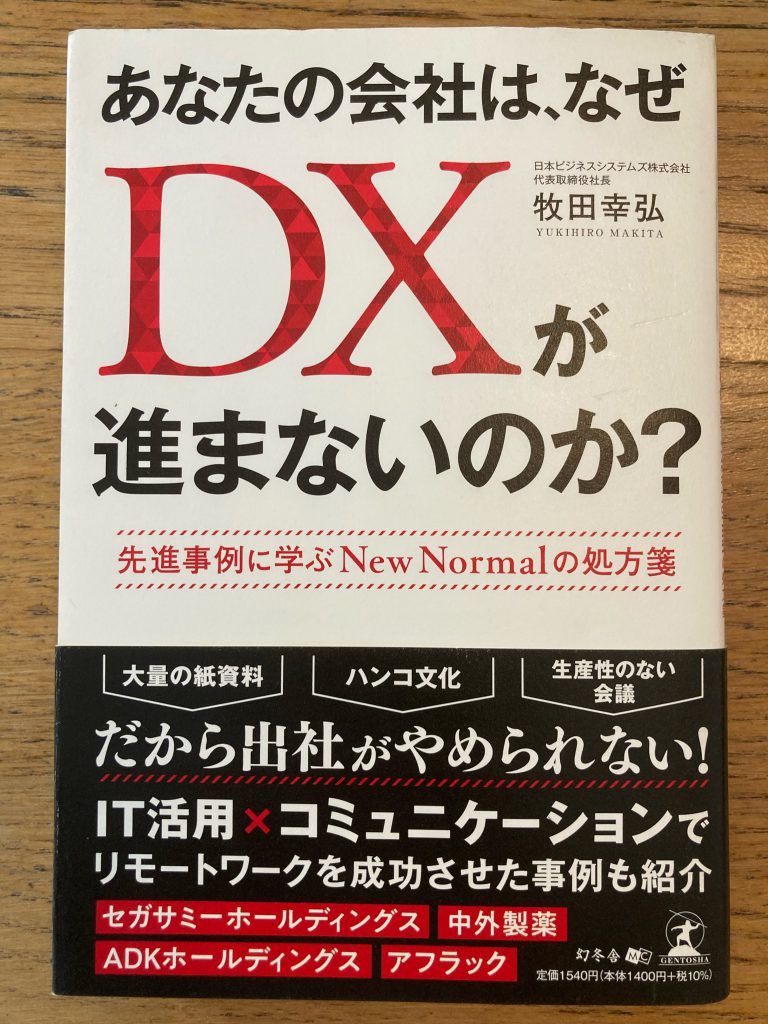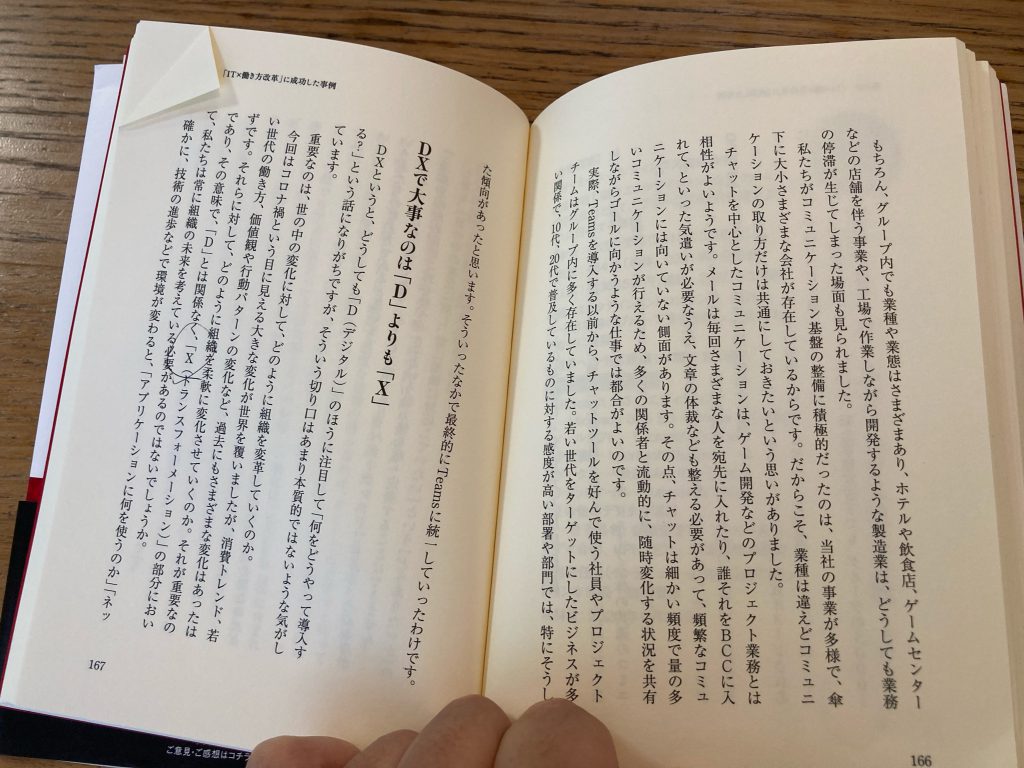第203週
2021/8/22
『人生が変わる哲学の教室』
小川仁志著 中経出版
3年以上前に買ったのですが手つかずだった本書。8月からデジタルデトックスを開始し、携帯に割く時間を読書に充てるようになり、その効用で読む気になりました。
本書は、人生とは?家族とは?幸福とは?などの哲学的なテーマについて、そのテーマにあった哲学者1名が、生徒達と対話形式で掘り下げていく内容になっています。
14名の哲学者の中で、今の私がとても印象深く感じた哲学者2名を挙げます。
一人は、ハンナ・アーレント氏です。女性の現代思想家で、ユダヤ系であるためナチスの迫害を受けアメリカに亡命した方。全体主義が発生するメカニズムを分析し世に出します。
アーレント氏の主著『人間の条件』に出てくる、労働と仕事の違い。そこからくる仕事の意味に共感をしました。
アーレント氏曰く、労働は「人間の肉体の生物学的過程に対応する活動力」を指し、食事や洗濯などいきるために必要な活動で自然性をおびます。一方仕事は「人間存在の非自然性に対応する活動力」を指し、道具や建築物などの工作物を生み出します。
労働は消費されるだけですが、仕事は形に残ります。自分の思いが形に残るので、この意味で、「仕事は自己実現に近い」とアーレントさんは言っています。
社会人になって以降、私はおそらく仕事を労働と思ったことがありません。生まれて初めて「ハマった」ものが仕事であり、自己実現の手段として無限の可能性を感じているから楽しいのでしょう。
一方でアーレント氏は仕事のやり過ぎはダメで、時間がなくなり大衆の社会への無関心を生む。それが全体主義へとつながると警鐘を鳴らしています。そして、労働や仕事の他に「活動」という、余暇や家庭との時間、地域社会への貢献など仕事以外の活動の意義を論じています。
全体主義云々というより、いち個人の幸福として「あ~本当にそうだな」と。
今の自分に大切なことは「バランス」です。仕事以外に使う時間の優先度を高め、バランスをとることが、より自身の幸福につながると実感しています。
もう一人については「再読」のどこかで書きます。
(848字)