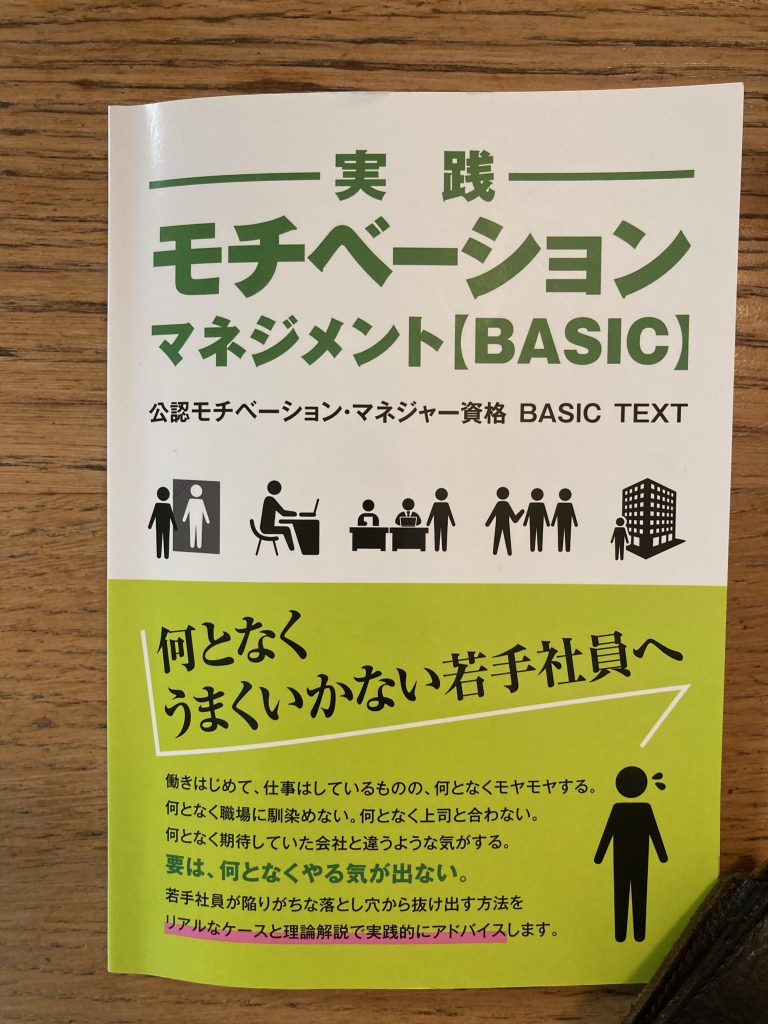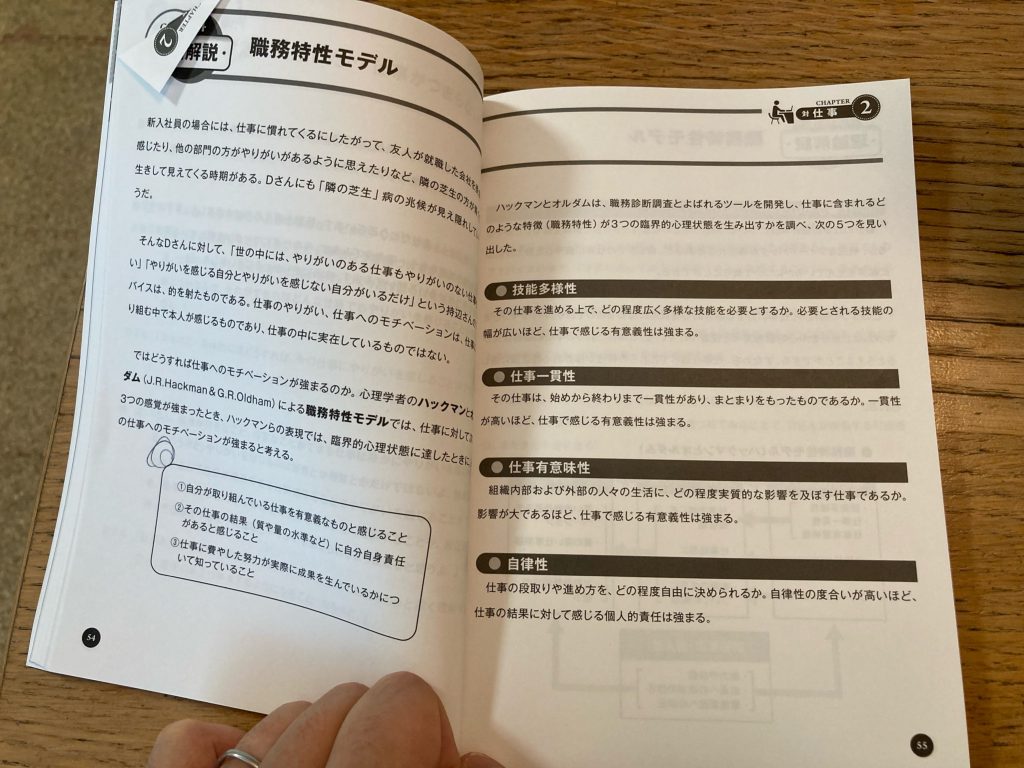第202週
2021/8/15
『モチベーションマネジメント【BASIC】』
一般社団法人モチベーション・マネジメント協会
受講者の方に「使える」と感じてもらえるモチベーションの書籍を探し続けている中、リアルなケース×理論が現場で使えると考え、手に取りました。
今回紹介されていた中で二つの理論が印象的でした。
まず、ロックとレイサム「目標設定理論」は以外と盲点であり、押さえておく必要があると感じました。
モチベーションが高まる目標とは何か。それは二つの要素があります。一つは困難な目標。もう一つは明確な目標。あわせれば「困難だが明確な目標」ということです。
モチベーションの違いはつまるところ「目標設定」によってもたらされるという考えは、非常に共感できます。この部分、研究内容を含めもう少し深堀りしてもよさそうです。
もう一つは、ハックマンとオルダムによる職務特性モデルです。
ハックマンとオルダムは、仕事に関して3つの感覚が高まったとき、臨界的心理状態となり、仕事へのモチベーションが高まること。またその3つの感覚を高めるには5つの職務特性があることを見出しました。
①仕事を有意義であると感じること→技能多様性・仕事一貫性・仕事有意味性が必要
②仕事の結果に責任があると感じること→自律性が必要
③仕事の努力が成果を生んでいるか知っていること→フィードバックが必要
①の仕事を有意義であると感じることについて、仕事そのものへ感じる価値だけでなく、技能の幅の広さや一貫性が影響することが発見でした。例えば、分けられている業務をつなげ、一気通貫してできる業務に移行するのは、技術多様性や仕事一貫性が増し、有意義に感じやすくなると考えます。仕事の振り方はモチベーションに大きく影響するので、押さえておくと便利な理論です。
(689字)