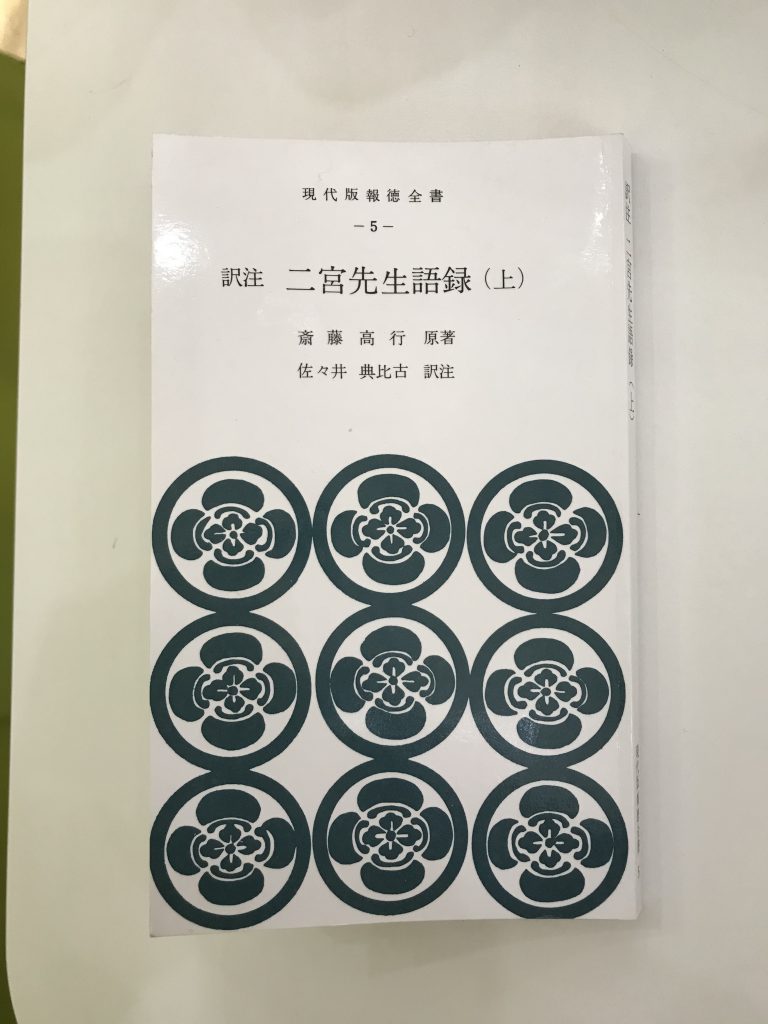第136週
2020/3/23
『訳注 二宮先生語録(上)』
斎藤高行 原著 佐々井典比古 訳注
私淑する二宮尊徳翁の教説を門弟である斎藤高之が記録したものです。尊徳翁の考えに毎日触れたくて、少しづつ読み進めてきました。あらためて強く思う事を三つ書きます。
一つ目は、「分度」の重要性です。支出の度を定めることを分度と言いますが、「分度は土台石」「分度は足もとの用意」「分度は仕法の基本」など、巻一で尊徳翁は言葉を変えながら再三再四分度の重要性を説いています。私は自分の給与を自分で決められる立場ですが、自身の分度を決めてから経営が安定した気がします。売上が大きく伸びたから、その分給与をもらうのは道理にかなっていると思いますが、利益に回せばその分投資もできますし、何かあったときの蓄財にもなるわけです。「国家の盛衰貧富は、分度を守るか分度を失うかによって生ずる」と尊徳翁の言葉を刻印し、今後も分度を守っていきます。
二つ目は、尊徳翁も人の子であることが分かりました。「そもそもわが道は、国政や三教が不備のため、その網から脱けおちて起る諸問題を救済してやる道なのだ。なんと偉大なものではないか。」「わが日掛縄綯法のごときは、女こどもでも実行できない者はない。なんと、まさに大道ではないか。」など、自身の考えや仕法を自賛している場面がありました。尊徳翁に対し、清廉潔白、常に自分に厳しく、謙虚で私心のないイメージをもっていましたが、人間らしい一面を見る事ができ、少し安心しました。
三つ目は、尊徳翁の解釈力の凄さです。そして解釈力の源にあるのは、農業や自然現象を用いた「たとえ話」をつくることではないかと推察できました。「禍福吉凶は一つである。ちょうど米にはぬかがあるし、魚には骨があるようなものだ。」「人道を左脚とすれば、鳥獣の道は右脚だ。」など、思想や事象を「たとえ」を使い分かりやすく説明する場面が頻繁に出てきます。一朝一夕には真似できませんが、手始めにスポーツメタファーを作っていきたいと思います。
(800字)