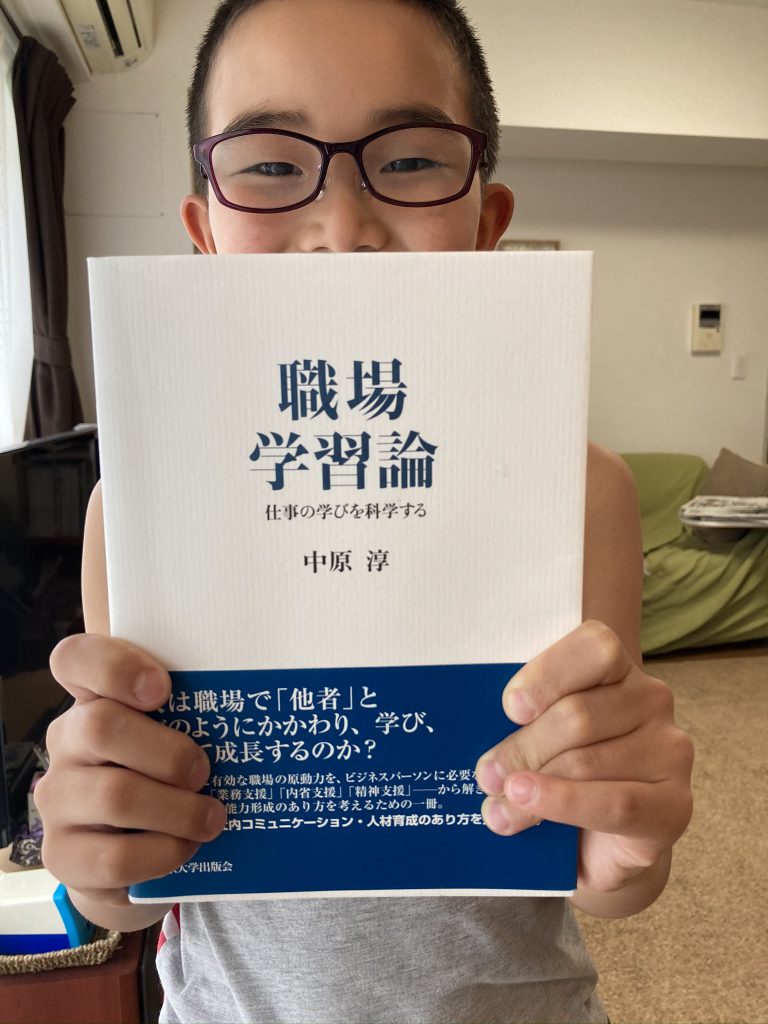第144週
2020/5/24
『職場学習論』
中原淳著 東京大学出版会
「成長する職場とは?」
この問いの解を探求することで、研修参加者の部課長に、成長する職場づくりのヒントを伝えられると考え、手に取りました。
まず、職場における他者からの支援は「業務支援」「内省支援」「精神支援」の3つであると著者は言っています。その上で二つのことを研修で伝えられそうです。
一つは、「上司が単独で育成を担うな」ということです。本書の調査から、業務支援は上司が多く、精神支援は同僚・同期が多いという結果が出ています。しかし、実際の効果は、
1)上司からの「業務支援」は量として多いが、能力向上に結びついていない
2)上司があまり行っていない「精神支援」は、能力向上に結びついている
という、著書曰く「アイロニカルで興味深い結果」になっています。
ここから、職場の上司や上位者だけが単独で育成を担うのではなく、皆で育成を担った方が効果が高いことが分かります。具体的には、同僚・同期からの業務支援や、上司からの精神支援はインパクトがあるので、独自のメンター制導入や、失敗成功体験を共有する自然な場づくり、1オン1の上司の育成面談は、成長促進に実に有効であると考えます。
もう一つは、成長する職場ために「互酬性規範(ごしゅうせいきはん)の形成」が必要ということです。
職場学習風土の3要素は「互酬性規範」「オープンコミュニケーション」「学習資源」であり、
「互酬性規範」は、
「困ったときにお互い助け合っている」
「他者を助ければ、今度は自分が困っているときに誰かが助けてくれるように自分の職場はできている」
「他者を助ければ、いずれその人から助けてもらえる」
「人から親切にしてもらった場合、自分も職場の他の人に親切にしようという気持ちになる」
の4つの項目で表されています。
本書では、調査結果から互酬性規範をつくることが、全ての支援の質を高める。ゆえに、職場内のメンバー間に互酬性規範が認知されているかどうかが重要である、と結論づけています。簡単に言えば、皆が「ここは助けあいのある職場だ」と思っていることが重要なのです。
それでは、互酬性規範はどうすれば形成できるのか。それは、仕事の割り振りや、人の組み合わせを工夫するなど上司のふるまいが大きいと本書は言っています。
例えば、ある仕事をやったことがないA君とやっているB君を組み合わせて、きつい納期で仕事をさせると、助け合わざるをえない、といった実際の管理職のコメントが掲載されていました。
この辺りは、更に探求をしていきたいと思います。
(1034字)