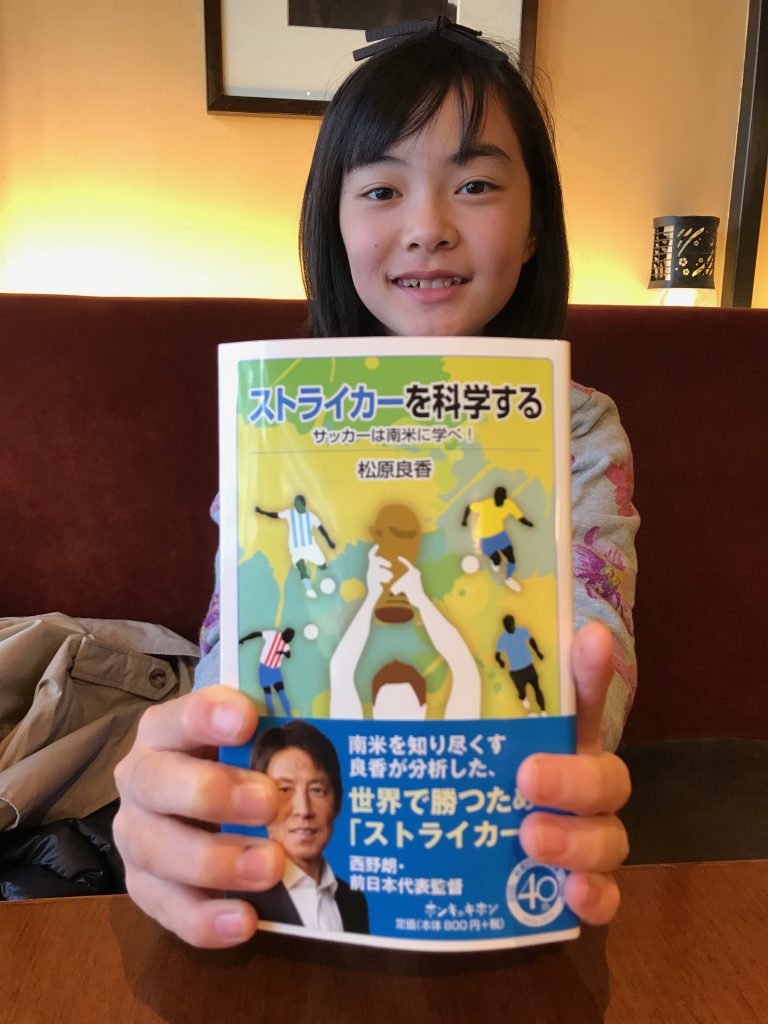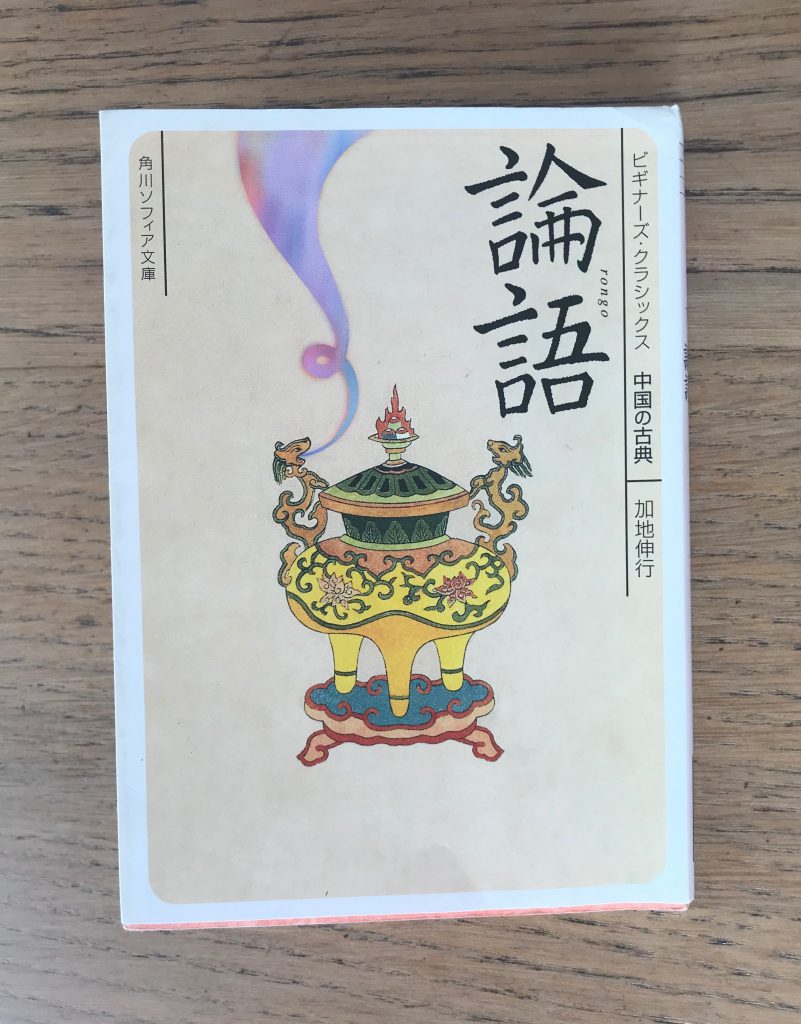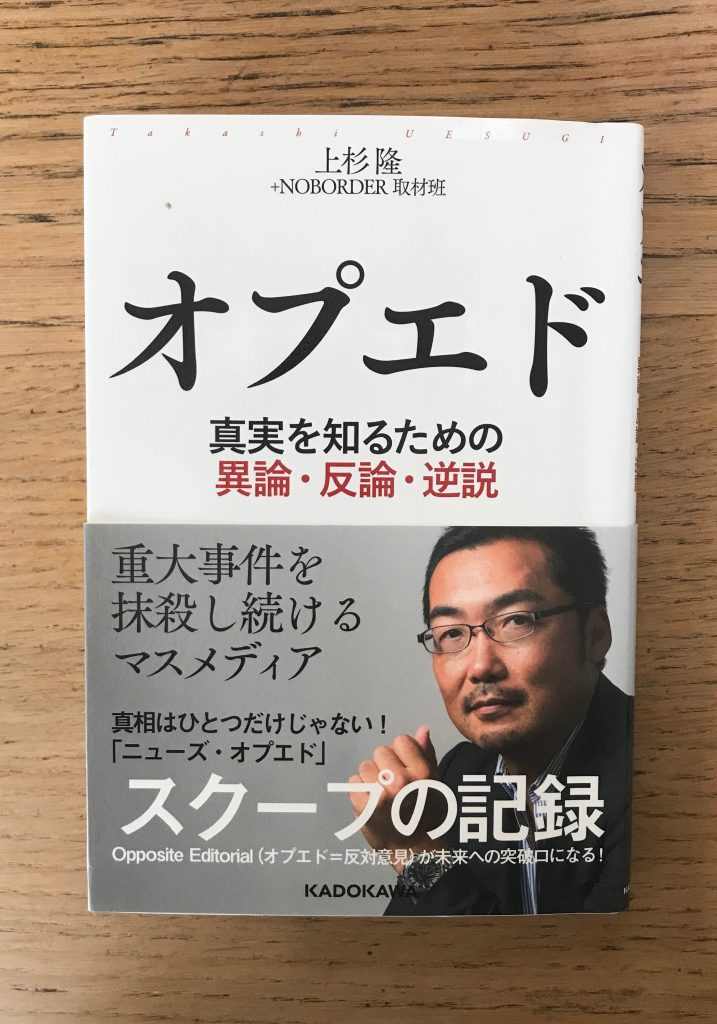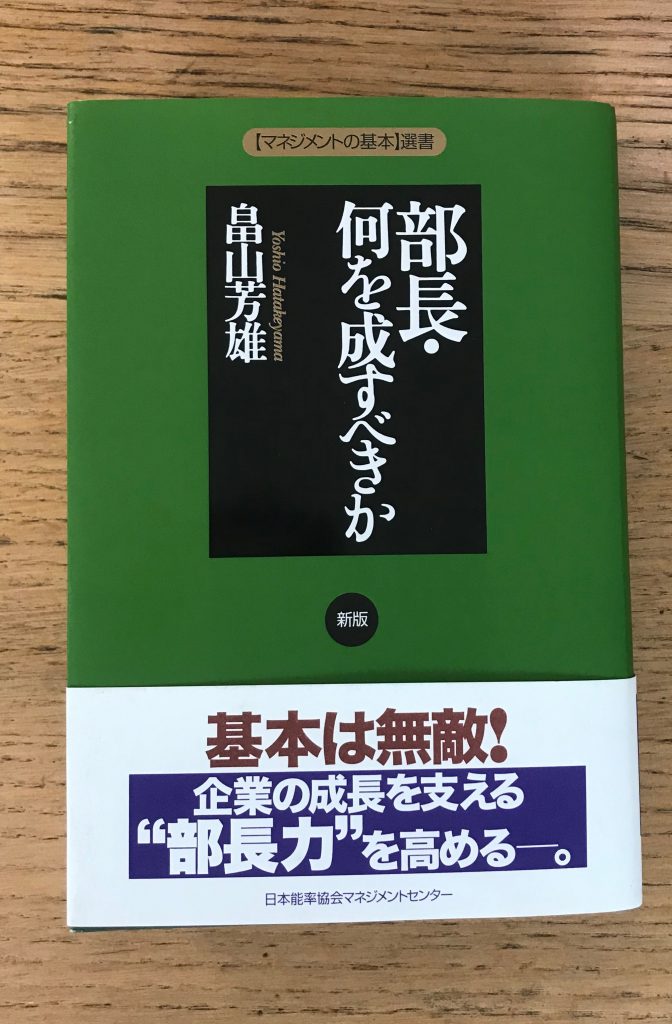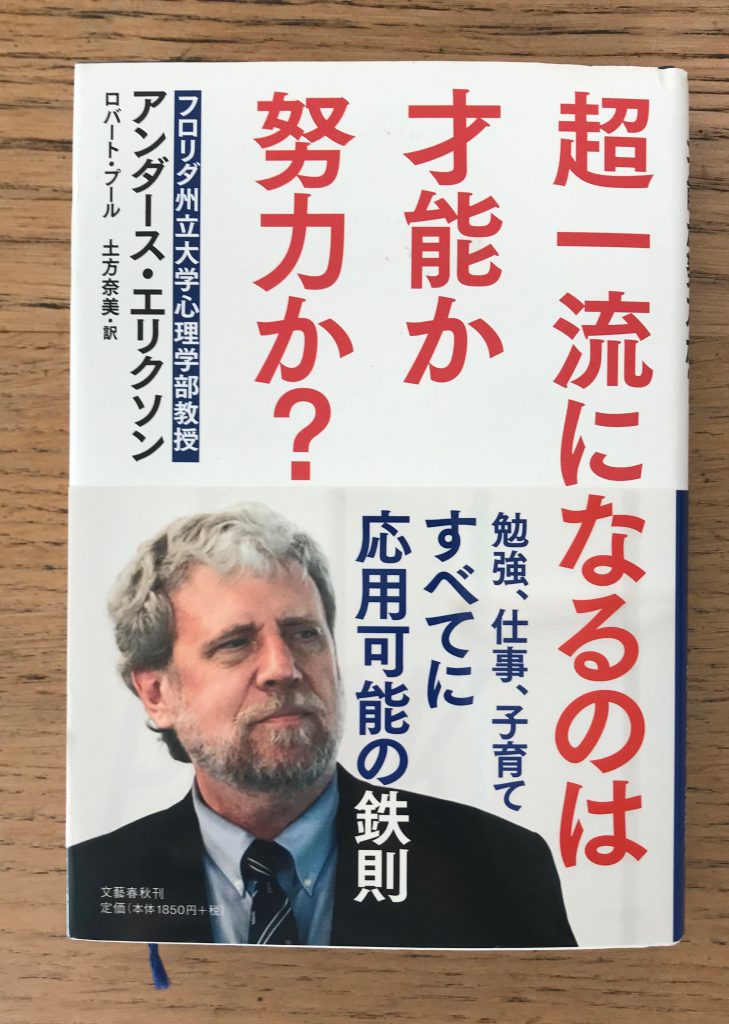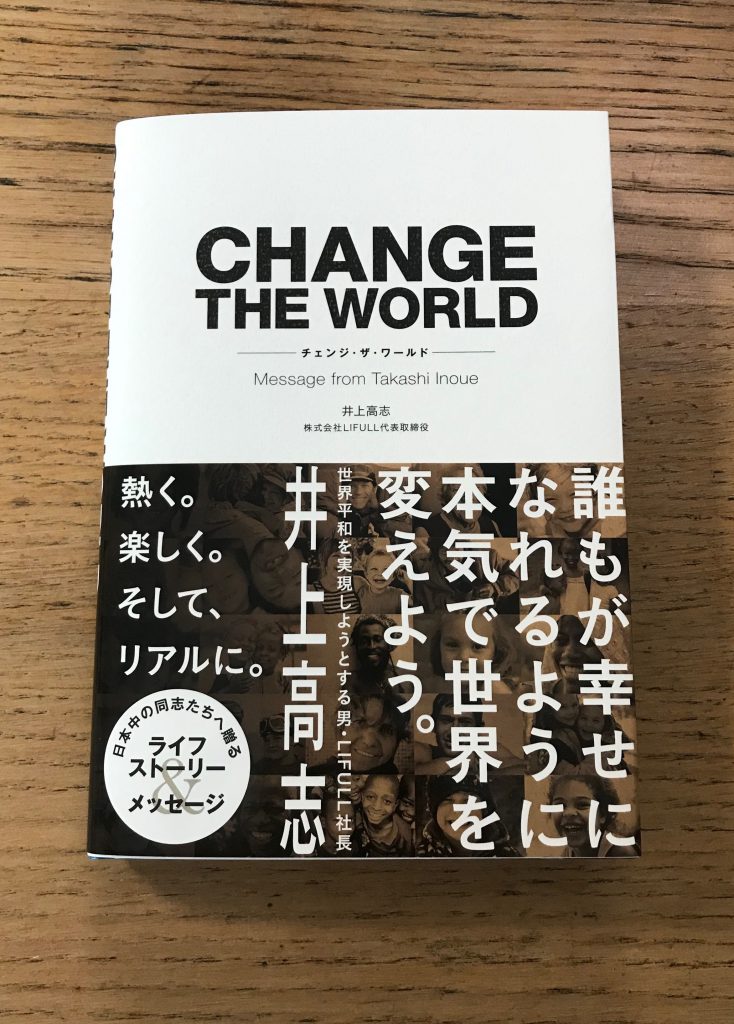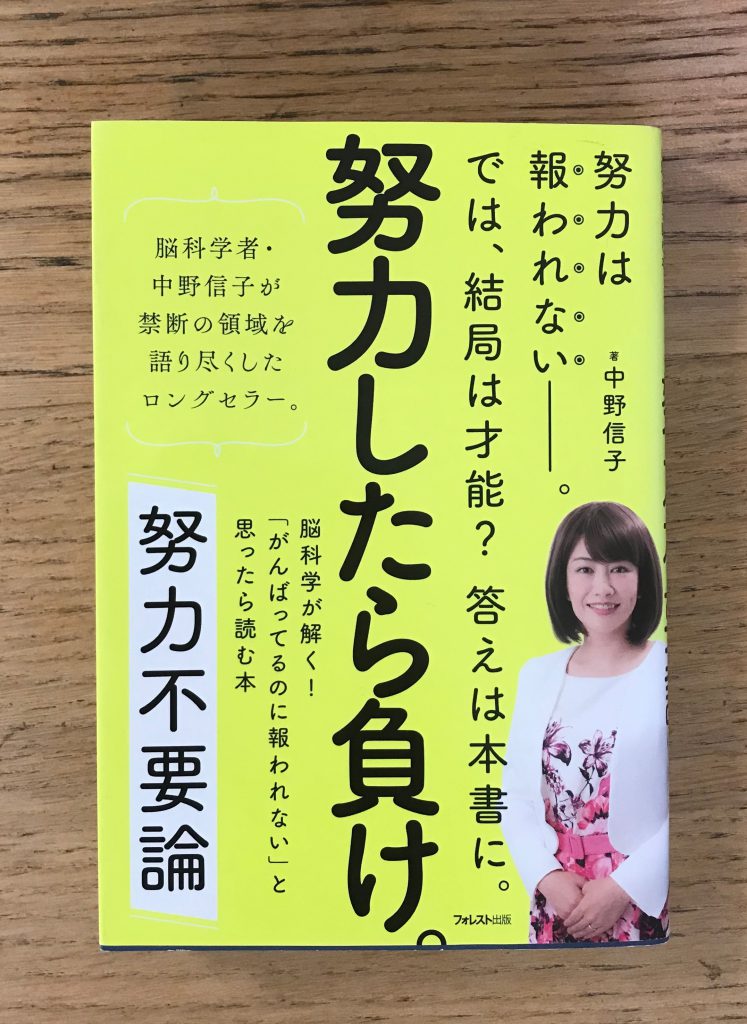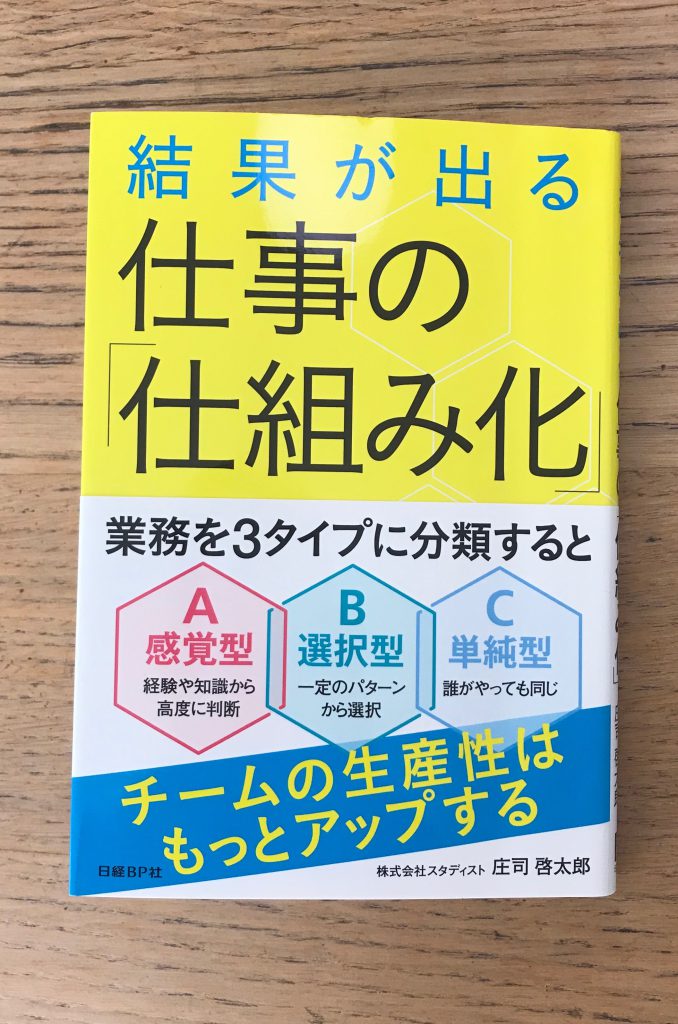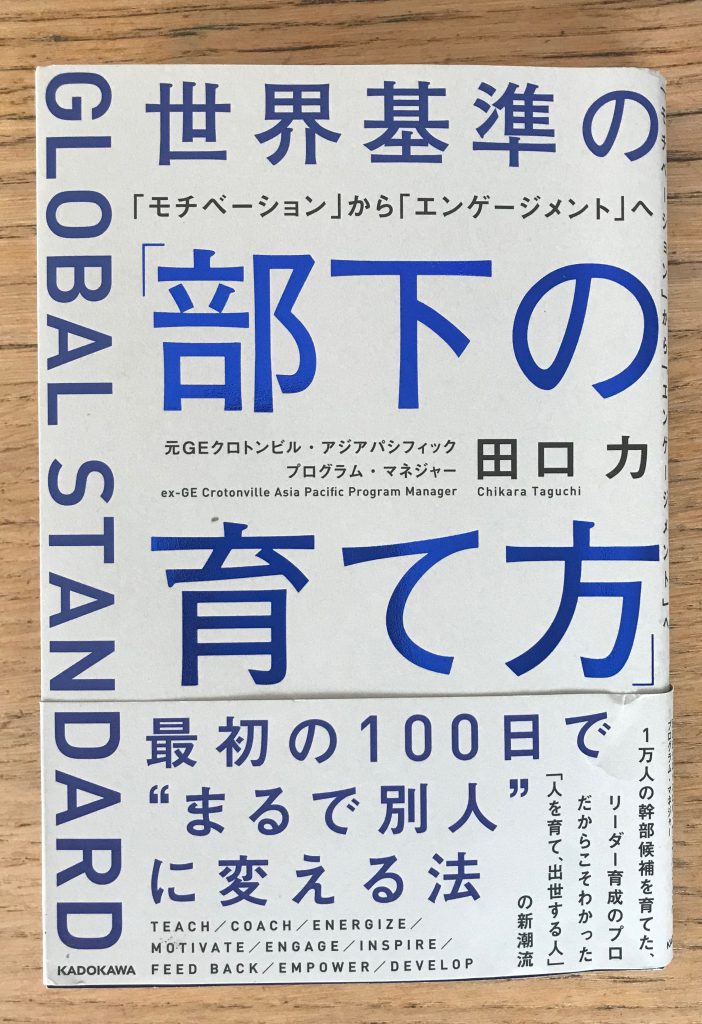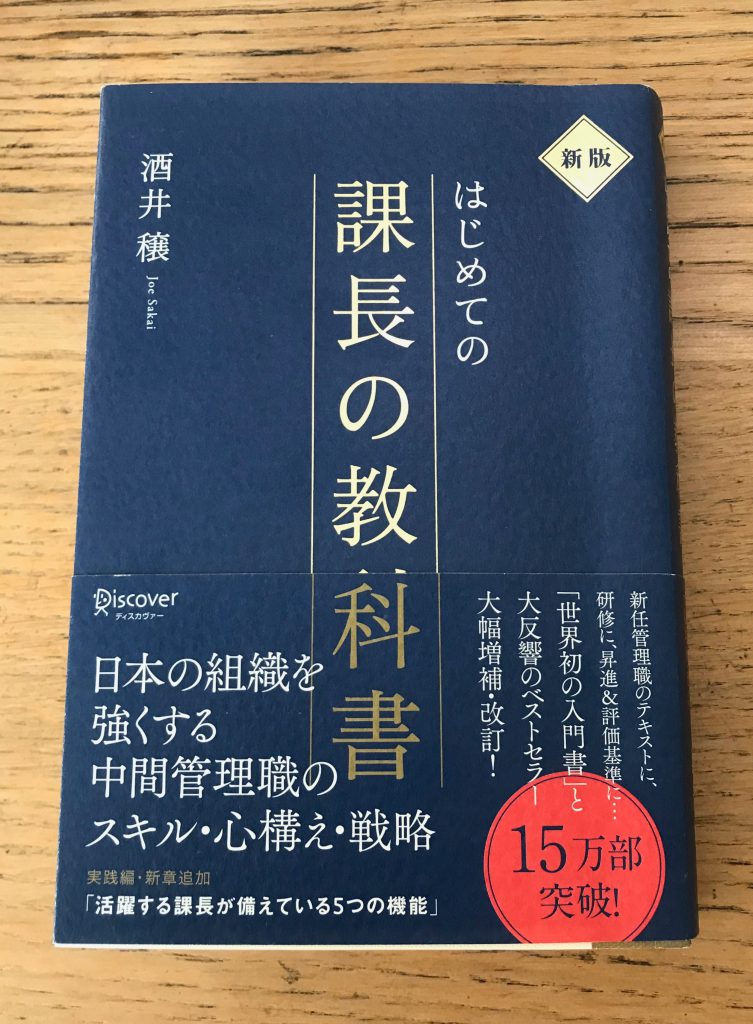第118週
2019/11/10
『ストライカーを科学する』
松原良香著 岩波ジュニア文庫
私はサッカーが好きで1993年Jリーグ発足以降、ずっと日本代表を応援していました。日本代表は間違いなく25年前より強くなっています。ただ、当初から言われ続けているのが「決定力不足」です。本書はこの課題に切り込んだ初めてのサッカー論ということで、私の課題意識とマッチし手に取りました。
ストライカーの要素として、とても印象的だったのが「賢さ」です。ウルグアイ代表のタバレス監督は、稀代のストライカーである同国のルイス・スアレス選手について『「とても賢くて吸収力があり、色々なことを学んでいきました。」』と述べています。グスタボ・ポジェコーチも、『「フィジカル面よりも賢さが、彼を現在のレベルに押し上げたと思う。」』と言っています。著者はこの「賢さ」について、『自分に足りないものを知り、それを改善する努力ができること。』いわば『自分を客観視する力である』とまとめています。
この賢さはサッカーだけでなく、ビジネスにもひいては人の成長全般に通用することです。そして、これがかなり難しい。プロの世界でも監督やコーチの言うことを素直に受け止めきれない選手がいるそうです。ビジネスの世界におきかえれば、上司の言うことを素直に受け止め仕事の中で改善努力をすること。プラス、自身の課題を解決するために勤務時間外でも読書をはじめ個人トレーニングをすることが伸びるには大切だと確認できました。
著者は日本人ストライカーを養成するために、様々な施策を提言しています。その中で私は「ストライカーコーチ」のライセンスを創ることが、一番実効性が高いと感じます。現行で「GKコーチ」のライセンスはあるそうですが、著者曰く「ストライカー」養成も特殊な専門領域となるとのこと。日本のラグビーが長谷川慎スクラムコーチのおかげで世界に並ぶスクラムが実現できたことは記憶に新しく、是非施策を実施し、世界的なストライカーを輩出して欲しいです。
(798字)
光の加減で上手く写真がとれず娘に持ってもらいました