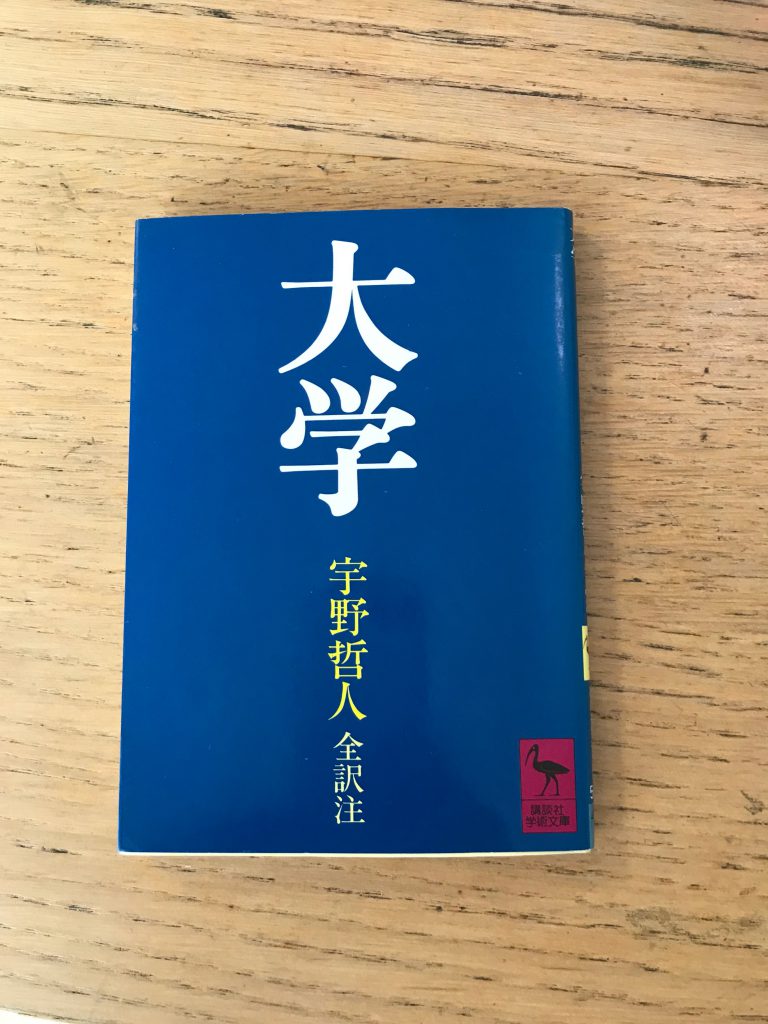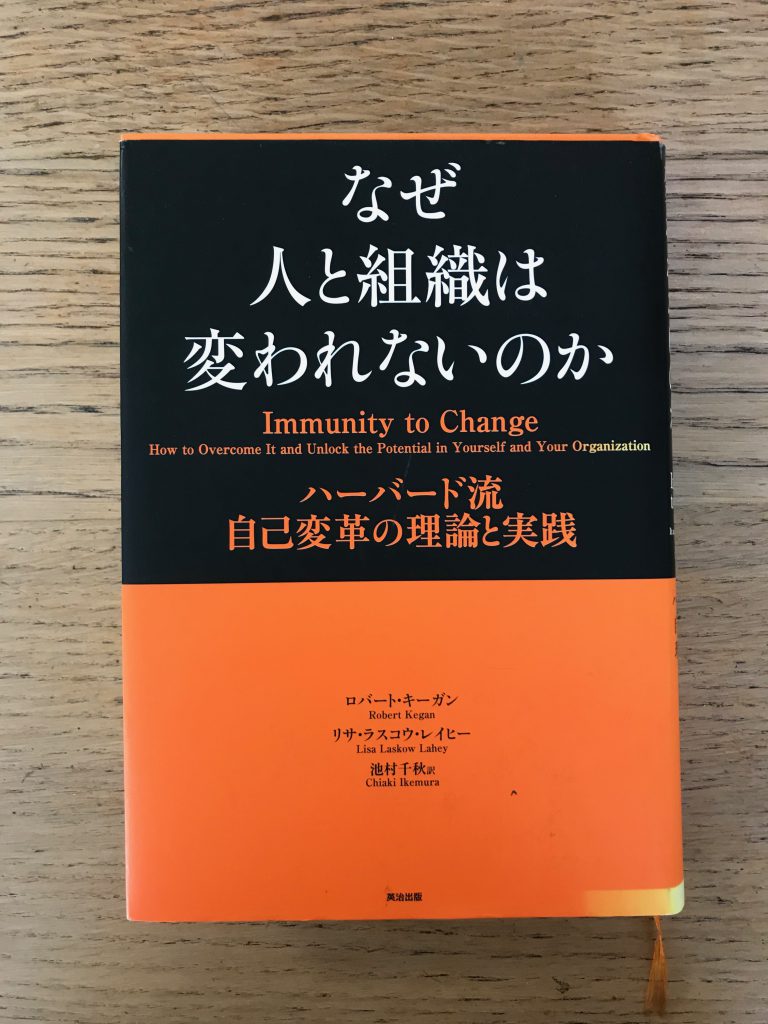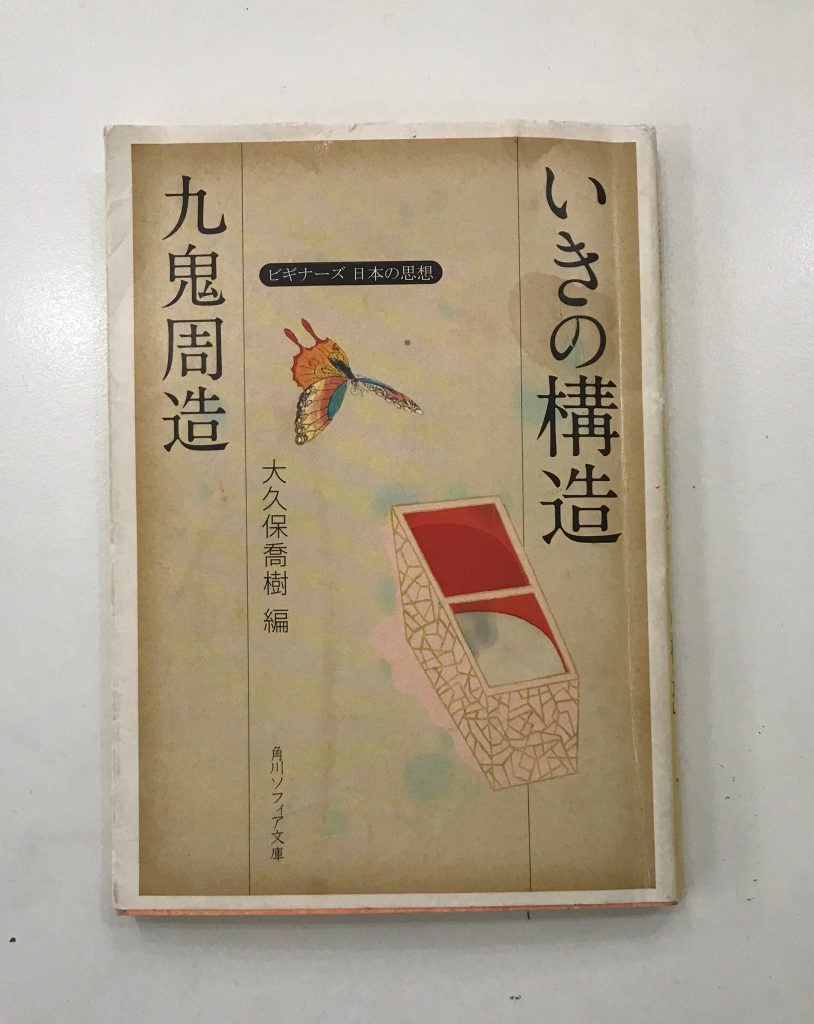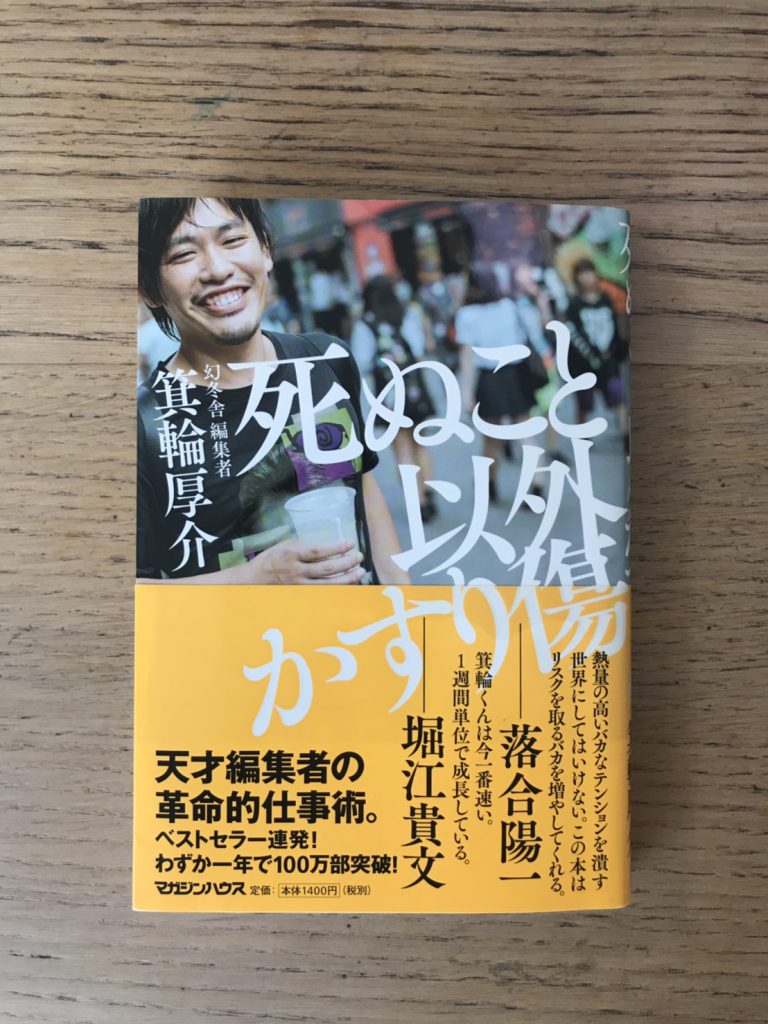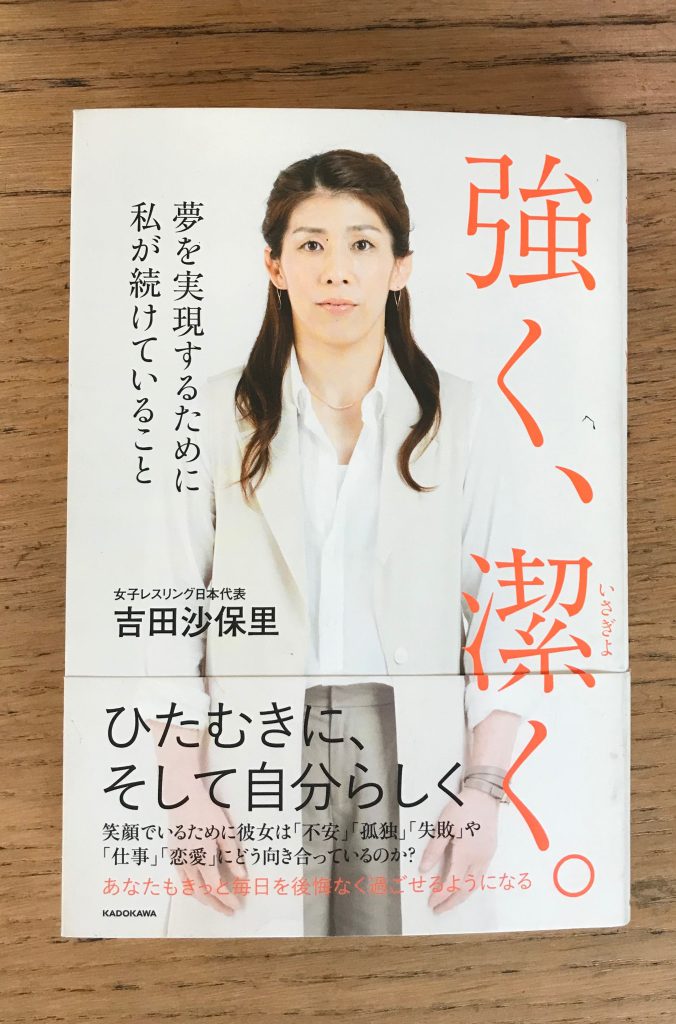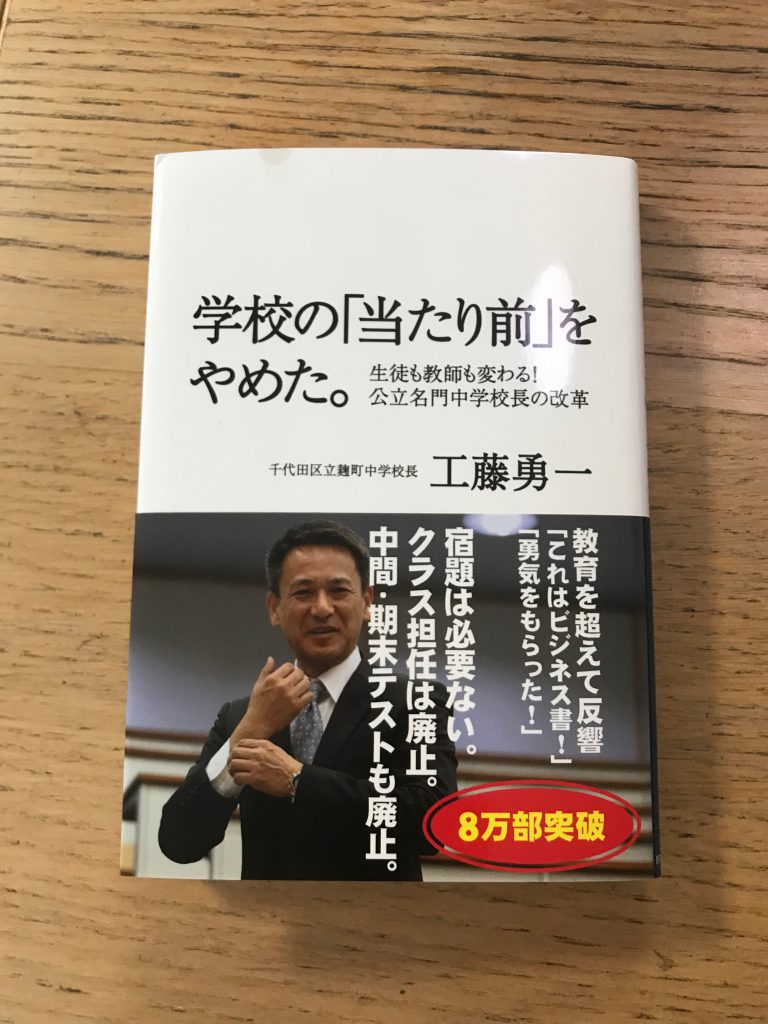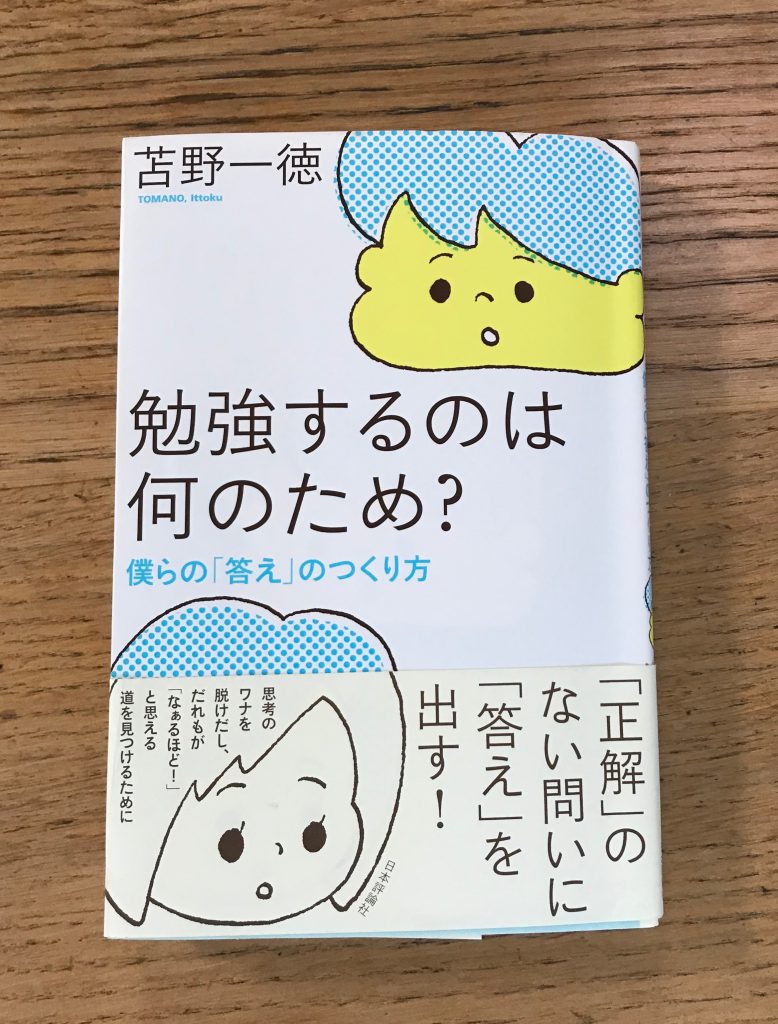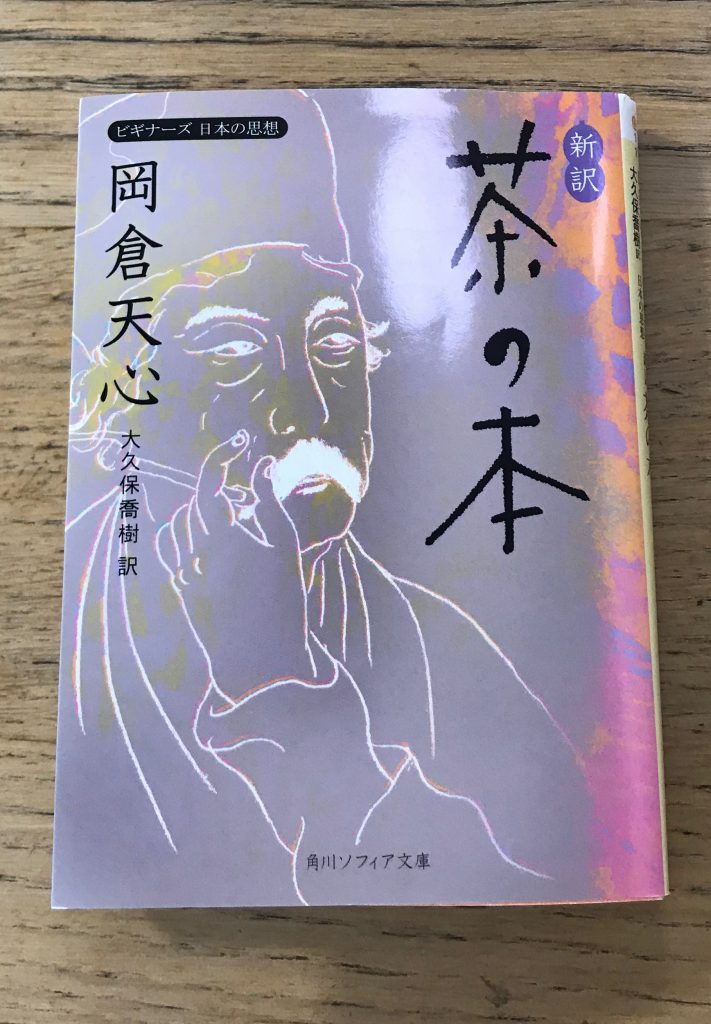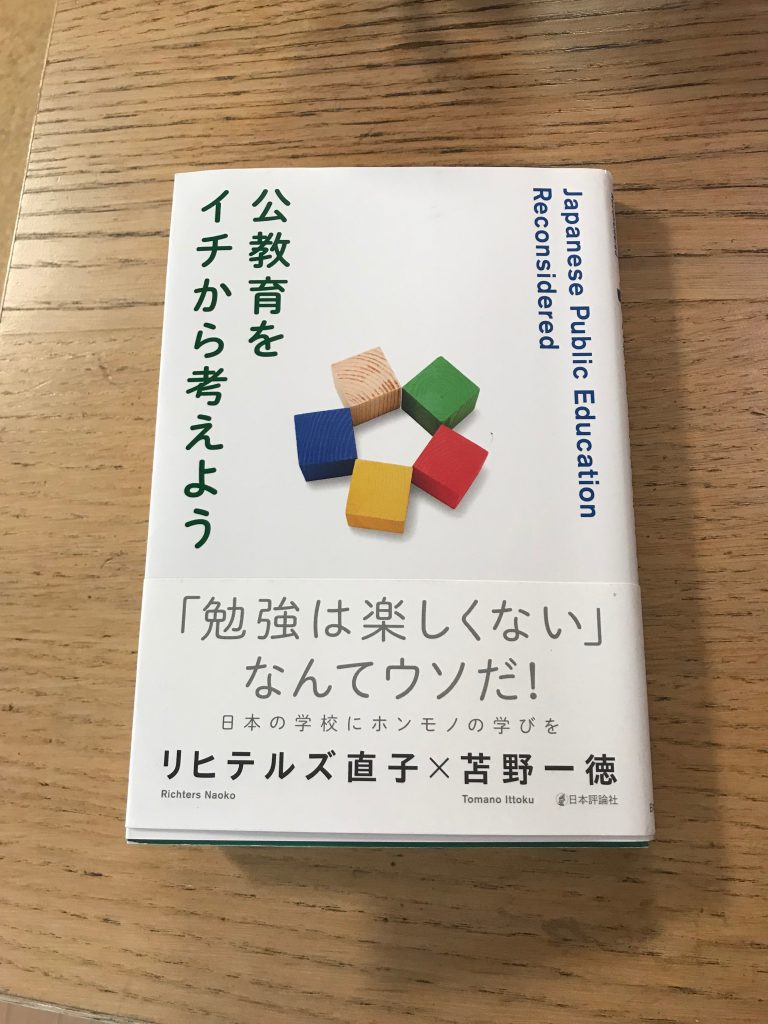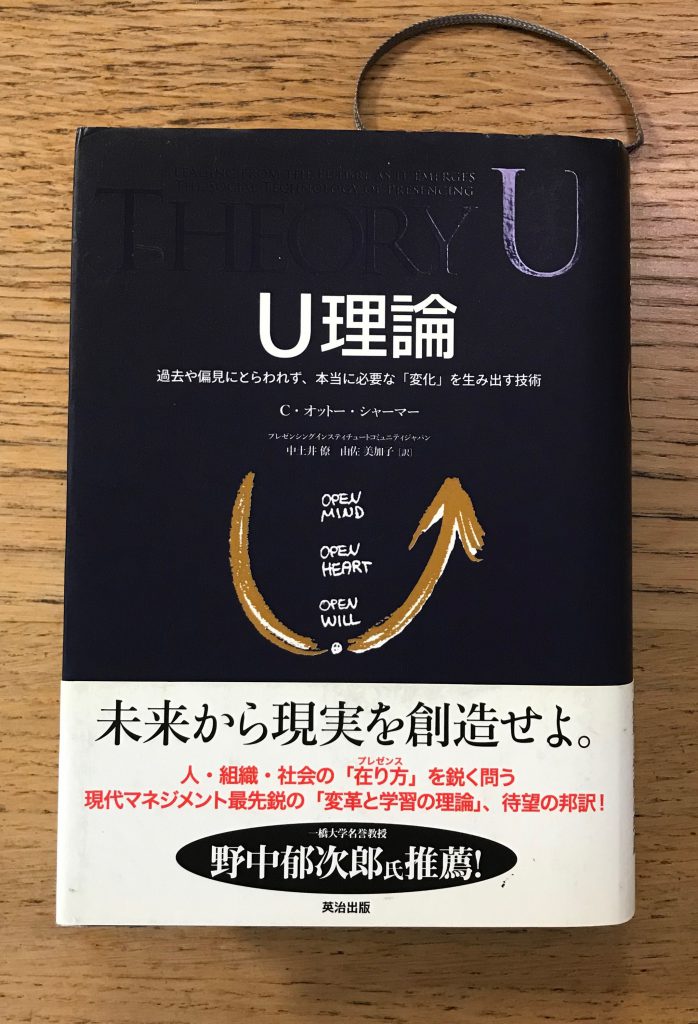第108週
2019/9/1
『大学』
宇野哲人全訳注 講談社学術文庫
私が私淑する人物は二宮尊徳翁です。尊徳翁の生き方に少しでも近づきたいと、報徳記をはじめ毎日触れています。その尊徳翁が幼少期、薪採りの往復時に読誦したと言われるのがこの『大学』です。尊徳翁の思想・行動の深奥をより理解をしたいと考え、本書を手にしました。
本書は儒教の政治思想の根幹を簡潔にまとめた書です。ただ為政者の心構えに止まらずむしろ人としてのあるべき心構えを述べている私は感じました。以下に印象深い章を4つ列記します。
『大学の道は明徳を明らかにするに在り、民を親たにするに在り、至善に止まるに在り。』(経一章)
『大学』の三綱領は、明徳・親民・止至善です。明徳は人が生来もっている立派な本性を指しており、外物に接して私欲の念が起こるが故に、明徳を取り戻す必要があると解釈できます。性善説的な考えに光が見えます。
『物格って后知至る。知至って后意誠なり。意誠にして后心正し。心正しくして后身修まる。身修まって后家斉う。家斉いて后国治まる。国治まって后天下平らかなり。』(経一章)
これは『大学』の八条目を表している文で、格物→到知→誠意→正心→修身→斉家→治国→平天下となっています。そして明徳は格物から修身までを行うことにより、実現するという位置づけになっています。格物到知という真理の探究がスタートになり、結局国を治めるにも一人の人間の探求(謙虚さ)と誠意から始まることが印象的です。
『所謂その意を誠にすとは、自ら欺くなきなり。』(伝六章)
誠実であるためには、自らをごまかし、本心を欺いてはいけない。しかもそれが分かるのは自分のみであり慎独せよという言葉です。ブルームウィルの社是「まっとうに誠実に」を追求していくのに身に沁みました。
『所謂国を治るには必ず先ずその家を斉うとは、その家教うべきからずして、能く人を教しうる者はこれ無し。故に君子は家を出でずして、教えを国に成す。』(伝九章)
自分の家さえ教えることができないのに、国を治めることはできない。身を修め家を教えることができれば自然に一国の模範となり国民が皆その徳に感化されるということです。社会を良くする前に、自分とその家族を良くしていく、というのも身に沁みます。何が起こってもまずは自分と家族と向き合うことです。
(935字)