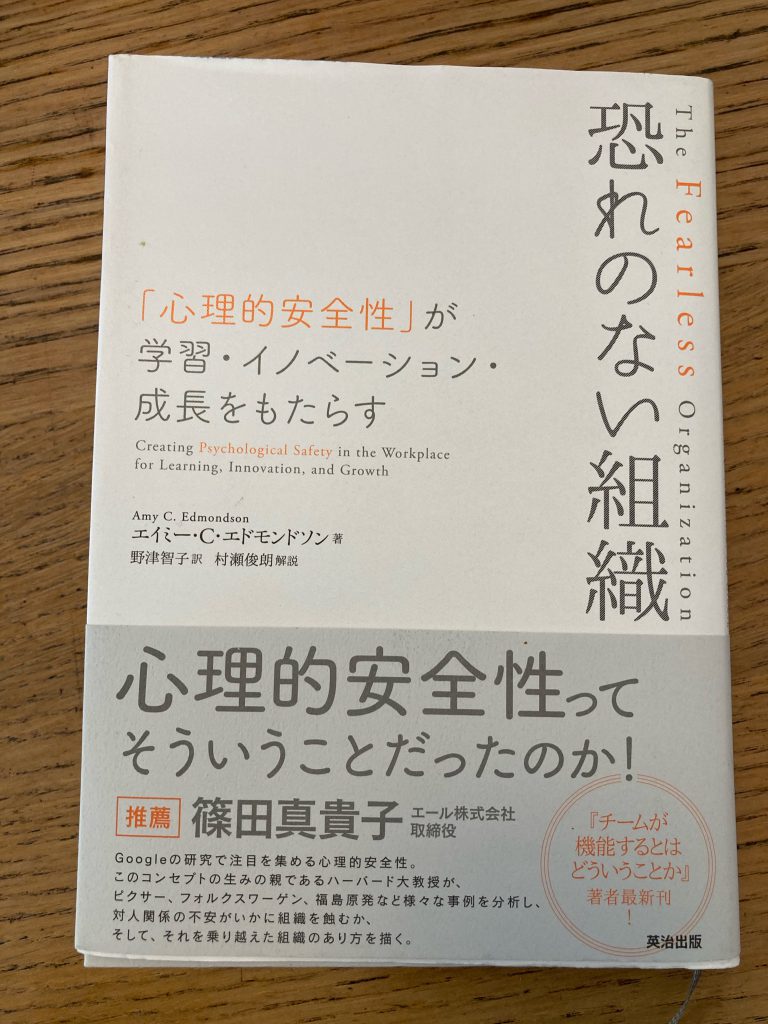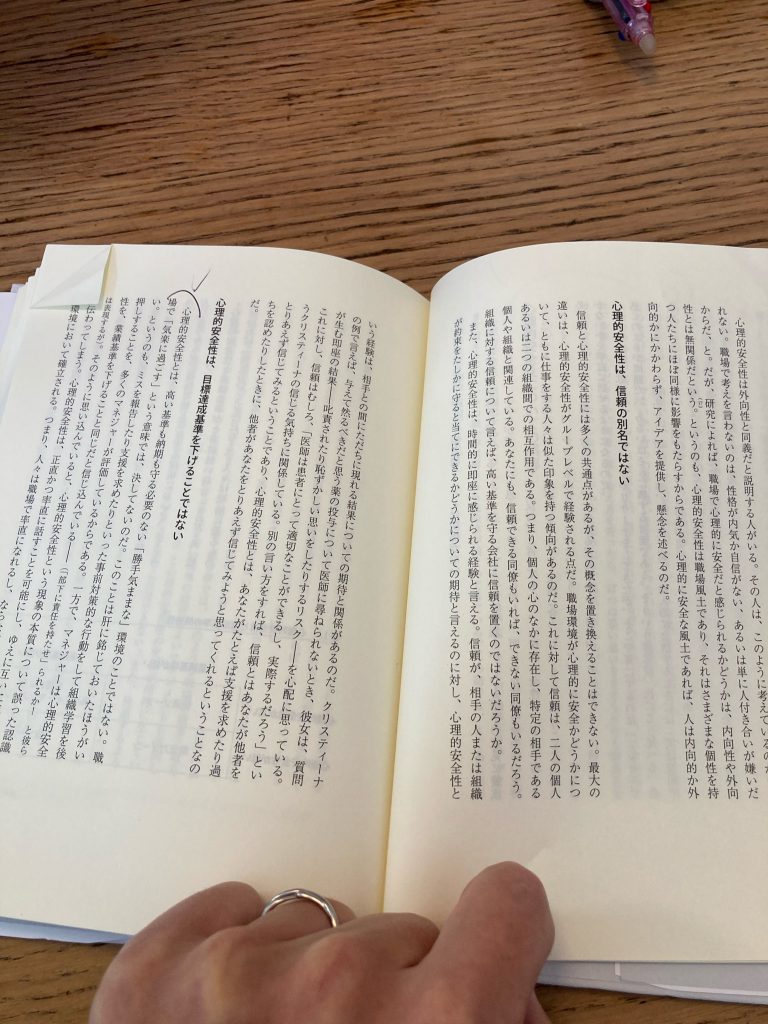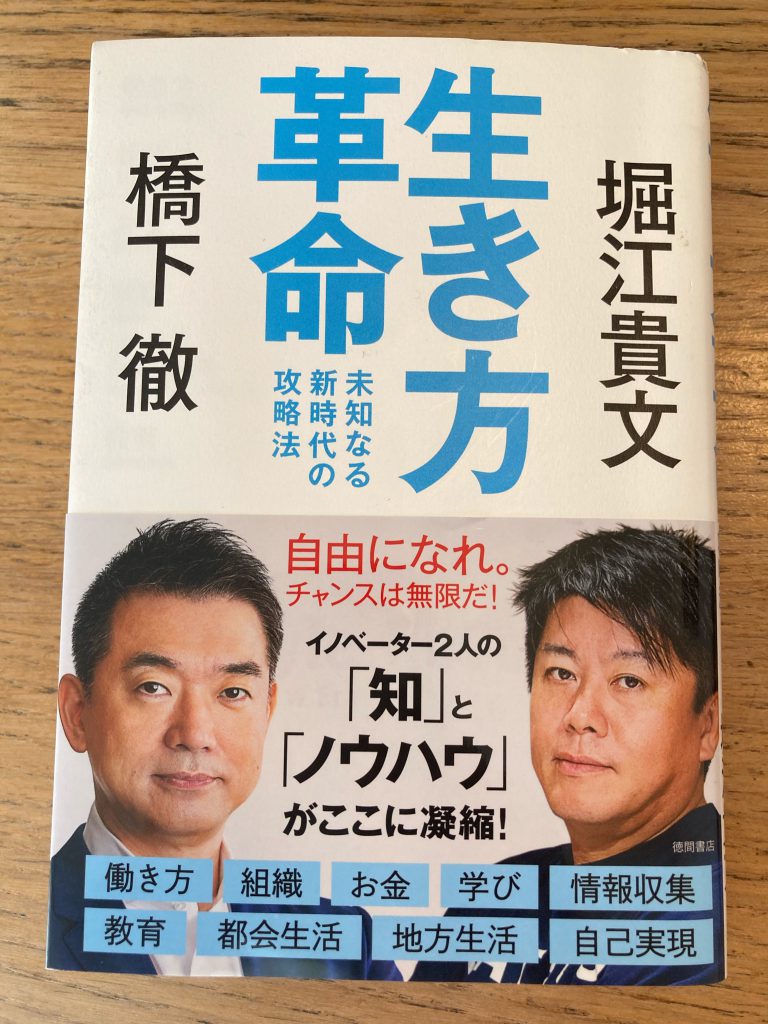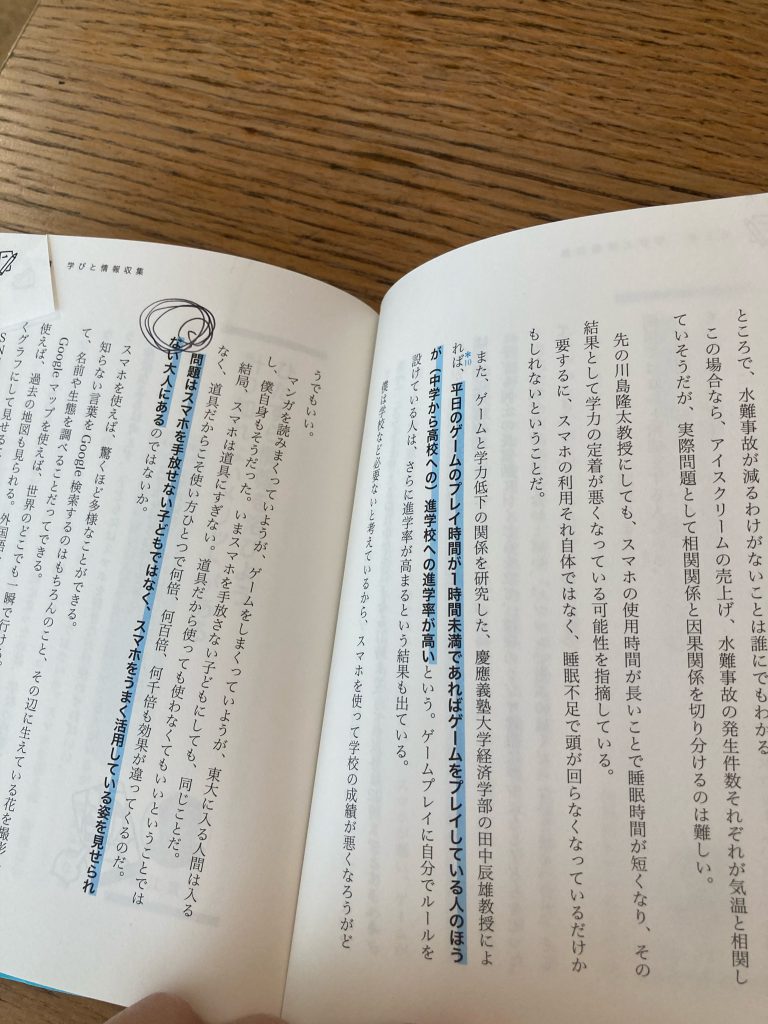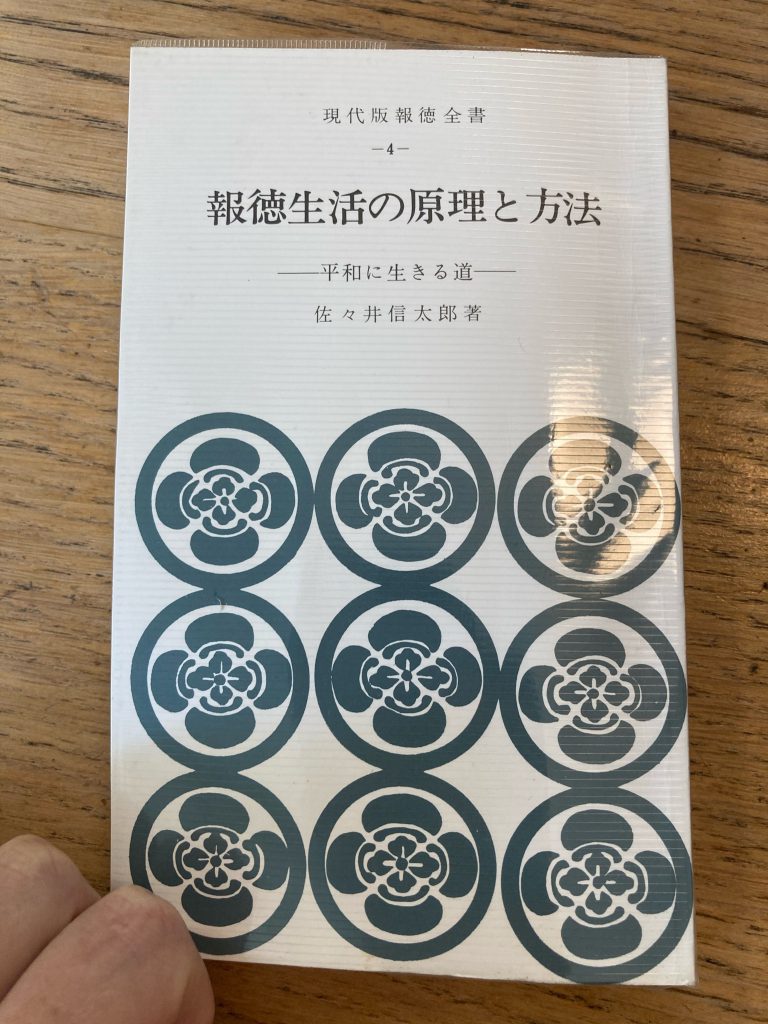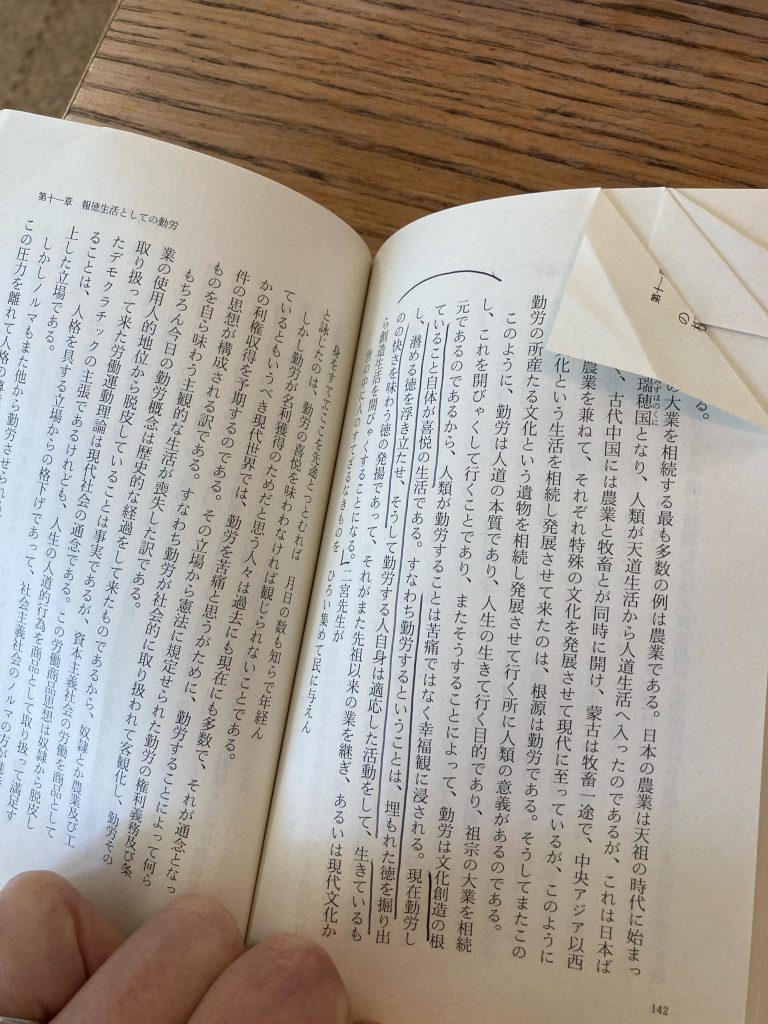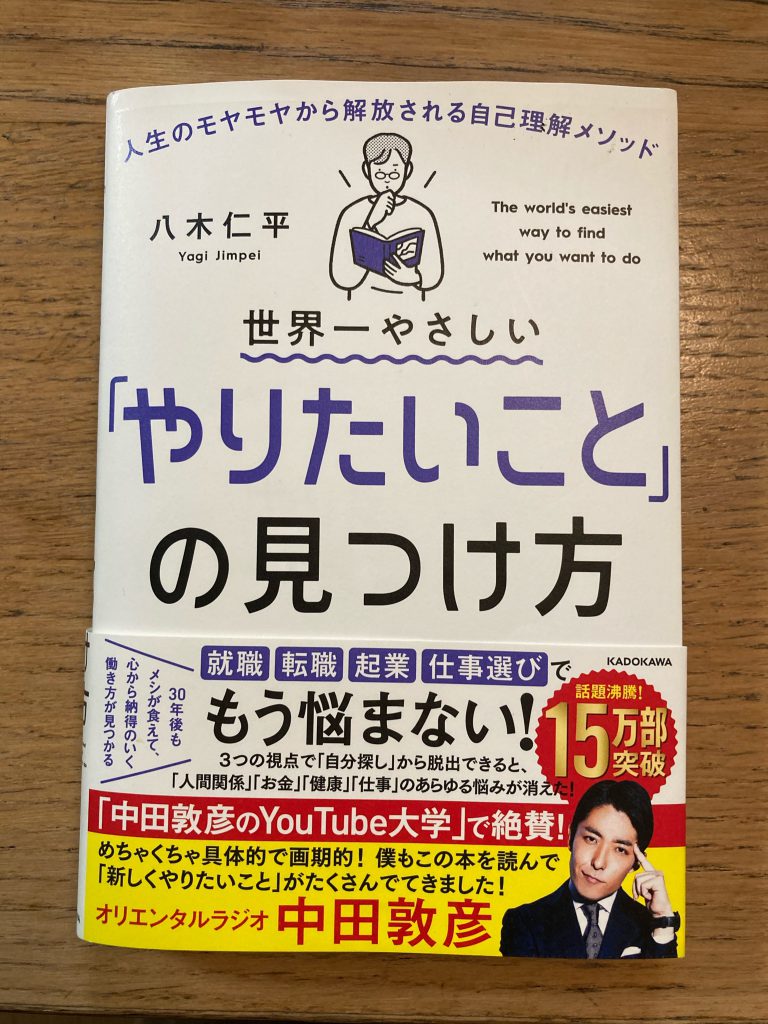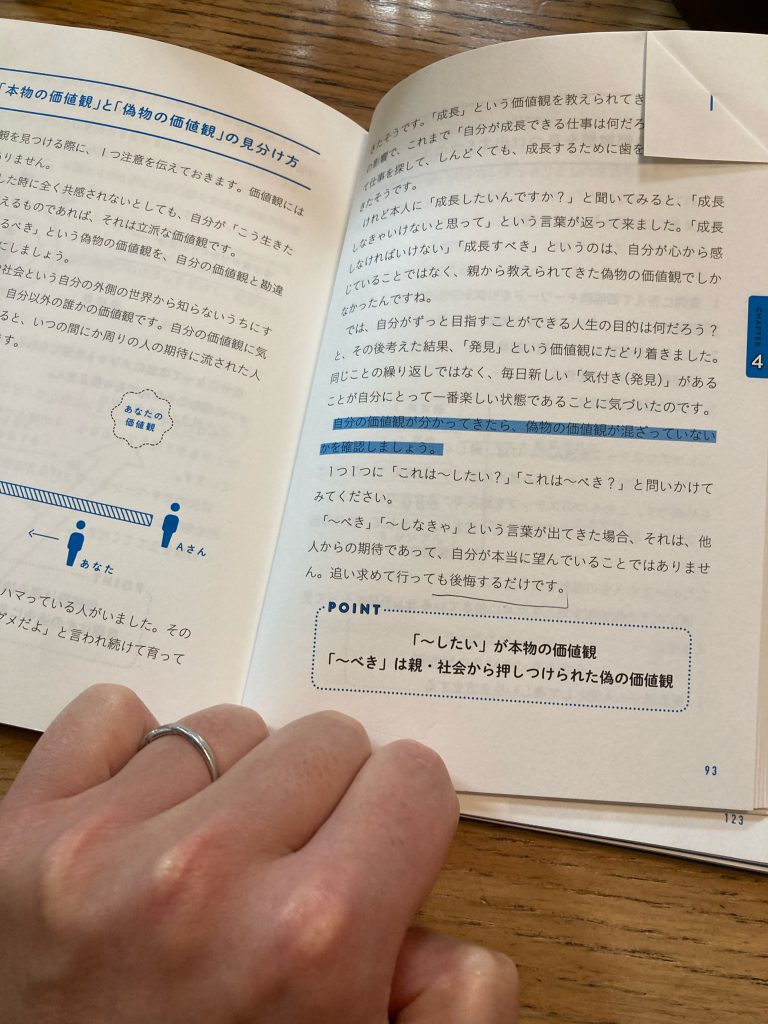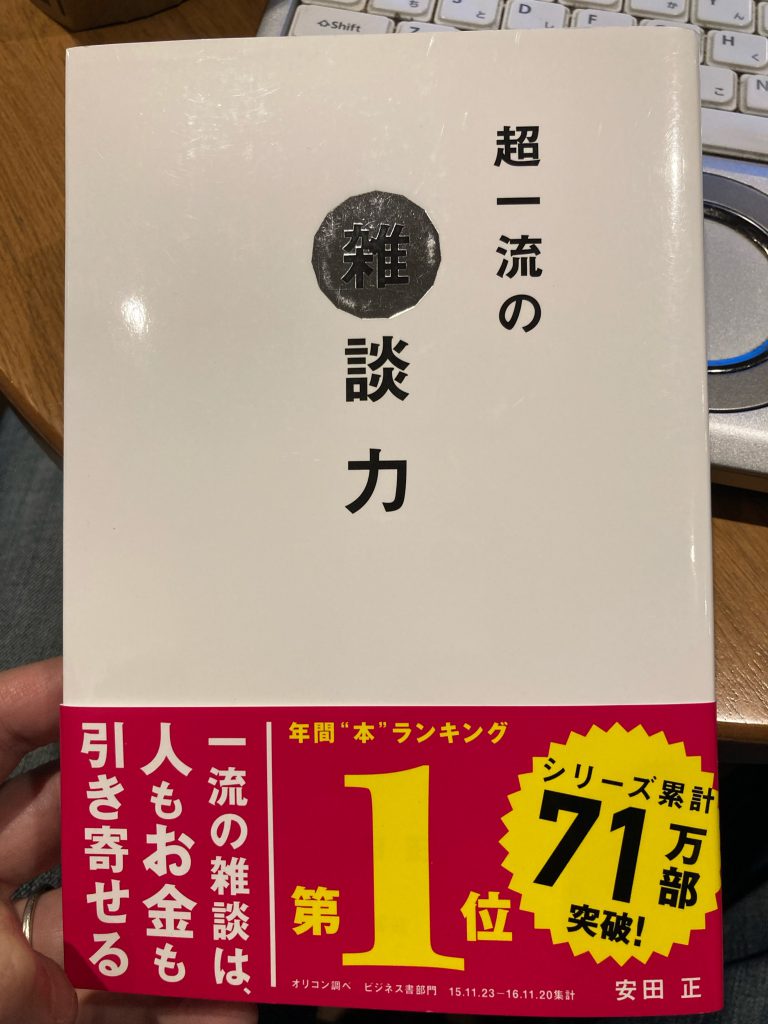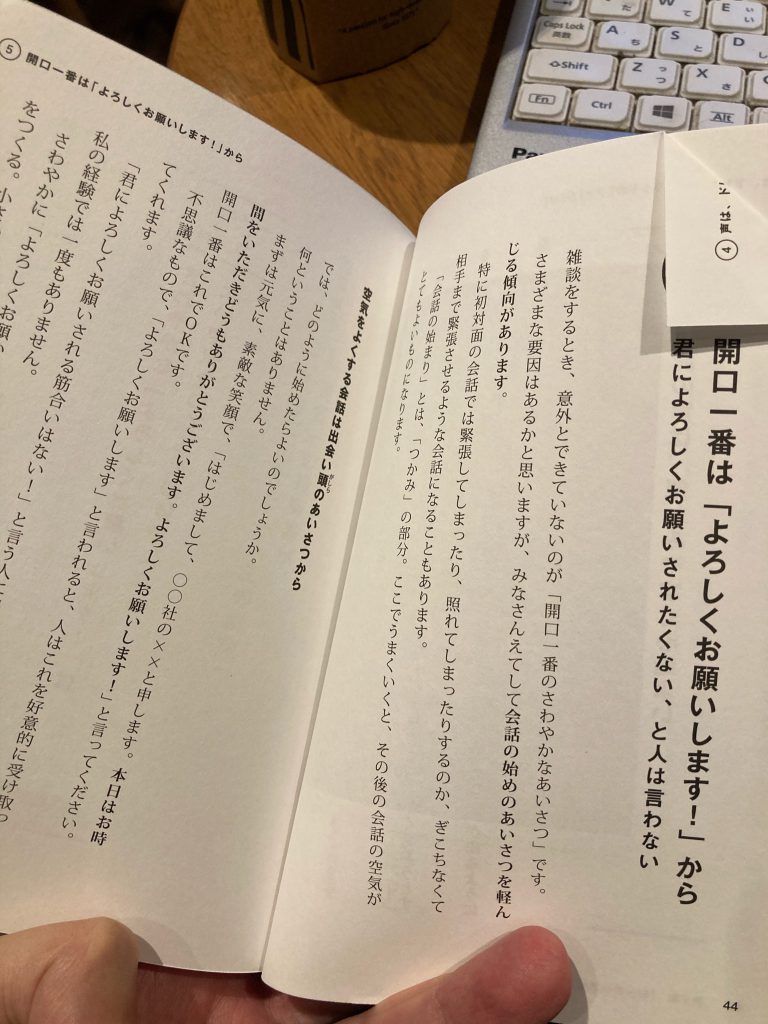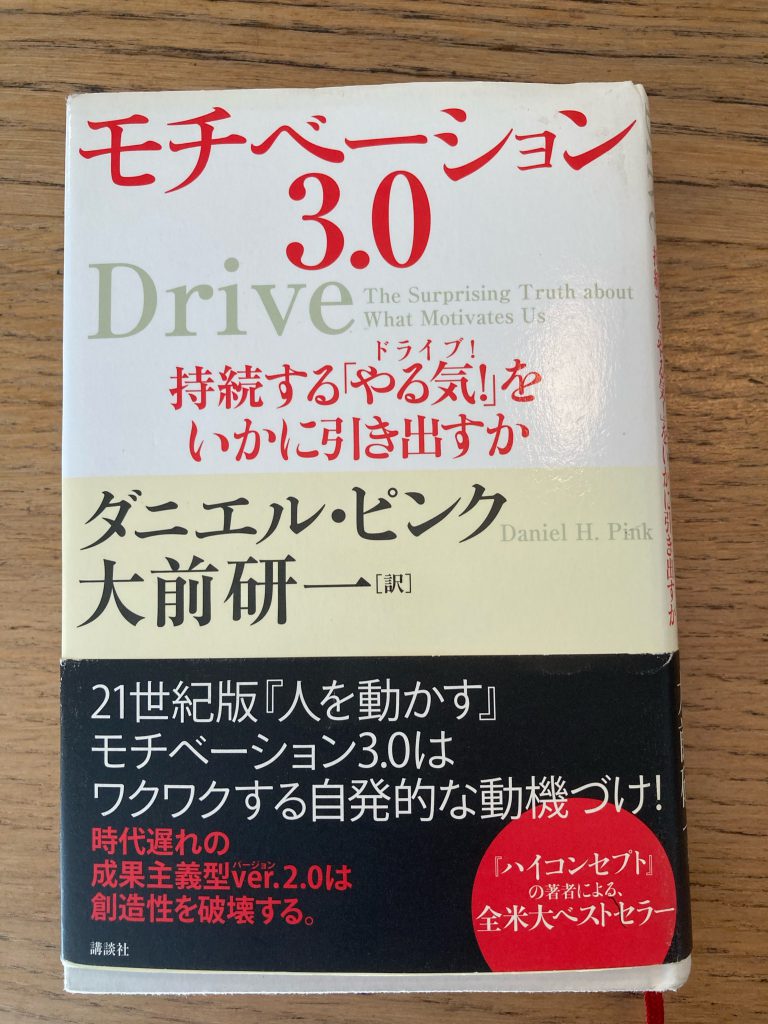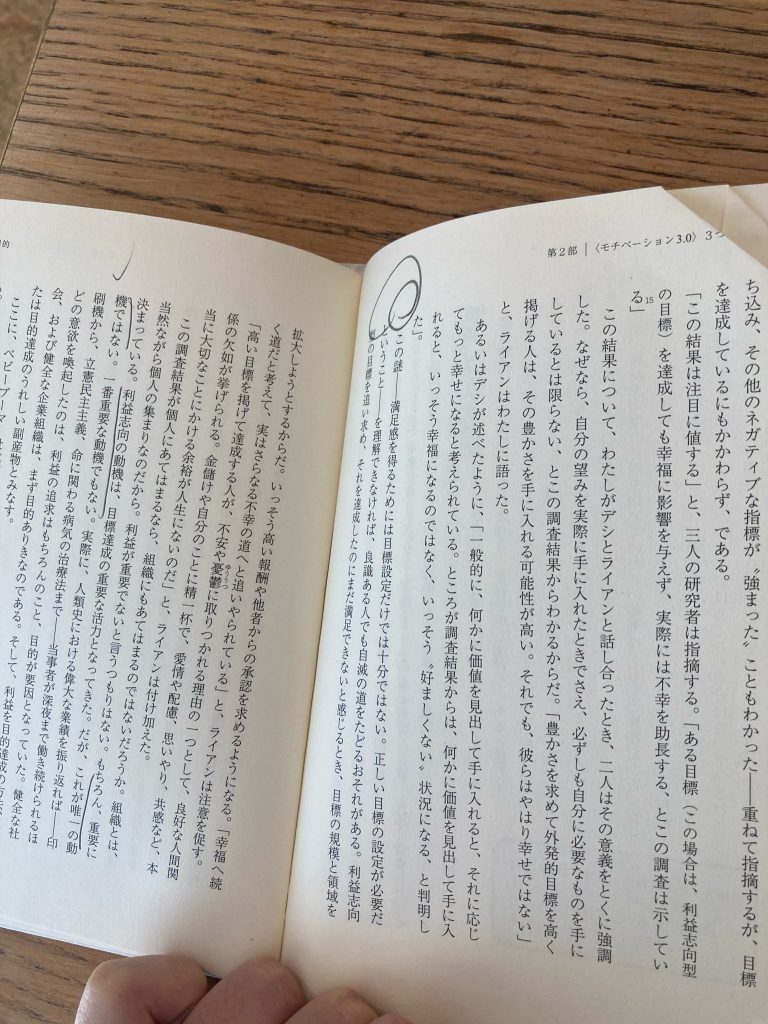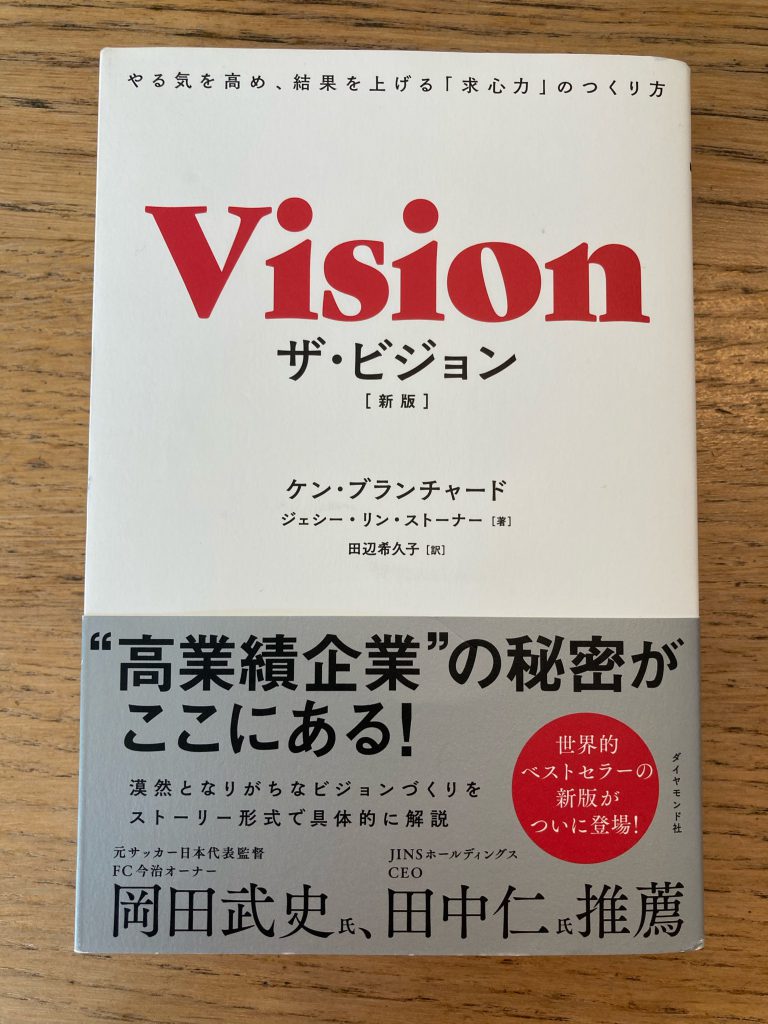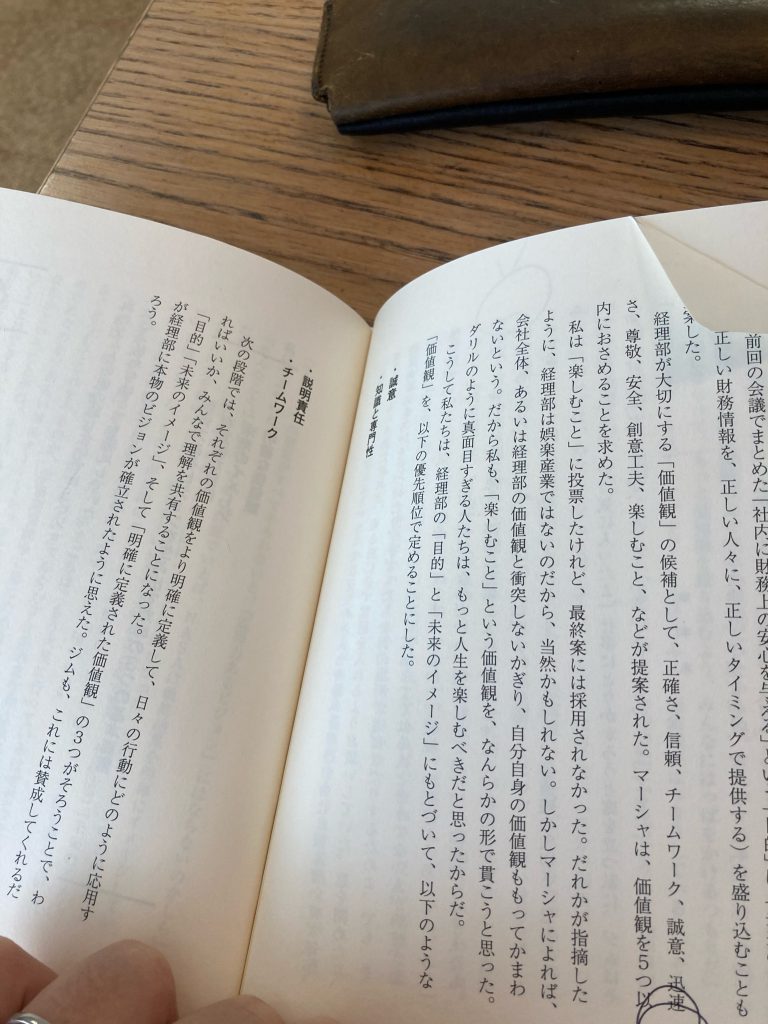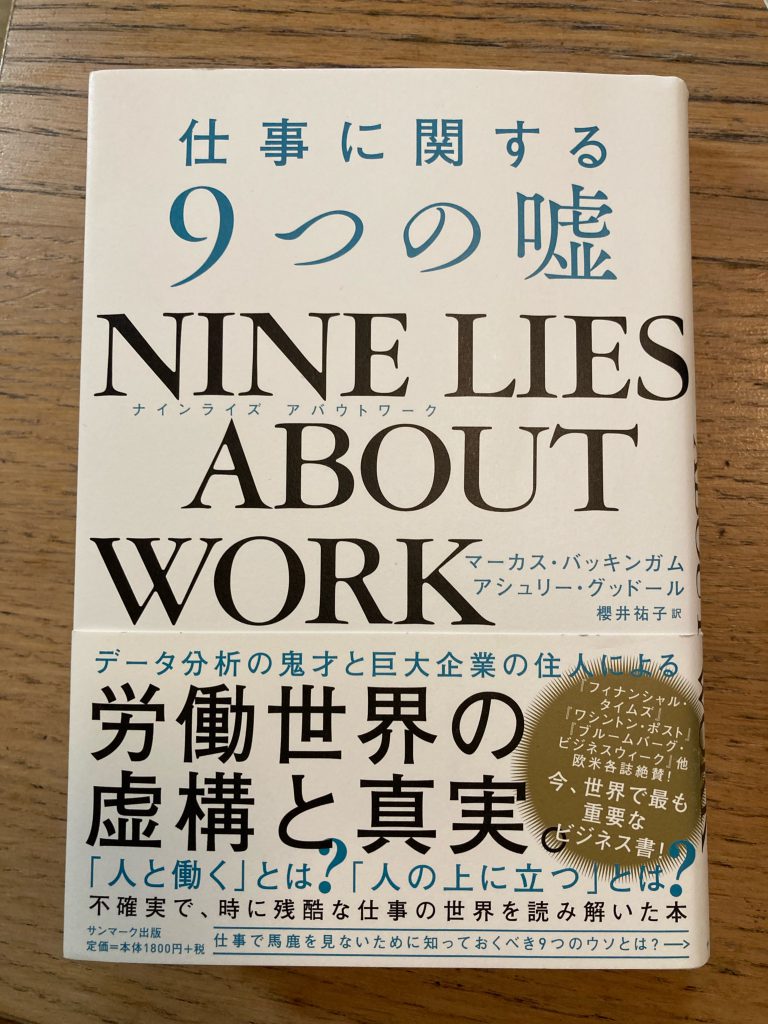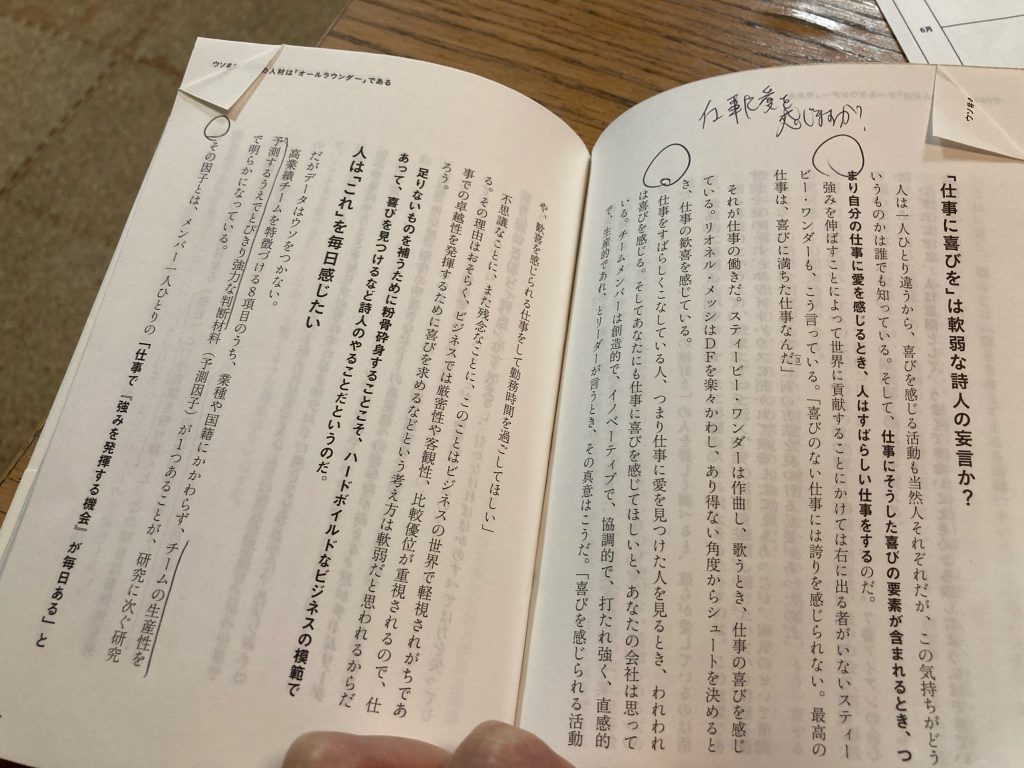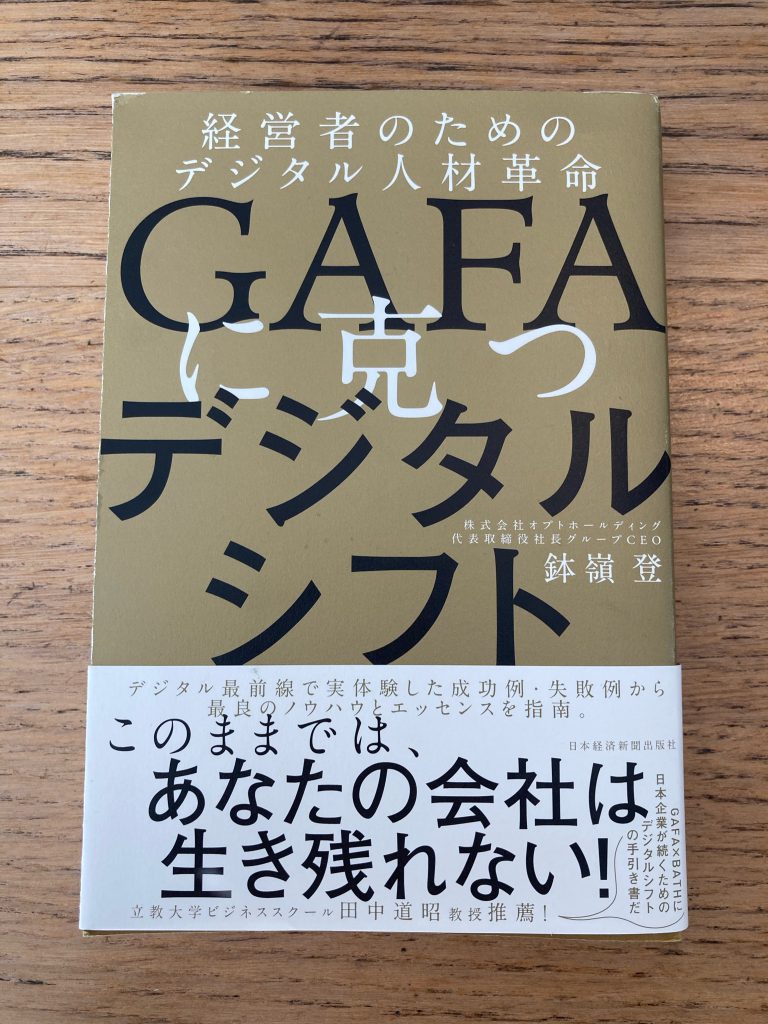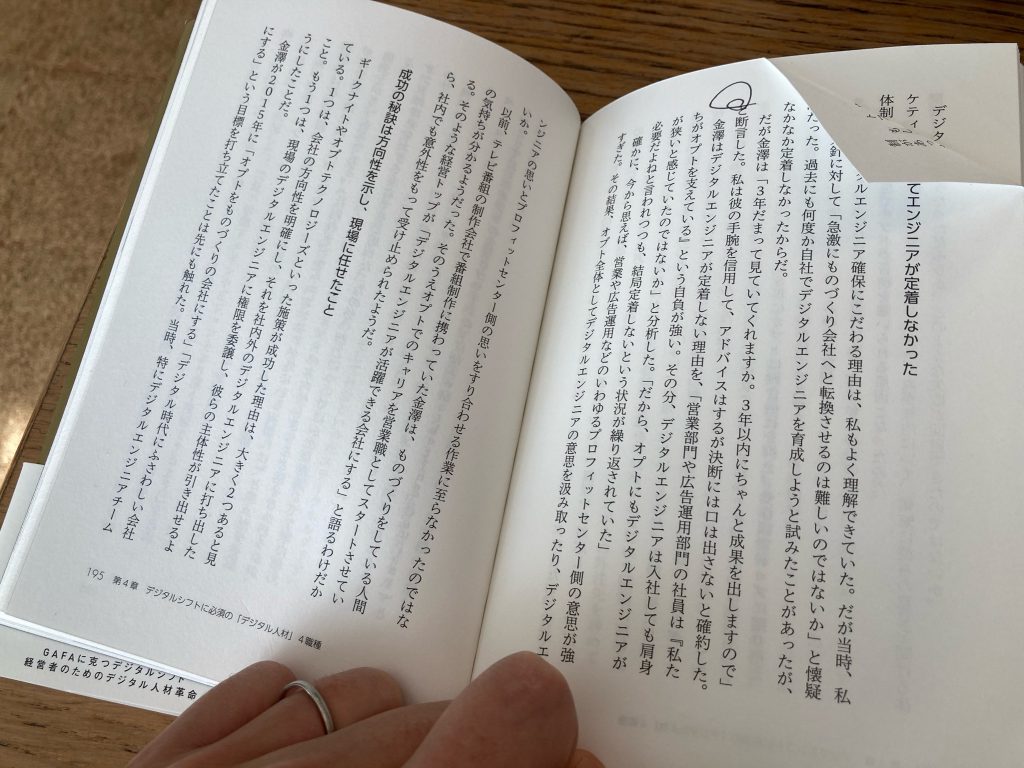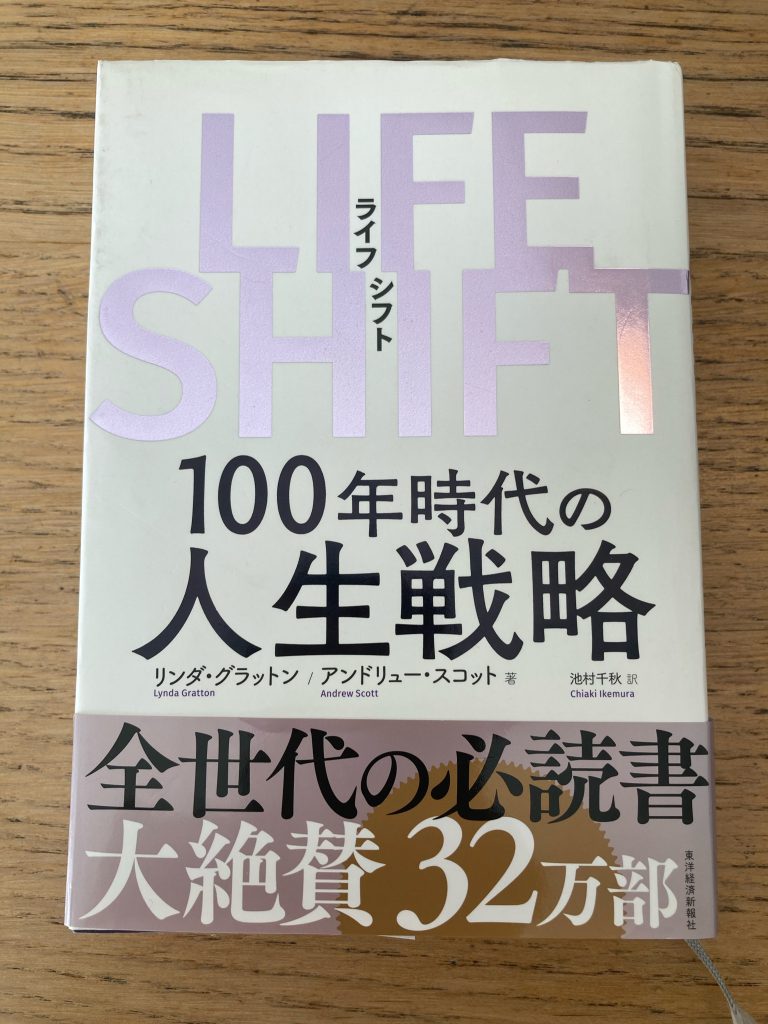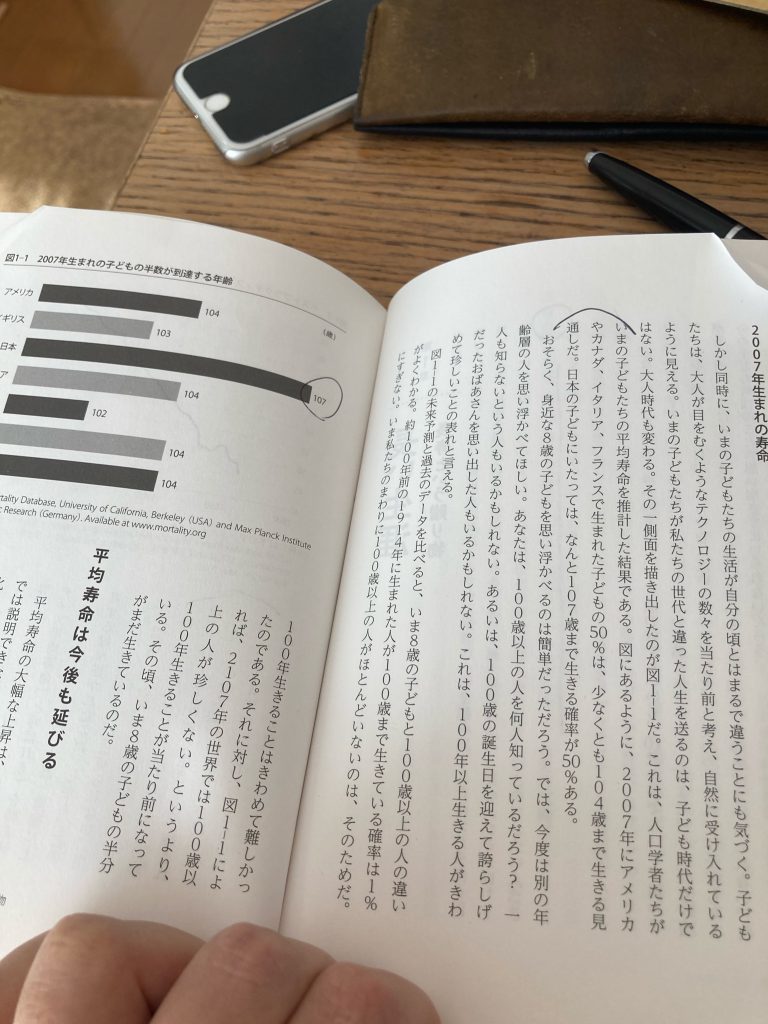第188週
2021/5/2
『恐れのない組織』
エイミー・C・エドモンドソン著 野津智子訳
「心理的安全性」について、まず浮かぶのはプロジェクトアリストテレスです。本プロジェクトはGoogle内で「最高のチームをつくる要因は何か」を発見するために、2012年に発足しました。そして5つの要因を見出しました。
下記、Google re:Workのサイトより引用です。
心理的安全性: 心理的安全性とは、対人関係においてリスクある行動を取ったときの結果に対する個人の認知の仕方、つまり、「無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動をしても、このチームなら大丈夫だ」と信じられるかどうかを意味します。心理的安全性の高いチームのメンバーは、他のメンバーに対してリスクを取ることに不安を感じていません。自分の過ちを認めたり、質問をしたり、新しいアイデアを披露したりしても、誰も自分を馬鹿にしたり罰したりしないと信じられる余地があります。
相互信頼: 相互信頼の高いチームのメンバーは、クオリティの高い仕事を時間内に仕上げます(これに対し、相互信頼の低いチームのメンバーは責任を転嫁します)。
構造と明確さ: 効果的なチームをつくるには、職務上で要求されていること、その要求を満たすためのプロセス、そしてメンバーの行動がもたらす成果について、個々のメンバーが理解していることが重要となります。目標は、個人レベルで設定することもグループレベルで設定することもできますが、具体的で取り組みがいがあり、なおかつ達成可能な内容でなければなりません。Google では、短期的な目標と長期的な目標を設定してメンバーに周知するために、「目標と成果指標(OKR)」という手法が広く使われています。
仕事の意味: チームの効果性を向上するためには、仕事そのもの、またはその成果に対して目的意識を感じられる必要があります。仕事の意味は属人的なものであり、経済的な安定を得る、家族を支える、チームの成功を助ける、自己表現するなど、人によってさまざまです。
インパクト: 自分の仕事には意義があるとメンバーが主観的に思えるかどうかは、チームにとって重要なことです。個人の仕事が組織の目標達成に貢献していることを可視化すると、個人の仕事のインパクトを把握しやすくなります。
(出典 Google re:Work
https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/define-team/Goolge)
心理的安全性について、本書は何度も読み返し、まとめたいと思う学術書です。
今回は特に印象深かった2のことを書きます。
1.心理的安全性についての誤解
「心理的安全性は、感じよく振る舞うこととは関係がない。」
「職場で『気楽に過ごす』という意味では、決してないのだ。」
「高い基準も納期も守る必要のない『勝手気ままな』環境のことではない。」
「正直かつ率直に話すことを可能にし、ゆえに互いに尊敬しあう環境において確立される。」
心理的安全性は、メンバーを擁護し、成果責任を問うことなく、何となくふわっとした印象をもっている方もいると思います。高い成果に向け、正直かつ率直に話せる関係性と捉えることがとても重要と考えます。
2.心理的安全性の作り方
子ども病院のジェリー・モラスCEOの例を出して説明しています。
(1)土台をつくる
仕事のフレーミングをすること。事故が起きるのはシステムの複雑さにはなく、能力不足という思い込みを変えてもらいたい考えた。医療事故が常に起きている統計などを示す。「調査する→研究する」「ミス→事故・失敗」と言葉を変えるなどした。
(2)参加を求める
スタッフから依然としてミスの報告が少ない中、「ミスがあったか」ではなく、「あなたの患者は、あなたが目指したとおり、今週ずっと、あらゆることにおいて安全でしたか」と問うように変えた。そしてクロスファンクショナルを「患者の安全運転委員会」のチームを作った。
(3)生産的に対応する
「責任を問われない報告」という方針を明確にした。実際に報告があれば感謝をした。
心理的安全性のレシピを読んでいて気づいたがことがあります。それは、リーダーが「あなたたちが悪いわけではない。システムが悪いのだ」という根本的な考えをもつことが必須ということです。
(1081字)