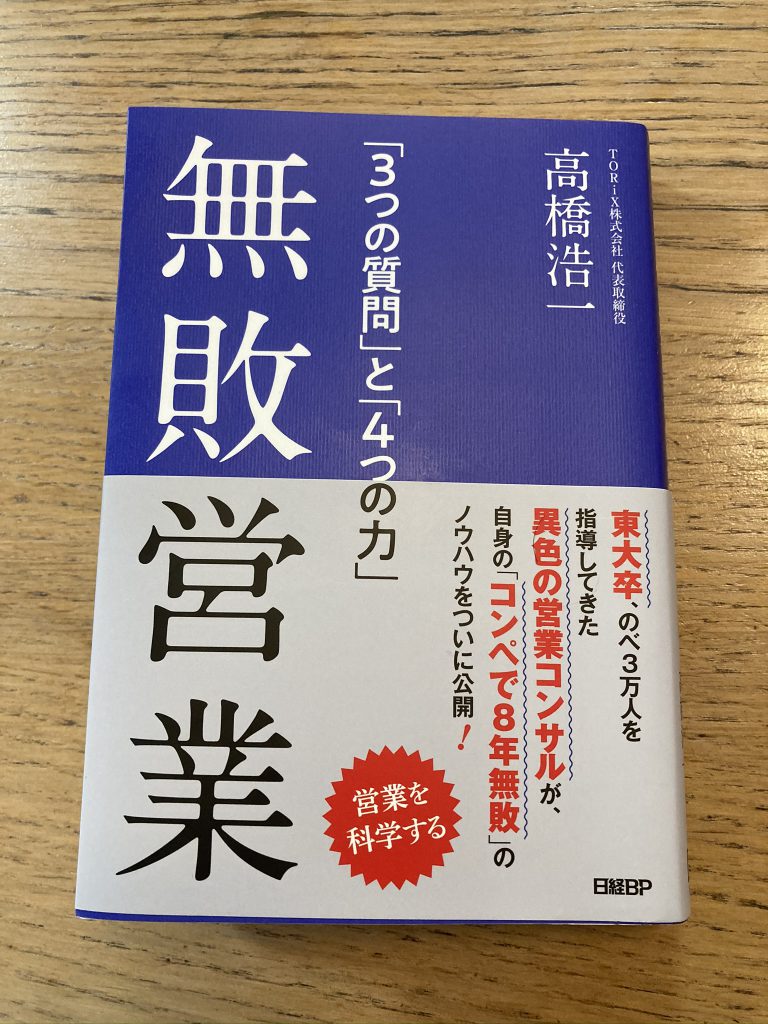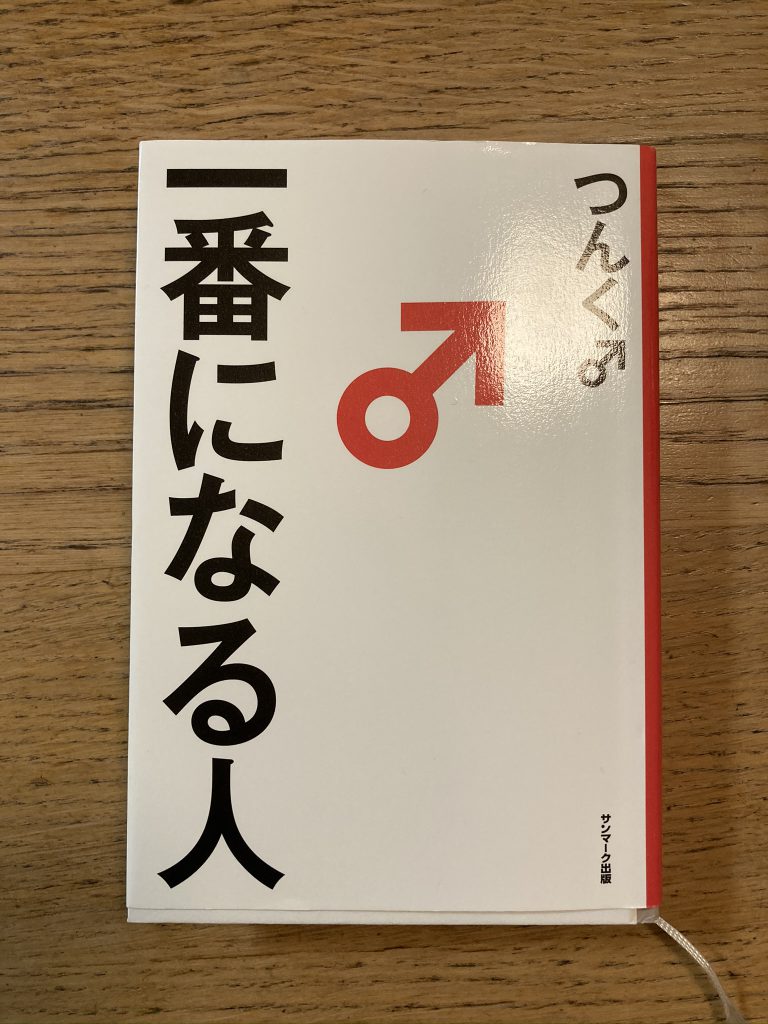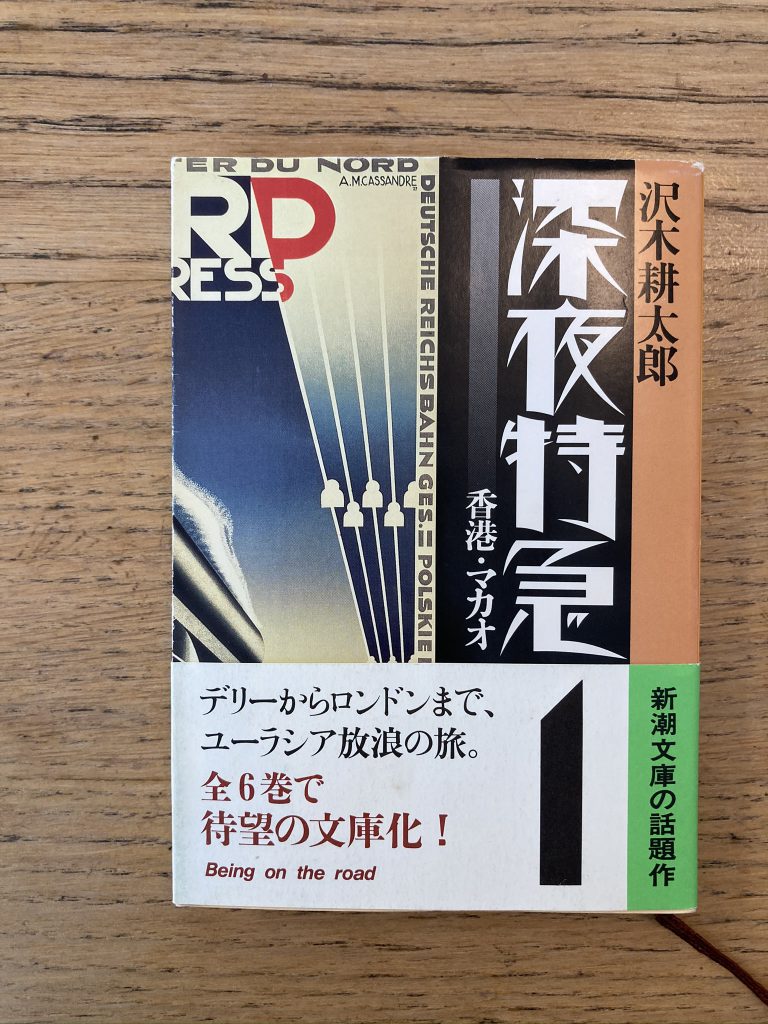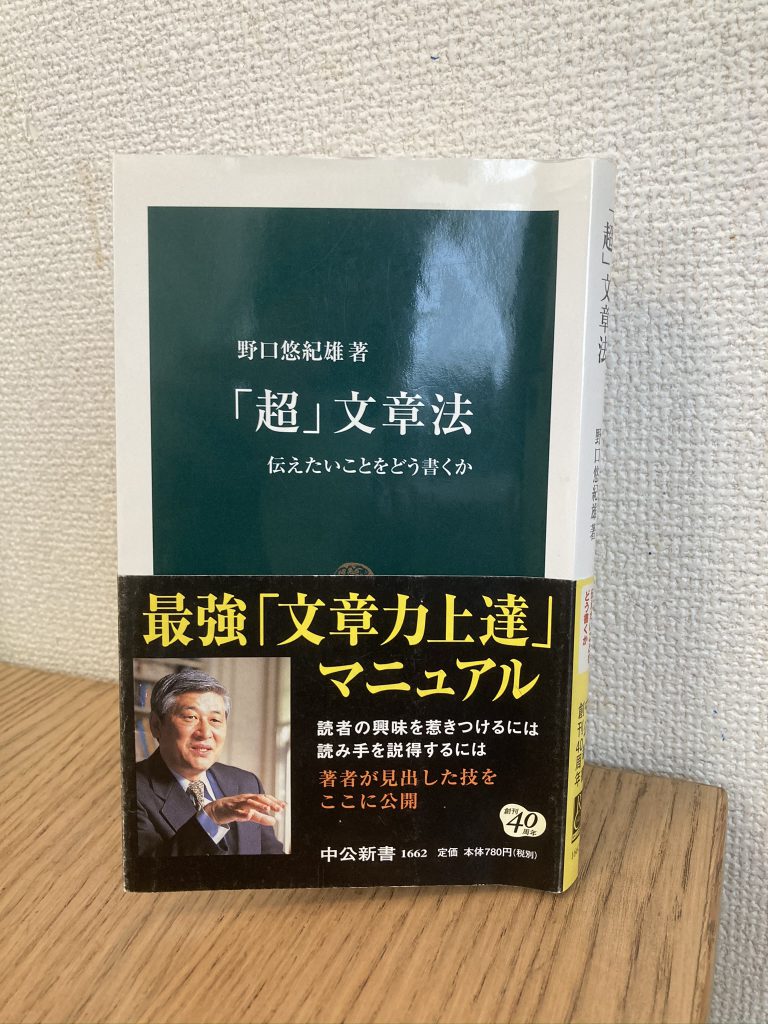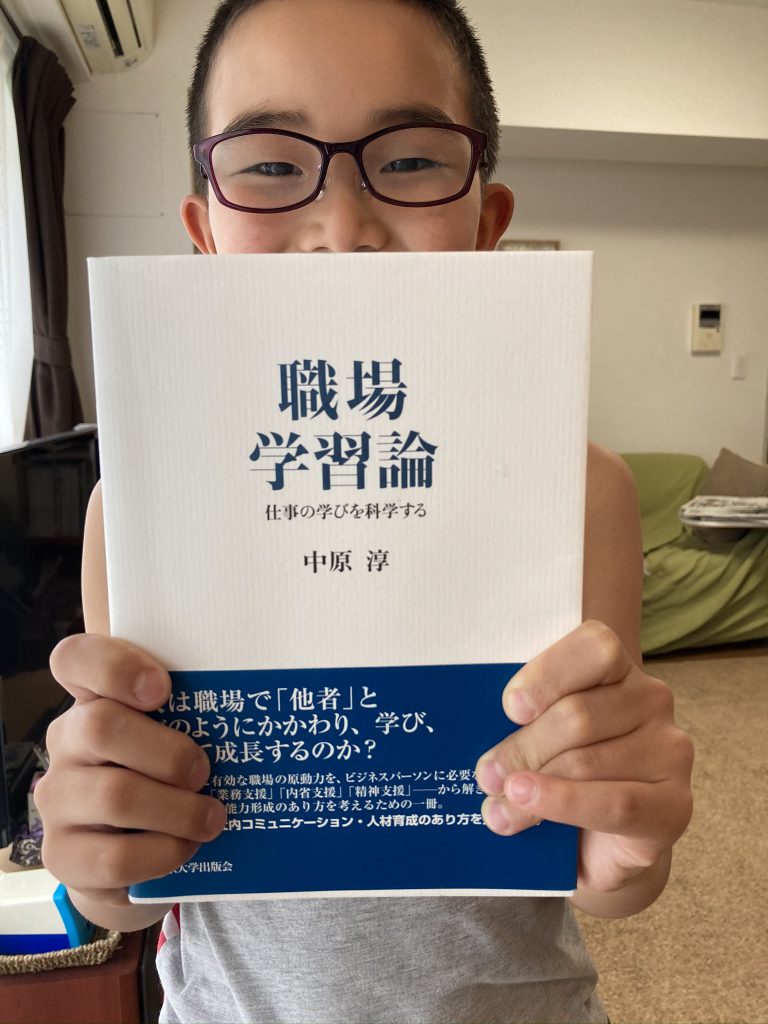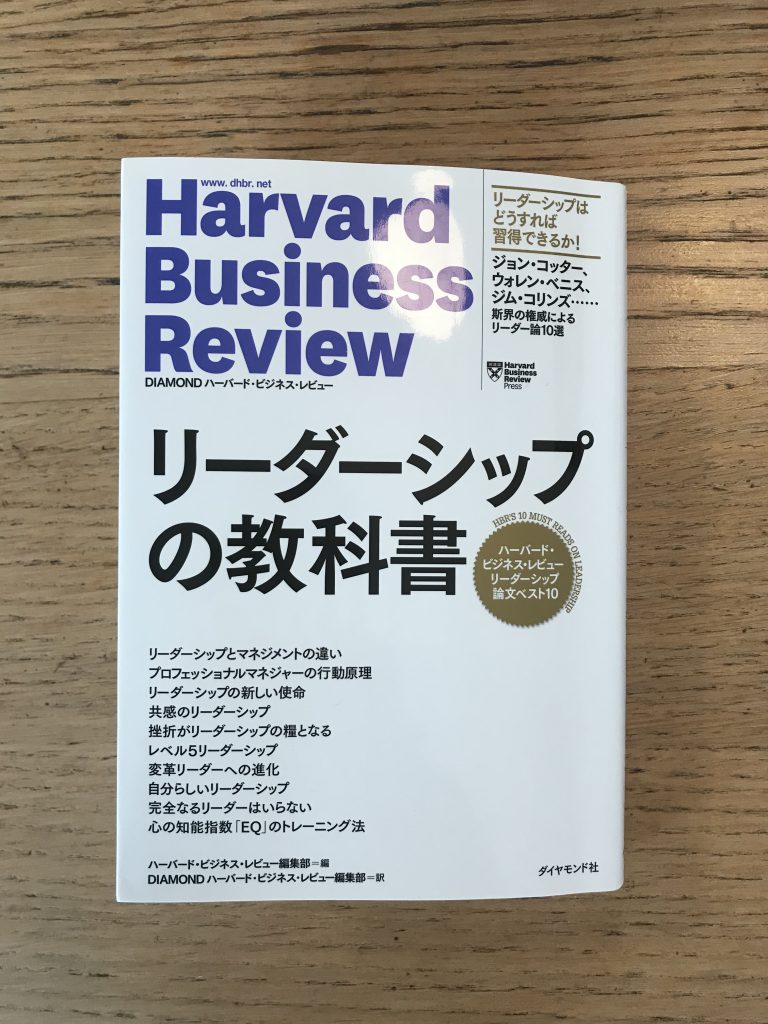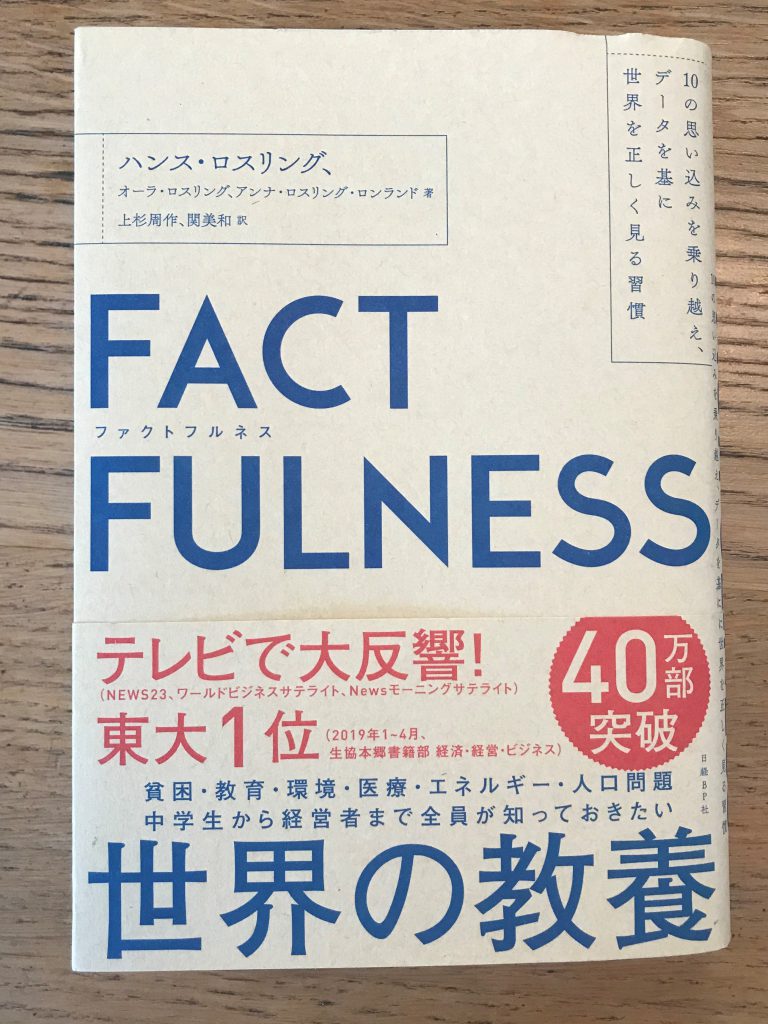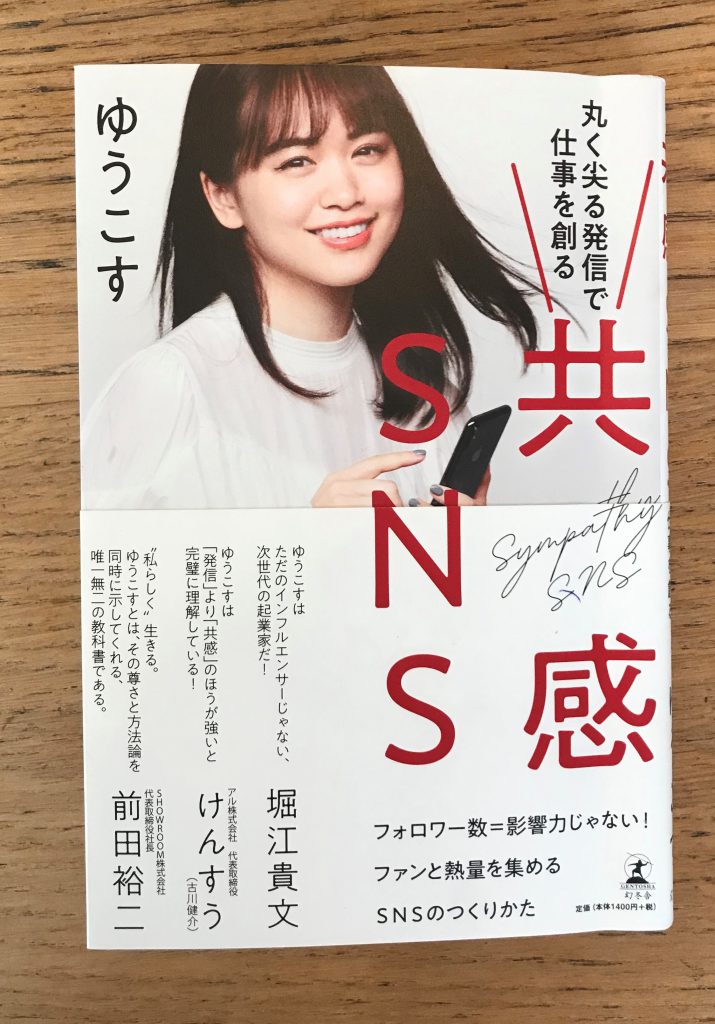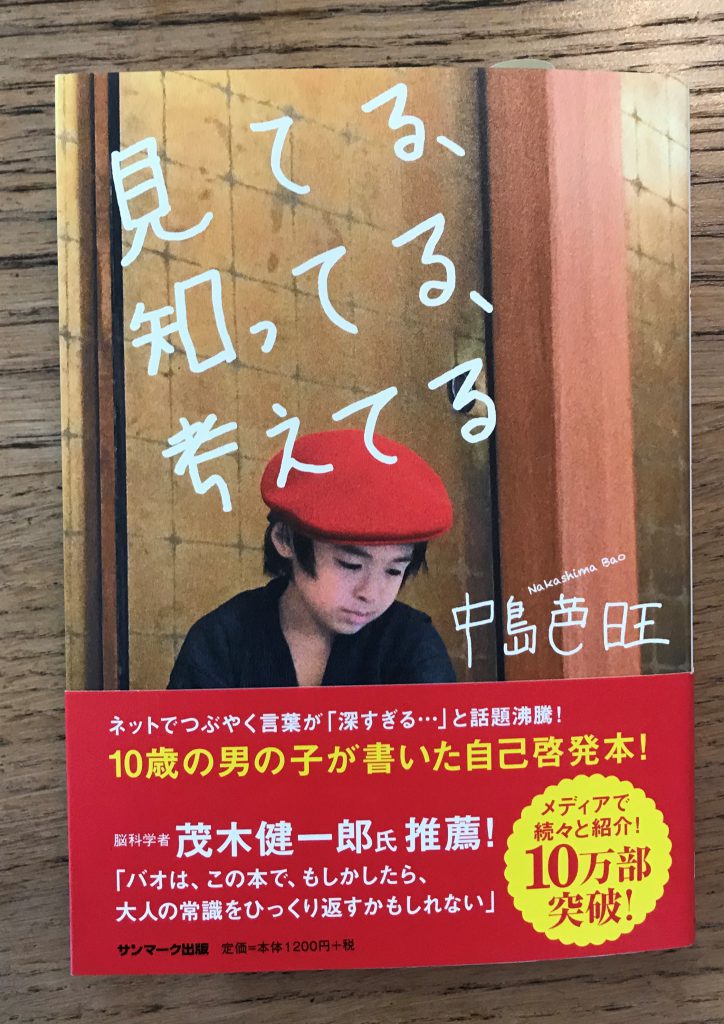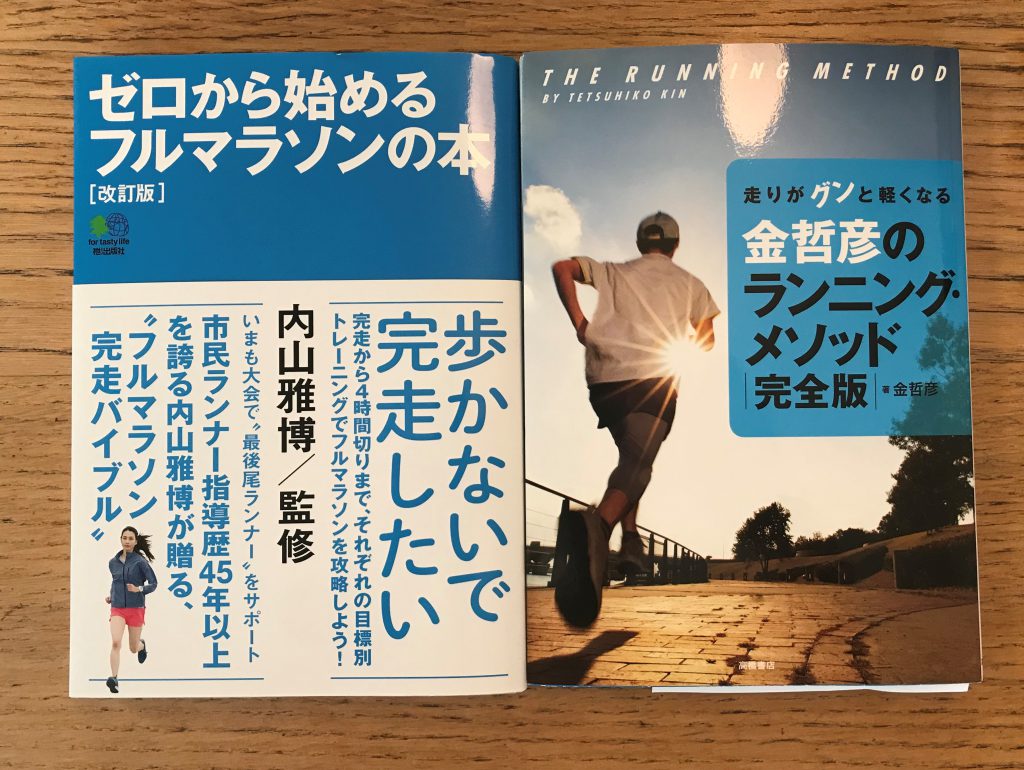第148週
2020/6/22
『無敗営業』
高橋浩一著 日経BP社
日経ビジネスの広告に何度も掲載されている本書。営業テクニックを体系的にまとめた本はあまりないため、あらたに営業組織を築く際の材料になるかと思い、手にとりました。
4つのことが印象に残っています。
一つ目は、お客様にとって営業は「ズレない」=「わかってくれる」ことが何より大切ということです。私は、初回や二回目など提案前の場面では、とにかくその企業様を理解することに努めます。お客様が真に目指したい姿や、深層の悩みが分かれば、的確な提案ができ信頼を得ることができるからです。「わかってる営業」もしくは「ズレない営業」になれるかどうか、営業部隊の合言葉にしても良いぐらいです。
二つ目は、営業状況の種類分けです。著者は案件や商談を「楽勝・接戦・惨敗」の3つに分けています。そして、強い組織に至るには「接戦」を勝ち抜く筋力をつけることが必要というのは同感です。案件を常に3つに分け、接戦の戦略を練ることや、惨敗案件をかぎ分けることはとても有用であり、また提示されていた既存顧客リテンションチームにも、新規顧客開拓を課すことも組織全体の営業力を高める良策だと考えます。ただいくら社内用語であれ「楽勝」というのは、お客様に失礼です。社内での使用言語が社員の考えや行動を規定するため、私であれば「相愛」という言葉を使います。
三つ目は、「決定の理由」ではなく「決定の場面を問う質問」を聞くというのは、是非取り入れたいです。「どんな場面で、心がぐっと動いたのでしょうか」という質問はいつ・何が必要だったかをより具体的に浮き上がらせると感じます。
四つ目は、この著者の「執念」の凄さです。著者は12年前あるIT系企業に対する20社の大型コンペで敗れました。どこが受注したのかお客様から教えてもらえなかったのですが、3ヶ月色々なツテをたどり、敗れた相手を見つけ出し直接会いにいったそうです。また、以前は失注したとしても「100%決定かどうか」「再提案させてくれないか」と必ず粘ったそうです。ある分野でプロとしての立ち位置を確立している方は、こういった「執念」があるのではと感じました。
(878字)