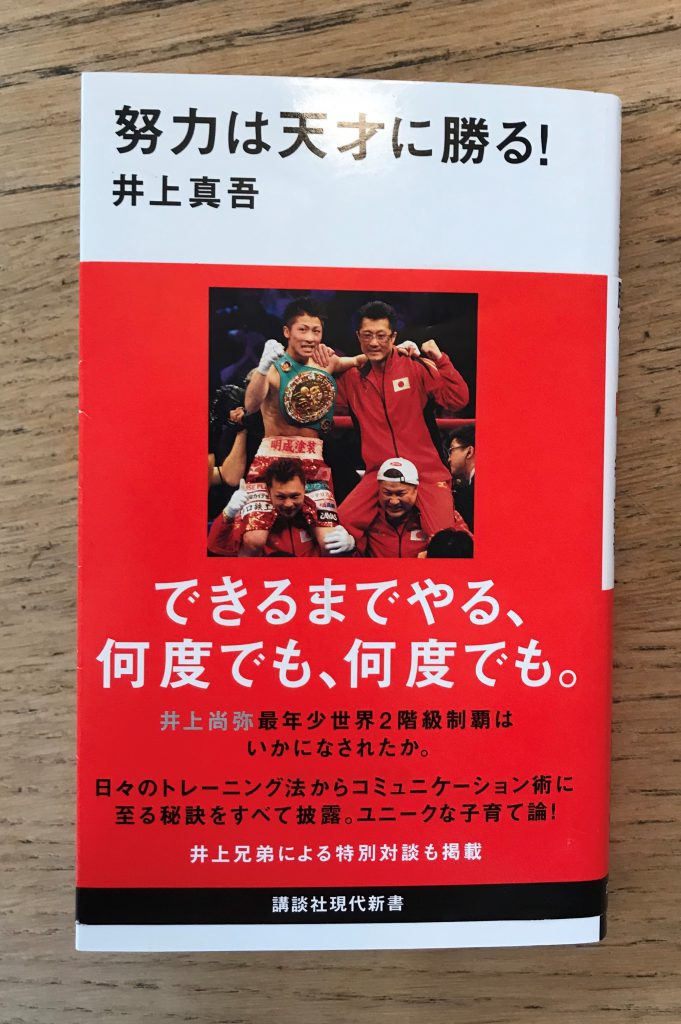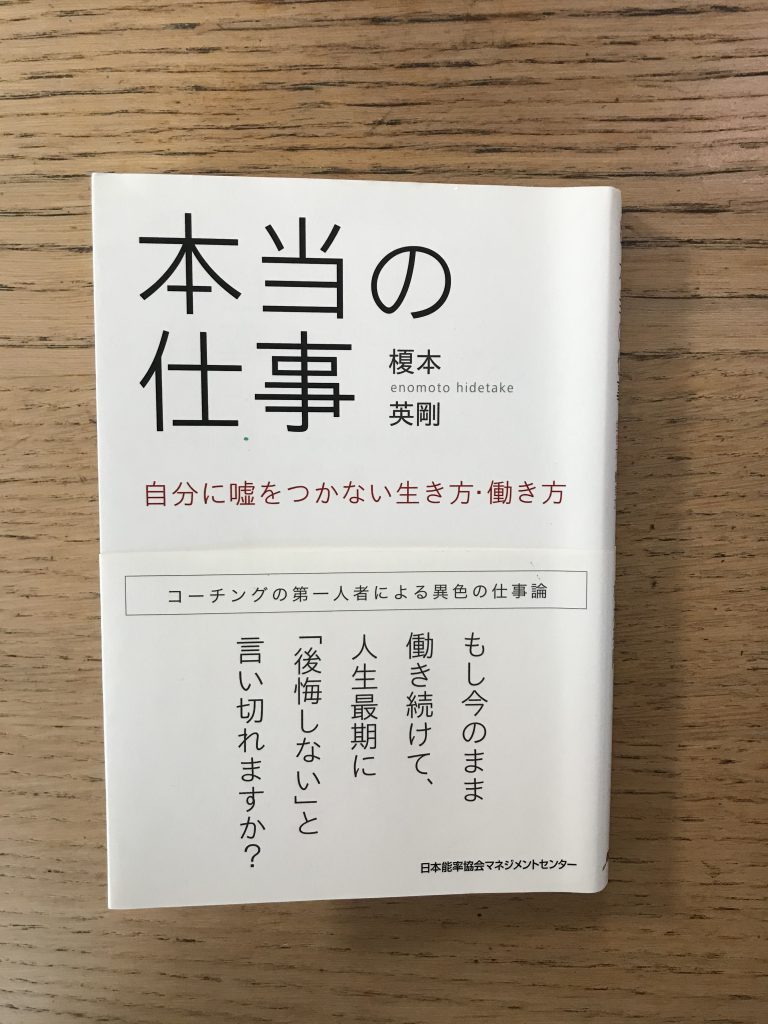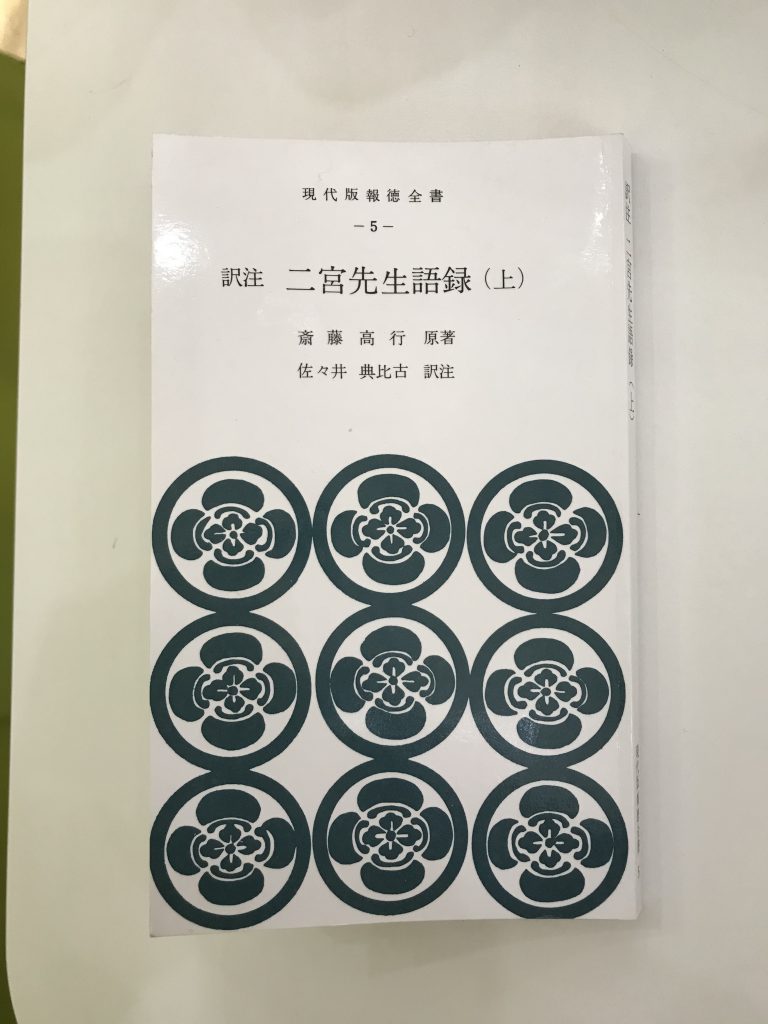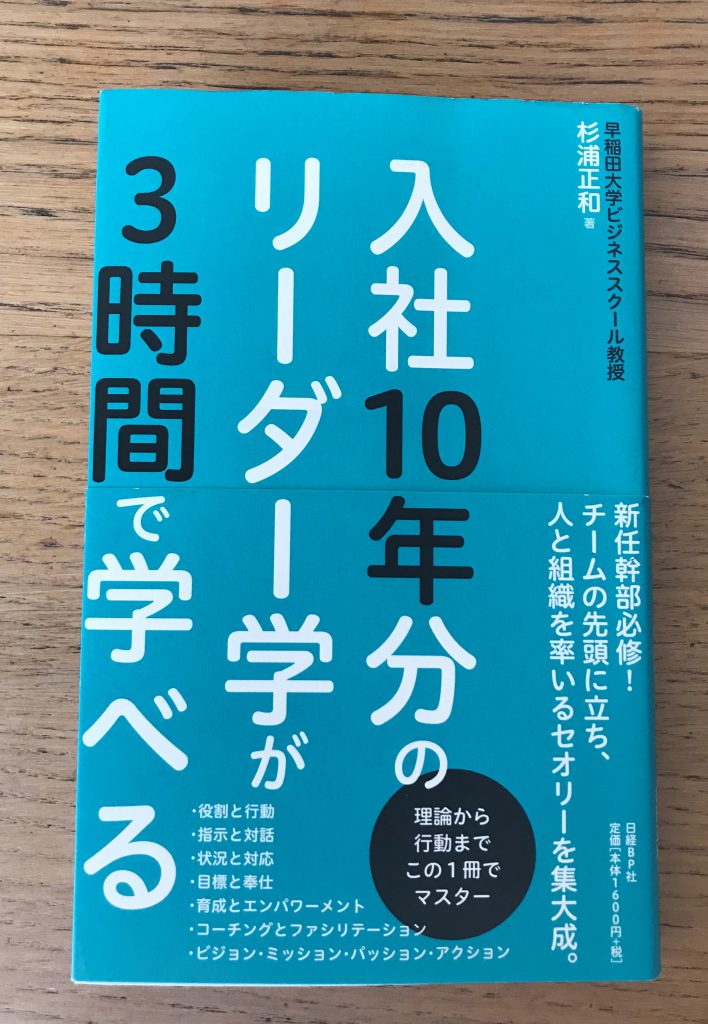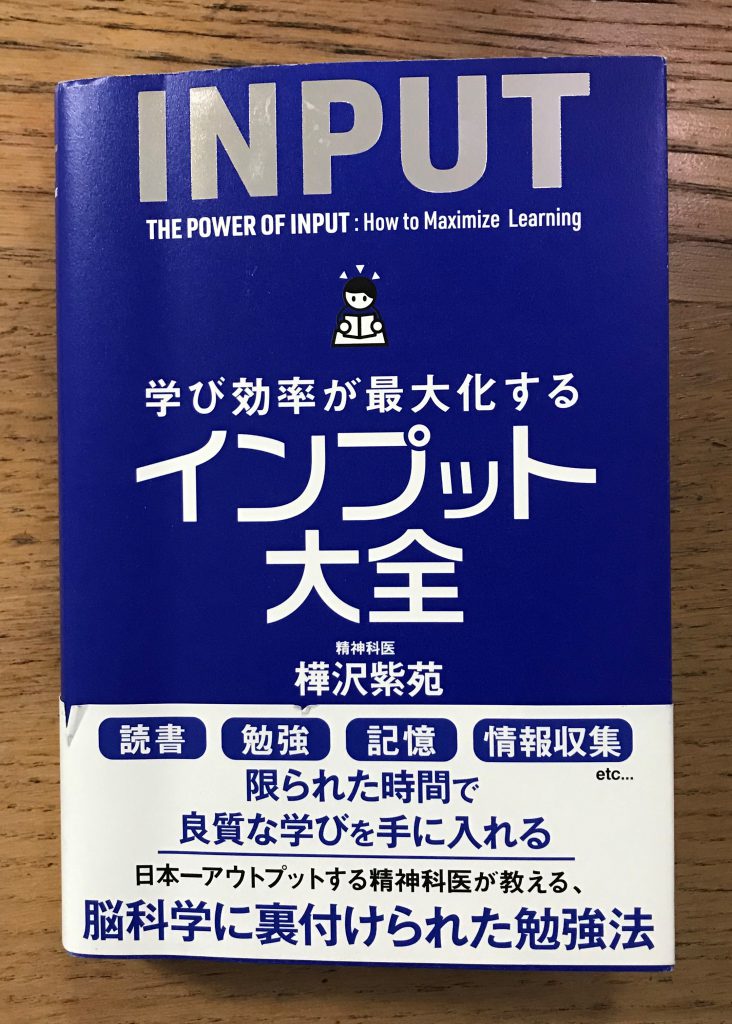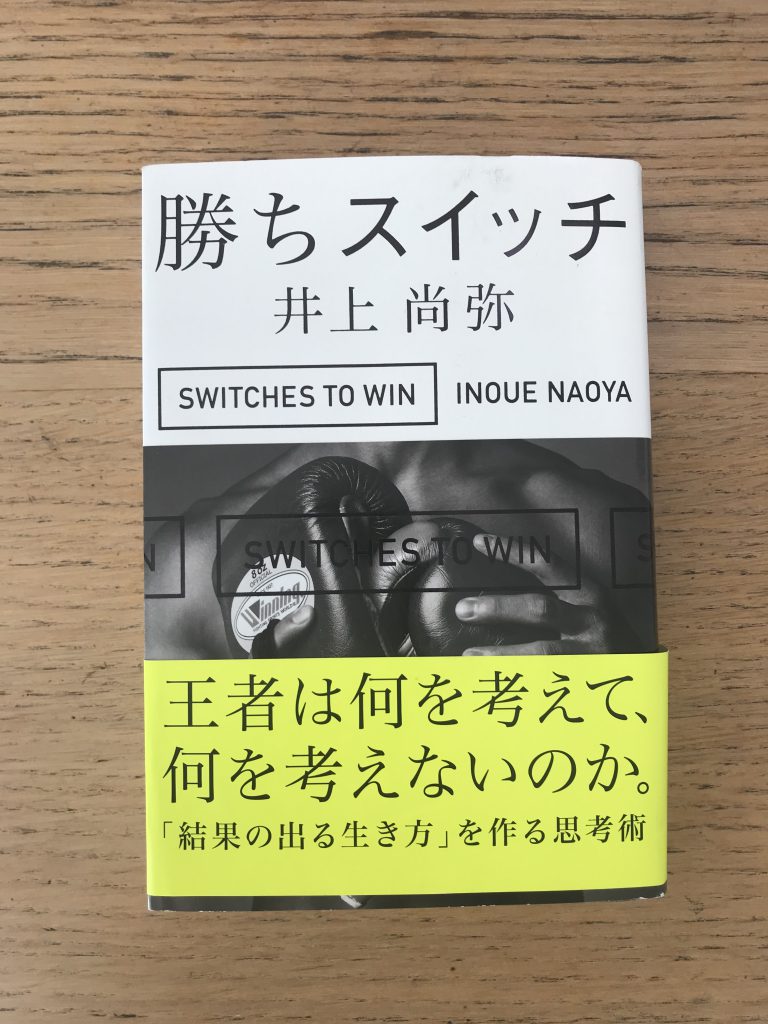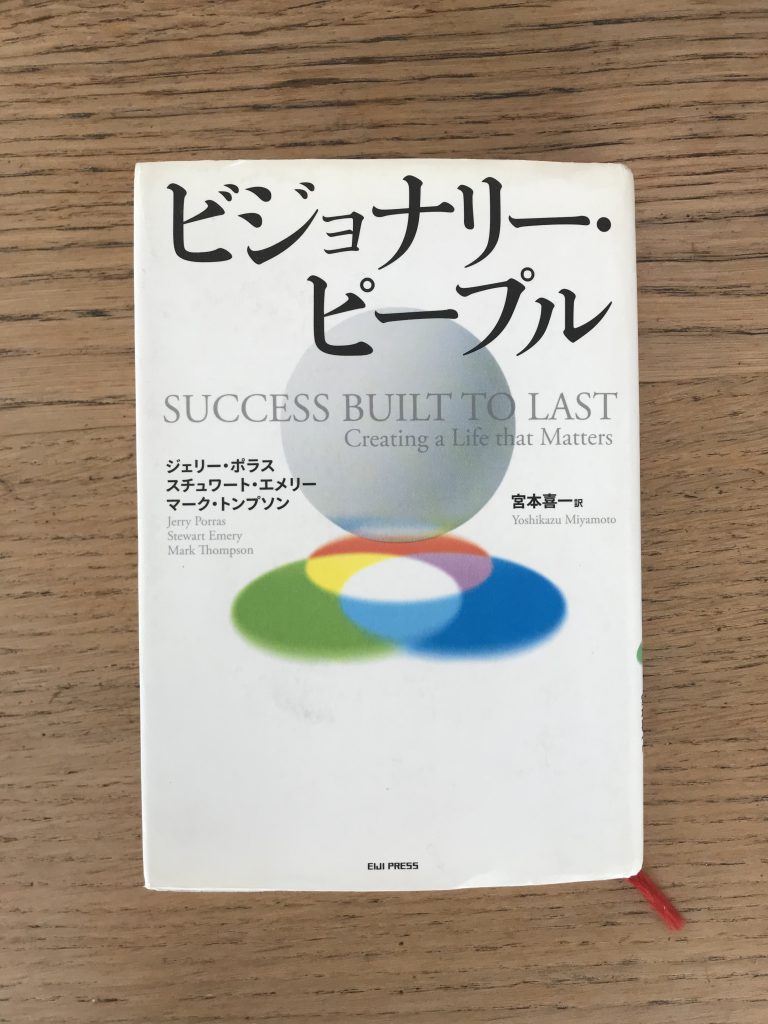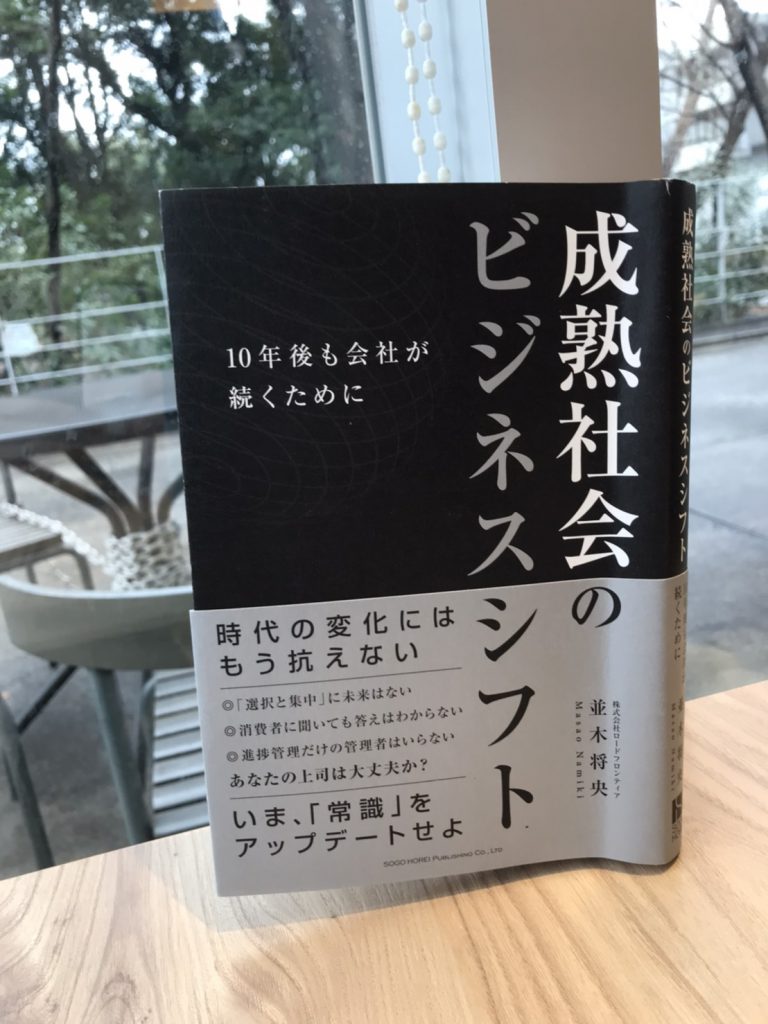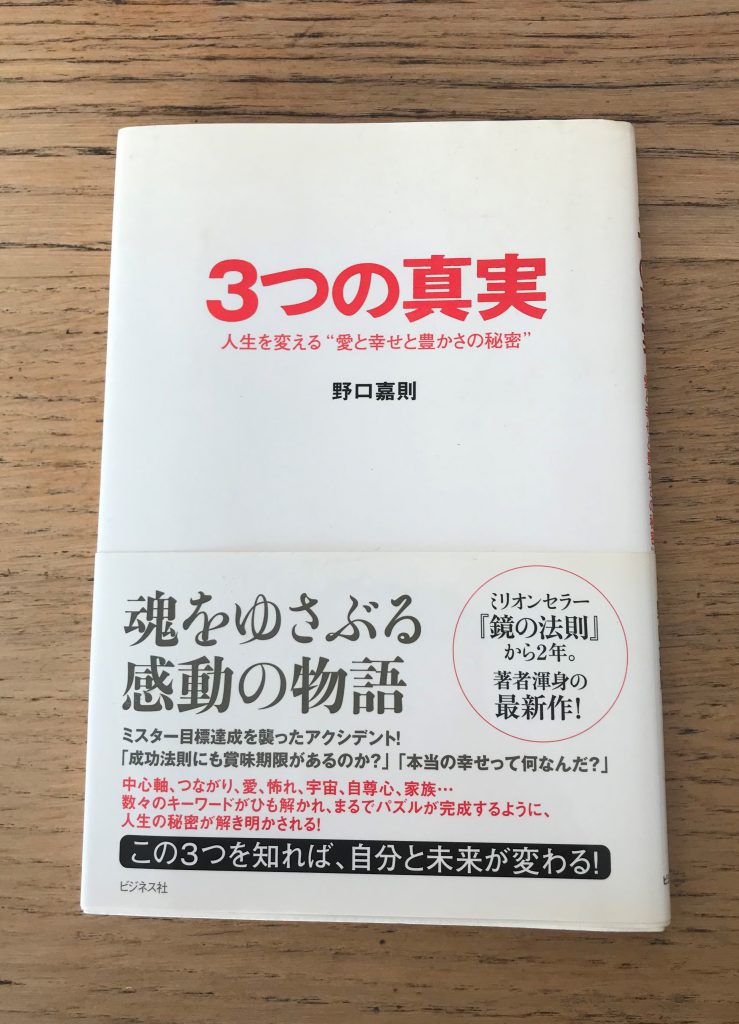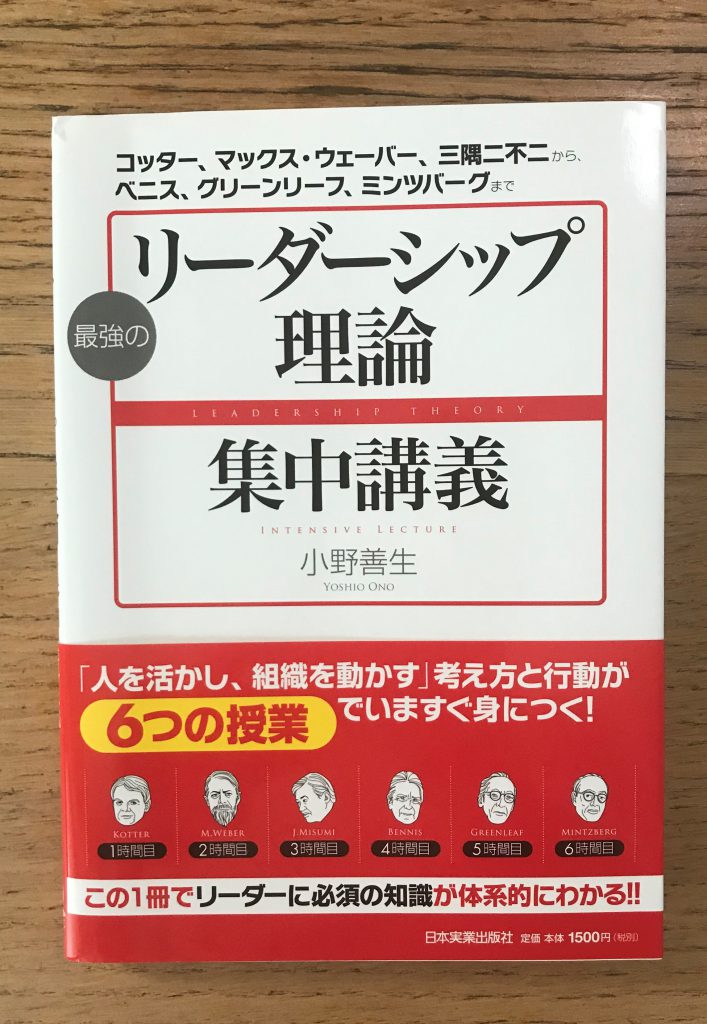第138週
2020/4/5
『努力は天才に勝る!』
井上真吾著 講談社現代新書
井上尚弥選手のような突き抜けた選手を生み出すには、どうすれば良いのか。その答えを探るため、父真吾さんの著書を手に取りました。
本書を読了し私が出した結論でいえば、やはり「チーム井上」で歩んできたことに尽きると思います。本書の終わりに、井上選手の母美穂さんが手記を寄せているのですが、「尚のベルトは『家族みんなで獲った』と思っています。尚も同じ気持ちでいると思います。」と言っています。
やはりチームの力は偉大です。私の娘も、息子もそれぞれ夢があります。その夢を実現するにはまず家族が「チーム吉田」になる必要があると強く思いました。では家族で強いチームを形成するにはどうしたらよいのか。二つの点が印象に残りました。
一つ目は、「リビング」の話です。「我が井上家に『強さの秘訣』があるとすれば―。それは『リビング』なのかもしれません。」と真吾さんは言っています。井上家では頻繁に家族会議が開かれ、リビングにある大きな木のテーブルで語り合うそうです。皆で集まる時もあれば、1on1もあるこの家族会議の目的は、子供達の考えや壁を把握することです。「ときには言葉を交わすことで、よりしっかりと意思を確認することができます。」と真吾さんは言っています。「子どもの今」を把握するのは、押しつけや的外れな導きを避けるためにとても重要なことです。吉田家のリビングもその目的で使っていこうとあらためて思いました。
もう一つは親が本気で取り組むということです。「『よし、二人とも頑張れよ』ではなく、『父さんも一緒に頑張るからな』『おまえたちがベストを尽くせるように環境は整えたぞ』と自分も本気になっている姿を見せたかった」と真吾さんは言っています。井上選手もあるインタビューで、お父さんに反抗せず厳しい練習についてきた理由を聞かれたとき、お父さんがやることをやっていたから納得していた、ようなことを言っていました。親が本気で取り組まなくては家族でチームにはなりえません。
美穂さんの手記の中で、真吾さんが悩んだ時期があったそうです。それは井上選手がプロ入りを決めた時に、世界のトップを知らない自分が尚の足を引っ張ることにつながらないか、と悩んでいたそうです。世の中には世界を知る名トレーナーが沢山います。この悩みは子供の未来を真剣に考える上では当然通る道でしょう。真吾さんは美穂さんの言葉でその悩みを越え、自分の手で二人を世界チャンピオンにすると心を決めたそうです。ここで真吾さんに覚悟ができたのだと思います。
(1039字)