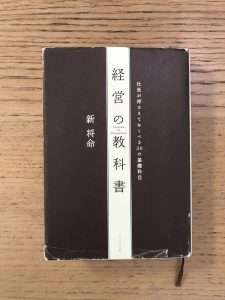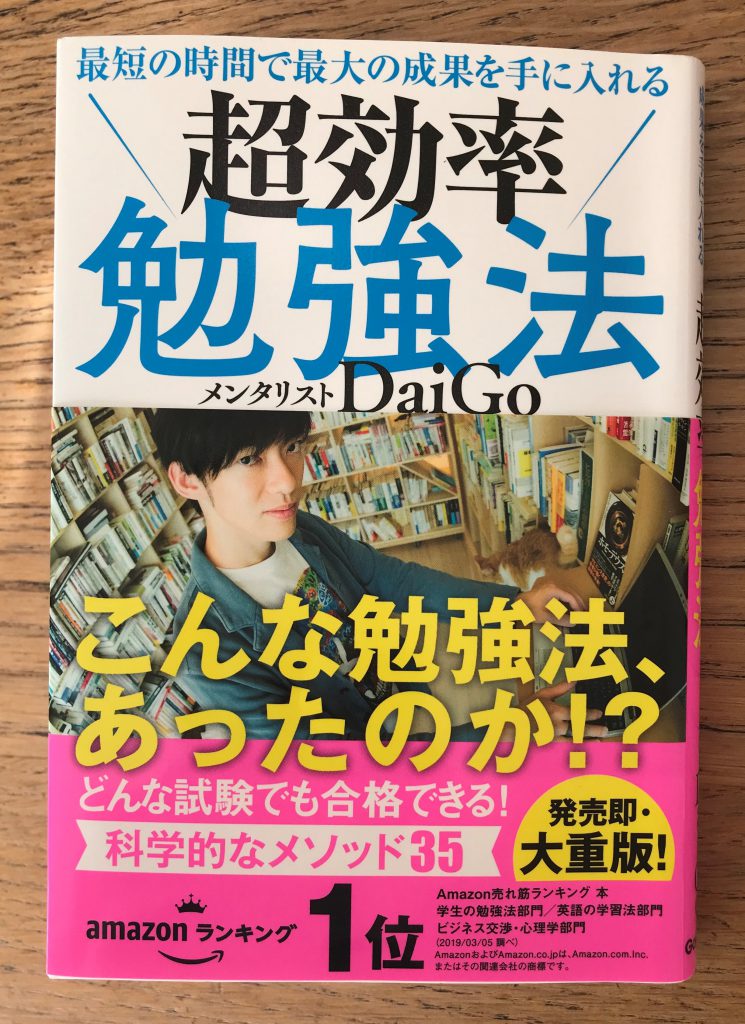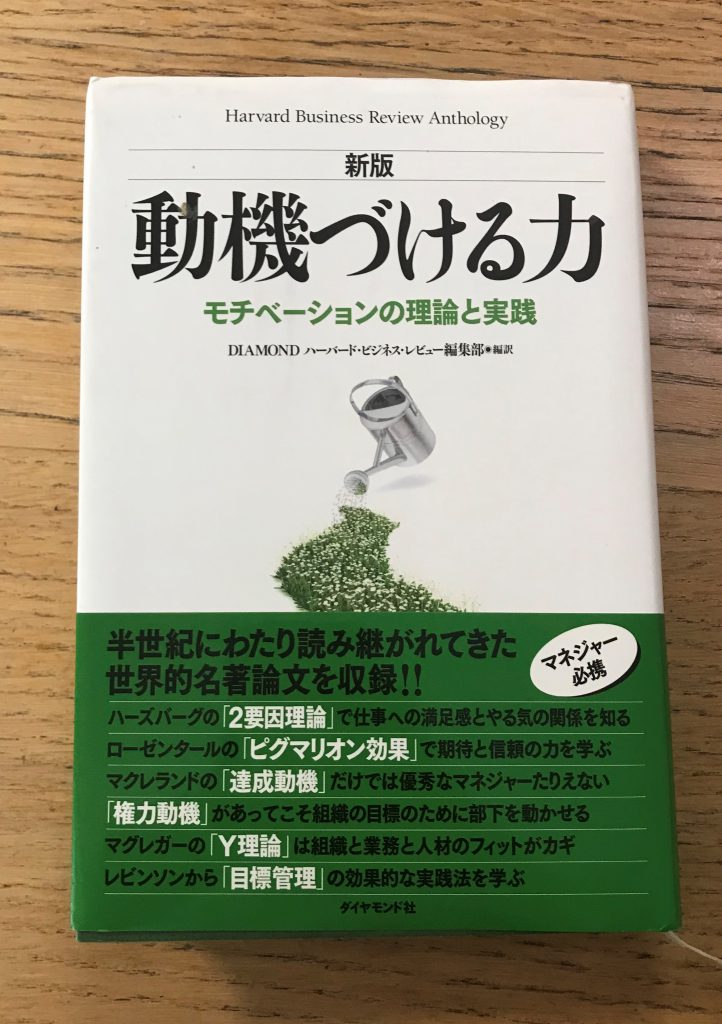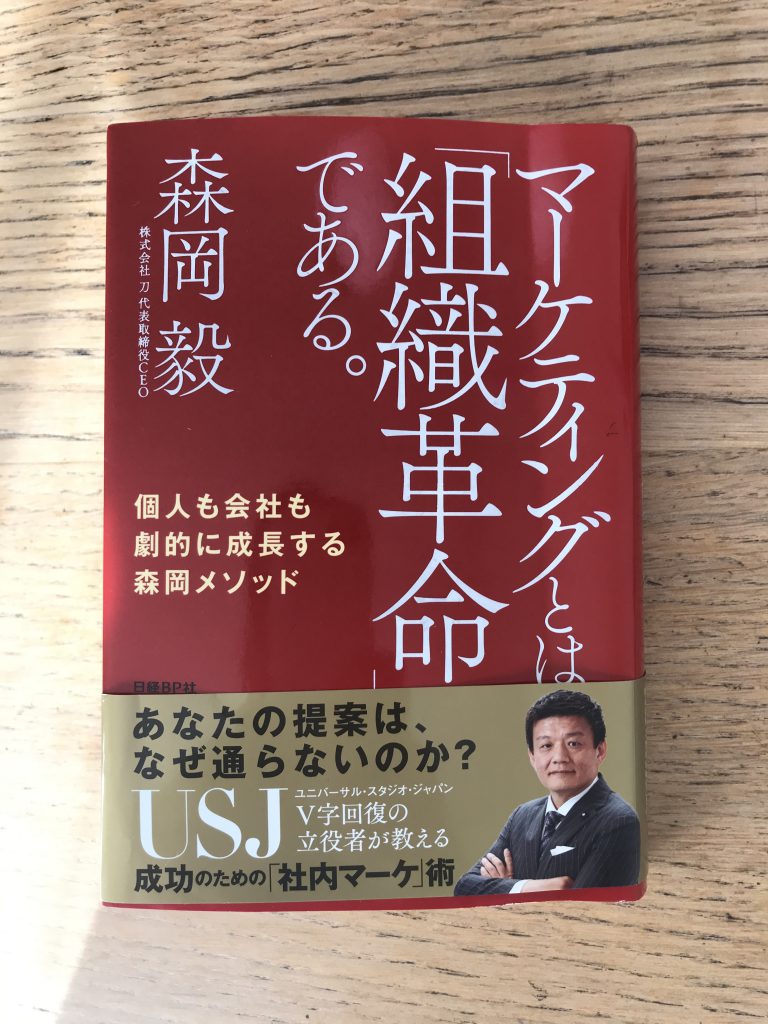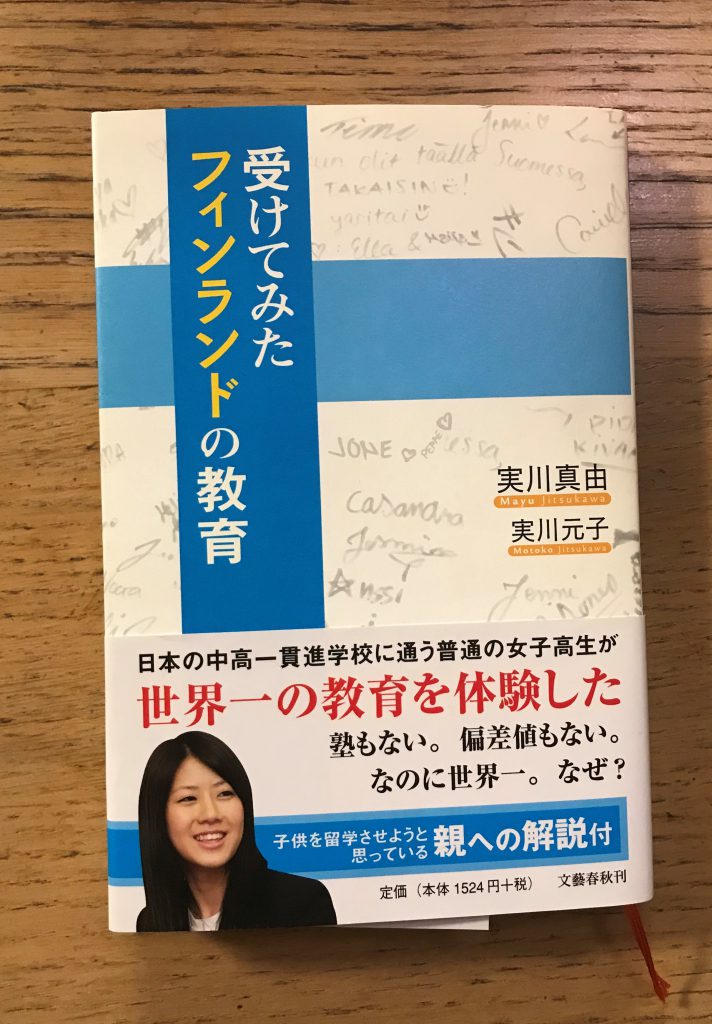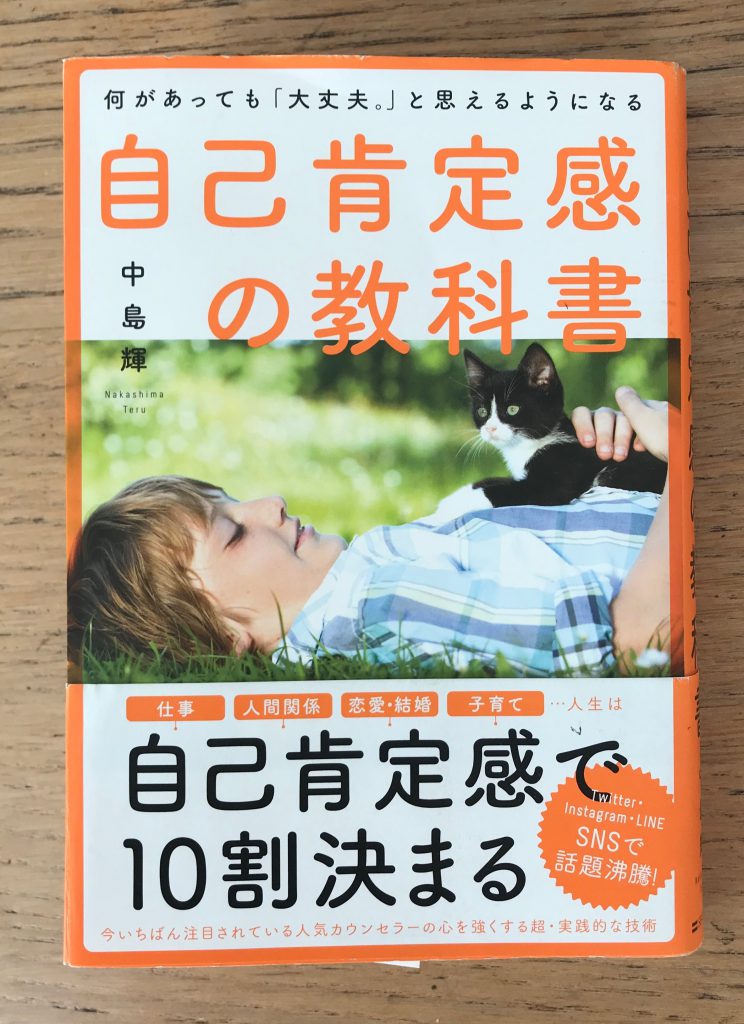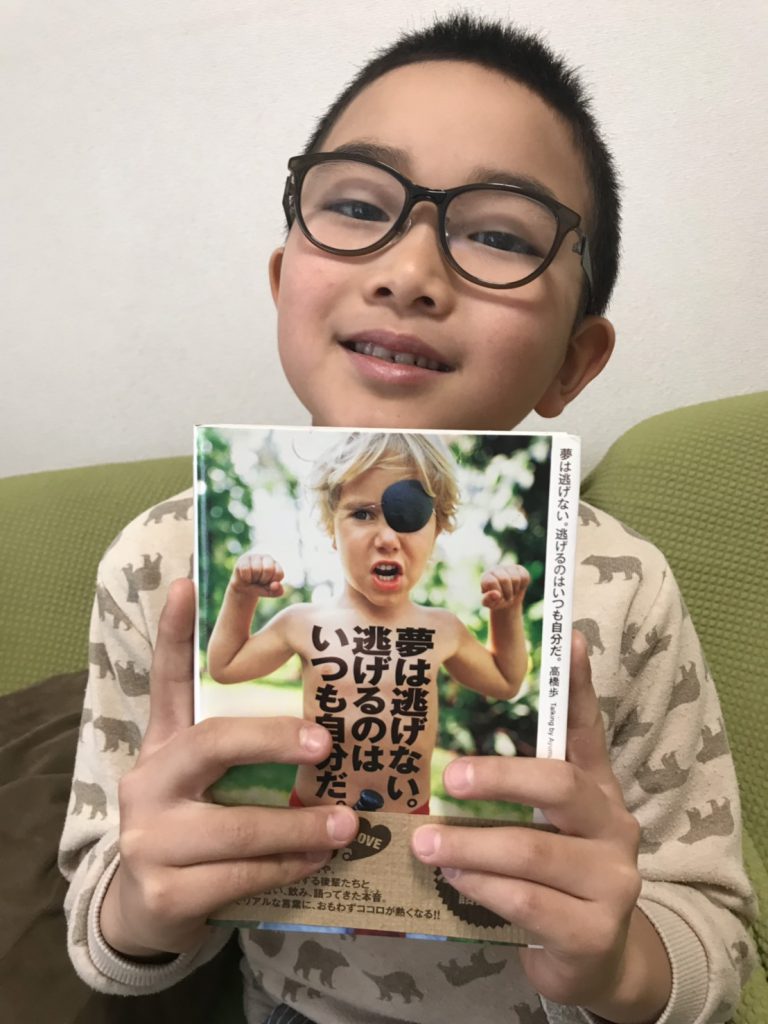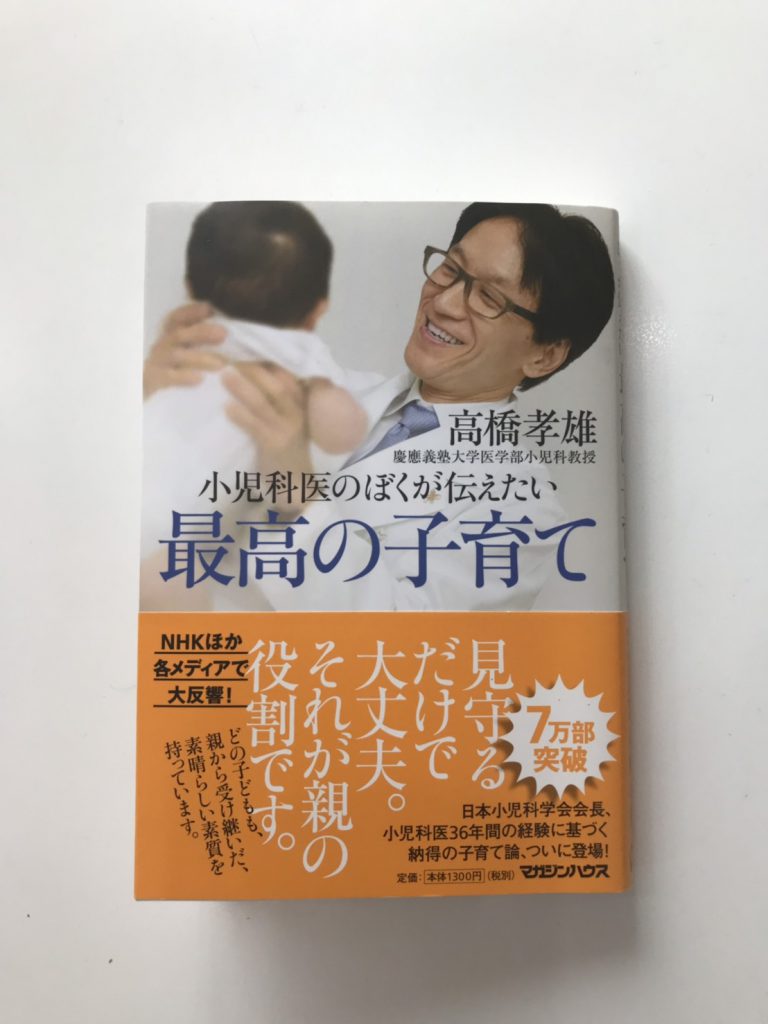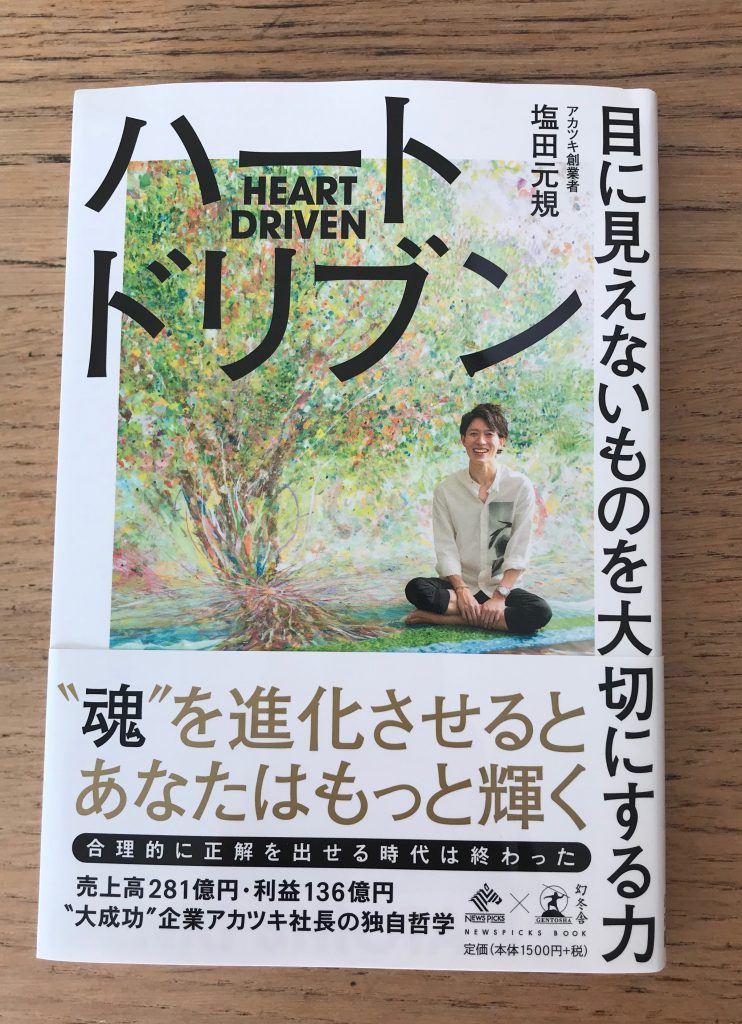第128週
2020/1/26
『経営の教科書』
新 将命(あたらし まさみ)著 ダイヤモンド社
5年前ぐらいに、今も大変お世話になっている経営者の方が、「新さんの経営方針が良い」と話題に出していたことを人づてに聞き購入した本です。当時はその経営者の方がどんな経営をしたいのかを理解する目的で読みましたが、今回は自身の新たな経営方針を設計するため再度手に取りました。
本書の内容は不易流行の不易部分である「経営の原理原則」をまとめたものです。琴線に触れる箇所が多くあり、沢山の折れと線が出来ました。その中で三つ程、記載します。
一つ目は、合言葉を自分で何個も作っている点です。直接「合言葉を持て」と言及してはいませんが、本書には何個も合言葉が出てきます。例えば、「多・長・根」という合言葉。これは陽明学をもとに筆者がまとめたもので、大局観を身につけるために必要な考え方です。多は、多面的・複眼的なものの見方。長は、長期的な視点、根は、目的など「そもそも」の視点です。社を預かった瞬間から『「多・長・根」「多・長・根」と“念仏”を唱えながら意思決定を行ったことが、私には非常に役に立った。』と筆者は述べています。他にも、人間関係能力づくりのために心がけていた「丁褒感微名」(ていほうかんびめい)。ダメな会社の3K(カミ、カイギ、コミッティ)など、再現性のあるフレームワークのように合言葉にしている所が秀逸だなと思いました。
二つ目は、「CSの前にES」です。筆者が提唱する勝ち残る企業づくりの流れは、経営(者)品質→社員品質(満足)→商品・サービス品質→顧客・社会満足→業績→株主満足→経営(者)品質・・・となっています。経営者品質である経営力、リーダーシップ、倫理観などのあとに、社員品質(満足)が来ており、『顧客満足を実現する当事者はだれか。銀行でもなければ、評論家でも証券会社でも、コンサルタントでもない。社員である。』と著者は述べています。ホワイト企業大賞の授賞式でも強く感じたことですが、私もやはり社員のやりがいを最重要におく経営をしていきたいと思います。
三つ目は、心の強さの章で出てきた数々の言葉です。
『私の経営者としての経験では、楽しいことよりもシンドイことのほうが多かった、というのが正直な思いである。』
『苦境のたびに立ち止まり、涙を流していられるほど人生は長くない。』
『5年、10年と経つうちに痛みはやがて癒えていく。』
『すぐれた経営者とは、気分転換が上手な人でもある。』
という筆者の言葉は、心の強さを希求する自分には心に響きました。
ちなみに、筆者も42歳の時にジョソン・エンド・ジョンソンの経営者になった際、米国総本社会長の『何かをやっていい結果を出したいなら、FUNでなくてはならない』『真剣であっても深刻になるな』言葉により、苦境でも切り替えられるようになったそうです。
(1144字)