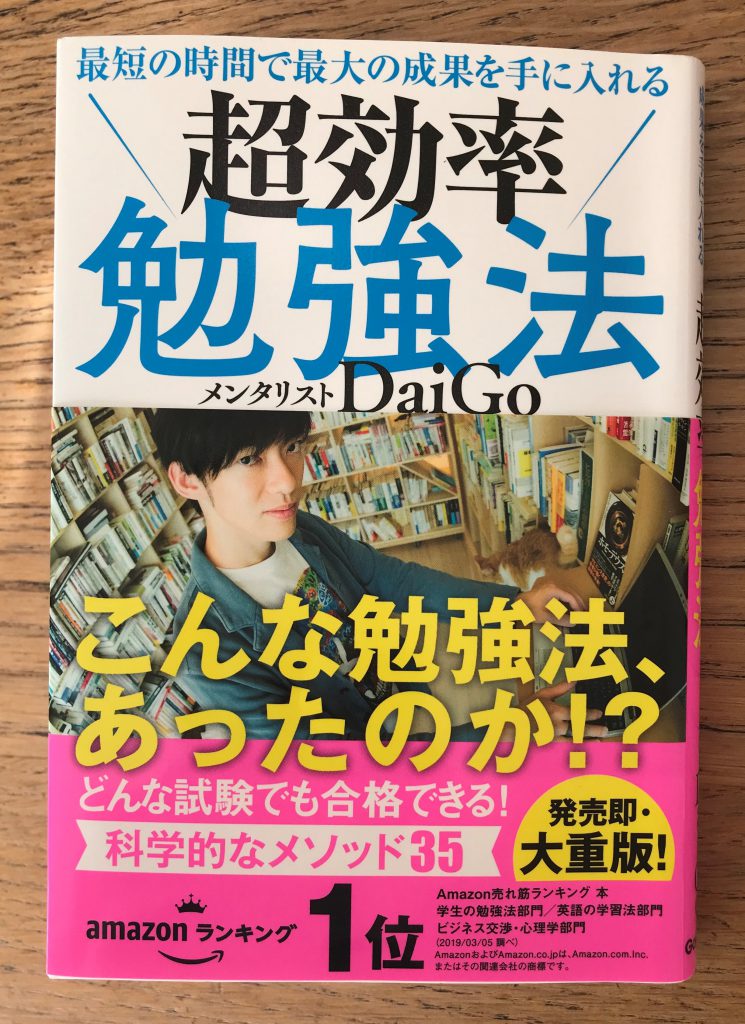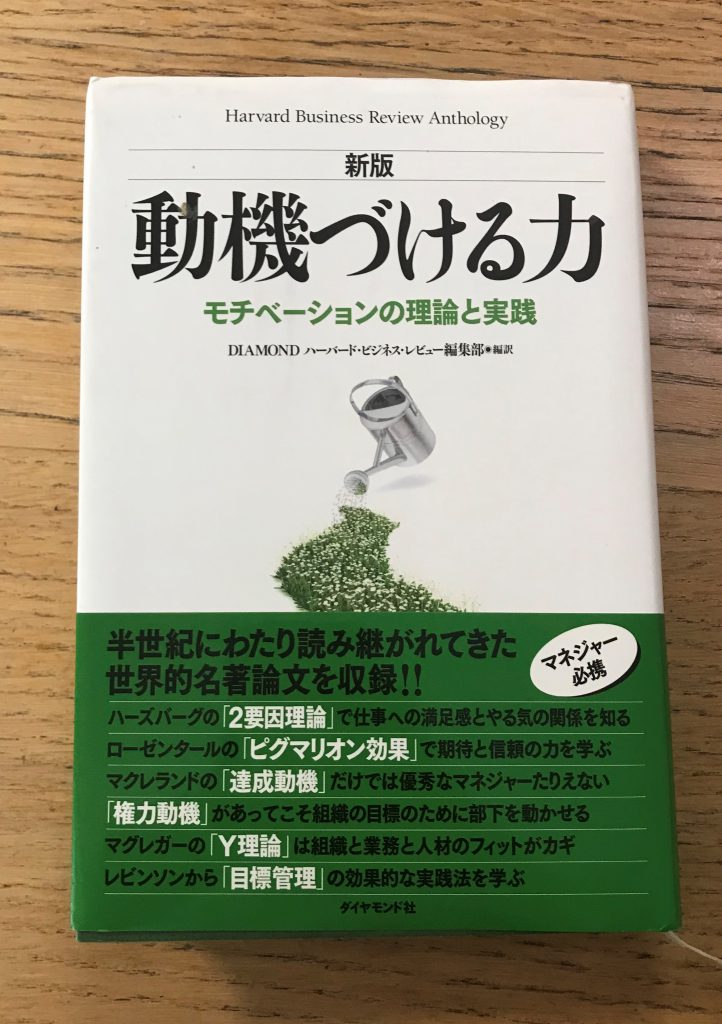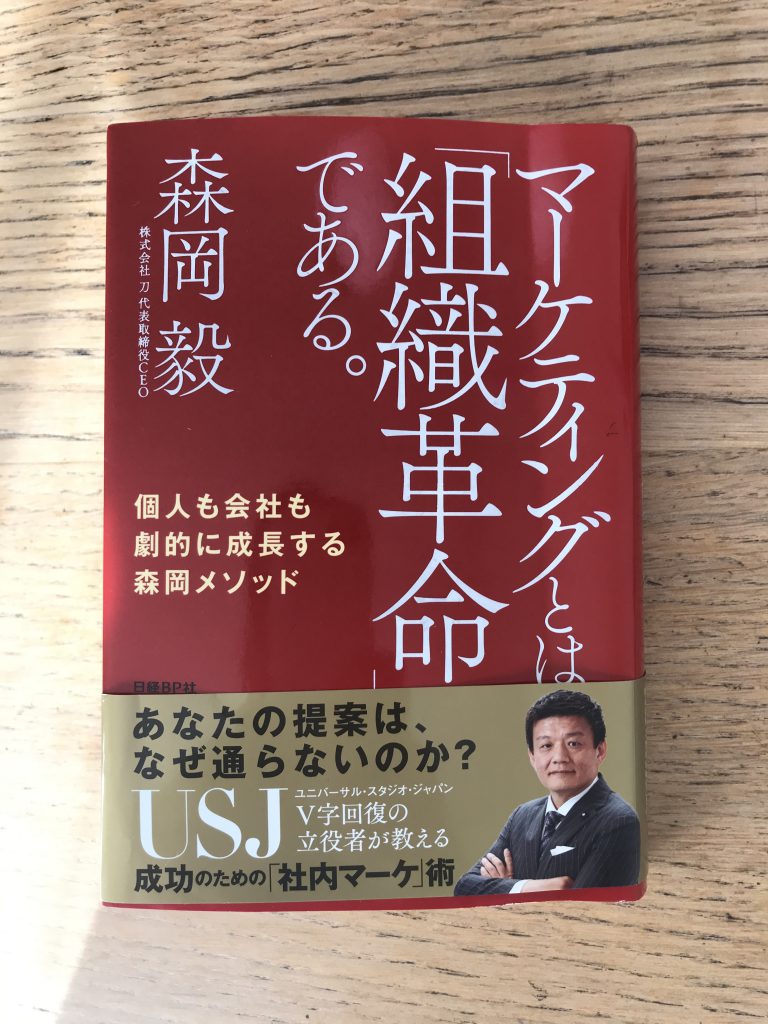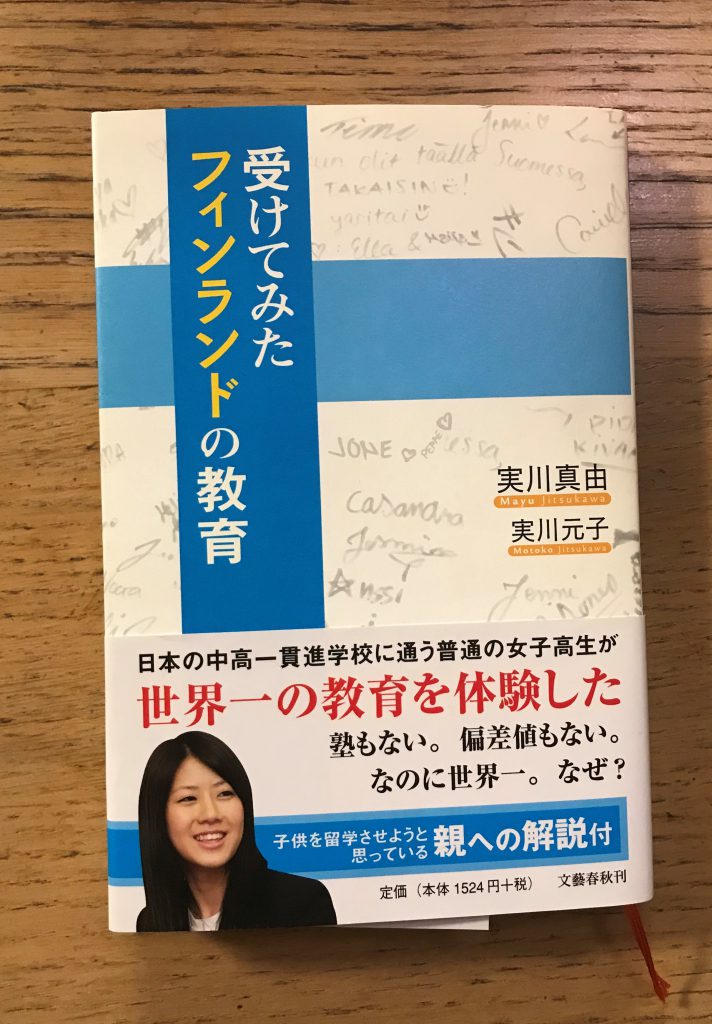先週の日曜日に、ホワイト企業大賞の授賞式に出席しました。
http://whitecompany.jp/#aWC
これは現在私が通塾している天外塾代表の天外さん主催の賞であり、「ホワイト企業=社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にしている企業」と定義しています。私自身「新しい経営の在り方」を設計しようとしており、そのためのインプットとして参加致しました。
授賞式~大賞企業の講演~ワールドカフェ形式の対話、という流れの中、心奥に達するような大変深い気づきのある場でした。
例えば・・・
・思い切って「やりたくないこと」を一切やめるとして、「やりたいこと」だけを社員に出してもらい、社員が話し合い決め、そこから生産性ややりがいなどが飛躍的に上がった大賞企業GCストーリー様。社員が仕事の解釈をし直し、自己決定するような「考える機会」を都度提供することは大切。
・社員の9割以上が「月曜日にワクワク出社する」西精工様、同じようなやりがい企業のネッツトヨタ南国様。衝撃。共通するのは社員が「居場所がある」と感じ、仲間とのつながりが強く、また皆で会社のために貢献しようという気持ちがある。
・この場の受賞企業や参加企業は、皆経営者が社員にやりがいをもってもらうことに心を砕いている。粉骨砕身して社員と組織のために尽くすというか。それが嫌ではなく、当然ながら経営者自身がそれを楽しみ、やりがいをもち、手ごたえをもっている。
要は「本気」で社員の幸せと働きがいに向き合う。これですね。
先週は毎日研修がある週で、緊張感はありますが張りがあり充実しました。忙しいのは、ありがたいことです。
今週も研修WEEKです。
※ちゃっかり発表してます